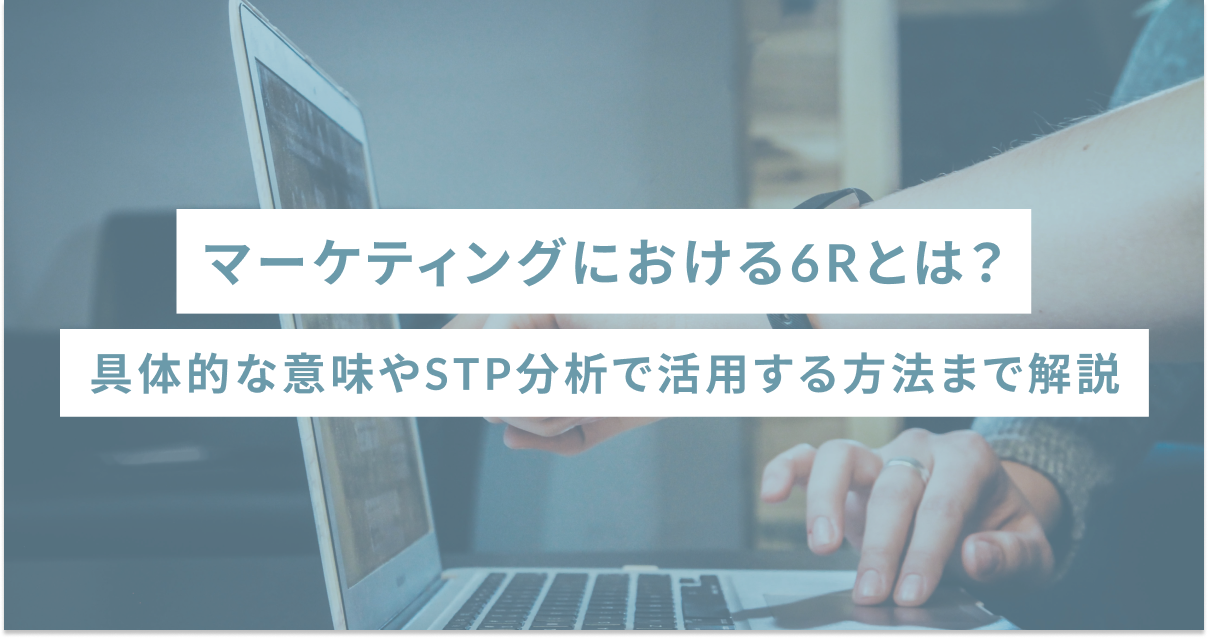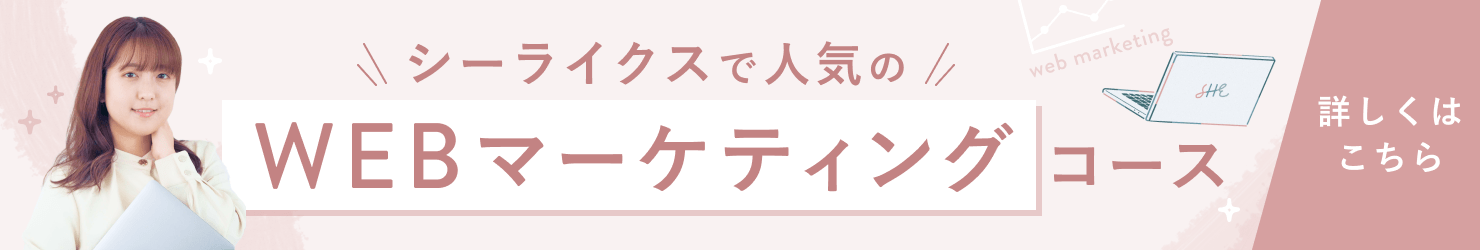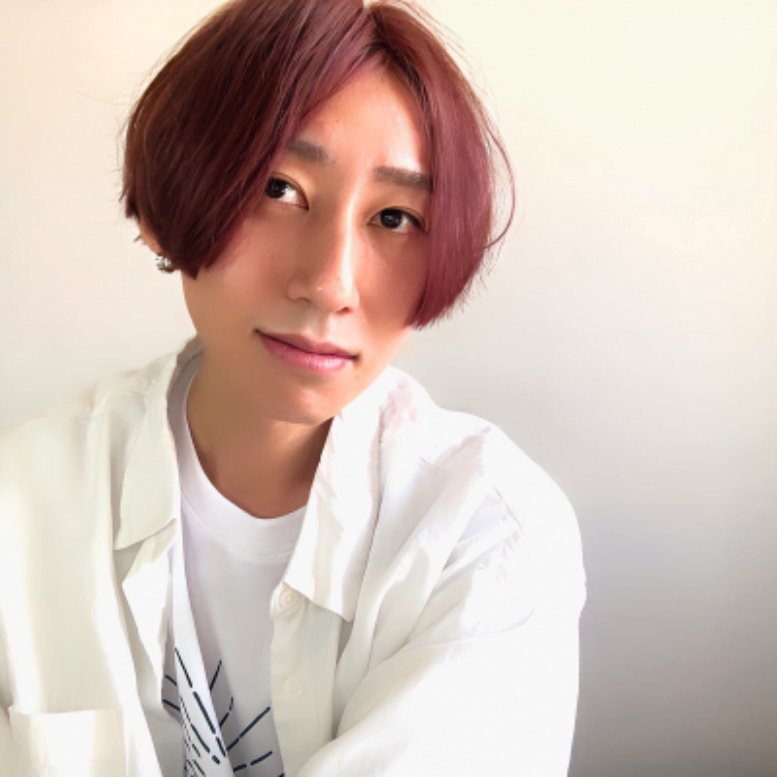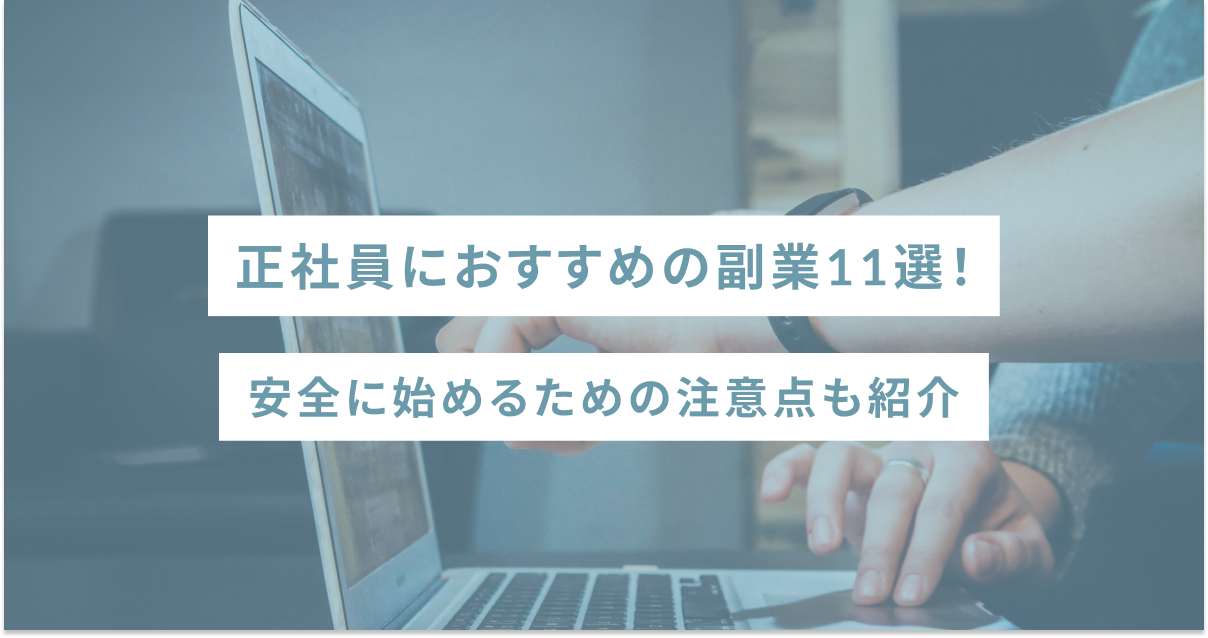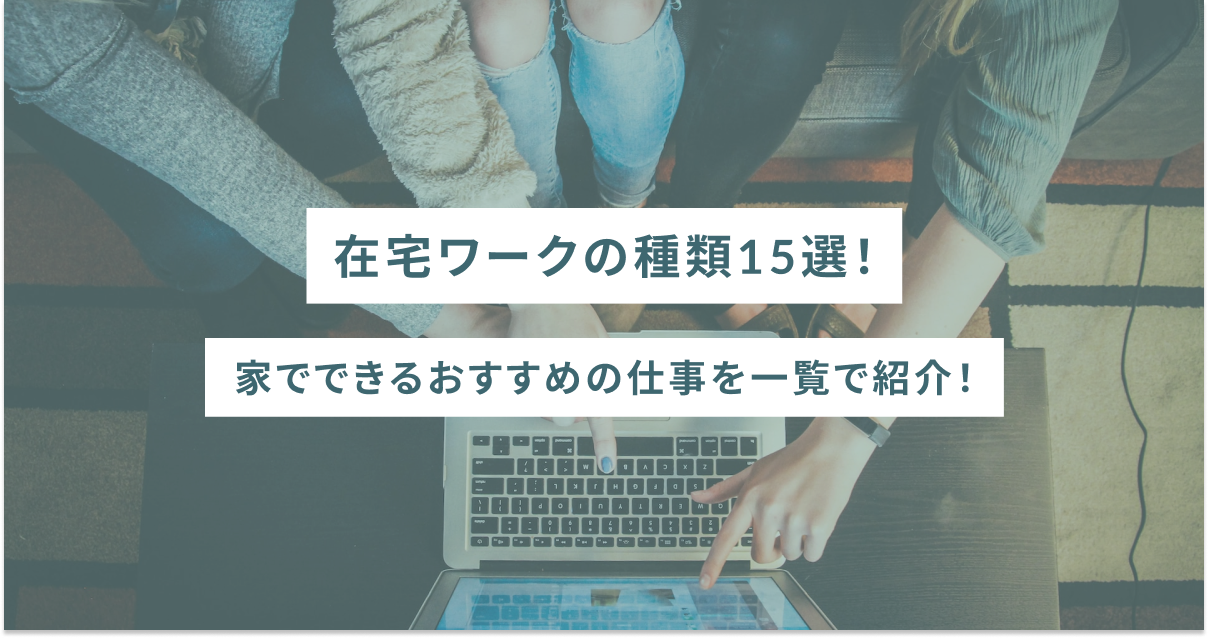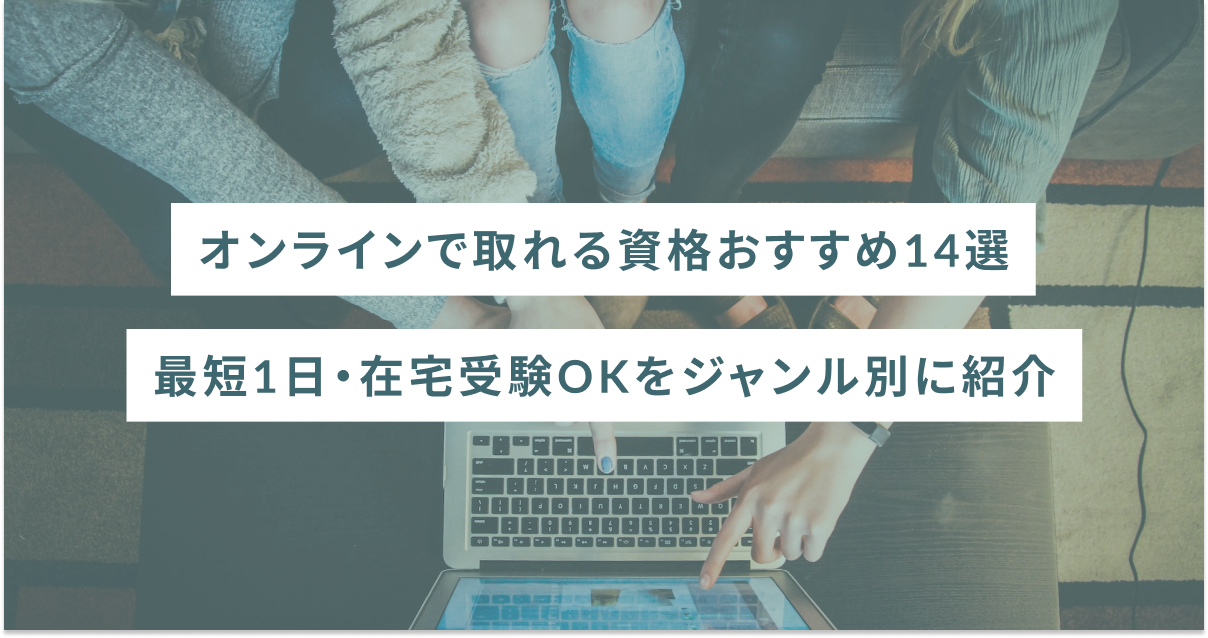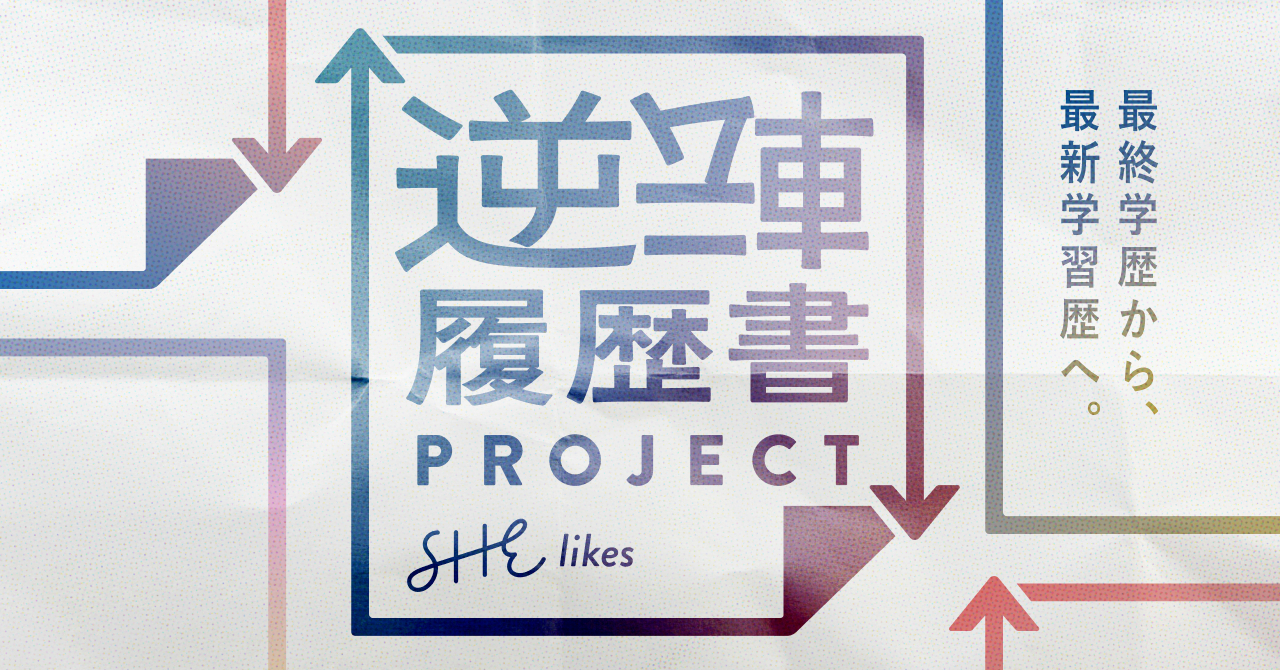マーケティング戦略を立てるうえで「誰に・何を・どう届けるか」を明確にすることは非常に重要です。しかし、感覚的なターゲティングでは施策がうまく機能せず、上司やクライアントから「なぜその市場なのか」などと問われて困った経験がある方も多いのではないでしょうか。
そんなときに役立つのが、6つの視点で市場を分析できる「マーケティングの6R」です。本記事では、6Rの具体的な指標やSTP分析との関係性、6Rを活用するメリットなどを詳しく解説します。マーケティング戦略の質を一段階高めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
マーケティングにおける6Rとは?

マーケティングにおける6Rとは、以下の頭文字をとった指標のこと。
- Realistic Scale(市場規模)
- Rate of growth(成長性)
- Rank(顧客の優先順位)
- Rival(競合状況)
- Reach(到達可能性)
- Response(反応の測定可能性)
上記の6つはマーケティング戦略の立案や目標設定などに使用される指標であり、ターゲットや市場ポジションの選定において的確な意思決定に役立ちます。
なかでも重要なのは、戦略設計の精度が高まるSTP分析(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)と組み合わせて活用することです。6Rを使えば、企業視点だけでなくユーザー視点も交えた現実的なマーケティング戦略を構築できます。
まだ6Rを使いこなせていない方は、まず各要素の意味を理解し、自社の商品や市場に照らし合わせて整理してみましょう。

なぜSTP分析で6Rの指標が大切なのか?
STP分析は以下の要素でマーケティング戦略の策定や改善を行うフレームワークです。
6Rは上記のステップを詳細に分析するための指標であり、STP分析の精度を高めることが可能です。各指標の具体的な内容は後述しますが、これらの指標を活用することで、市場環境や消費者のニーズに適したマーケティング戦略を策定できます。

マーケティングの6Rの具体的な指標
それでは、6Rの具体的な意味を見ていきましょう。
上記の順番で解説するので、気になるところから読み進めてください。
1.Realistic Scale(市場規模)
Realistic Scale(市場規模)は、自社が参入する市場の規模を表す指標です。たとえば大きい市場には消費者が多く、販売する商品やサービスによっては高い利益が期待できます。しかし、強力な他社がいる可能性も高いので、ポジションの確立が困難になることも。
一方で小規模な市場は競合他社が少なく、マーケットによってはビジネスチャンスが期待できます。ただし、大規模の市場に比べると消費者の分母は多くありません。ニッチな市場を狙う際は、顧客単価や消費サイクルなどを調べ、自社の利益率を把握することが大切です。
2.Rate of growth(成長性)
Rate of growth(成長性)は、市場の成長率を表す指標です。たとえば「これから成長する市場」であれば、新規参入ができるチャンスがあるでしょう。一方で「成熟している市場」や「衰退が予想される市場」などに参入すると、事業に悪影響を与える可能性もあります。
「公益社団法人 全国出版協会」のニュースリリースによると、2023年出版市場は「紙+電子は2.1%減の1兆5,963 億円、紙が6.0%減、電子が6.7%増」*1と発表されています。つまり、データにおいて衰退が見られる紙媒体の出版市場への参入はリスクがあるのです。新たな市場に参入する際は成長率を見極め、適切な判断をしましょう。
3.Rank(顧客の優先順位)
Rank(顧客の優先順位)は、自社の製品やサービスに対する顧客の優先度を表す指標のこと。価格や利便性、製品デザインなどが挙げられます。たとえばデジタル出版市場は、インターネットやデジタルデバイスの普及により、「本の保管場所に困らない」や「好きなタイミングで読める」などのメリットが生まれました。これらの波及効果が、市場の成長を促進したと考えられます。
つまり、市場のトレンドやテクノロジーの発達などの社会的な動向も、顧客にとって関心度や優先順位が変化する要因です。情報発信のやり方も流行によって最適解が異なるので、市場の動向を見極めながら戦略を考えましょう。
4.Rival(競合状況)
Rival(競合状況)は、競合他社の状況や実力を把握するための指標です。具体的には商品の価格や品質、市場でのシェア率などが挙げられます。実店舗を展開するサービスであれば、店舗のエリアや立地環境などの地理的要因を調査することが大切です。
Amazonや楽天などで競合製品が販売されている場合、評価やレビューを確認して消費者の反応を調査できます。レビューの内容次第では、顧客の優先順位が理解できることも。競合他社の成功要因を深く分析すれば、自社に生かせる取り組みが見つかる可能性もあります。
5.Reach(到達可能性)
Reach(到達可能性)は、自社製品をターゲットにアプローチできるかどうかを判断する指標です。たとえば若年層のユーザーには、TikTokでの情報発信や広告配信などのプロモーションが有効です。一方、年齢層が高いユーザーやインターネット環境が整っていない地域では、チラシやDMといった媒体のほうが効果的かもしれません。
また、資金力やブランド力のある企業が市場に存在する場合、情報の到達頻度や知名度の差で消費者の関心を集めにくくなる可能性があります。したがってターゲットの属性だけでなく、投資できる予算や自社の影響力も考慮して発信方法を考えることが大切です。
6.Response(反応の測定可能性)
Response(反応の測定可能性)は、マーケティング施策の効果を測定できるかを判断するための指標のこと。たとえば利益率の向上を目標にする場合、「売上」や「集客率」などの計測が重要です。広告を使用する場合は費用対効果を分析する「ROAS」や、広告コンテンツの「滞在時間」や「離脱率」などが指標となるでしょう。
数値化が難しい「顧客満足度」や「消費者の購買理由」などは、5段階評価のアンケート調査を実施したり、顧客の声をジャンルごとに分類したりすることで一定の数値として計測できます。目標により必要な指標は異なるので、事前に測定方法も考えておきましょう。
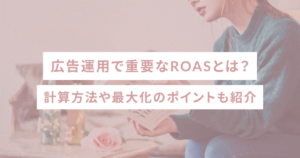
マーケティング戦略に6Rを活用するメリット
ここでは、6Rを取り入れることで得られる主な3つのメリットを紹介します。
自社の戦略立案にどのように生かせるのか、具体的にイメージしながら読み進めてみてください。
コストを抑えられる
6Rを活用することで、予算を押さえつつも効果的なターゲティングが可能になります。特に「Realistic Scale(市場規模)」や「Reach(到達可能性)」といった指標を使うことで、反応が見込める層に的を絞った施策を展開可能です。
たとえば、全方位に広告を出すよりも、成長性が高く自社商品に関心を持ちやすい層に絞ってアプローチすれば、無駄な広告費を抑えつつ成果が出やすくなります。まずは6Rの各項目に沿って市場を見直してみると、費用対効果の高い戦略が見えてくるはずです。
他社との差別化ができる
6Rを活用すると、競合と異なる市場や顧客層を見つけやすくなります。特に「Rank(顧客の優先順位)」や「Rival(競合状況)」を分析することで、他社とバッティングしないニッチなターゲット層を選定できるようになるでしょう。
たとえば、同じ商品を扱っていても、「女性」ではなく「子育てと仕事を両立している30代女性」に絞るだけで、他社との差別化が可能になります。狭い市場でも、自社の価値をしっかり届けられれば、高い成約率が見込めるでしょう。
コンバージョンの高い顧客を見いだせる
6Rを用いた分析では、実際に商品やサービスを利用している顧客層の特徴を具体的に把握できます。特に「Response(反応の測定可能性)」や「Rank(顧客の優先順位)」に注目してみてください。
たとえば、幅広い年齢層に広告を出していても、実際にコンバージョンしているのは特定の年齢や職業のユーザーだった、というケースもあります。こうしたデータをもとに対象を絞れば、確度の高い層へのリーチが可能です。
【失敗しないために!】6Rを活用する際の注意点
6Rを導き出す際は、以下のポイントを念頭に置き分析を行いましょう。
それぞれ順番に解説します。
適切なフレームワークを活用する
STP分析では、分析する指標に応じて有効なフレームワークが異なります。たとえばRival(競合状況)の指標を導き出す際は、内部環境と外部環境を比較して分析する「SWOT分析」や、市場の構造を把握できる「ファイブフォース分析」などが有効です。
ターゲティングに重要なRank(顧客の優先順位)を分析する際は、顧客視点で市場を分析する「4C分析」や、客観的な市場環境調査から戦略策定に役立つ「3C分析」などが活用できます。ビジネスのフェーズによっても必要なリサーチ内容は異なるので、自社に適したフレームワークを使って調査を進めましょう。
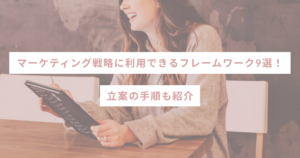
複数の要素で分析を行う
指標を割り出す際は、多角的な視点での現状分析が大切です。たとえばRank(顧客の優先順位)は商品の価格や利便性だけではなく、為替レートの変動やトレンドなど社会的要因にも左右されます。
また、強力な他社の参入により急速に変化するケースもリスクとして想定できるでしょう。6Rを基に分析を行う際は現在の市場を調査しながら、社会情勢や技術の発達、国内外の新規サービスなどにも目を向けて計画を立てることが大切です。
競合他社の成功要因を分析する
効果的な戦略を考えるなら、市場でポジションを確立している企業の成功要因を深く分析しましょう。成果を挙げている企業は、表面的には消費者のニーズに適した製品を提供しているだけに見えるかもしれません。しかし、実際には製品デザインや広告手法なども最適化されているケースがほとんどです。
他社の内面的な強みを分析して、自社の戦略を効果的にするヒントを見つけましょう。なお、企業の具体的な事例は以下の記事でも解説しているので、あわせて参考にしてください。
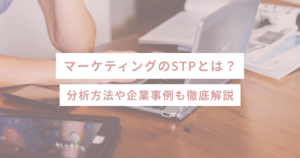
6Rを理解してマーケティング戦略の質を高めよう
6Rは、ターゲティングや市場分析の精度を高めるために非常に有効なフレームワークです。6つの指標を通じて「誰に・どのようにアプローチすべきか」を可視化することで、論理的に戦略を構築できます。6Rを上手く活用しながら、自社にあった方向性を考えてみてください。
6RやSTP分析といったマーケティングに関する指標やフレームワークは、専門的な知識であり、初心者が実務で使いこなすには難しいと感じるかもしれません。少しでも効率的に学びたい場合は、マーケティングを学習できるスクールの活用がおすすめです。
たとえば女性向けキャリアスクールSHElikes(シーライクス)のマーケティング関連コースでは、マーケティング戦略の考え方や効果的な情報発信の方法などを学習できます。デザインやライティングなどコンテンツ作成に必須のスキルも勉強できるので、ビジネスアイデアを形にするところまでの複合的なスキルが習得できるでしょう。
興味のある方は、ぜひ無料体験レッスンにお越しください。
※出典
*1:公益社団法人 全国出版協会 出版科学研究所|「出版指標」より