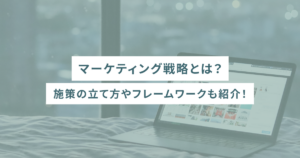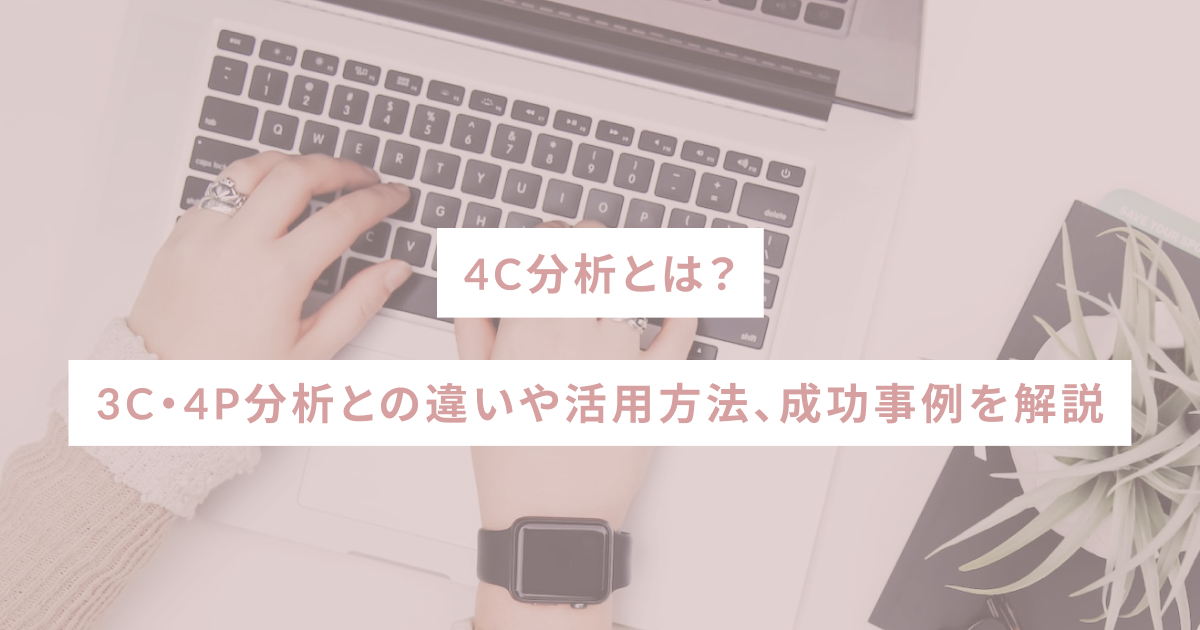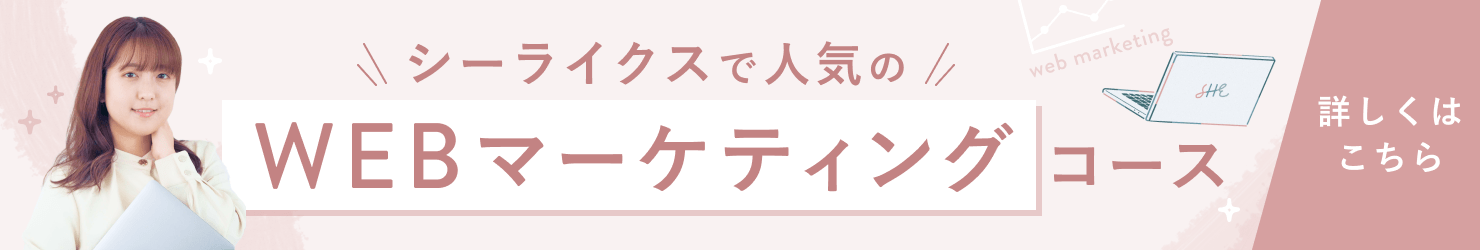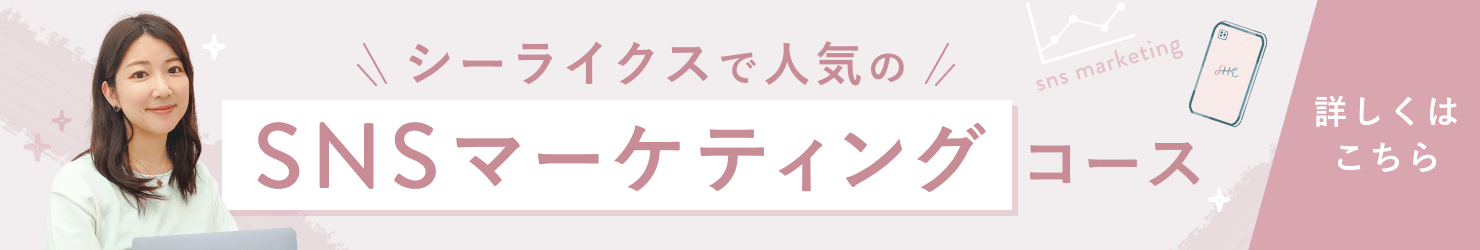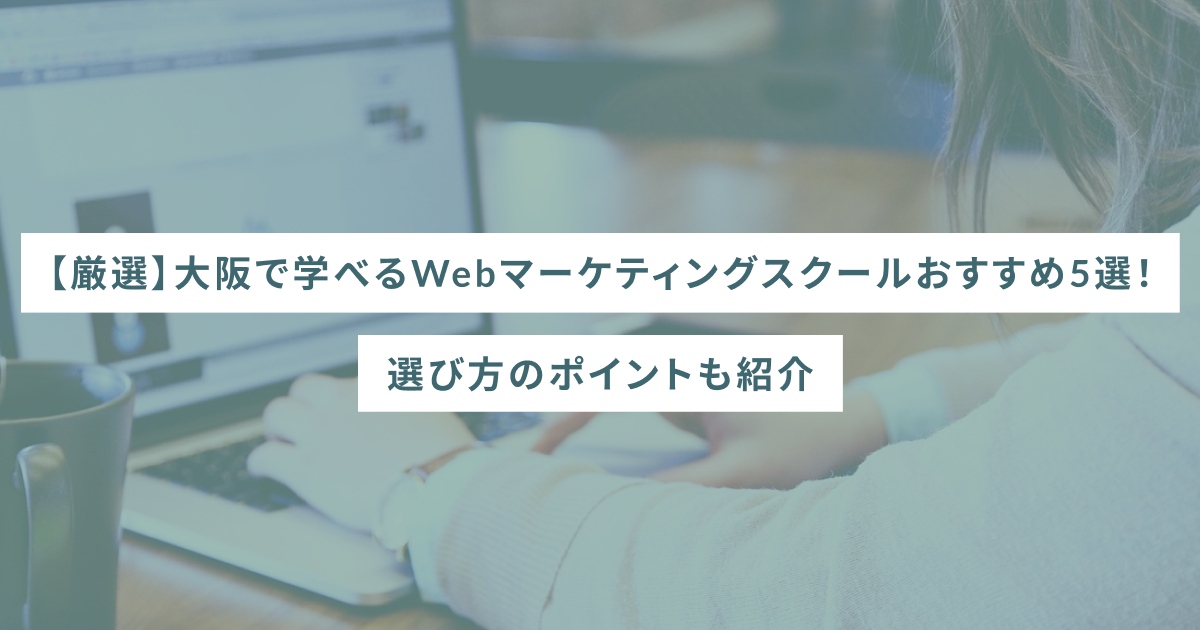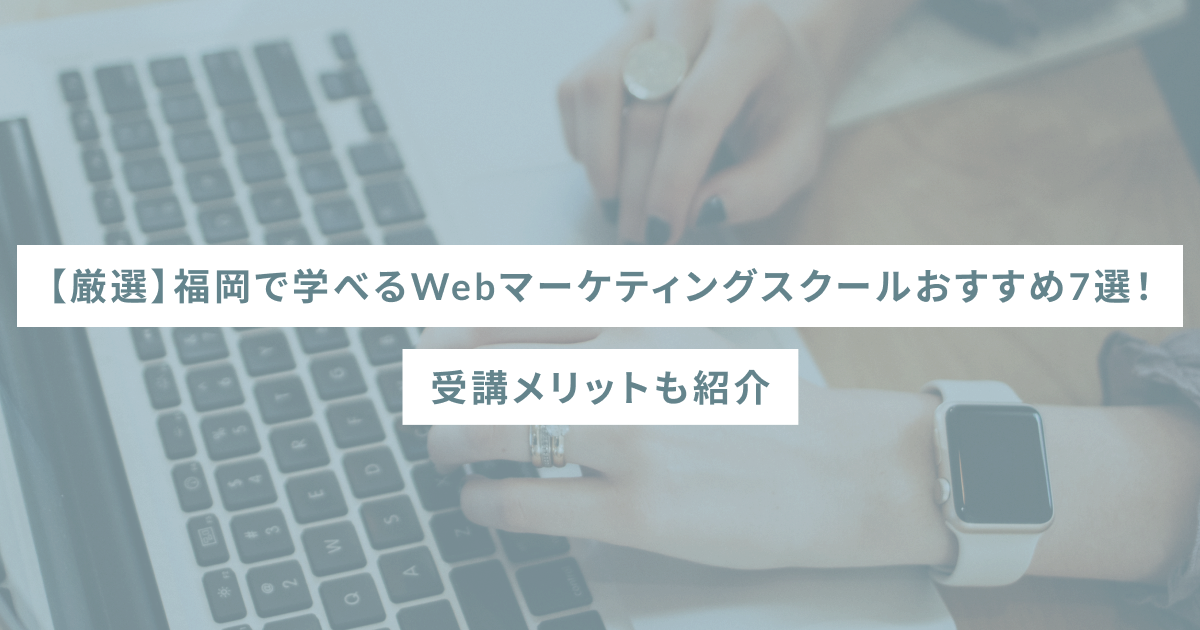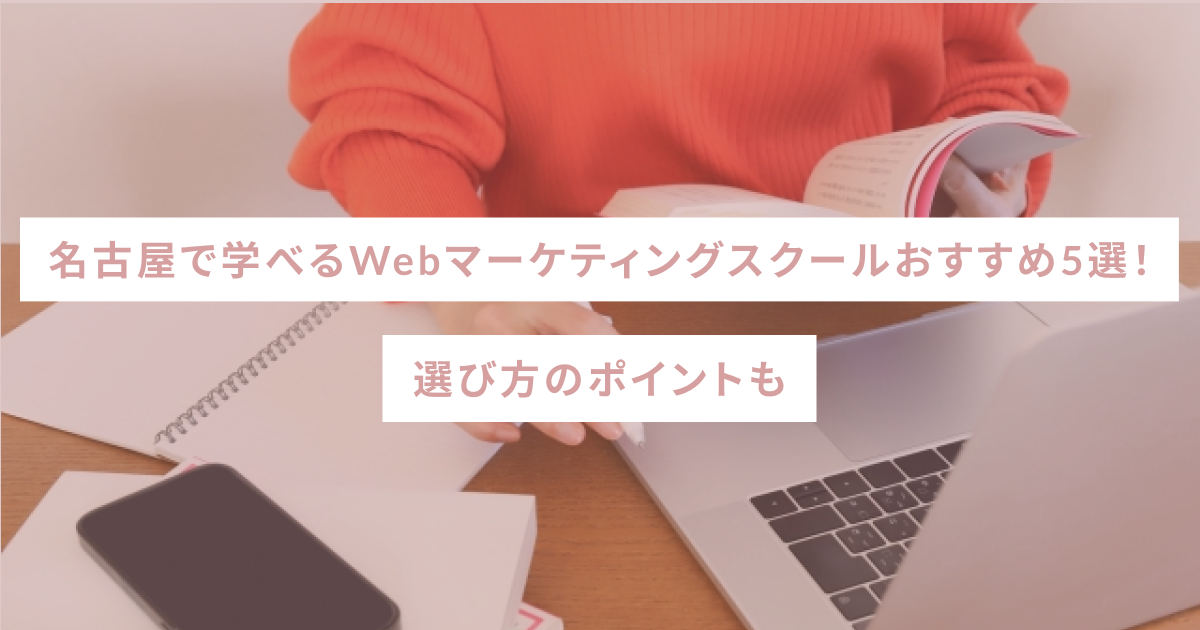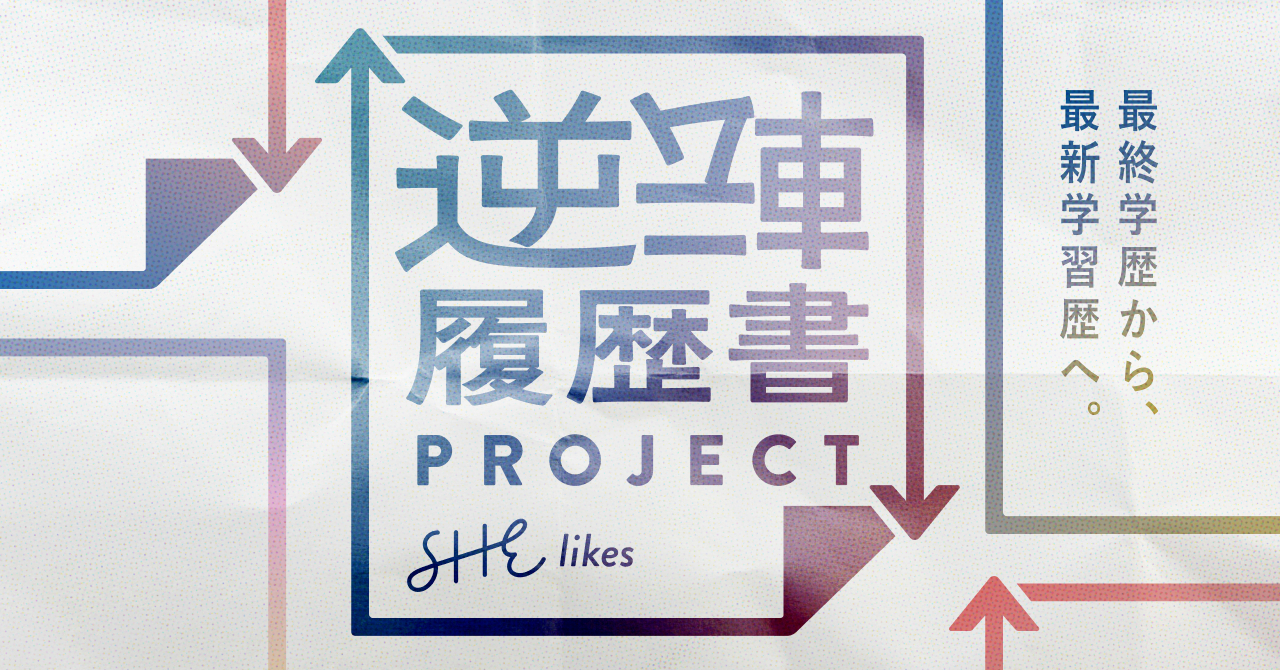4C分析は、有効的なマーケティング戦略や、市場に適した商品・サービス開発に役立つフレームワークの一つ。従来の4P分析とは異なり、消費者視点からアプローチすることで、顧客ニーズをより的確に捉えることが可能です。
本記事では、4C分析の各要素や活用方法のほか、活用事例まで詳しく解説します。マーケティングやサービスの開発・ブラッシュアップに活用したいという方は、ぜひ最後までご覧ください。
4C分析とは

4C分析とはCustomer Value(顧客価値)、Cost(コスト)、Convenience(利便性)、Communication(コミュニケーション)の頭文字を取ったマーケティング理論です。従来の4P分析を発展させたフレームワークとして知られています。
顧客視点に立って分析する点が特徴で、マーケティング戦略の立案や新規事業の立ち上げ、既存事業の見直しなどに活用されます。
4C分析の重要性
4C分析は、1990年代にアメリカのマーケティング理論家ロバート・ラウターボーンによって提唱されました。マーケティング市場の激化によって商品・サービスの差別化が求められるようになり、「企業視点ではなく顧客視点でのマーケティング戦略が重要」という考え方が広がり、4C分析の概念が誕生したのです。
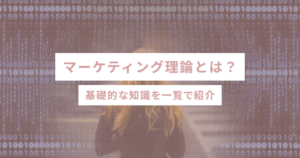
4C分析の各要素
ここからは、4C分析の各要素について紹介します。
顧客視点でのマーケティング戦略において重要な要素なので、それぞれ理解しておきましょう。
Customer Value(顧客価値)
4C分析におけるCustomer Value(顧客価値)とは、顧客のニーズや欲求に焦点を当て、製品やサービスがどのようにニーズを満たすかを考えるものです。商品の品質、他社との違い、デザイン、アフターフォローなどさまざまな要素が、顧客価値につながります。
顧客が抱える課題を洗い出し、その課題を解決させられる商品やサービスにこそ、顧客にとっての価値があるといえるでしょう。
Cost(コスト)
Cost(費用)が示すのは、製品やサービスにかかるコストだけではありません。顧客が商品を購入するまでの労力や時間、またその際の感情にも着目します。
企業としては、商品やサービスの製造・販売などの経費を価格設定に含めたいところ。しかし4C分析では、「顧客が設定された価格をどう捉えるか」といった視点を考慮します。
Convenience(利便性)
Convenience(利便性)とは、顧客にとって製品やサービスの購入がどれだけ便利であるかということ。従来の4P分析における「Place(流通)」と関連のある概念で、ECサイトなどの普及により、場所や時間に限定されない利便性が重要視され、求められるようになりました。
具体的には「この製品がどこで買えると便利か」「ECサイトはわかりやすいデザインか」といった、顧客視点での利便性について検討します。
Communication(コミュニケーション)
Communication(コミュニケーション)は、企業が顧客との対話を通じて信頼関係を築くことを目的とした概念です。従来の4P分析における「Promotion(プロモーション)」に該当する概念で、一方的な広告を意味します。
一方、4C分析のCommunicationでは、顧客と企業の双方向においてフィードバックをもとに、製品やサービスを改善するためのアプローチとして活用されます。実行する媒体は、イベント、SNS、広告などさまざまです。
他のフレームワークとの違い
ここからは、4C分析が従来の4P分析やほかのフレームワークと異なる点について解説します。
3C分析
3C分析とは、Customer(ターゲット顧客や市場)、Competitor(競合他社)、Company(自社)の3つの要素で構成されるフレームワークです。
4C分析が顧客の視点から商品やサービスを分析するのに対して、3C分析は競合や市場を分析して自社の強みと弱みを把握したり、市場におけるポジショニングを把握したりします。
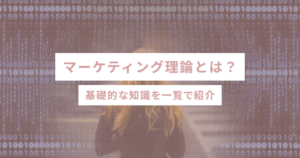
5C分析
5C分析とは、3C分析のCustomer(ターゲット顧客や市場)、Competitor(競合他社)、Company(自社)の要素に、Customer’s Customer(中間顧客)とCommunity(地域)の要素を加えたフレームワークです。
中間顧客とは販売代理店、卸売業者、流通経路など、自社と顧客の間に入る存在のこと。地域は、法規制、景気、世論など、事業に与える外部要因のことを指します。外部環境を分析できる2つの要素を加えることで、3C分析よりも多角的な分析が可能です。
4P分析
4P分析とは、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販売促進)の4つの視点から、マーケティング施策を立案するフレームワークです。
4C分析が「顧客視点」であるのに対し、4P分析は「企業視点」で要素を分析するのが特徴。商品開発や販促活動において、ターゲット市場にどうアプローチするかを考える際に有効です。
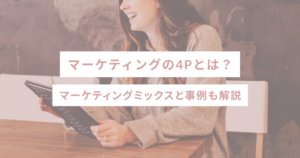
STP分析
STP分析とは、Segmentation(市場細分化)、Targeting(ターゲット設定)、Positioning(差別化戦略)の3段階で構成されるフレームワークです。
4C分析が提供価値を深堀りするのに対し、STP分析は「どの市場に」「どういったニーズの顧客に」を分析し、市場におけるポジションを明確化するフェーズに活用されます。4C分析と組み合わせることで、施策の方向性と具体性が増します。

SWOT分析
SWOT分析とは、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの要素から自社の内外環境を分析するフレームワークです。
4C分析が顧客目線でマーケティング戦略を立てるのに対し、SWOT分析は内部環境と外部環境から自社の現状を把握し、戦略立案の土台を築きます。4C分析を行う前にSWOT分析で自社への理解を深めることで、より正確な顧客ニーズを把握できるようになるでしょう。
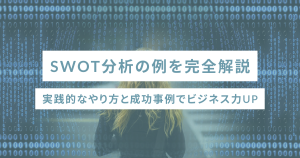
4C分析を活用するメリット
4C分析を活用すると、競合と差別化できたり、顧客にとっての付加価値が提供できたりと、さまざまなメリットがあります。
一つずつ詳しく見ていきましょう。
競合との差別化ができる
4C分析では、顧客のニーズや使いやすさを意識した「顧客視点」で商品やサービスを見直します。そのため、顧客にとって競合他社にはない価値のあるサービスの提供が可能です。
たとえば、価格よりも利便性や顧客サポートに重点を置くことで「価格が高くてもこの商品を使いたい」と思ってもらえるようになります。その結果、他社との価格競争に巻き込まれず、ブランド独自のポジションを確立しやすくなるでしょう。
顧客ニーズにあった商品を開発できる
4C分析は、企業視点での高性能な商品や目標達成を目指すのではなく、顧客にとっての価値や、顧客が支払う対価を重視します。ゆえに、実際のニーズに合った商品の開発やマーケティング戦略の展開が可能です。
顧客データや顧客フィードバックに基づいて分析を行うため、企業視点では見落としがちな細かな要望や不満まで気付けるでしょう。
付加価値の提供ができる
4C分析は顧客のConvenience(利便性)やCommunication(対話)など多角的な視点を取り入れるため、企業視点では見落としがちな細かな要望や不満まで気付くことができます。
購入後のサポート体制や使いやすい購入チャネルの整備など、顧客にとっての付加価値を提供しやすくなるのがメリットです。
【4C分析】活用のタイミング5つ
4C分析はさまざまな場面で活用できるフレームワークですが、とくに効果的に活用できるタイミングは以下の5つです。
各タイミングでの活用方法について、詳しく解説していきます。
1.新規製品やサービスを開発するとき
新規製品やサービスを開発するタイミングで4C分析を活用すると、顧客の潜在的なニーズや不満点を見出せるため、それらを解決する製品やサービスを設計できます。考慮すべきポイントは、顧客が「何を求め、何を課題に感じているか」という点です。
製品設計や戦略が立案できるだけでなく、顧客からのフィードバックを活かすことで、よりよい製品やサービスづくりへブラッシュアップすることもできます。
2.ターゲット市場を選定するとき
自社が参入すべきターゲット市場を選定する際も、4C分析は有効です。
顧客ニーズの高い市場セグメントを調査および選定し、Convenience(利便性)やCost(費用)を自社の対応力と照らし合わせることで、適したターゲット市場を選ぶことができます。
3.既存製品やサービスを見直すとき
既存製品やサービスを見直したいときにも、4C分析を活用できます。たとえば、製品やサービスをリリースしたあと顧客ニーズが変化していないか、既存製品やサービスが顧客ニーズを満たし続けられているか、といった点の確認が可能です。
また、物価高など経済情勢の変動が起きた際などに、既存の価格設定が適切であるかどうか、製品やサービスへの総コストが競合と比較して高くないか、といったコストの見直しにも活用できます。
4.ロイヤルティ向上のために戦略を立案するとき
マーケティング戦略を成功に導くためには、顧客ロイヤルティ(商品・サービスへの信頼・愛着)の向上も大切なポイントです。4C分析を活用すると顧客がリピートしたくなる理由や不満点を細かく抽出できるので、顧客ロイヤルティの向上につながる戦略を立てられます。
また、ロイヤルティ向上には顧客と消費者の長期的な関係性(顧客エンゲージメント)の構築が重要です。4C分析は商品・サービスのブラッシュアップにも有効的なので、長期的な関係構築にも役立つでしょう。
5.競合他社と差別化させるとき
顧客視点から自社製品やサービスを分析できる4C分析は、競合他社と差別化を図り、製品やサービスの競争優位性を確立したいときにも活用できます。
たとえば新製品の開発段階で4C分析を活用すれば、競合が見落としている顧客のニーズを満たすことが可能です。顧客が求めているものの競合が提供していない製品やサービスの開発につながるため、競合他社との差別化を図れるでしょう。
4C分析を行う際のポイント
4C分析を効果的に行うためには、適切なターゲット設定や、各要素の整合性を保つことが大切です。
それぞれ詳しく解説します。
ターゲットを定める
4C分析は顧客視点で戦略を練るフレームワークのため、まずどのターゲットに向けた商品・サービスかを明確にすることが重要です。
年齢層やライフスタイル、価値観などを具体的に設定すれば、「スマホの利用時間が長いから、SNS広告を充実させよう」「仕事のあとに利用できるよう、営業時間を工夫しよう」など、各要素を具体的に設定できます。
それぞれの要素の整合性を保つ
4C分析の4つの要素は相互に関連し合っているため、各要素の整合性を意識して設定する必要があります。たとえば、高価格な商品を提供する場合には、顧客にとって価格に見合ったCustomer Value(顧客価値)やConvenience(利便性)が必要です。
それぞれの要素の影響を意識して、一貫性のある戦略設計を立てましょう。
STP分析で自社のポジションを明確にしておく
4C分析を効果的に行うには、あらかじめSTP分析で自社の市場におけるポジションを明確にしておくのが有効です。
STP分析を通して適切なターゲット市場を選定したり、自社の強み・弱みを整理したりすることで、戦略を立てる土台が整います。そうすれば、4Cの各要素を具体的かつ適切に設定しやすくなるでしょう。
4C分析の活用事例3選
ここからは、4C分析を活用して成功した以下の3つの企業事例を紹介します。
各企業がどのように4C分析を行なっているか、ぜひ参考にしてみてください。
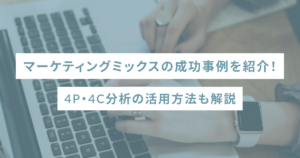
スターバックスコーヒージャパン株式会社
| 顧客価値 | 単なるコーヒーショップではなく、「第三の場所」を求めるニーズに応える |
|---|---|
| コスト | 価格競争ではなく、顧客が感じる「価値」を重視 |
| 利便性 | 都市部や商業施設など、簡単に利用できる場所に展開 |
| コミュニケーション | 名前を呼びオーダーを確認するなど、パーソナルな接客 |
スターバックスコーヒージャパン株式会社は、顧客中心のマーケティング戦略を通じて成功を収めている企業です。こだわりのコーヒーを提供するだけでなく、「コーヒーを飲む空間そのもの」に付加価値を提供しています。
また、他のコーヒーチェーン店と比較するとやや高価格帯に位置しますが、顧客に納得感と満足感を与えるマーケティング戦略により、ブランドロイヤルティを高めることに成功しているのも特徴といえるでしょう。
ファーストリテイリング(株式会社ユニクロ)
| 顧客価値 | 高品質で手頃な価格の衣類を提供 |
|---|---|
| コスト | 商品企画・生産・物流・販売まで自社で行うことにより低価格を実現。 セールや特典、アプリ限定クーポンの配信によるコストメリットの提供 |
| 利便性 | 広範な店舗展開とオンラインストア展開による利便性向上 |
| コミュニケーション | 持続可能性に関する取り組みの発信や、SNSを通じた双方向のコミュニケーションによるロイヤルティ向上 |
ファーストリテイリング(株式会社ユニクロ)は、高品質な衣類を低価格で身に付けたいという顧客ニーズを的確に捉えた戦略により、手頃な価格と高い利便性を両立させています。とくに、シンプルで機能的なデザイン、広範な店舗ネットワークやECサイト・アプリ展開による利便性の向上により、顧客満足度を向上させている事例です。
サステナビリティに配慮したブランドイメージを広告に打ち出し、ブランドそのものの長期的な将来性を伝えることで、ブランド価値向上にもつながるよう工夫しています。
コメダ珈琲店
| 顧客価値 | 長年愛される定番メニューで、幅広い層がくつろげる空間を工夫 |
|---|---|
| コスト | モーニングサービスやフードのボリュームの大きさなど、お得感のある価格戦略 |
| 利便性 | 郊外型の大型店舗展開や早朝開店の店舗展開 |
| コミュニケーション | 親しみやすい接客と地域密着型のプロモーションによる信頼形成 |
コメダ珈琲店は、顧客が「くつろぎの空間」を満喫できるよう価値を提供しています。競合他社と比較すると価格設定はやや高価格ながらも、価格以上の居心地の良さやフードのボリューム感を提供し、顧客へ高い満足感をもたらしているのが特徴です。
また、店舗の立地や営業時間に工夫したり、期間限定メニューやコラボ企画を行ったりすることで顧客と深い関係を築き、リピーターを獲得しています。
4C分析の理解を深めるには、マーケティングスキルの習得が大切!

4C分析を効果的に行うなら、マーケティングの基礎知識が必要です。マーケティングの基礎を身に着けたうえで4C分析を活用すれば、より顧客にとって価値のある体験が提供できるようになります。
たとえば、女性向けオンラインキャリアスクールSHElikes(シーライクス)では、マーケティングの基礎知識が学べる「マーケティング入門コース」のほか、より実務に活かせる「Webマーケティングコース」など、全50以上の職種スキルが学び放題です。
マーケティングや商品・サービス開発に興味がある方は、ぜひ一度無料体験レッスンへ参加してみてはいかがでしょうか。