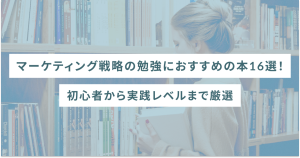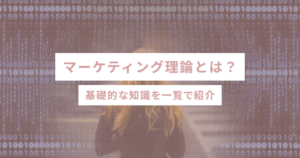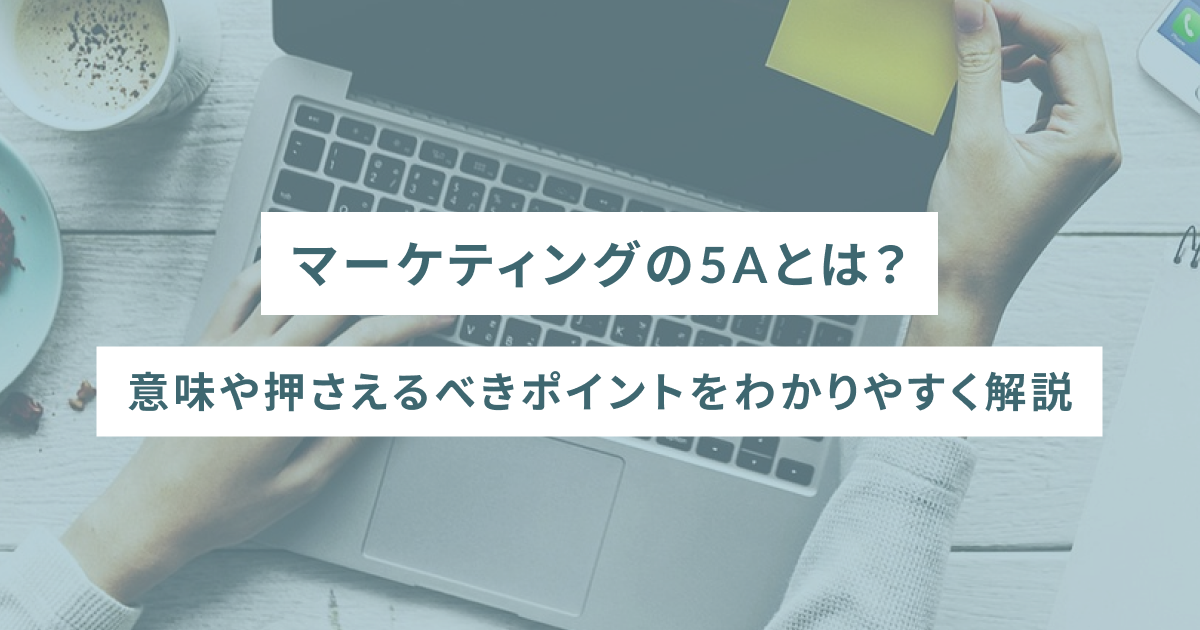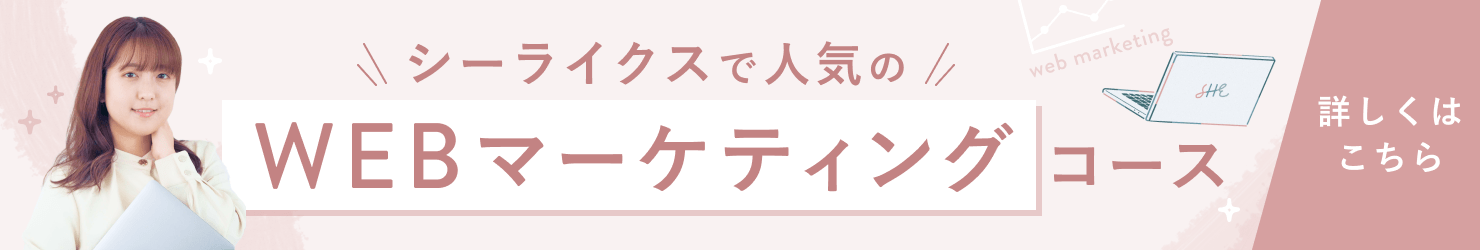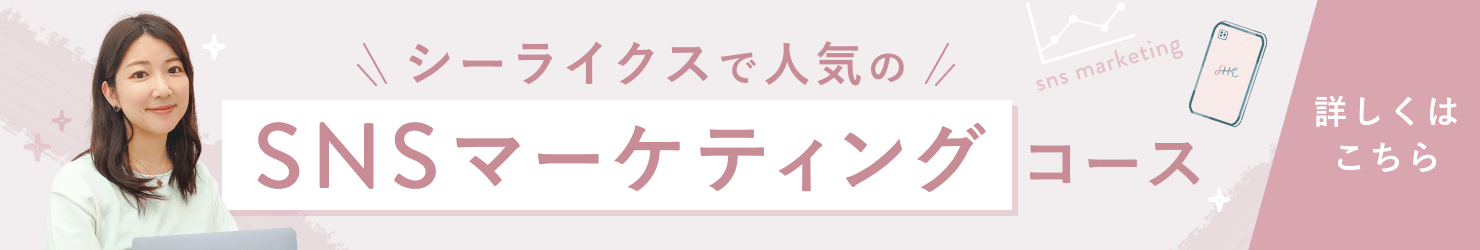モバイル端末やSNSの普及により、消費者の購買行動は大きく変化しています。そのような現代の消費者心理を読み解くために注目されているのが5A理論に基づくマーケティングです。顧客がどのように行動し、企業やブランドと関わっていくのかを5つのステップで可視化したこの理論は、効果的なマーケティング戦略を立てるうえで欠かせません。
そこで今回は、5A理論の概要や、押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。5A理論を正しく理解し、マーケティングに役立ててください。
5A理論はコトラーによる新たなカスタマージャーニーの考え方
5A理論とは、アメリカの経済学者であり「マーケティングの父」と称されるフィリップ・コトラーが提唱した、現代の消費者の購買プロセスをとらえるマーケティングモデルです。5A理論では、顧客が商品やサービスに出会ってから購入に至るまでのカスタマージャーニーを、5つのステップで表します。
テクノロジーの進化や社会構造などの時代の流れに合わせて、マーケティングも以下のように5つのフェーズで進化しています。
| フェーズ | 特徴 | マーケティングの方向性 | 企業の役割 |
|---|---|---|---|
| マーケティング1.0 | 製品思考 | 商品やサービスを作る側が主導 | よりよい製品を作る |
| マーケティング2.0 | 顧客志向 | 顧客ニーズをキャッチ | 顧客満足を追求する |
| マーケティング3.0 | 人間思考 | 感情や価値観に訴える | 社会的責任を果たす |
| マーケティング4.0 | 消費者の自己実現 | デジタルとアナログの融合 | 顧客と関係を築く |
| マーケティング5.0 | テクノロジー×人間 | 最先端技術を活用 | テクノロジーを倫理的かつ創造的に活用 |
このうち、マーケティング4.0において、コトラーが提唱しているのが5A理論です。「自己実現」を目指す消費者に対して購買を促進し、消費者の情報拡散により顧客を増やすことを目指すのが、マーケティング4.0の特徴となっています。
また、コトラーによると、2020年代はマーケティング5.0のフェーズに入ったとされており、マーケティング4.0の「自己実現」を引き続き重視しつつ、AIやビッグデータなどの新しいテクノロジーを活用していく時代になったとされています。
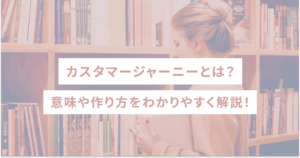
5Aの各ステップの詳細
5Aでは、消費者の購買プロセスであるカスタマージャーニーを以下の5つのステージでとらえます。それぞれのキーワードの頭文字をとって、5Aと呼ばれています。
この理論以前では、最終的なゴールを購入などの行動に位置づけるのが一般的でしたが、5A理論では最後のステップを推奨としているのが特徴です。それぞれのステップの詳細を解説します。
認知(Aware)
認知(Aware)は、消費者が最初に商品やブランドの存在を知る段階を指します。商品やサービスを購買につなげるには、まず認知してもらうことが第一ステップです。最近は広告だけでなく、SNSやPRなどが認知の役割を担っています。また、友人や知人の口コミが認知のきっかけになることもあります。
<認知の一例>
- インフルエンサーが商品を紹介する投稿を見る
- SNSやテレビCM、Web広告などで受動的に商品情報を知る
- 家族や友人との会話の中でブランド名を耳にする
認知の段階では、消費者はまだ関心があるわけではなく、店頭で商品を見たときに「この商品を見たことがある」と思うなど、ただ商品やサービスを知っているという状態です。ここで注目を集め、記憶に残ることが次のステップへ進むための第一歩となります。
訴求(Appeal)
訴求は、消費者が商品やブランドに対して魅力を感じ、興味を持ち始める段階です。認知したたくさんの商品やサービスのうち、いいなと思うポイントがあり検討の対象に入った状態を指します。
<訴求の一例>
- SNSで見た商品に興味を持ち、公式アカウントをフォローする
- テレビCMやWeb広告に惹かれて、ブランド名を記憶する
- 家族や友人におすすめと聞き、気になり始める
訴求の段階では、商品やサービスの特徴やメリットを強調し、消費者が購入・利用したくなるよう導くことが重要です。
調査(Ask)
調査は、消費者が主体的に商品やサービスの情報を収集する段階です。現代の消費者は、商品やサービスの購入にあたって、常に比較検討を行います。情報収集に使用されるのは、Webサイトの情報やSNSなどの口コミ・レビュー、知人の意見などです。
<調査の一例>
- インターネット検索で評価やレビューを確認する
- 商品を提供している企業に質問や問い合わせを行う
- 商品を使用している友人に感想を聞く
信頼できる情報源からの評価やほかの消費者の体験談が、この段階での決定に大きな影響を与えます。企業に問い合わせるなど直接コミュニケーションを取るケースも少なくありません。
疑問や不安に寄り添った丁寧な対応が、次のステップに進んでもらうポイントになります。
行動(Act)
行動は、消費者が実際に商品を購入したり、サービスを利用したりすることを決める段階です。調査によって得た情報で強い魅力を感じた場合に、行動に至ります。
<行動の一例>
- 店舗で購入する
- サービスを契約する
- 顧客登録を行う
購入時の疑問への迅速な対応、購入のしやすさ、期間限定のキャンペーンなどの要素も、購入決定の後押しとなります。また、購入した商品やサービスを利用することや、アフターケアを受けることなども、行動に含まれます。
推奨(Advocate)
推奨は、商品やサービスを購入した消費者が満足し、その経験を自発的にシェアする段階です。現代は、SNSやブログなどで個人が情報を発信することも珍しくありません。ほかの人に商品やサービスを勧めたくなるのは、感情を動かされたときです。
商品やサービスのファンになった消費者は、積極的に推奨してくれます。
<推奨の一例>
- 商品を継続利用する
- サービスの契約を更新する
- SNSなどを通してほかの人におすすめする
近年はSNSを通じて推奨情報が広まりやすくなりました。購入や契約の意志決定にそのような情報が大きな影響を与えるようになったというのが、5A理論の大きな特徴です。「推奨」の段階において重要なのが、リピーターを作り、ブランドのファンを育てることです。
顧客が自然に推奨してくれるような商品やサービスを提供することが、成果につながる重要な要素になります。
5A理論で押さえるべきポイント
5A理論をマーケティングに活用するにあたって、押さえるべきポイントは以下の3つです。
それぞれ詳しく解説します。
顧客同士のつながりが重要に
5A理論の大きな特徴のひとつは、顧客同士のつながりが購入に与える影響の重要性が増している点です。現在は、SNSや口コミ、レビューサイトなどで顧客が自発的に情報を発信し、他者に影響を与えることができます。
特に「推奨」の段階では、商品やサービスに満足した顧客が自発的にブランドを推奨し、ほかの潜在顧客にアプローチするのがポイントです。そのため、商品やサービスを提供して終わりではなく、顧客と継続したコミュニケーションの場を設け、ニーズや不満を汲み取り適切に対応していくことが、「推奨」を得るために必要となります。
デジタル化やSNSの普及で購買プロセスが複雑化
SNSやモバイル端末の普及により、消費者の購買プロセスは複雑化しています。商品やサービスの購買にあたって、消費者はSNSにおける情報や口コミを重視するようになり、購入前に複数の情報源をチェックすることが一般的です。
そのため、従来のようにテレビCMやポスターなどの一方通行の広告だけでは、消費者の心をつかむことが難しくなっています。そのため、企業はデジタルとリアルの両方のチャネルを駆使して消費者との接点を増やし、購買意欲を引き出す必要があります。
デジタルとリアルを組み合わせた施策が重要
デジタル化が進む今、重要視されているのはオンラインとオフラインを融合させた施策です。消費者がまずオンラインで情報を集めてから店舗で商品を見たり、逆に店舗で商品を体験したあとにオンラインで購入したりするケースが増えており、5A理論でもそうした行動に注目しています。
デジタルとリアルをうまく組み合わせた体験を提供することで、消費者の満足度を高め、購買までの流れをスムーズに進めることができます。
ほかのフレームワークとの違い
5A理論は、ほかのフレームワークとどう違うのでしょうか。
それぞれ理解していきましょう。
AISASとの違い
AISASは、消費者の購買プロセスを以下の5つの段階に分けたフレームワークです。
- 注意(Attention):商品やサービスを知る
- 関心(Interest):商品やサービスに関心を示す
- 検索(Search):インターネット検索で評判を調べる
- 購買(Action):店舗やECサイトで購買する
- 情報共有(Share):SNSなどで情報共有する
5AとAISASは比較的近い考え方ですが、インターネットに限定されているかどうかという点が違います。AISASの「検索」や「情報共有」は、インターネットに限定した行動です。それに対して5Aの「調査」や「推奨」は、オンラインやオフラインを限定していません。
AIDMAとの違い
AIDMAは、サミュエル・ローランド・ホールが提唱したマスマーケティングが主流の時代のフレームワークです。購買プロセスは以下のようになっています。
- 注意(Attention):商品やサービスを知る
- 興味(Interest):関心を持つ
- 欲求(Desire):商品やサービスを欲しいと感じる
- 記憶(Memory):商品やサービスを記憶する
- 行動(Action):商品やサービスを購入する
AIDMAは単方向的なコミュニケーションとなっているのに対し、5A理論では双方向のコミュニケーションと関係性の構築に重点を置いています。
4Aとの違い
4Aは、マーケティング施策において、訪れた消費者に購入してもらうことやリピーターになってもらうことを重視したフレームワークです。
- 認知(Aware):商品やサービスを知る
- 態度(Attitude):興味や関心などの感情を持つ
- 行動(Act):商品やサービスを購入する
- 再行動(Act again):使用したうえで再購入する
4Aは「再行動」というフェーズがゴールとなっています。それに対して5Aは、消費者が周囲の意見を参考にしながら購買判断をする流れを反映し、「推奨」がゴールとなっています。顧客が商品やサービスをどのように評価して推奨するかというプロセスに着目した、より顧客視点の考え方になっているということです。
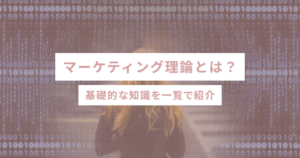
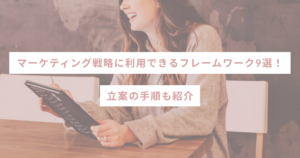
5A理論を取り入れたマーケティングで顧客の心をつかもう!
今回は、マーケティングで欠かせない5A理論について解説しました。5Aは、現代の消費者行動を理解し、効果的な戦略を立てるために欠かせないフレームワークです。認知から推奨までの各ステップを押さえ、顧客との関係を深めるために5A理論を活用しましょう。
マーケティングについて詳しく学ぶなら、女性向けキャリアスクールSHElikes(シーライクス)がおすすめです。SHElikesは、全50以上の職種スキルが学び放題のオンラインスクール。マーケティングの概要から実践的なスキルまで丸ごと学べる、さまざまなコースを用意しています。
SHElikesでマーケティングの知識を深めたいなら、まずは無料体験レッスンに参加してみてください。