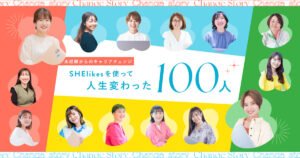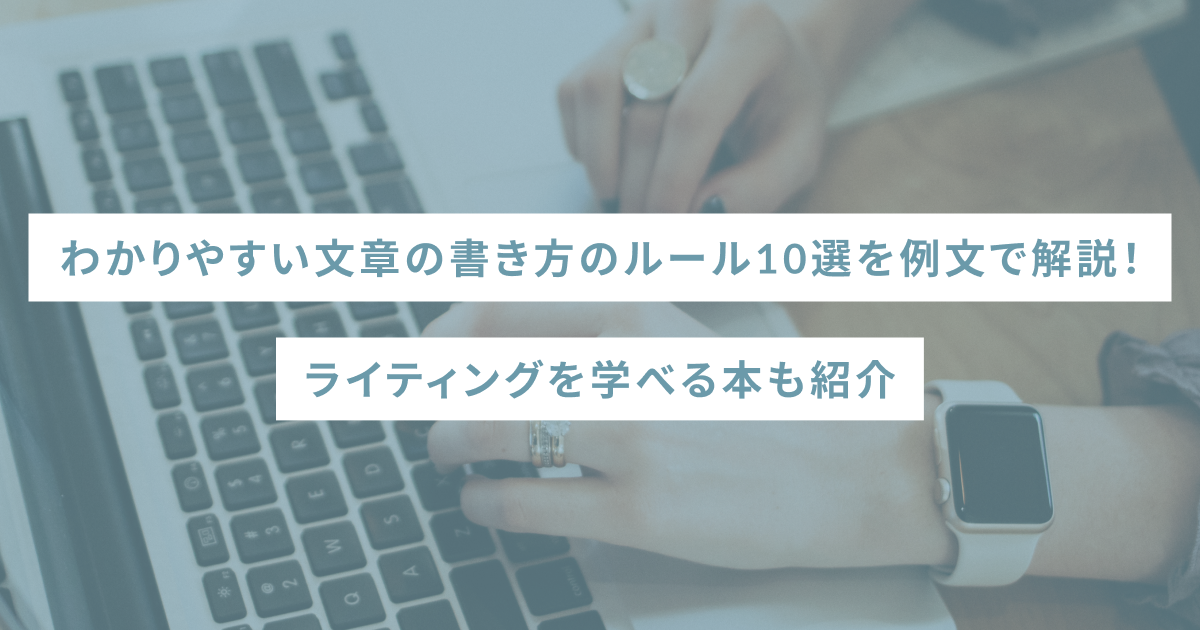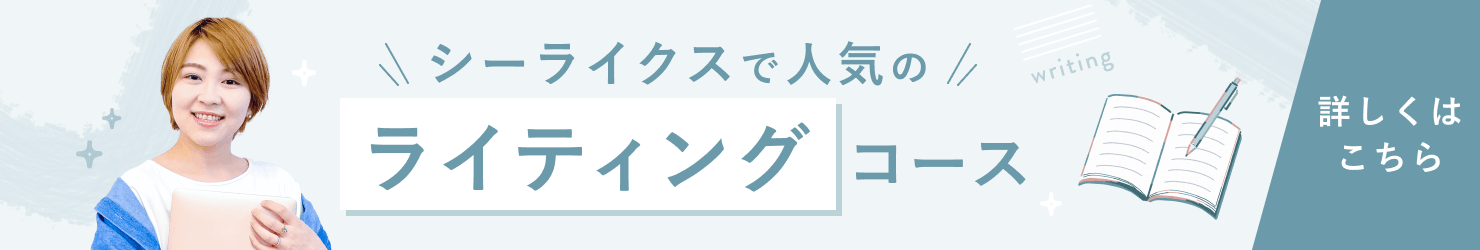職場での資料作成や転職時の自己PR、ブログなど日常のあらゆる場面で「文章をわかりやすく伝える力」が求められます。
一方で、「文章を書くのに時間がかかる」「文章を書いたものの、うまく伝わるか自信がない」そんな悩みを感じる方は少なくないでしょう。実際に、文章は書き方ひとつで相手への伝わりやすさが大きく変わります。
この記事では、簡単に実践できる文章の書き方のルール10選を、具体例とともに解説します。文章力を磨くためのアウトプット方法や、学習に役立つ本も紹介するので、ぜひ最後まで読んでみてください。
わかりやすい文章の書き方のルール10選!
わかりやすい文章を書くためには、センスや才能ではなく、基本的なルールを身につけることが大切です。基本的なルールは主に以下の10個です。
- 一文を短くする
- 結論を最初に書く
- 主語と述語を近づける
- 主語をはっきりと書く
- 文末を回りくどくしない
- 適切な位置に読点を置く
- 修飾語は被修飾語の直前におく
- 不要な接続詞を削る
- 指示語を多用しない
- 抽象的な表現を避ける
それぞれ解説します。
一文を短くする
一文は短くすると読みやすく、読者が理解しやすくなります。情報を詰め込みすぎると論点がぼやけ、伝えたいことが伝わりにくくなってしまうでしょう。
修正前:彼は、川沿いにできた新しいカフェに行き、チーズケーキとカフェラテを注文し、読書をして過ごした。
修正後:彼は、川沿いにできた新しいカフェに行った。そこでチーズケーキとカフェラテを注文し、読書をして過ごした。
同じ主語を持つ内容であっても、2つに分割することによって文章の構造がシンプルになります。一文に盛り込む情報を絞り、文を短く簡潔にすることを意識しましょう。
結論を最初に書く
文章は、結論を最初に書くことで、読者に伝わりやすくなります。結論を先に述べることで、読者は文章の主旨をすぐに理解できます。理由や説明を先に書くと、何を伝えたいのかが分かりづらくなってしまうでしょう。
修正前:私たちは普段から理由を先に考えて、結論を出していますが、文章の場合は順序が逆です。結論が先に述べてあることで、その文章が伝えたい内容が明確になります。わかりやすい文章とは、結論が最初に書かれている文章です。
修正後:わかりやすい文章とは、結論が最初に書かれている文章です。私たちは、普段から理由を先に考えて結論を出していますが、文章の場合は順序が逆です。結論が先に述べてあることで、その文章が伝えたい内容が明確になります。
結論を先に提示することで、読み手は内容を素早く理解できます。結論を最初に書くことで、読者がスムーズに理解できるため、文章全体の意図が明確になるでしょう。
主語と述語を近づける
主語と述語を近づけると、文章が分かりやすくなります。主語と述語が離れていると、読者は文の構造を理解するのに時間がかかってしまうでしょう。特に、間に修飾語や別の情報が入ると、主述の対応が分かりにくくなります。
修正前:私の兄で、大学でサッカー部に入っていて、とても運動が得意な太郎が、サッカーの試合でゴールを決めました。
修正後:私の兄の太郎が、サッカーの試合でゴールを決めました。大学ではサッカー部に入っていて、とても運動が得意です。
正確な情報を相手に伝えるためには、主語と述語を近づけることを意識しましょう。
主語をはっきりと書く
主語をはっきりと書くことで、文章の意味が分かりやすくなります。主語が曖昧だと、誰が何をしたのかが読者に分かりにくくなってしまうでしょう。
修正前:読める文章を意識しましょう。
修正後:書き手は読める文章を意識しましょう。
主語を明確にすることで読者に誤解を与えず、伝えたいことが正しく伝わります。
文末を回りくどくしない
文末を簡潔にすると、読みやすくなります。回りくどい表現は、読者にストレスを与え、文章の印象を悪くします。
修正前:今後の状況を踏まえた上で、慎重に検討を重ねる必要があるのではないかと思われます。
修正後:この件は、今後の状況を見て検討します。
文末をすっきりさせることで文章が引き締まり、読者にとって、分かりやすい文章になります。
適切な位置に読点を置く
読点の位置に厳密なルールはありませんが、誤読を防ぐために適切に打つことが重要です。読点を適切に配置すると、文章が格段に読みやすくなります。読点がないと、文の意味が誤解されることがあります。
例文1:刑事は、血まみれになりながら逃げた強盗を追いかけた。
例文2:刑事は血まみれになりながら、逃げた強盗を追いかけた。
このように、読点の位置によって、文章の意味が変わります。読点を適切に配置し、スムーズな文章になるよう心がけましょう。
修飾語は被修飾語の直前におく
修飾語は被修飾語の直前におくと、文の意味が明確になります。修飾語とは、ある語句の状況や見た目、事情を説明する語のことで、修飾語が説明する語を被修飾語と呼びます。修飾語と被修飾語が離れると、どの語句を説明しているのかが分かりにくくなり、誤解を招く可能性があります。
例文1:私は昨日、友人が買った本を読んだ。
例文2:私は、友人が昨日買った本を読んだ。
適切な位置に修飾語をおくことで、読者に意味が伝わりやすくなるでしょう。
不要な接続詞を削る
不要な接続詞を削ると、文章が簡潔になります。接続詞が多すぎると、読みにくくなり、読者に冗長な印象を与えます。接続詞は、因果関係が明確であれば、省略しても問題ありません。
修正前:彼はとても疲れていた。しかし、それでも最後まで仕事を終わらせた。
修正後:彼はとても疲れていた。それでも最後まで仕事を終わらせた。
文章は、接続詞を適切に削り、テンポのよい文章を心がけましょう。
指示語を多用しない
「これ」や「それ」のような指示語を多用しないことで、文章の意味が明確になります。指示語が多すぎると、どの事柄を指しているのかが分かりにくい文章になります。特に、長文になると「これ」「それ」が何を示しているのか混乱しやすくなるでしょう。
修正前:これは簡単だが、それを実践するのは難しい。
修正後:言うのは簡単だが、実践は難しい。
「わかりやすさ」と「簡潔さ」のバランスを考えて、指示語は適切に使いましょう。目安として、5,000文字の記事に2〜3個が適量です。
抽象的な表現を避ける
抽象的な表現は、読者にとって曖昧で伝わりにくいことがあります。抽象的な表現を避け、具体的な言葉を用いることで、読者に明確なイメージを伝えられます。
修正前:ツールを導入すれば、業務を効率化できます。
修正後:ツールを導入すれば、日報を書く30分を顧客対応に使えます。
抽象的な表現ではなく、数字や具体的な事例を用いることで、説得力が増す文章になるでしょう。
もっとわかりやすい文章の書き方のコツを知りたい方におすすめの本
「わかりやすい文章を書きたいけれど、どうすればいいのかわからない……」という悩みを抱える方に向けて、わかりやすい文章の書き方を学べるおすすめの本を紹介します。
- 『「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』著:藤吉 豊 、小川 真理
- 『20歳の自分に受けさせたい文章講義』著:古賀史健
- 『伝わる文章が「速く」「思い通り」に書ける 87の法則』著:山口拓朗
『「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』著:藤吉 豊 、小川 真理子
『「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』は、文章術に関する名著100冊を精読し、その共通するエッセンスを抽出・ランキング化した書籍です。 この本は、文章作成の基本からプロの技術まで、段階的に学べる構成となっています。
特徴として、1位から7位は「基本的な文章術」、8位から20位は「ワンランク上の文章術」、21位から40位は「プロの文章術」と、ランキング形式で重要ポイントを整理しています。
ライティング初心者からプロまで、幅広い層に役立つ内容で、文章力を高めたい方におすすめの一冊です。
『20歳の自分に受けさせたい文章講義』著:古賀史健
『20歳の自分に受けさせたい文章講義』は、文章を書くことに悩む人々に向けて執筆された本です。この本では、多くの人が「話せるのに書けない」理由を分析し、そのギャップを埋める方法を提示しています。文章のリズムや構成の重要性を説き、具体的な書き方の技術を紹介しているのが特徴です。
読者視点で文章を見直す重要性を強調したり、推敲の技術にも触れてより洗練された文章を生み出す方法を解説したりしています。
単なる文章術の解説にとどまらず、書くことへの考え方や姿勢を深く掘り下げています。初心者からプロのライターまで、幅広い層に役立つ内容です。
『伝わる文章が「速く」「思い通り」に書ける 87の法則』著:山口拓朗
『伝わる文章が「速く」「思い通り」に書ける 87の法則』は、効果的な文章作成のための実践的な87個の法則をまとめた本です。
この本では、文章を書く際の準備から速く書く方法、簡潔で分かりやすい表現、正確な日本語の使い方など、幅広いテーマの文章の書き方のコツがを具体的にまとめられています。
さらに、MicroSoft Wordの活用法やブログ・SNS投稿の書き方など、現代のメディアに応用できる知識も充実しています。文章に自信がない人や、より伝わる文章を書きたい人におすすめの一冊です。
文章力を磨くためのアウトプットの方法
文章力を磨くためには、インプットだけでなく、実際に書いてアウトプットすることが不可欠です。一方で、ただ書くだけでは思うように成長しないこともあります。ここでは、 文章力を効果的に磨くためのアウトプット方法を紹介します。
ブログなどで定期的に文章を書く
ブログなどで文章を定期的に書くことは、文章力を磨くために効果的です。継続的な執筆によって表現力や構成力が磨かれ、論理的に伝える力が鍛えられます。
情報を整理して的確に表現する練習にもなるため、わかりやすい文章を書くスキルはもちろん、語彙や表現の幅も広がるでしょう。またブログを書くことで過去の記事と比較できるため、成長を実感し継続のモチベーションにつながります。
さらに、ブログはポートフォリオとして活用できるため、ライターとしての実績を示す作品集としても役立ちます。まずは短い記事から書き始め、定期的な執筆を習慣化することが大切です。
人に読んでもらう機会を作る
文章力を向上させるには、人に読んでもらう機会を作ることが重要です。書きっぱなしでは、文章の伝わりにくい表現や改善点に気づきにくいものです。他の人に読んでもらい、良い点と悪い点を指摘してもらうことで、よりわかりやすく、魅力的な文章が書けるようになります。
たとえば、自分の文章を媒体で公開したときに、友人から率直な意見をもらえれば、自分では気づけないポイントが明確になります。先に友人に読んでもらってから、ブログなどに公開するのもよいでしょう。
他の人からのフィードバックを積極的に取り入れつつ、プロの文章を参考にしながら改善を重ねることで、伝わる文章が書けるようになります。
女性向けキャリアスクールSHElikesなら文章力が磨ける!
文章力を磨きたいものの、学習方法がわからない方におすすめなのが、女性向けキャリアスクールのSHElikes(シーライクス)です。
SHElikesの「ライティングコース」では、ライティングの基礎知識を身につけられます。相手に伝わる文章の書き方がわかるだけではなく、ライターとして必要な知識も学べるのが特徴です。SEOライティングやインタビュー記事の書き方といった副業につながる専門スキルも習得できます。
SHElikesでは課題を通してアウトプットの機会があったり、TA(ティーチングアシスタント)によるフィードバックも受けられたりします。そのため、独学では得られない実践的な学びが得られるでしょう。
下記は、SHElikesの受講者にインタビューした記事です。一人目のこじまりさんは、事務職からフリーランスライターへと転身し、最高で月収14万円アップを達成しました。

二人目のぱんさんは、接客業から未経験でフリーライターに転身しました。ぱんさんはSHElikesでライティングスキルを学び、5社と業務委託契約を結ぶまでに成長しました。現在は、月に最高20記事を納品する売れっ子ライターとして、活躍しています。

SHElikesで文章の書き方を学ぼう!
文章力を磨きたい方は、まず文章の基本ルールを押さえることが大切です。「一文を短くする」「結論を最初に書く」など、シンプルな工夫で文章は格段に読みやすくなります。
とはいえ、独学では「自分の文章が本当に伝わるのか?」を判断するのが難しいでしょう。添削を受けながらライティングを学べるスクールであれば、できている点とできていない点を明確にしながら、学ぶことができます。
文章スキルはさまざまな職種で役立てることができるスキルです。SHElikesは、定額で学び放題の全50以上の職種スキルが学べるスクールです。ライティングを基本としながら、Webデザインやマーケティング、ビジネススキルを学べば、新たなキャリアが開かれるかもしれません。
文章力を磨きたい方は、ぜひ無料体験レッスンに参加してみてください。