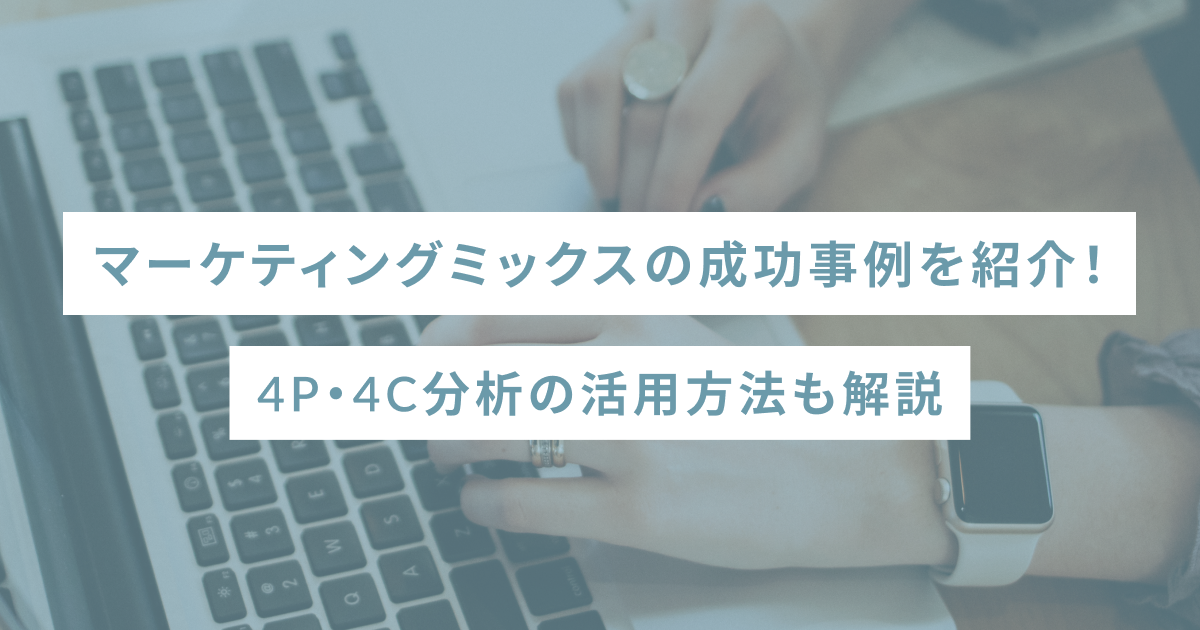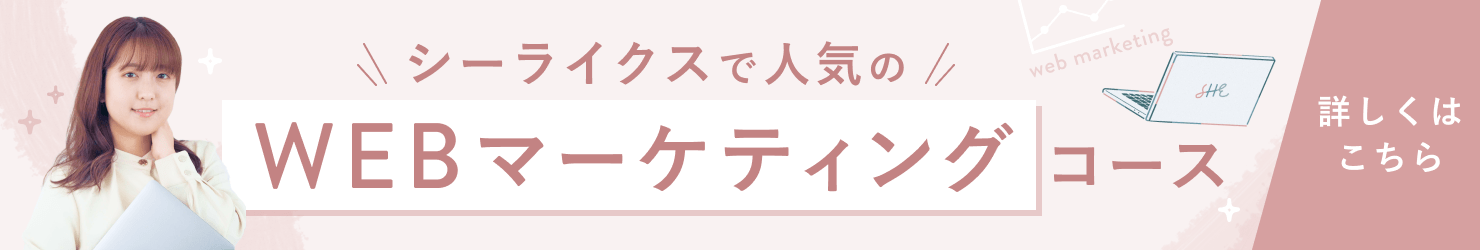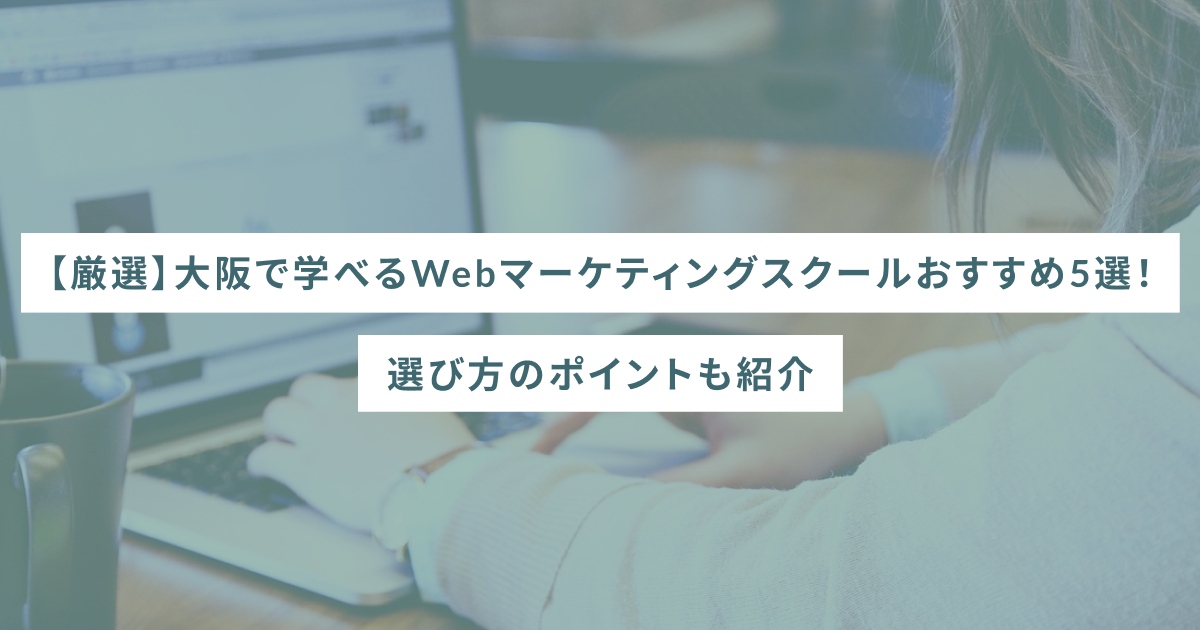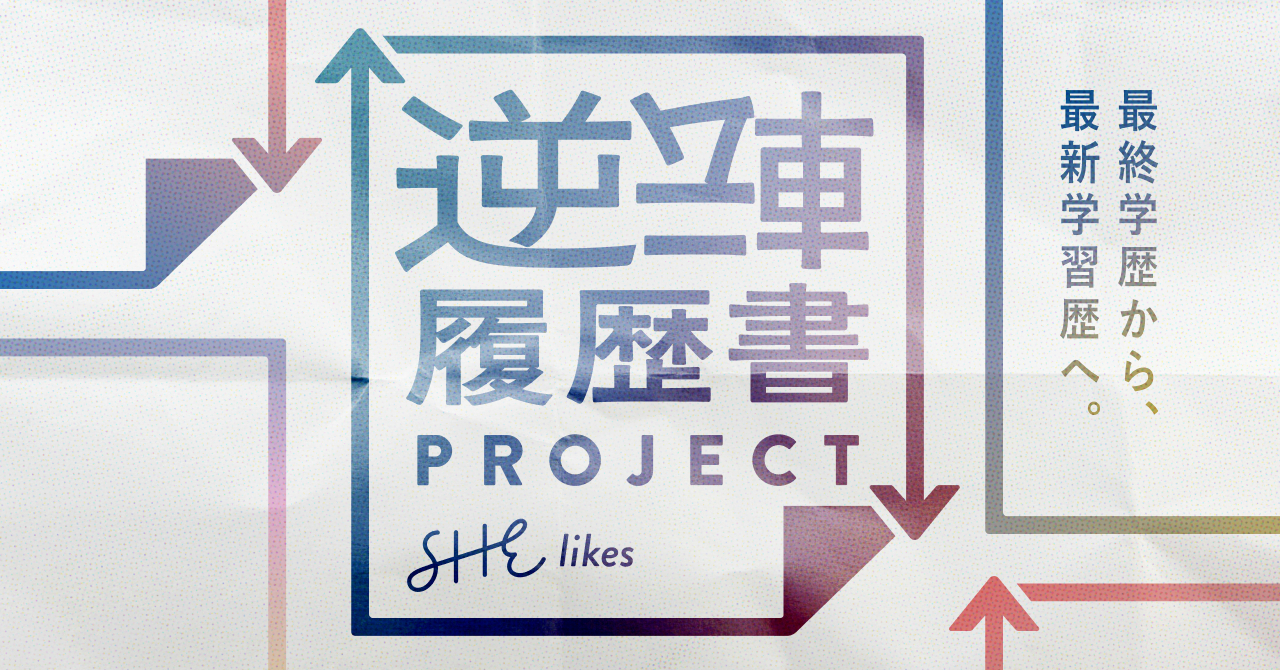マーケティングミックスとは、企業が商品やサービスを「どう売るか」を考える際に活用する基本戦略のこと。特に有名なのが「4P(Product・Price・Place・Promotion)」と「4C(Customer Valu・Cost・Convenience・Communication)」という2つの分析フレームワークです。
本記事では、マーケティングミックスの意味をわかりやすく解説しながら、4P・4C分析の違いや、実際の企業の活用例を交えて紹介します。これからマーケティング戦略を立てたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
マーケティングミックスとは?
マーケティングミックスとは、「商品を市場でどう展開し、顧客にどのように届けるか」を体系的に考えるための枠組みです。簡単にいえば、「売れる仕組みをつくるための設計図」のことを指します。
アメリカのマーケティング学者ジェローム・マッカーシーが提唱した「4P(Product/Price/Place/Promotion)」が原型とされ、のちに顧客視点を取り入れた「4C分析」へと発展しました。この2つの視点を組み合わせることで、企業は時代や顧客ニーズに合った戦略を構築できます。
マーケティングミックスの重要性
マーケティングミックスの最大の意義は、自社の商品・サービスを効果的に市場へ浸透させるための判断軸を整理できること。商品開発や価格設定、販売チャネル、広告戦略などをバラバラに考えるのではなく、全体のバランスを見ながら戦略を立てられるのが特徴です。
たとえ優れた商品でも「価格設定が高すぎる」「販売チャネルが不十分」といった問題があれば売上は伸びません。マーケティングミックスは、そうした“見落としがちな課題”を防ぎ、顧客に届く最適な戦略を導くための土台となります。
マーケティングミックスの4P・4Cとは?

マーケティングミックスにおける4P・4Cとは、マーケティング戦略を立てる際に「企業側」と「顧客側」という異なる視点から考えるためのフレームワークです。
簡単にいえば、4Pは商品・価格・流通・販促など“企業主体の戦略”を整理する枠組みで、4Cは顧客のニーズや体験を重視した“顧客主体の戦略”を考えるためのものになります。ここでは、
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
商品主体で考える4P分析
4P分析とは、企業が「どのように商品を市場に提供するか」を体系的に整理するためのマーケティングミックス手法です。アメリカのマーケティング学者ジェローム・マッカーシーによって提唱され、現在でもあらゆる業界で活用されています。
4Pの4つの要素は以下の通りです。
- Product(製品)
- 何を売るのか。商品・サービスの特徴、デザイン、品質、ブランドコンセプトなどを設計する。
- Price(価格)
- いくらで売るのか。価格設定、割引戦略、支払い条件を決め、利益と顧客満足のバランスを取る。
- Place(流通)
- どこで売るのか。販売経路や物流体制を整え、顧客に届くまでの効率を最適化する。
- Promotion(販売促進)
- どうやって知らせ、購入してもらうか。広告、SNS、イベント、PRなどでブランドを広める。
このように4P分析は、企業側の視点から顧客満足を最大化するための戦略づくりの基礎となります。
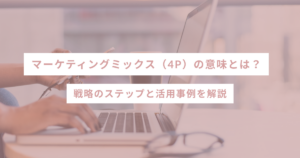
顧客主体で考える4C分析
一方で4C分析は、4Pを顧客目線に置き換えたマーケティングフレームワークです。市場が成熟し、消費者の価値観が多様化した現代では、「売る側」よりも「買う側」からの視点が欠かせません。
4Cの要素は以下の通りです。
- Customor Value(顧客価値)
- 顧客が本当に求める価値を満たしているか。商品自体の性能だけでなく、体験・感情面の価値も含めて考える。
- Cost(顧客コスト)
- 顧客が支払う金額だけでなく、購入までにかかる手間・時間・心理的負担なども含めて捉える。
- Convenience(利便性)
- どこで・どのように商品を入手できるか。店舗・EC・デリバリーなどの利便性が鍵。
- Communication(コミュニケーション)
- 広告による一方的な発信ではなく、SNSやレビューなどを通じた双方向のやり取りを重視。
たとえば、ユニクロは「高品質を手頃な価格で提供(Customer Value & Cost)」し、さらに「店舗・ECどちらでも購入できる利便性(Convenience)」も実現しています。このように4C分析は、顧客の体験を中心に据えて“選ばれるブランド”をつくるための戦略づくりに役立ちます。
4Pと4Cの関連性
4Pと4Cは、マーケティング戦略において相互補完的な役割を持ちます。簡単にいうと、4P の企業視点でのマーケティング基本要素に対し、顧客視点から再解釈するのが4Cといったイメージです。以下に、各要素の具体的な対応関係をまとめました。
- Product(製品)↔︎Customer Value(顧客価値)
- 企業が提供する製品・サービス(Product)に対し、顧客にどのような価値を提供するか(Customer Value)という視点に転換
- Price(価格)↔︎Cost(顧客コスト)
- 製品やサービスの価格設定(Price)に対し、価格や購入にかかる時間などの総合的な負担を顧客視点のコスト(Cost)として捉える
- Place(流通)↔Convenience(利便性)
- どこで購入できるのか(Place)に対し、どれだけ便利に製品を入手できるのか(Convenience)といった視点から捉える
- Promotion(販売促進)↔︎Communication(コミュニケーション)
- 企業の販促活動(Promotion)に対し、顧客の声を反映させた双方向のコミュニケーション(Communication)を重要視する視点
企業が「新商品を発売(Product)」しても、顧客が「その価値を感じ取れない(Customer Value)」なら販売は伸びません。4Pと4Cの両輪でマーケティングを設計することで、顧客満足度と収益性を同時に高める戦略が実現できます。
マーケティングミックスを活用した戦略策定の流れ
マーケティングミックス(4P・4C)は、単独で活用するのではなく、戦略全体の流れの中で検討することが重要です。ここでは、企業が新しい商品やサービスを展開する際に、どのようにマーケティングミックスを取り入れて戦略を立てるのか、具体的な流れを解説します。
それぞれの工程でどんなことをするのか、目的は何なのかを詳しく見ていきましょう。
環境分析をする
最初のステップは、外部・内部の環境分析です。自社の強みや弱みを洗い出す「SWOT分析」や、市場や競合の動向を把握する「PEST分析」などが有効なフレームワークになるでしょう。
外部環境では消費者トレンドや法改正、為替変動など、事業に影響する要素を確認します。一方で内部環境では、自社のリソース(人材・技術・資金)を分析し、「どの領域で勝てるか」を明確にすることが目的です。この段階で得た情報が、のちのマーケティングミックス設計の基礎となります。
STP分析し、基本戦略を策定する
環境分析の次は、STP分析(Segmentation・Targeting・Positioning)を行い、基本戦略を策定します。市場をセグメント(細分化)し、自社が狙うターゲット層を明確に設定しましょう。そのうえで「自社の商品をどのように位置づけるか(ポジショニング)」を決めます。
たとえ同じスキンケアブランドでも、「高品質志向の30代女性」と「時短を求める20代女性」では、求められる価値や価格設定が異なるものです。この段階で明確なターゲットと方向性を定めることで、次のマーケティングミックス(4P・4C)の検討がスムーズに進みます。

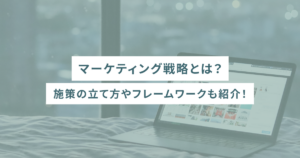
マーケティングミックスを検討する
STP分析で基本戦略を定めたら、次にその戦略を「どう実行するか」を設計します。ここで用いるのが、冒頭で解説した4Pと4Cです。
たとえば、「20代女性をターゲットにしたコスメブランド」を立ち上げる場合、
- Product(製品):肌に優しい成分とトレンドカラーを両立
- Price(価格):手に取りやすい1,500〜2,000円台
- Place(流通):ドラッグストア+オンライン販売
- Promotion(販促):SNSキャンペーンやインフルエンサー施策
といった形で戦略を具現化していきます。4Pだけでなく、顧客体験を意識した4Cの視点を取り入れて、より実効性の高いマーケティング戦略に仕上げていきましょう。
戦略の実行・評価をする
最後のステップは、戦略の実行と効果検証です。マーケティングミックスは立てて終わりではありません。PDCAサイクルを回しながら継続的に改善していく必要があります。SNS広告の反応率や販売データをもとに、価格設定やプロモーション方法を見直すなど、小さな調整を繰り返して精度を高めていきましょう。
調整の段階では、顧客の声を収集・分析して改善点を洗い出すことも重要です。成功企業の多くは「分析→実行→検証→再設計」のサイクルをスピーディーに回しています。戦略を実行したあとのフィードバックこそが、次の成長のカギとなるのです。
マーケティングミックス(4P)の成功事例5つ
ここからは、実際にマーケティングミックス(4P分析)を活用して成功を収めた企業の事例を紹介します。
自社の商品やサービスをどのように「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(販売促進)」の4つの要素に落とし込み、戦略として展開したのかを具体的に見ていきましょう。
1.スターバックスコーヒージャパン
アメリカ・シアトル発祥の大手コーヒーチェーン「スターバックスコーヒージャパン」は、コーヒーを主な製品として全国展開しています。スターバックスコーヒーの4Pは以下の通りです。
- Product(製品)
- 「高品質でこだわりのある一杯」を楽しめるコーヒーをメインに展開
- Price(価格)
- 高級感を求めるユーザーをターゲットにした「高価格戦略」でブランドイメージとの整合性をもたせる
- Place(流通)
- ターゲットに合わせて「立地の良い場所」に店舗を展開
- Promotion(販売促進)
- 広告宣伝をほとんど行わず、「口コミ」をメインとしたプロモーション活動を行う
このように、ターゲットに対し質の高いサービスを提供するため、4P分析を活用しマーケティングしていることがわかります。
2.freee会計
freee(フリー)会計は、フリー株式会社が展開する経理業務を自動化するクラウド会計ソフトです。freee会計の4P分析は以下の通りです。
- Product(製品)
- 組織全体および個人事業主の業務効率化のため、「簡単、自動化」をコンセプトに競合他社との差別化を図り、クラウド会計ソフトを展開
- Price(価格)
- ユーザーの事業規模や求める機能に合わせた3段階の料金体系
- Place(流通)
- 自社サイトやパートナー企業からの流通
- Promotion(販売促進)
- ユーザーの事業規模や求める機能に合わせた3段階の料金体系
煩雑になりやすい経理業務を自動化させたいというニーズに答えるべく、多角的な視点からアプローチできるマーケティング戦略が立てられています。
3.ニトリ
「お、ねだん以上。」のキャッチコピーで知られる「ニトリ」。一時は経営難でしたが、4Pを活用したマーケティング戦略により、現在400を超える店舗数の大手家具メーカーへ成長しています。以下に、ニトリの4P分析をまとめました。
- Product(製品)
- 生産コストを下げるため、他国や他企業で生産された製品の一部分を輸入し、現地で組み立てを行うノックダウン生産を採用
- Price(価格)
- 生産から販売までを一貫して行うSPA*によりコスト削減
- Place(流通)
- SPAを採用することで、無駄のない流通を目指しパフォーマンス向上を図る
- Promotion(販売促進)
- CMなど広告宣伝に力を入れ、高品質で低価格を表現
このように、高品質な製品を低価格で購入したい層へターゲットを絞ったマーケティングで成功していることがわかります。
*SPA:製造小売業(Speciality Store Retailer of Private Lavel Apparelの略)
4. ラクスル
印刷・広告のオンラインプラットフォーム「ラクスル」は、“仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる”を掲げ、従来の印刷業界に新風を吹き込みました。
- Product(製品)
- ネット上で簡単に発注・配送まで完結するオンライン印刷サービスを提供
- Price(価格)
- 余剰印刷機の稼働を最適化することで低価格を実現し、コストパフォーマンスの高さで差別化
- Place(流通)
- 完全オンライン型のビジネスモデルを採用し、全国どこからでも利用可能に
- Promotion(販売促進)
- 「ラクスルで印刷をもっと自由に」というキャッチコピーのもと、テレビCMとデジタル広告を組み合わせた戦略を展開
ラクスルの強みは、業界構造そのものを変革するビジネスモデルをマーケティングに落とし込んだ点。4Pが一貫して“顧客の不便を解消する”という価値提供に向けて機能している好例です。
参考:https://satori.marketing/marketing-blog/marketing-mix/
5. マクドナルド
世界的ファストフードチェーン「マクドナルド」は、4Pを巧みに活用しながら、国や地域ごとに最適化されたマーケティング戦略を展開しています。
- Product(製品)
- 定番メニューのほか、期間限定商品や地域限定メニューを導入し、常に新鮮なブランド体験を提供
- Price(価格)
- 手頃な価格設定とセットメニューの導入で“誰もが利用しやすい価格帯”を維持
- Place(流通)
- 全国の主要都市に加え、ドライブスルー・モバイルオーダー・デリバリーなど多様な販売チャネルを展開
- Promotion(販売促進)
- テレビCMやSNSキャンペーンを通じて、新商品や季節限定メニューを効果的に訴求
とくにマクドナルドは、「変わらない価値」と「変化するトレンド」の両立を実現しており、4Pを常にアップデートし続けることで長期的なブランド力を維持しています。
マーケティングミックス(4C)の成功事例5つ
ここからは、顧客主体の4C分析を活用してマーケティングミックスを成功に導いた企業の事例を紹介します。
顧客の視点に立ち、「Customer Value(顧客価値)」「Cost(顧客コスト)」「Convenience(利便性)」「Communication(コミュニケーション)」の4つの要素をどのように最適化しているのかを見ていきましょう。
1. Uber Eats
アメリカの企業「ウーバー・テクノロジーズ」が展開するフードデリバリーサービスの「Uber Eats」は、2016年に日本でのサービスを開始しました。Uber Eatsは、以下の4Cの視点からユーザーを獲得しています。
- Costomer Value(顧客価値)
- 自宅にいながら、時間や場所を選ばずデリバリーサービスが受けられる点を顧客価値としている
- Cost(顧客コスト)
- 加盟店の豊富さによりユーザーは食べたいものを一括検索でき、手間を省くことで価格面以外のコストを削減
- Convevnience(利便性)
- アプリひとつで注文を完結でき、オンライン決済方法も豊富
- Communication(コミュニケーション)
- 配達員の評価制度やカスタマーサービスなどにより、ユーザーと配達員のほか、企業の間でコミュニケーションが可能
これらの視点から、「デリバリーサービスを利用したいユーザー」「飲食店」「配達で収入を得たいユーザー」の3つを繋ぐデリバリーサービスとして人気を集めるようになりました。
2. サントリー
日本の大手飲料メーカー「サントリー」から展開されるスポーツ飲料「DAKARA」の4C分析を紹介します。
- Costomer Value(顧客価値)
- スポーツシーン以外にも、日常的な水分補給として摂取できるスポーツ飲料
- Cost(顧客コスト)
- 競合他社の製品と同価格帯
- Convevnience(利便性)
- 日常で手に入れやすいコンビニやスーパー、ドラッグストアを主に展開
- 日常の水分補給に摂取できることを伝えるため、競合の少ない冬季にCMを放送
- 競合他社の製品と同価格帯
このように、スポーツシーン以外でも日常生活で気軽に摂取できることを独自の価値としたマーケティングで成功へと導きました。
3. Amazon
アメリカ・シアトルを本拠地とする「Amazon」はEverything store(あらゆるものを扱う店)といったコンセプトのもと、2000年から日本での事業を展開してきました。現在は国内最大規模のECサイトとなったAmazonですが、どのような4C分析が活用されてきたのか紹介します。
- Costomer Value(顧客価値)
- 数あるECサイトのなかでも、圧倒的な商品数と豊富な商品選択肢でほとんどのニーズに対応できるプラットフォームを持つ
- Cost(顧客コスト)
- 豊富な商品価格の選択肢やどの場所からでも可能な注文、翌日もしくは当日配送といったオプションを用意し総合的な顧客コストを削減
- Convevnience(利便性)
- ワンクリック注文や簡潔的な返品プロセスなど、ユーザーフレンドリーな利用が可能
- Communication(コミュニケーション)
- ユーザーレビューやおすすめ商品の紹介により、商品(企業)とユーザー間のコミュニケーションが可能
徹底的な顧客ニーズの理解により、マーケティング戦略を強化してきたAmazon。顧客中心の戦略が成功の要因であることがわかります。
4. ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
大阪にあるテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)」は、4Cの視点を活用し、エンターテインメント体験を再構築したことで復活を遂げました。
- Costomer Value(顧客価値)
- 映画の世界を“体験”できる非日常空間を提供し、来場者の感動体験を重視
- Cost(顧客コスト)
- チケット価格を上げながらも、それに見合う付加価値(新エリア・限定ショー)を設け、顧客の納得感を向上
- Convevnience(利便性)
- 公式アプリでの入場予約や混雑状況の確認など、ストレスの少ないパーク体験を実現
- Communication(コミュニケーション)
- SNSを活用し、来場者が自然に発信したくなる仕掛けを多数導入
「顧客の感動体験」を中心に据えた戦略が、USJのブランド再生と顧客ロイヤルティ向上に大きく寄与しています。
5. ZARA
スペイン発のファッションブランド「ZARA」は、4Cを意識したグローバルマーケティングで、世界的なファストファッション企業として成長しました。
- Costomer Value(顧客価値)
- 「最新トレンドを手頃な価格で」という明確な価値を提供
- Cost(顧客コスト)
- 品質とデザイン性を両立させながらも、購買しやすい価格帯を維持
- Convevnience(利便性)
- オンラインと店舗の両方で商品をチェック・購入できる“オムニチャネル戦略”を採用
- Communication(コミュニケーション)
- 広告費を最小限に抑え、SNSやショーウィンドウなど、ブランドの世界観を直接的に伝えている
ZARAの強みは、顧客の声や購買データをすばやく反映し、デザインから販売までのサイクルを短期間で回せる点。4Cを通じて「顧客が求める今」をスピーディーに提供する仕組みが、世界的成功のカギとなっています。
成功事例から学ぶマーケティングミックス活用のポイント5つ
ここからは、マーケティングミックス(4P・4C)を効果的に活用するためのポイントを紹介します。マーケティング戦略を実践で成果に結びつけるためには、以下の5つを意識することが重要です。
それぞれ詳しく解説していきましょう。
環境分析やSTP分析で戦略を明確にする
マーケティングミックスを効果的に活用するためには、まず環境分析(SWOT分析など)で市場の動向、競合、自社の強み・弱みを客観的に洗い出し、その結果を踏まえてSTP分析で「進むべき道」を定めましょう。ちなみにSTP分析は、以下の3つの要素から構成されます。
- セグメンテーション
- 顧客の年齢・性別・ライフスタイルなどの特性をもとに市場を細分化する
- ターゲティング
- 細分化された市場から、自社に最も適した顧客層を選定する
- ポジショニング
- 選んだターゲットに対して、どのように自社ブランドや商品を認知させるかを明確にする
このステップを踏むことで、「どんな顧客に、どんな価値を、どのように届けるのか」という戦略の軸を定められます。これらを起点にすることで、マーケティングミックスの施策がぶれず、一貫した戦略を構築できるでしょう。

「4P」と「4C」の関連性をもたせる
前述した成功事例からもわかるように、4P(企業視点)と4C(顧客視点)の関連性を意識して戦略を立てることが重要です。
たとえばUSJの事例では、「感動体験(Customer Value)」という顧客価値を軸に、それに見合う価格(Price)や体験の利便性(Convenience)が設計されていました。 また、ZARAの事例では、顧客が求める「トレンド(Customer Value)」を「スピーディーに(Convenience)」届けるため、生産(Product)から流通(Place)までの4P全体が最適化されています。
4Pだけで「売りたいもの」を考えるのではなく、4Cの視点を取り入れて「求められるもの」を届けるマーケティングを設計すること。それが、ブランドの持続的な成長と顧客ロイヤルティの向上につながるポイントです。
各要素のバランスと相乗効果を意識する
4Pや4Cの各要素は、単体で機能させるのではなく全体のバランスと相乗効果を意識することが大切です。価格を低く設定しても製品品質が低ければ、ブランドイメージを損なう可能性があります。逆に高価格戦略をとる場合は、それに見合う価値や顧客体験を提供しなければなりません。
すべての要素を整合的に設計することで、マーケティング全体に一貫性が生まれ、ブランドメッセージがより明確に伝わります。短期的な施策ではなく、中長期的な視点でのバランス設計を意識しましょう。
競合他社のマーケティングミックスとの差別化を図る
市場には数多くの競合が存在します。その中で自社を選んでもらうためには、競合他社との差別化が不可欠です。まずは競合のマーケティングミックスを分析し、どのような製品戦略・価格戦略・販路戦略・プロモーション戦略を行っているのかを把握します。
そのうえで、「自社ならではの強み」や「他社が提供していない価値」を見つけ出し、ポジショニングを明確化することが大切です。差別化により、顧客ロイヤルティの向上やブランドの独自性確立につながり、結果的に長期的な競争優位を築けます。
プロモーションばかりに偏らない
マーケティング戦略では、つい広告やSNS施策などの「Promotion(販売促進)」に注力しがちです。しかし、他の要素(Product・Price・Place)が整っていなければ、効果は一時的なものになってしまいます。
顧客の満足度を高めるためには、製品やサービスそのものの価値を磨き、適切な価格設定や販売チャネルを設計することが重要です。プロモーションはあくまで「伝える手段」なので、「提供価値をどう届けるか」という全体設計があってこそ、真の効果を発揮します。
マーケティングミックスを検討する際に活用できるフレームワーク
マーケティングミックスを設計する前段階では、まず戦略の方向性を定めるための分析が重要です。市場や顧客、自社の立ち位置を客観的に把握することで、より効果的な4P・4C戦略を立てることができます。ここでは、マーケティングミックスを考える前に活用したい代表的な3つのフレームワークを紹介します。
それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。
1. 3C分析
3C分析とは、「Company(自社)」「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」の3つの視点から市場環境を整理するフレームワークです。
自社の強みや課題を明確にしながら、顧客ニーズや競合の動向を分析することで、自社が優位に立てるポジションを把握できます。マーケティング戦略の出発点として、多くの企業で活用されています。
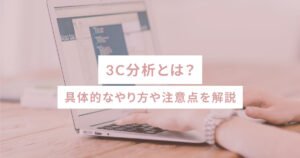
2. ポジショニングマップ
ポジショニングマップとは、縦軸と横軸に異なる要素(例:価格・デザイン性・品質など)を設定し、自社と競合の位置関係を可視化する手法です。
視覚的に「市場の空白」や「差別化できるポジション」を見つけられるため、新商品の企画やブランド戦略に役立ちます。自社がどの立ち位置で勝負すべきかを明確にできるのが特徴です。
3. バリュープロポジション
バリュープロポジションとは、顧客に対して「なぜこの商品・サービスを選ぶべきなのか」という独自の価値提案を明確にする考え方です。
顧客の課題・ニーズ、自社の強み、競合との差別化要因を掛け合わせることで、他社には真似できない独自価値を打ち出すことができます。マーケティングミックスを設計する際の、重要な基盤となるフレームワークです。
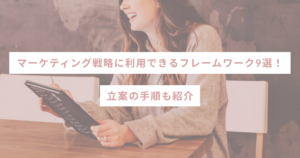
マーケティングミックスの成功事例を参考に、マーケティングスキルを高めよう!

本記事で紹介した成功事例のように、マーケティングスキルを磨くには、知識(フレームワーク)を学ぶだけでなく、「なぜこの戦略が成功したのか」を考えることが大切です。
女性向けキャリアスクールSHElikes(シーライクス)では、マーケティングの基礎が学べる「マーケティング入門コース」や、SNS運用・集客・リピーター育成など実践的スキルを身につけられる「Webマーケティングコース」など、50以上の職種スキルが定額で学べます。
マーケティングミックスを活用して顧客ニーズを捉え、成果を出せるマーケターを目指したい方は、ぜひ一度無料体験レッスンに参加してみてください。