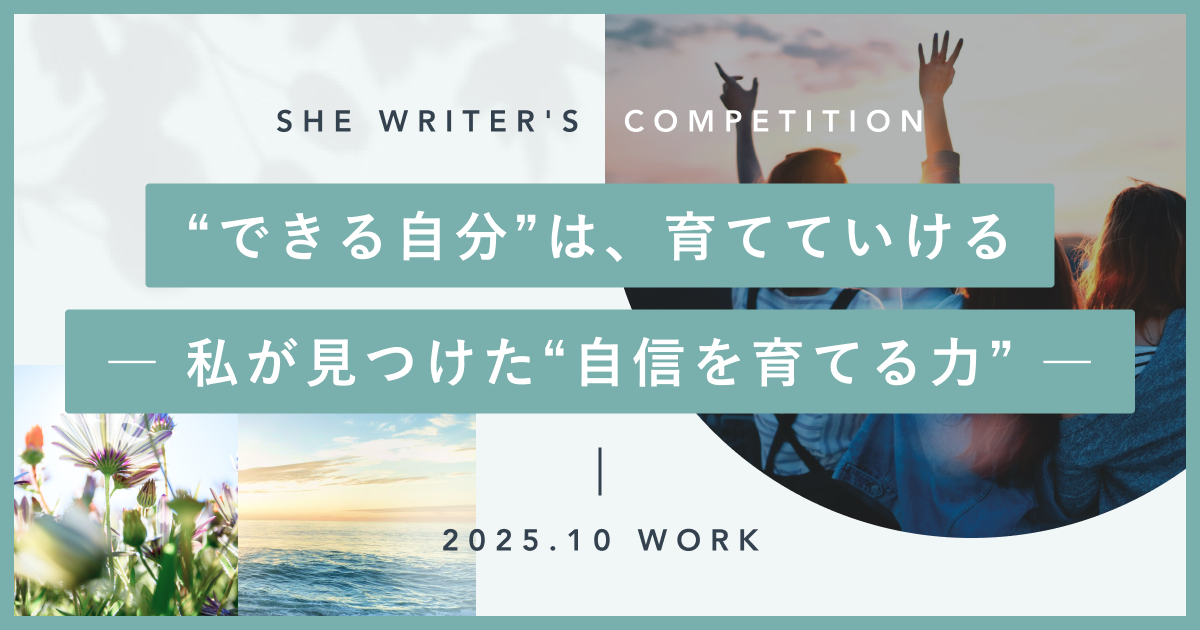「私……こんなにできないんだ」
約2年前、部署異動をきっかけに私は深い焦りを感じていました。同じ会社でも職種が異なる“社内ジョブチェンジ”。毎日が手探りで、うまくいかない現実に落ち込む日々。
さらにSNSでは、独立や転職などキャリアチェンジを成功させた友人たちの姿が目に入り、「私の人生、これでいいのかな」と自信をなくしていきました。
そんなときに出会ったのが、「自己効力感」という考え方です。
本記事では、心理学に基づく“根拠ある自信”=自己効力感の育て方を、私自身の経験を交えながらご紹介します。
「自己効力感」とは?「自己肯定感」との違い
「自己効力感(Self-efficacy)」とは、心理学者アルバート・バンデューラが提唱した概念で、「自分ならこの課題を達成できる」と信じる感覚のこと。
一方、「自己肯定感」は「自分には価値がある」と無条件に自分を認める感情。つまり、自己効力感=行動の自信で、自己肯定感=存在の自信ともいえます。
私たちはよく「自信がない」と一括りにしてしまいますが、実際はこの2つを混同していることが多いのです。
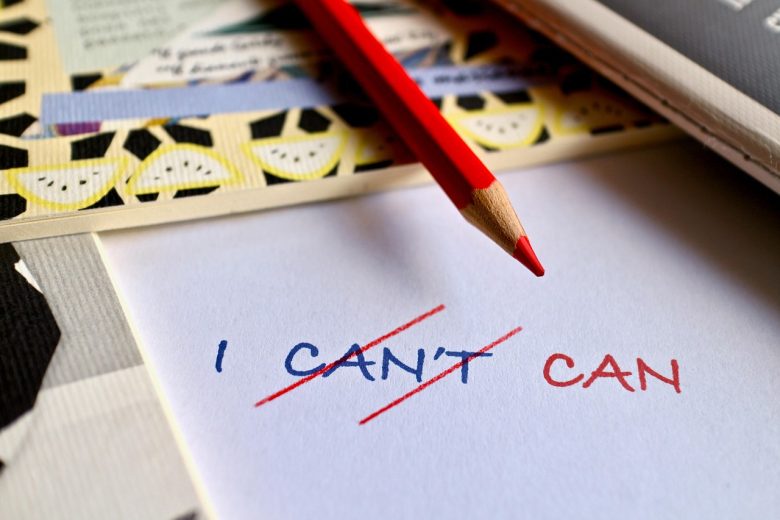
うれしいことに、自己効力感は“後から育てられる”もの。心理学的には、次の4つの要素で強化されるとされています。
①成功体験 ②代理経験 ③言語的説得 ④生理的・情緒的安定
これらの観点とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。ここからは、それぞれの要素を少しずつ紐解いていきます。
“成功体験”は小さく積むほど強くなる
自己効力感の源は「できた」という実感です。
大切なのは「できた」の基準を高くしすぎないこと。人は「目標」や「ゴール」と聞くと、つい無意識に高めに設定してしまいがち。
志が高いのは素晴らしいことですが、大切なのは“積み重ね”。少し頑張ればできることに目を向け、目標やタスクを細分化して、日々の中に“小さな成功体験”を増やしていきましょう。
これには脳科学的な裏付けも。小さな成功のたびに、脳内では「快感」や「やる気」をもたらす神経伝達物質・ドーパミンが分泌されます。この反応が、次の行動を後押しし、モチベーションを持続させてくれるのです。
努力を「快感」と結びつけることが、自己効力感を育てる第一歩と言えるでしょう。
また、達成を可視化することも効果的。例えばToDoリストにチェックを入れる、達成項目に色をつけるなど。最近はアプリなど便利なツールも豊富にあります。ぜひ生活に取り入れてみてください。
“できた”を積み重ねるあなた自身が、次の自信を育てていくのです。
他者との比較より“代理経験”を活用する
SNSが普及した今、良くも悪くも情報があふれています。「あの人と比べて私は……」と、他人の投稿を見て落ち込んだり焦ったりしていませんか?
この“比較”という行動は、自己効力感を削りやすいもの。できれば避けたい行動です。でも本来、他人の成功は落ち込む材料ではなく学びの素材。
「あの人にできたなら、自分にもできるかも」と、視点を変えてみましょう。
このように、他者の行動や結果を観察することで自分の学習や行動に活かすことを、心理学では“代理経験”と呼びます。

“代理経験”を活用するうえで大切なのが、ロールモデルの存在です。ポイントは、その人に共感できるかどうか。「同じ業界で少し先を走る人」「自分と似た背景や能力を持つ人」の成功を観察すると、まるで自分が体験しているように感じられ、それが自己効力感を高めることにつながります。
比較を「自己否定」の材料ではなく、「自己効力感を育てるヒント」に変えていきましょう。
“根拠ある自信”は、人との関わりで育つ
どれだけ行動しても、その自信が“根拠あるもの”でなければ、簡単に揺らいでしまいます。
そこでポイントとなるのが、他人の言葉の力――バンデューラ理論で言う“言語的説得”です。
上司や友人、仲間からの「あなたならできる」「前より成長してるね」といった一言は、自分への信頼を裏付ける“根拠”となり、自己効力感を高めてくれます。
誰からその言葉をもらうかという点も重要。信頼できる人・自分をよく理解してくれている人からのフィードバックこそが、心にポジティブな影響を与えます。
一方で、否定的な言葉をかける人との関係は、自己効力感を削る要因にもなります。成長のための建設的な指摘は大切ですが、“否定”や“比較”を繰り返す関係は、逆に成長の妨げに。
「この人間関係は自分の成長を支えてくれているか?」と、立ち止まって“環境”を見直してみることも大切です。
また言語的説得はセルフでも可能。「自分を褒める日記」「できたことメモ」などポジティブな言葉を文字に残して、自信の“根拠”を蓄積しましょう。
自分を責める前に、“状態を整える”
不安や疲れ、焦りが強いと、どんなに頑張っても自信は感じにくいもの。生理的・情緒的安定――つまり、心と身体の安定も自己効力感の大事な柱です。
睡眠・運動・食事など“自分を整える”行為は、心の土台を作ります。「なんだかうまくいってないな」という時は、まずは生活を見つめてみましょう。
まずは「30分早く寝る」「寝る前に10分ストレッチをする」など。ここでもハードルが低い「できた」で大丈夫!

また、日中のストレスで緊張した身体をほぐすことも大切です。呼吸法や瞑想などを生活に取り入れてみるのもおすすめ。安定した精神状態は、自然と前向きな思考を導きます。
自己効力感とは、“行動できる自分”を支えるエネルギー残量のようなもの。自身の身体と対話をしながら、いつでも“心地よい状態”をキープできるように調整してみましょう。
私に自信をくれたSHElikesとの出会い
少し前の私は、焦りと不安を抱えて生きていました。そんな時に出会ったのが、SHElikesです。
「スキルを上げて、自信をつけよう」
そう思って入会したものの、ネガティブ思考が先行してなかなか不安が消えない日々。
そんな私を変えたのが、SHElikesのカリキュラムのひとつ「コーチング」でした。
月に1度のセッションでは、目標の確認と振り返りを行います。「1カ月前と比べてどうだったか?」「次に何をすればいいのか?」を客観的に見つめ直すことで、少しずつ“根拠ある自信”が育っていきました。
そしてコーチからの言葉は、いつも前向きであたたかいもの。
「あなたならできる」「前より成長しているね」――その一言ひとことが、私の中の“自己効力感”を強くしてくれました。言語的説得の力を、まさに体感しています。
もちろん今でもネガティブな気持ちになることはあります。でも、月に一度のこの時間があるからこそ、マインドをリセットされ、前向きな自分に戻ることができています。
自己効力感という考え方、そしてSHElikesとの出会いは、私を明るい方向へ導いてくれた大きな転機だった――振り返った今、改めてそう感じています。
少しずつ、“できる自分”に

自己効力感は、誰にでも育てられるスキルです。
完璧じゃなくていい。小さな成功を、コツコツと積み重ねていけばいい。
せっかくの一度きりの人生。自分を信じ、認めながら歩んでいきましょう。
************
本記事はSHElikesの受講生を対象とした「SHEライターコンペ」の採用作品です。(執筆者 きょうこさん)
SHElikesについて
https://cutt.ly/cwv7g0aJ
自分らしいキャリアのヒントに出会えるメディア、SHEsharesはこちらhttps://shares.shelikes.jp/