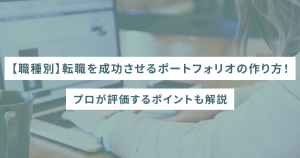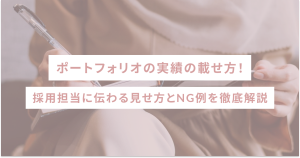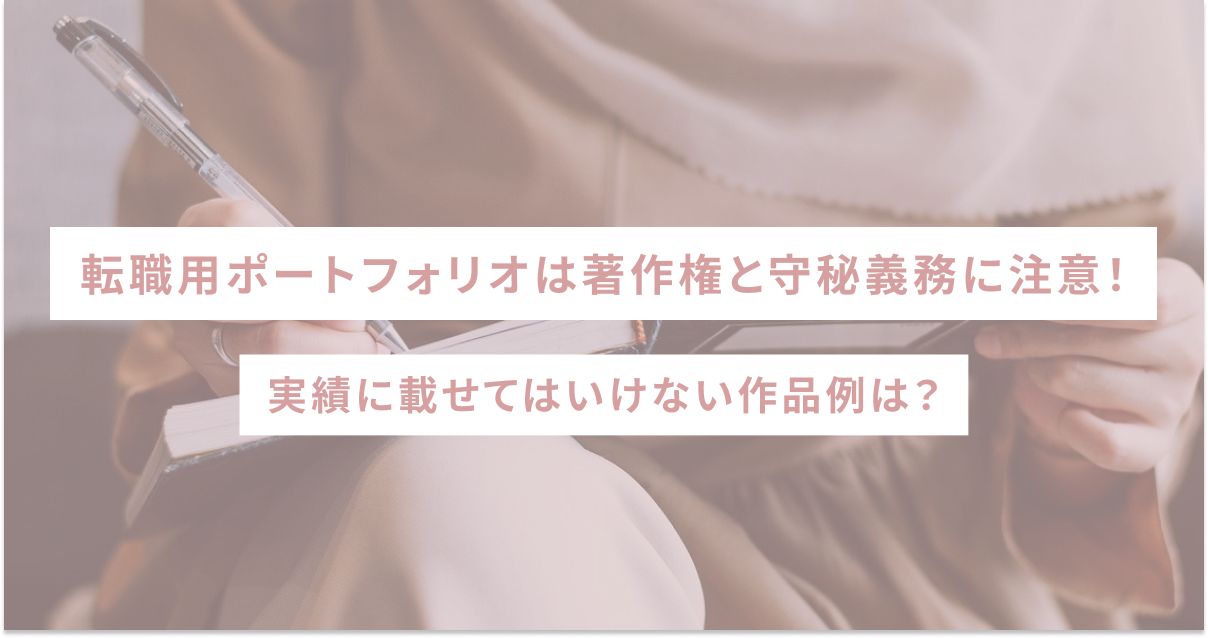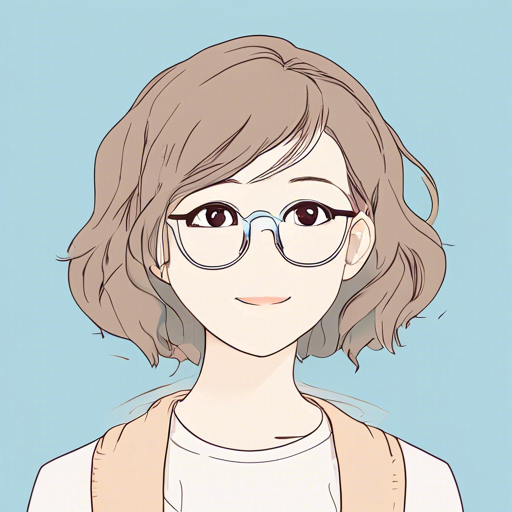クリエイターの転職活動に必要なポートフォリオ作成では、守秘義務や著作権への配慮が欠かせません。法的なリスクを正しく理解し、安全にポートフォリオを作成するための知識を身につけておくことで、大切な情報を守りながら実績をアピールできます。
本記事では、秘密保持契約(NDA)や著作権の基本的な意味から、実際に気をつけたい訴訟・損害賠償リスク、載せてはいけない作品例までを解説します。また、リスクを回避しながら安心してアピールできるポートフォリオの作り方や、ポートフォリオに役立つ実践的なスキルが学べるサービスも紹介します。
転職活動におけるポートフォリオの重要性
ポートフォリオは、転職活動において自分のスキルや実績を伝えるうえで外せないツールです。履歴書や職務経歴書だけでは伝わりにくい具体的な成果を視覚的に示し、自分の強みを採用担当者により深く伝えられます。
たとえば過去に携わったプロジェクトの成果物を通じて、どのような価値を提供できるのかを明確にアピールできます。転職を成功させるためには、専門性や魅力が伝わるポートフォリオを用意することが大切です。
以下の記事では、未経験者のポートフォリオ事例や、スキル習得と実績作りで転職成功を目指せるSHElikesの特徴を紹介しています。興味のある方はチェックしてみてください。

守秘義務とは?ポートフォリオに関わる法的リスク
転職活動でポートフォリオを公開する際に注意すべきなのが、クライアントや勤務先との守秘義務です。守秘義務とは業務上知り得た秘密情報を第三者に漏らさないよう義務づけるもので、在職中だけでなく退職後も効力が続く場合があります。
ここでは、守秘義務を遵守するうえであわせて確認しておきたい秘密保持契約(NDA)と著作権の意味の違い、違反によって生じる法的なリスクについて解説します。
秘密保持契約(NDA)と著作権の違い
秘密保持契約(NDA)は、守秘義務を法的に明確化・強化するための契約です。企業間や個人間で秘密情報をやり取りする際に締結され、どの情報が秘密に該当するか、開示・使用の範囲、違反時の責任などが定められます。もっとも、秘密保持義務自体はNDAに限られるものではなく、業務委託契約や雇用契約、就業規則などで定められている場合もあります。
著作権とは、創作物に対してその作者が持つ独占的な権利であり、自分の制作物を勝手に使われないようにするための法律上の権利です。NDAが「情報の取り扱いに関する約束」であるのに対し、著作権は「作品そのものを守る権利」である点に違いがあります。
訴訟や損害賠償の可能性
守秘義務や著作権を無視したポートフォリオの公開は、法的リスクを招くおそれがあります。たとえば前職で得た情報を秘密保持契約(NDA)に反して公開した場合、企業から警告を受けるだけでなく、公開取下げ、契約違反による損害賠償請求の提起(不正競争防止法の第2条6項の営業秘密漏洩罪や民法の不法行為)をされる可能性があります。
たとえ法的な問題に発展しなかった場合でも、企業からの信頼を損ない、選考中止や内定取り消しにつながるリスクもあります。ポートフォリオを公開する際は、法的・倫理的な観点から注意を払い、慎重に判断することが重要です。
ポートフォリオの実績に載せてはいけない作品例
転職時にポートフォリオへ掲載する実績は自分の優れた作品を選びたいものですが、実際には公開することができない場合もあります。ここでは、ポートフォリオに載せてはいけない作品の例を紹介します。
- 一般公開前の作品
- 提案段階で不採用になった未公開の作品案
- チーム・グループで制作した作品
- 契約により、著作権がクライアントや企業に帰属する旨が規定されている場合
- クライアントから掲載許諾を得ていないもの
- ユーザーデータや秘密情報が含まれる画面キャプチャ及び一切の情報
自分の実績が載せてよいものかどうかを確認し、自信を持って掲載しましょう。
一般公開前の作品
リリース前・公開前のプロジェクト作品は、守秘義務上ポートフォリオに載せることはできません。社内の一般公開前の情報は、企業の戦略や競争力に直結しており、その作品や内容が社外秘情報に該当するためです。
たとえば発表前の広告バナーやプロモーション画像、リリース前の新製品に関するUIデザインなど、社外に公開されていない未発表のものは、実績として掲載しないようにしてください。
提案段階で不採用になった未公開の作品案
採用されなかった提案や未公開の作品は、原則としてポートフォリオに掲載すべきではありません。自分自身が制作したものであっても、それが企業やクライアントとのやり取りの中で生まれたものである以上、知的財産として扱われる可能性があるからです。
たとえば、社内コンペで不採用となったファッションブランドのロゴ案や、納品後にクライアント側の戦略やデザイン方針が見直され、最終的に使用されなかったキャッチコピーなど、第三者に権利が帰属する可能性のあるものは実績として公開しないようにしてください。
チーム・グループで制作した作品
複数人で制作した作品を、自分ひとりの成果であるかのように掲載するのは、ポートフォリオに載せてはいけない代表的な例です。チームやグループで取り組んだプロジェクトを載せること自体は問題ありませんが、すべて個人の成果と誤解されるような表現は避けましょう。
たとえば、共同制作の動画やコンペで開発したプロダクトを、自分名義だけで紹介するのは不適切です。掲載する際は関係者の許可を得たうえで、「UIデザインを担当」「企画のみ参加」など自分の担当領域を正確に記載してください。著作権や守秘義務への配慮を忘れず、誠実な実績の提示を心がけましょう。
契約により、著作権がクライアントや企業に帰属する旨が規定されている場合
契約書において、制作物の著作権がクライアントや企業に帰属すると定められている場合、たとえ自分が制作した作品でも、著作権は契約に基づき相手方に移転しており、自分の所有物とはなりません。そのため、クライアントや企業の許可なく無断で公開することは重大な契約違反となります。
たとえば、業務委託で制作した企業ロゴやWebサイトなどの成果物が、契約上クライアントに帰属する場合、それらはクライアントの財産になります。掲載を検討する際は契約内容をくまなく確認し、必要に応じてクライアントや企業から許可を得たうえでポートフォリオに含めるようにしましょう。
クライアントから掲載許諾を得ていないもの
これまでの説明を総括すると、最も重要な点は、クライアントから明確な許諾を得ていない情報・成果物等は、原則として掲載できないということです。
契約書における取り決めも、突き詰めれば、その許諾を法的に有効な形で得るための一つの手段に他なりません。
ユーザーデータや秘密情報が含まれる画面キャプチャ及び一切の情報
クライアントの個人情報や内部システムの秘密データが映り込んだスクリーンショットや、知り得た情報の中で公になっていない全ての情報が、守秘義務違反に該当します。情報漏洩として問題視されるだけでなく、個人情報保護法などの法令違反に問われる可能性もあります。
たとえば会員制サービスの管理画面やユーザーの利用履歴が見える画面などは、第三者に見せることでプライバシーを侵害するおそれがあります。画面キャプチャを使用する際は、見えている情報すべてにリスクが潜んでいないか細部まで確認しましょう。
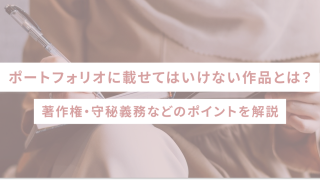
守秘義務違反のリスクを回避するポートフォリオの作り方
転職活動を行う際のポートフォリオでは、公開できない案件が多い場合でも、守秘義務をしっかりと遵守しつつ、工夫次第でスキルを証明する方法はあります。ここでは、守秘義務違反のリスクを回避するポートフォリオの作り方を紹介します。
自分の実力を最大限に伝えるために、さまざまな方法を活用してみてください。
架空プロジェクトで再現性を示す
実際の案件を守秘義務の関係で公開できない場合は、架空の案件であることを明記したうえで、架空のプロジェクトを企画・制作する方法があります。この方法なら、成果物に実際のクライアント情報や秘密データが含まれないため、守秘義務違反のリスクはありません。
たとえば動画制作であれば、実在しない「仮想のクライアント」を想定し、企画立案から絵コンテ作成、撮影・編集、ナレーションやBGMの選定、書き出しまでを一通り行ってみましょう。実務に近い環境を自分で再現することで、仕事の進め方や課題解決力など、実務と同等のスキルを持っていることを効果的に伝えられます。
成果・スキルを定量的に可視化する
ポートフォリオではテキスト情報も活用し、成果やスキルを数値や具体的な指標で記載すると説得力が増します。定量的なデータと具体的なエピソードを組み合わせて提示すれば、客観的な評価材料となり、自身のスキルを裏付ける有力な根拠になるからです。
たとえばWebライティングであれば「記事リライトで検索順位が5位から1位に上昇」「文章改善でCVRが10%向上」など、KPIや達成数値を明記しましょう。さらに、制作過程で工夫した点や、直面した課題への対処法といった問題解決のアプローチを補足すれば、結果だけでなくスキルや思考のプロセスも伝えられます。
面接で“オフラインで見せる”戦略を取る
守秘義務の関係で公開が難しい作品については、面接時に限定的な閲覧という形で紹介する方法があります。たとえば自分のPCやタブレットに必要な資料を用意し、その場で採用担当者にのみ一部を見せるといった形が効果的です。
もちろん、過去のプロジェクトに関する内容を提示する際は「何を、どのように見せるか」について、あらかじめ関わった全ての企業から明確な許可を得ておくことが必要です。このような段取りを慎重に踏むことで、応募先の企業には「守るべき情報には配慮しつつ、伝えるべきことはしっかり伝える」という姿勢をアピールし、情報管理への意識の高さも伝えられます。
職務経歴書やドキュメントで背景を補完する
ポートフォリオに掲載できない守秘義務のある案件は、守秘義務の範囲に配慮したうえで、職務経歴書や補足資料を通じて背景を伝えることが可能です。各プロジェクトの概要・担当業務・成果などを具体的に記載すれば、ポートフォリオに作品の画像やリンクがなくても面接官に実績を理解してもらえます。
実績は必ずしもビジュアルで見せる必要はなく、伝え方次第で評価につなげることができます。作品が見せられなくても、業務の進め方や工夫した点を丁寧に伝えることで信頼性を補うことが可能です。


転職活動用ポートフォリオ作成時によくある質問
ここでは、転職活動向けのポートフォリオを作成する際によくある質問をまとめました。実績を掲載する際の許可の取り方や、秘密保持契約(NDA)で確認すべき項目について、事前に押さえておくべきポイントを解説します。
ポートフォリオに実績を掲載する際の許可取り例文
ポートフォリオ掲載の許可取りが必要な場合の例文を紹介します。
私が請負いました、貴社の案件である「〇〇プロジェクト」に関して、ポートフォリオへの掲載をご相談させていただきたく、ご連絡いたしました。
私個人の制作実績として、以下の形で紹介させていただければと考えております。
- プロジェクトの概要
ECサイト「〇〇オンラインストア」のユーザー体験改善プロジェクト - 担当業務
ユーザーリサーチ、カスタマージャーニー設計、UIリニューアル、レスポンシブ対応の実装 - 紹介予定の内容
改善前後のトップページや商品詳細ページのデザインについて、画面の一部をキャプチャ画像にてご紹介
掲載にあたり、もし秘密情報や非公開とすべき内容が含まれる場合は、ご指摘いただけますと幸いです。記載方法や内容に関して、ご希望がありましたら柔軟に対応いたします。
ご多忙のところ恐縮ですが、ご確認のほどよろしくお願い申し上げます。
具体的に何をどの範囲で載せたいか明示し、相手が判断に迷わないよう依頼をしましょう。また、許可取りはメールや書面で記録を残すのがポイントです。
秘密保持契約(NDA)のチェックポイントは?
ポートフォリオを作成する前に秘密保持契約(NDA)で確認しておきたいポイントは、以下の通りです。
| 項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 適用範囲 | どの情報(技術情報、クライアント情報、成果物)が秘密情報と定義されているか |
| 存続期間 | 守秘義務がいつまで継続するか |
| 禁止事項 | 成果物の第三者提供やSNS投稿の禁止が明記されていないか |
| 例外条件 | 公開済み情報や許可を得た場合の例外があるか |
| 成果物の権利 | 誰が著作権を持っているか |
また、秘密保持契約(NDA)だけでなく、業務委託契約書や雇用契約書、就業規則に記載されている秘密保持義務や著作権の取り扱いについても、必ず併せて確認してください。
それでも内容が不明確な場合や判断に迷う点がある場合は、元の会社やクライアントに直接確認を取ることも検討しましょう。
SHElikesならポートフォリオ作りにも役立つ実践スキルが学べる!
「ポートフォリオに掲載できる実績が欲しい」と考えているなら、SHElikes(シーライクス)の利用がおすすめ。SHElikesは、WebライティングやWebデザイン、プログラミングなど、50以上の職種スキルを定額で学び放題の女性向けキャリアスクールです。
著作権とNDAコースでは、著作権・肖像権・NDAの基本を学べるため、ポートフォリオ作成やクリエイティブ制作業務を行ううえでリスクを回避できる危機管理能力が養えます。また、デザインやライティングコースの修了時に取り組む最終課題や、実務経験を積める「お仕事チャレンジ*」を活用すれば、ポートフォリオに掲載可能な作品を増やせる可能性があります。
*お仕事チャレンジ:一定のスキルが身についた方向けに、お仕事に挑戦できる機会の提供を行っています。ただし、すべての受講生のお仕事獲得を保証するものではありません。
SHElikesの受講生が作った作品を見たい方は、以下の記事からチェックしてみてください。
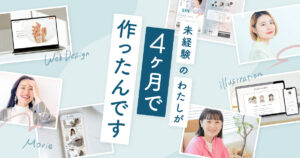
守秘義務に配慮したポートフォリオで転職を成功させよう
転職活動で提出するポートフォリオには、契約書の内容をよく確認し、守秘義務や著作権に配慮した掲載を行いましょう。実績を見せにくい場合は、架空のプロジェクトを作る・補足資料で説明するなど、スキルを誠実に伝える工夫が効果的です。
「スキルと実績を積み上げ魅力的なポートフォリオをつくりたい」と感じている方には、女性向けキャリアスクールSHElikes(シーライクス)がおすすめです。SHElikesでは随時無料体験レッスンをオンラインで開催しています。「最初の一歩を踏み出すのが不安」という方も、まずは気軽に雰囲気を感じてみてはいかがでしょうか。