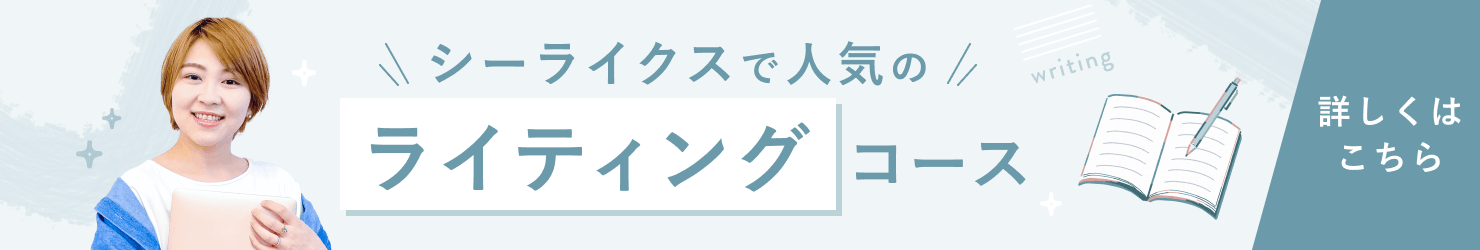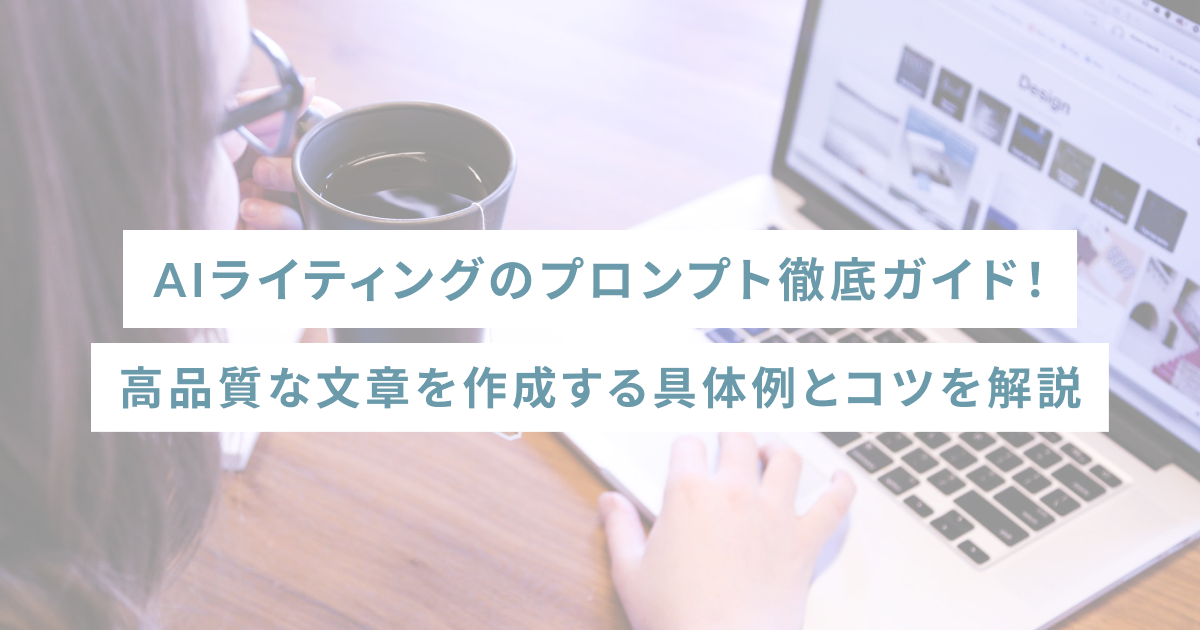昨今、AI(人工知能)の進化によって「Webライターの需要がなくなるのでは?」と心配する声が多く聞かれます。しかし、AIはWebライターの仕事を完全に奪うものではありません。AIの特徴を押さえて上手に活用すれば、Webライティングの効率が上がるなどのメリットもあります。
そこで本記事では、AIの進化がWebライターの仕事に与える影響を解説するとともに、5年後も第一線で活躍し続けるための具体的なAI活用術をご紹介します。
なぜ「AIでWebライターの仕事はなくなる」と言われるのか?3つの理由

Webコンテンツがある限り、Webライティングの需要がなくなることはないといえるでしょう。現段階のAIは、データ分析や文章作成をスピーディーに行うのが得意な一方で、創造性や共感性など人間の感情を汲んだ表現をするのは不得意といった特徴があるからです。
しかしAIの進化により、Webライター職の将来性を不安視する声も多くあります。ここでは、なぜ「AIでWebライターの仕事はなくなる」と言われるのか、その理由を3つにわけて紹介します。
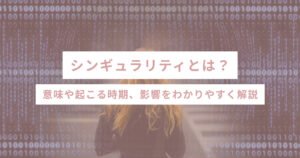
AIの文章生成クオリティの向上
近年、ChatGPTやGeminiといった生成AIの技術は飛躍的に向上しました。簡単な指示を与えるだけで、まるで人間が書いたかのような自然で論理的な文章を瞬時に作成できます。ブログ記事やSNS投稿、商品説明文など、これまでWebライターが担ってきた領域の多くをカバーできるようになったのです。
もちろんAIは絶対ではないため、引き続き人間の目で確かめる工程は欠かせません。しかし、それでも一定品質のコンテンツが量産できるようになったため、「ライターの仕事はAIに奪われる」という懸念が広がる大きな要因となっています。
単純作業の自動化
記事全体の要約や指定した文章のリライト、簡単な商品説明文の作成といった、パターン化された作業がAIの得意分野です。これまでライターが時間をかけて行っていたこれらの業務が、AIによって自動化されつつあります。
これにより、ライターは単純作業から解放される一方で、より高度で創造的なスキルが求められるようになりました。単純作業のみを請け負っていたライターは、AIに代替される可能性が高いと考えられています。
コスト削減の動き
一部の企業では、コンテンツ制作にかかる費用を抑える目的で、AIライティングツールの導入を進めています。特に、大量のテキスト生成が必要な場合や、コストを最優先する案件において、人間のライターではなくAIが選ばれるケースも増えてきました。
これにより、単価の低いライティング案件はAIに代替され、Webライターにはより付加価値の高い仕事が求められるようになっています。
AIの台頭で仕事がなくなるライター・なくならないライターの違い
AI時代において、Webライターの需要が二極化していくと予想されます。AIに仕事を奪われるライターと、逆にAIを使いこなし需要を高めるライターには、どのような違いがあるのでしょうか。それぞれの特徴を以下にまとめました。
仕事がなくなるライターの特徴
- 指示されたキーワードでしか書けない「作業者」ライター
- リサーチが浅く、独自性のない記事しか作れないライター
- AIを「脅威」と捉え、学ぼうとしないライター
仕事がなくならない(むしろ需要が増す)ライターの特徴
- AIを「アシスタント」として使いこなせるライター
- 読者の悩みに寄り添い、心を動かす文章が書けるライター
- 専門性や実体験など、AIにはない「一次情報」を提供できるライター
AI時代にも稼げるライターになりたい人には、女性向けキャリアスクールSHElikes(シーライクス)での学習がおすすめです。以下の記事では、AI副業で稼げない理由と、そう悩む人にSHElikesが適している理由をまとめました。ぜひあわせてお読みください。

WebライターのAI活用術4選
AIはWebライターの仕事を奪う脅威ではなく、業務を効率化し、コンテンツの質を高めるための強力なパートナーとなり得ます。ここでは、具体的なAIの活用術を4つまとめました。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
リサーチの時短に活用する
記事執筆で最も時間がかかる工程の一つがリサーチです。AIを活用すれば、関連情報や統計データ、専門家の意見などをインターネット上から瞬時に収集・要約させることができます。
たとえば「Webマーケティングの最新トレンドを5つ教えて」と指示するだけで、概要を素早く把握できるのです。AIにより情報収集の時間が大幅に短縮されれば、集めた情報の深掘りや独自の切り口を考えるといった、より創造的な作業に集中できるようになります。
構成案や企画の壁打ち相手にする
記事のテーマは決まっているものの、どのような構成にすれば読者に響くか悩むことは多いでしょう。そんなときAIは、優れた壁打ち相手になります。テーマやキーワードを伝えるだけで、複数の構成案や見出し案を瞬時に提案してくれるのです。
自分一人では思いつかなかった視点や切り口を得られるため、企画の幅が大きく広がります。提案された案を元に、さらにアイデアを深めていくことで、より独自性のある骨子を作成できるでしょう。
表現の幅を広げるために活用する
同じような言い回しが続いてしまう、もっとキャッチーな表現はないか、といった悩みもAIで解決できることをご存じでしょうか。たとえば、作成した文章をAIに見せて「この文章を別の表現で5パターン書き換えて」と指示すれば、多様な言い換え案を提示してくれます。
タイトル案のブレストにも有効で、読者の興味を引くような魅力的なタイトルを複数提案させることも可能です。表現の引き出しを増やすアシスタントとして、AIは大いに役立ちます。
文字起こしや文章の校正・改善に活用する
インタビュー音源の文字起こしや、執筆後の誤字脱字チェックは、時間がかかるうえに集中力を要する作業です。AIツールを使えば、これらの作業を自動化し、大幅な時間短縮できます。
さらに、AIは文法的な誤りだけでなく、「より自然な表現」や「もっと分かりやすい言い回し」を提案してくれる機能も備えています。ライティング以外の周辺作業をAIに任せることで、ライターは本来の「書く仕事」に専念でき、生産性を大きく向上させられるでしょう。
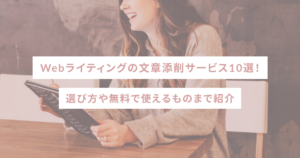
WebライティングにAIを活用する際の注意点
AIは便利なツールですが、万能ではありません。AIが生成した文章には時に誤りや偏りが含まれていたり、人間の感情や経験による文章生成は不得意だったりと弱みもあります。ここでは、WebライティングにAIツールを活用する際の注意点をまとめました。
それぞれ詳しく解説していきます。
必ず人の目で推敲する
AIが生成する文章は一見すると不備がないように思えますが、必ずしも完璧ではありません。AIは文法的に正しい文章を生成できる一方で、内容が不自然だったり、読者の心に響かない無機質な表現が含まれたりすることがあります。
特に、文脈にそぐわない表現や冗長な部分は、Webライター自身が人の目で推敲し、調整する必要があります。AIの活用は補助目的として考え、最終的な仕上げはライター自身が行ったうえでコンテンツを提供するようにしましょう。
ファクトチェックは念入りに行う
AIが生成する文章は情報量が多い反面、すべてが正しく集約・整理できているかというとそうではありません。特にデータや統計のほか、引用内容などについては、信頼できる一次情報を元に確認を行う必要があります。
万が一、誤った情報が拡散されるとライター自身の信用を失うだけでなく、コンテンツの信頼性やクライアントのブランドイメージにも影響を与えてしまいます。AIが提示した内容を鵜呑みにせず、自ら調査・検証を行うことが、Webライターとしての重要な役割です。
倫理的・法的に問題ないか確認する
AIを活用して作成した文章が、倫理的または法的に問題ないかを確認することも重要です。AIは、著作権のある作品情報を含めて生成する可能性があるため、他者の権利を侵害していないか細心の注意を払うようにしましょう。
また、差別的な表現や誤解を招く内容が含まれていないかも確認が必要です。ライターとして、AIツールを使用する際には法令やガイドラインを遵守し、読者に対して誠実なコンテンツを提供する責任があります。
Webライターにおすすめ!AIライティングツール5選
ここからは、WebライターにおすすめのAIライティングツールを5つ紹介します。
| ツール名 | 特徴 |
|---|---|
| ChatGPT | ブログ記事やSNS投稿、メール文面など汎用性が高く、あらゆる用途に活用できる |
| Gemini | 最新情報へのアクセスやGoogle検索との連携が得意で、リサーチに強い |
| Emma Tools | SEOコンテンツ制作に特化し、競合分析や構成案作成を強力に支援する |
| ブンゴウ | 自然な日本語生成に特化し、文体や語彙選びを細かくカスタマイズ可能 |
| Claude | 長文の読解・生成が得意で、レポートや資料作成などで高品質なコンテンツ制作が可能 |
それぞれの特徴とライティングに活かせるポイント、また使い方についても触れているので、ぜひ参考にしてみてください。
1. ChatGPT
ChatGPTは、高い文章生成能力を誇るAIライティングツールです。自然な言い回しや多様なトーンに対応しており、ブログ記事やSNS投稿、メール文面など幅広い用途で活躍します。
また、指示に対する柔軟性が高く、詳細な指示を与えることで、より意図に沿った文章を生成できます。無料プランも用意されており、初心者からプロのWebライターまで幅広い層に支持されるAIツールです。
2. Gemini
Googleが開発したGeminiは、最新のWeb情報にリアルタイムでアクセスできるのが最大の特徴です。そのため、情報の鮮度や正確性が求められるトピックに強く、最新のトレンドを反映したSEO記事作成やファクトチェックでその能力を発揮します。
ちなみに、文章だけでなく画像や音声も同時に理解できるマルチモーダル性能も備えており、より複雑で高度な指示に対応可能です。Googleの各種サービスとの連携もスムーズで、リサーチからコンテンツ作成までをシームレスに支援してくれます。
3. Emma Tools
Emma Toolsは、SEOコンテンツ制作に特化したAIライティングツールです。最大の特徴は、キーワードの使用率や文字数などを基に、記事のSEO品質を独自の指標でスコア化してくれる点にあります。これにより、SEO初心者でも検索上位表示の可能性が高い記事を客観的な数値に基づいて作成できます。
キーワード選定から競合分析、AIによる構成案や本文の自動生成、コピー率チェックまで、SEO記事作成に必要な作業を一気通貫でサポートしてくれるので、大幅な時間短縮と品質向上が期待できるでしょう。
4. ブンゴウ
ブンゴウは、日本語コンテンツに特化したAIライティングツールです。自然な日本語表現と正確な文法で、多くのWebライターに支持されています。ブンゴウならではの特徴は、文体や語彙選びを細かくカスタマイズできる点です。硬めの記事からカジュアルな文章まで幅広く対応可能です。
さらに、日本特有の文化や慣習を考慮した表現にも対応しており、特に日本語メディア向けのコンテンツ制作に向いています。
5. Claude
Claudeは、AIスタートアップAnthropicが開発したライティングツールで、人間に近い直感的な文章生成能力が特徴です。特に、長文の構成や論理的な文章生成が得意なため、レポートやコラムなどのジャンルに適応する高品質なコンテンツ制作が可能です。
また、使いやすいインターフェースと精度の高い文章生成で、ライター初心者から上級者まで幅広く活用できます。高いセキュリティ性も備えており、安心して利用できる点も魅力です。
未経験から「AIに負けないWebライター」になるための3ステップ
ここでは、未経験からでもAIを味方につけ、「あなたにお願いしたい」と選ばれるライターになるための具体的なロードマップを3つのステップでご紹介します。
闇雲に手を動かすのではなく、正しい順序で着実にスキルを身につけていきましょう。
ステップ1. Webライティングの基礎を学ぶ
AIを効果的に活用するためには、その土台となるWebライティングの基礎知識が不可欠です。検索エンジンで上位表示させるためのSEOの仕組みや、読者の行動を促すセールスライティングの技術、論理的な文章構成の作り方などをまず学びましょう。
基礎がなければ、AIに的確な指示を出したり、AIが生成した文章の良し悪しを判断したりすることができません。まずはAIに頼らず、自力で記事を書き上げるスキルを身につけることが重要です。
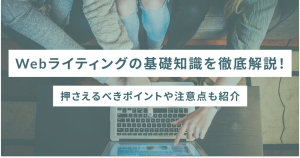
ステップ2. AIツールに触れてみる
Webライティングの基礎を学んだら、次に実際にAIツールを使ってみましょう。まずはChatGPTやGeminiの無料版など、お金をかけずに利用できるツールからで十分です。構成案を作らせたり、文章をリライトさせたりと、様々な指示を試してみてください。
実際に使うことで、AIが得意なこと(情報収集、アイデア出しなど)と、苦手なこと(感情表現、実体験の記述など)が具体的に理解できます。この体験を通じて、AIを使いこなすための感覚を養うことができます。
ステップ3. 専門分野や「好き」を掛け合わせる
ライティングの基礎を固め、AIの使い方も理解したら、最後のステップとして「自分だけの強み」を確立します。あなたのこれまでの経験や職歴、趣味で得た知識など、専門分野や「好き」なことをライティングに掛け合わせましょう。
たとえば、元美容部員ならコスメ関連、趣味がキャンプならアウトドアといった分野がおすすめです。AIにはない実体験に基づいた一次情報は、コンテンツの独自性と信頼性を飛躍的に高めます。AI×専門性で、あなたにしか書けない価値ある記事を提供しましょう。
AI×ライティングを学ぶならSHElikesがおすすめ!
前述したように、AI時代に活躍し続けるWebライターになるには、ライティングスキルとAI活用スキルの両方をバランスよく学ぶことが不可欠です。女性向けキャリアスクールSHElikesなら、ライティング関連コースで基礎から実践的な執筆スキルまでを体系的に学べるほか、生成AI入門コースでツールを使いこなす方法も習得できます。
他にも多種多様なコースの中から、自分に必要なスキルを組み合わせて学べるのがSHElikesの魅力です。未経験からでも、市場価値の高い「AIに負けないWebライター」を目指すことができます。

AIと共存するには、正しいライティング・AI活用スキルの習得が大切!

「AIでWebライターの仕事はなくなる」という不安は、AIを脅威と捉えているからこそ生まれるものです。しかし、AIはライターの仕事を奪う「敵」ではなく、生産性を高め、創造性を引き出してくれる「強力なパートナー」となります。時代の変化にあわせて正しいライティングスキルとAI活用スキルを身につけ、選ばれ続けるWebライターを目指しましょう。
女性向けキャリアスクールSHElikesでは、基礎的なライティングスキルやWeb記事の制作に必要な構成力が身につく「ライティングコース」や、ユーザーに届く記事作成について学べる「SEOライティングコース」など、AIツールを活用するうえで欠かせないスキルが習得できます。生成AIコースでAI活用の基礎を学べるのも魅力です。
AIを味方につけつつ質の高いコンテンツを作りたいと考えている方は、ぜひ一度無料体験レッスンへ参加してみてはいかがでしょうか。