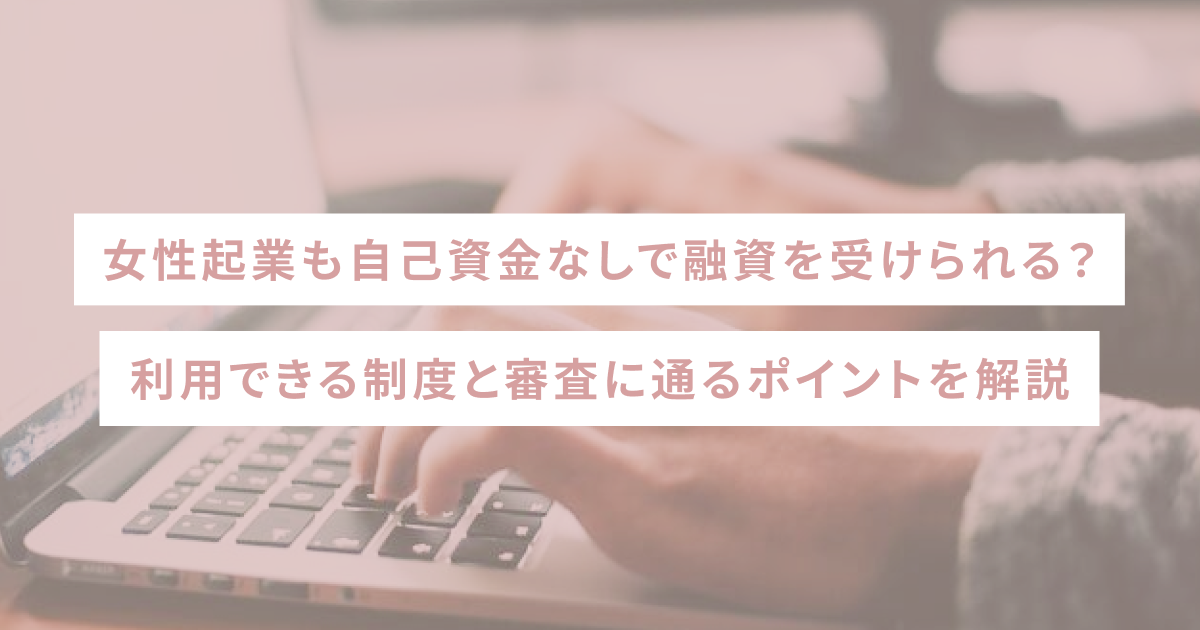「起業したいけどお金がない」「女性でも自己資金なしで起業できるの?」」と悩む方は少なくありません。本来、起業時の融資にはある程度の自己資金が必要とされますが、工夫次第で資金ゼロからスタートできる可能性もあります。
この記事では、自己資金ゼロでも創業融資を受けて開業するための方法や注意点を、初心者でもわかりやすく解説します。
自己資金なしでも融資は受けられる?女性起業家が知っておくべきこと
「資金ゼロで起業したい」というのは理想のように思えるかもしれませんが、実は不可能ではありません。ただし、自己資金なしで融資を受ける場合、審査のハードルが上がるのも事実です。まずは、自己資金の意味と、その重要性を正しく理解しておきましょう。
ここでは、実際に融資審査で重視されるポイントや必要な自己資金の目安、自己資金に該当するお金の例などを具体的に解説します。
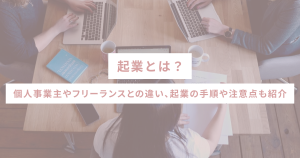
創業融資における自己資金の重要性
「自己資金はいくら必要?」と不安に思う方も多いかもしれません。一般的には、開業資金の2〜3割程度を自己資金として用意するのが望ましいとされています。というのも、自己資金は「事業への本気度」や「計画性」を示す要素として、融資審査で重視されるからです。
ただし、手元に十分な資金がない場合でもチャンスはあります。たとえば、すでに支払った起業準備費用などは「みなし自己資金」として評価されることも。ゼロスタートでも、工夫次第で融資の可能性は広がるため、事前に制度内容をしっかり確認しておくことが大切です。
必要な自己資金の額は事業や制度によって異なる
必要な自己資金の額は一律ではなく、起業する業種や規模、利用する融資制度によって変わります。たとえば、日本政策金融公庫の「新規開業実態調査」によると、起業にかかった費用の平均は約1,027万円です。そのうち自己資金でまかなわれた額は約280万円とされています*1。
こうしたデータからも、自己資金は開業資金の2〜3割を目安に用意しておくと、融資を受けやすくなると考えられます。ただし、あくまで参考値であり、事業の内容や準備状況によって必要額は異なるため、ケースに応じた計画を立てることが重要です。
自己資金に該当するお金の例
自己資金とは、単に貯金だけを指すわけではありません。以下のようなお金も自己資金として認められるケースがあります。
- 預貯金:長期間かけて自分で貯めた資金
- 退職金:転職や退職時に受け取った資金
- 相続金:遺産として得たお金
- 保険の解約返戻金:生命保険などを解約して得た現金
- 資産売却益:車や不動産、宝飾品などを売って得た資金
- みなし自己資金:名刺作成や什器購入など、すでに事業のために使った出費
自己資金として認められるかどうかは、資金の出所が証明できるかがポイントです。たとえば、タンス預金でも「給与や生活費から少しずつ貯めたことが証明できる」なら評価される場合もありますが、出所が不明確だと借入金と見なされて、自己資金として扱われない可能性があります。
自己資金ゼロでも利用できる!起業家向けの融資制度
資金がない状態で起業するなら、融資制度の活用を検討しましょう。なかでも日本政策金融公庫や各地の信用保証協会が提供する制度は、自己資金ゼロでも相談可能なケースがあり、特に女性やシニア、若者などには優遇措置もあります*2。
ここでは、具体的な制度とその特徴、利用時のポイントについてわかりやすく解説します。
日本政策金融公庫の創業融資
日本政策金融公庫では、創業間もない起業家に向けた融資制度を多数用意しています。自己資金が少なくても利用しやすいのが特徴です。年齢やライフステージに応じたサポートもあり、特に初めての起業には心強い存在といえるでしょう。
新規開業資金
「新創業融資制度」は2024年3月末で終了し、現在は「新規開業資金」などの各融資制度に無担保・無保証人の条件が統合されています。大きな変更点として、申込要件であった「自己資金1/10以上」は撤廃されました。
制度上は自己資金要件がなくなりましたが、審査の現場では依然として自己資金の有無が重視されています。ゼロでも申し込み自体は可能ですが、減額や却下となる可能性もあるため、最低限の自己資金を準備しておくことが現実的な対策です。担保・保証人は原則不要で、融資上限の目安は従来通り(最大3,000万円/うち運転資金は1,500万円まで)となっています。
女性、若者/シニア起業家支援資金
女性や、35歳未満の若者、または55歳以上のシニアで、事業開始後おおむね7年以内の方が対象の制度です。この制度も新規開業資金同様、2024年4月の制度改正により、自己資金の要件が撤廃されました。低金利で利用できるため、ライフイベントと両立しながら起業を目指す人に適しているでしょう。
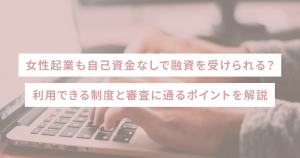
中小企業経営力強化資金
「認定経営革新等支援機関」(税理士や中小企業診断士など)から経営に関する指導や助言を受けながら事業計画を立てる方が利用できる融資制度です。専門家と協力して事業計画を策定することで、融資の審査に通りやすくなる傾向があります。金利優遇も受けられるのが特徴です。
挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)
返済の優先順位が低く、金融機関の資産査定で「自己資本」とみなされる特殊なローンです。財務体質が強化され、他の金融機関からの追加融資が受けやすくなる効果が期待できます。無担保・無保証人で、赤字でも利息負担が軽減される仕組みがあり、将来的な成長を目指す事業に適している制度です。
信用保証協会を利用する
信用保証協会とは、民間の金融機関から融資を受ける際に、事業者の保証人となる公的機関です。万が一返済が困難になった場合、事業者に代わって金融機関に返済(代位弁済)を行います。これにより、金融機関のリスクが軽減され、自己資金が少ない創業者でも融資のハードルが下がります。
信用保証協会を利用する場合、融資額に応じた保証料の支払いが必要になります。自治体によっては保証料の一部を補助してくれる制度もあります。また、返済が滞った場合は保証協会が代位弁済しますが、その後は事業者に返済義務が残る点に注意が必要です。
地方自治体の制度融資
多くの自治体では、信用保証協会を通じた独自の創業支援融資制度を用意しています。金利の一部を自治体が負担する「利子補給」や、信用保証協会に支払う保証料の補助など、創業者に有利な条件が特徴です。自己資金が少ない場合でも相談しやすいため、お住まいの自治体の制度を一度チェックする価値はあるでしょう。
銀行・信用金庫の創業融資
銀行や信用金庫でも、独自の創業者向けの融資を提供しています。特に地域密着型の信用金庫は、事業内容や人物面も見て判断してくれるケースがあり、柔軟な対応が期待できるのがメリットです。ただし、一般的に日本政策金融公庫や保証協会付融資と比べて審査は慎重になるため、事業計画書の内容や自己資金の準備状況がカギになります。
起業する際に融資を受けやすくするためのポイント
自己資金なしで挑戦する場合、融資審査に通るかどうかが大きなハードルになります。とはいえ、自己資金が少なくても審査通過率を高める工夫は可能です。
ここでは、融資を受けやすくするために実践しておきたい具体的なポイントを5つ紹介します。しっかり準備を進めることで、資金面の不安を軽減し、安心してスタートを切ることができるはずです。
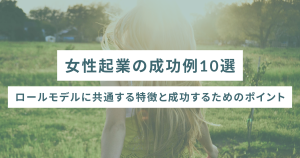
可能な限り自己資金を貯める
自己資金なしでの起業は可能ですが、融資だけに頼ると毎月の返済負担が重くなります。事業がすぐに軌道に乗らなかった場合、キャッシュフローが厳しくなり、経営が立ち行かなくなる恐れも。そのため、少額でもよいので自己資金を準備しておくことが望ましいです。
実際に、融資審査では「どれだけ自分で資金を用意したか」が本気度として評価される傾向があります。地道に貯金をしてから申し込むことで、審査通過の可能性が高まり、より良い条件でスタートできるでしょう。
抜け漏れなく創業計画を立てる
金融機関に提出する事業計画書は、融資審査の中核を担う重要な書類です。内容に不備があったり説得力が弱かったりする場合、審査通過は難しくなります。計画書には、「なぜこの事業をやるのか」という想いに加え、市場調査・競合分析・収支計画などを具体的に記載しましょう。
競合とどう差別化するのか、収益化までのタイムラインはどうか、売上が伸びなかったときのリスク対応策なども盛り込むと安心です。数字に裏付けられた計画があるかどうかで、事業の信頼性は大きく変わります。
創業前の実績や既に決まっている契約があればアピールする
創業時は決算書などの実績がないため、事業に関連する過去の職務経験やスキルが重視されます。長年飲食業界で働いていた人が飲食店を開業する場合、経験の蓄積が大きな信頼材料になることも。また、すでに決まっている取引先や販売ルートがあれば、それを計画書に明記して事業の安定性をアピールするのも効果的です。
「この人なら成功しそう」と審査担当者に思わせるために、起業に至るまでのストーリーと実績のつながりを丁寧に説明しましょう。
現在所属する会社と同業で独立開業する
同業での独立は、まったくの未経験よりも信用が得やすく、融資審査においても有利に働くケースが多いです。業界知識や人脈、業務スキルを活かして事業を軌道に乗せやすいため、成功の可能性が高いと評価されやすいためです。
また、過去の勤務先から仕事を請け負う形で起業する「暖簾分け」や「業務委託契約」も、事業計画に実績として書けるため、説得力が増します。
認定支援機関に相談する
金融機関の審査に自信がない場合や、事業計画の作成に不安がある場合は、認定支援機関に相談するのがおすすめです。これらの支援機関では、創業融資の計画作成やアドバイス、伴走型支援を無料または安価で受けられることがあります。
ちなみに該当する支援機関は商工会議所、よろず支援拠点、中小企業診断士などです。専門家と一緒に計画を立てていくことで、融資の通過率が高まり、安心して創業準備を進められるでしょう。
自己資金が少ない場合に融資を申し込む際の注意点
自己資金が少ない状態で起業融資を申し込む場合、事前に知っておくべき注意点があります。融資審査では、資金の出所や事業の信頼性が厳しくチェックされるため、対策を講じずに申し込むと却下される可能性も。
上記のポイントを押さえて、リスクを避けながら準備を進めましょう。
希望の融資額が減額される可能性がある
自己資金は、事業に対する熱意や計画性を示す指標と見なされます。そのため、自己資金が少ないと「準備不足」や「事業への本気度が低い」と判断され、希望額から減額されたり、審査がより慎重になったりすることも。
自己資金が少ないことをカバーするなら、事業計画書での説得力のある数値管理や、みなし自己資金の提示などで信頼を補うことが重要です。資金負担や返済リスクを見越して、無理のない借入額を設定することも大切です。
「見せ金」や「預け合い」は違法となる
融資を通すために「一時的に口座へ入金して、見かけ上の自己資金を演出する」といった行為は「見せ金」と呼ばれ、明確な違法行為です。さらに、金融機関と共謀してお金を一時的に入金し、引き出しを制限する「預け合い」も同様に違法となります。
これらが発覚すると、今後一切の融資が受けられなくなる恐れがあるだけでなく、信用も大きく損なわれかねません。金融機関は通帳の履歴や資金の流れまで厳しく審査しており、見せかけの資金はすぐに見破られるので、絶対にやめましょう。
資金計画を立てないと返済できなくなる恐れがある
自己資金が少ないまま融資を受けると、返済が資金繰りの大きな負担となることがあります。想定どおりに売上が伸びなければ、会計上は黒字でも手元資金が不足し、返済や事業継続に支障をきたす可能性も。起業前に資金繰り表を作成し、入金・支出のタイミングを踏まえたシミュレーションを行い、最悪のケースにも備えておくことが重要です。
返済原資を確保するためにも、初期費用や運転資金の見積もりは慎重に行いましょう。認定支援機関や専門家に相談して、現実的な資金計画を立てることをおすすめします。
自己資金なしで起業したい・融資を得たい人によくある質問
自己資金が少ない状態での起業や融資に不安を感じている方のために、よくある質問をまとめました。
「自分でも本当にできるのかな?」と感じている方こそ、ぜひチェックしてみてください。
女性は融資を受けられる可能性が低い?
女性だから融資が受けられないということはありません。実際には、女性起業家は男性に比べて準備できる自己資金が少ない傾向があるため、結果的に融資額が低くなるケースがあるのは事実です。
こうした背景も踏まえて、日本政策金融公庫をはじめ、女性起業家向けの制度や補助金が数多く用意されています。資金調達に不安がある場合は、これらの制度を上手に活用するとよいでしょう。
融資以外の資金調達方法はある?
自己資金がない場合でも、融資以外に以下のような選択肢があります。
- クラウドファンディング:起業アイデアや商品コンセプトに共感してもらい、資金を募る仕組み。実績がなくても挑戦可能です。
- 助成金・補助金:国や自治体、民間団体が提供する資金サポート。返済義務がない点が魅力ですが、応募条件や審査があるため事前に確認が必要です。
- 家族・親族からの贈与:近しい人から資金を援助してもらう方法。贈与税のルールや信頼関係のバランスにも注意が必要です。
いずれの方法も、信頼や準備がカギになります。
手持ちゼロから自己資金を増やせる?
可能です。副業から始めて収入を得たり、日々の支出を見直して小さく積み立てることで、現実的なペースで自己資金を増やすことができます。また、起業準備のためにかかった費用(設備購入費や講座受講費など)は「みなし自己資金」として評価されることも。
ゼロスタートでも工夫次第で自己資金は増やせるので、ぜひ検討してみてください。
自己資金なしで融資を受けて起業する際は事前準備が大事!
自己資金がなくても、日本政策金融公庫や自治体の制度を活用すれば、融資を受けて起業することは可能です。ただし、希望通りの金額を借りられない場合や、金利負担が大きくなる可能性もあるため、事前準備は欠かせません。事業計画の精度を高め、資金繰りのシミュレーションを行うなど、しっかり準備を進めましょう。
「何から始めていいかわからない」と感じている方には、女性向けキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」の活用がおすすめです。50以上の職種スキルが学べるほか、起業に役立つコース・サポートも豊富にそろっています。
さらに、お金の管理や自己資金づくりに不安がある方には「SHEmoney(シーマネー)」もおすすめです。お金のプロと一緒に、あなたに合った起業準備や貯金プランを立てることができます。将来を見据えた自分の経営に、自信を持って挑めるはずです。
どちらも無料体験が用意されているので、「起業したいけどお金がない……」という方こそ、まずは相談から始めてみてはいかがでしょうか?

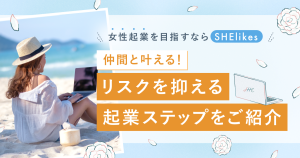
※出典
*1:2023年度新規開業実体調査~アンケート結果の概要~
*2:日本政策金融公庫|新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)