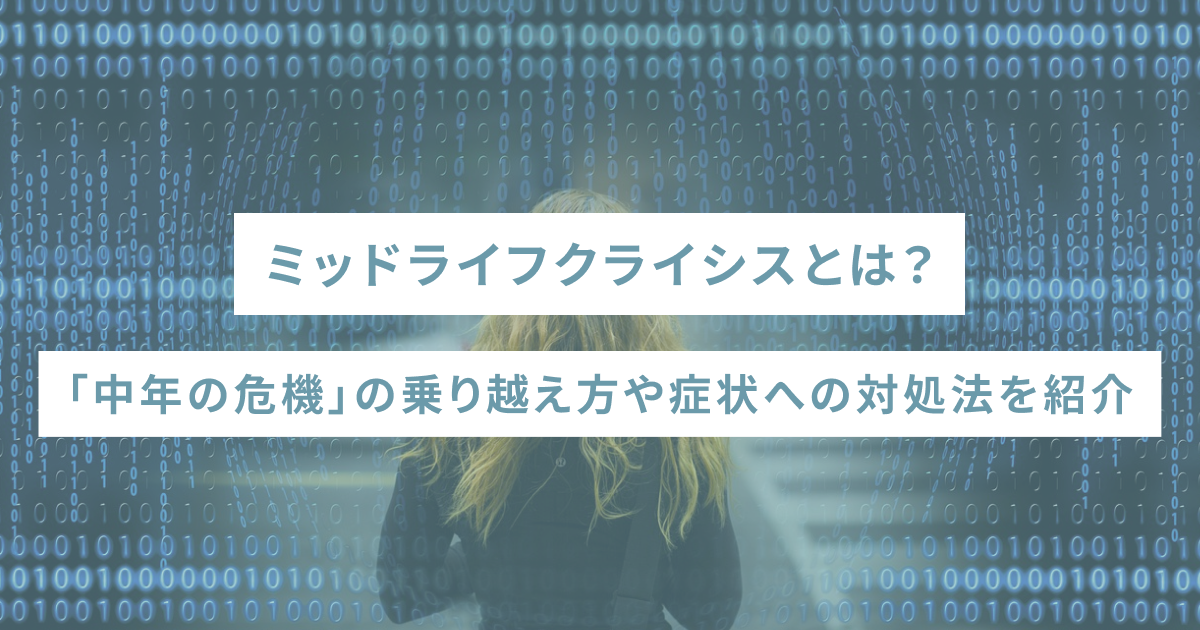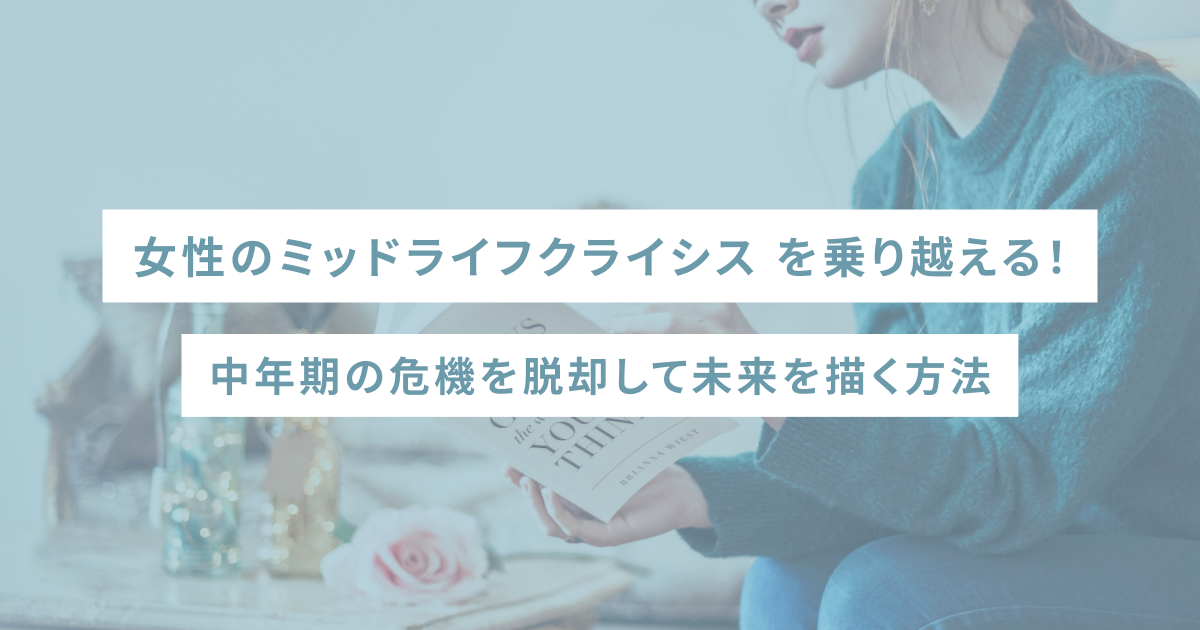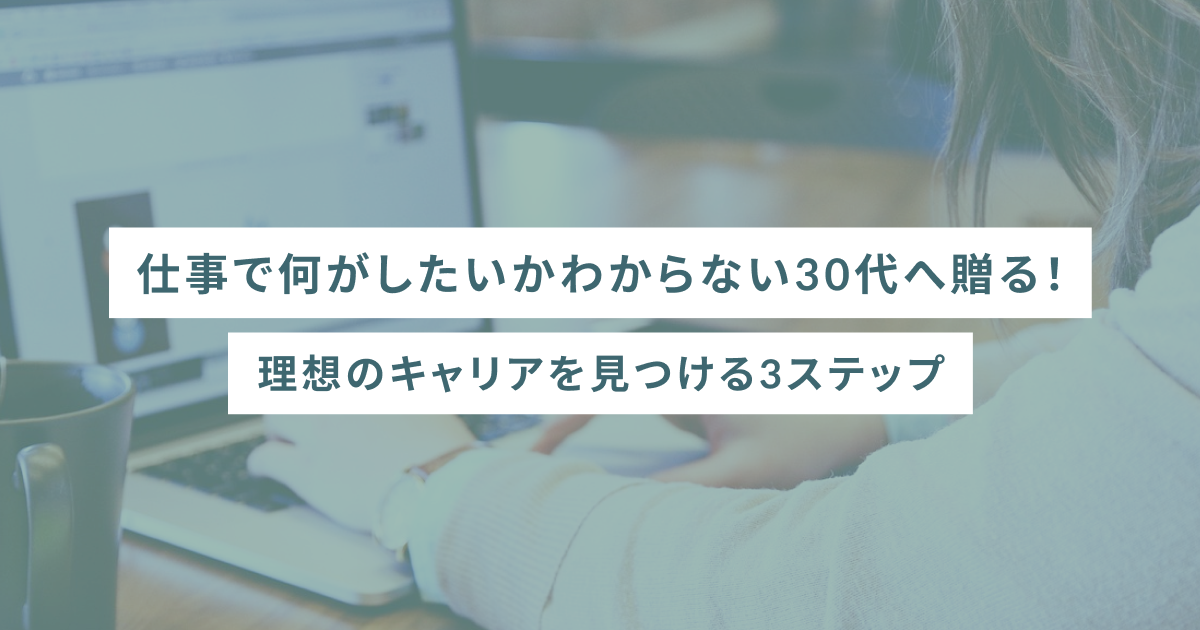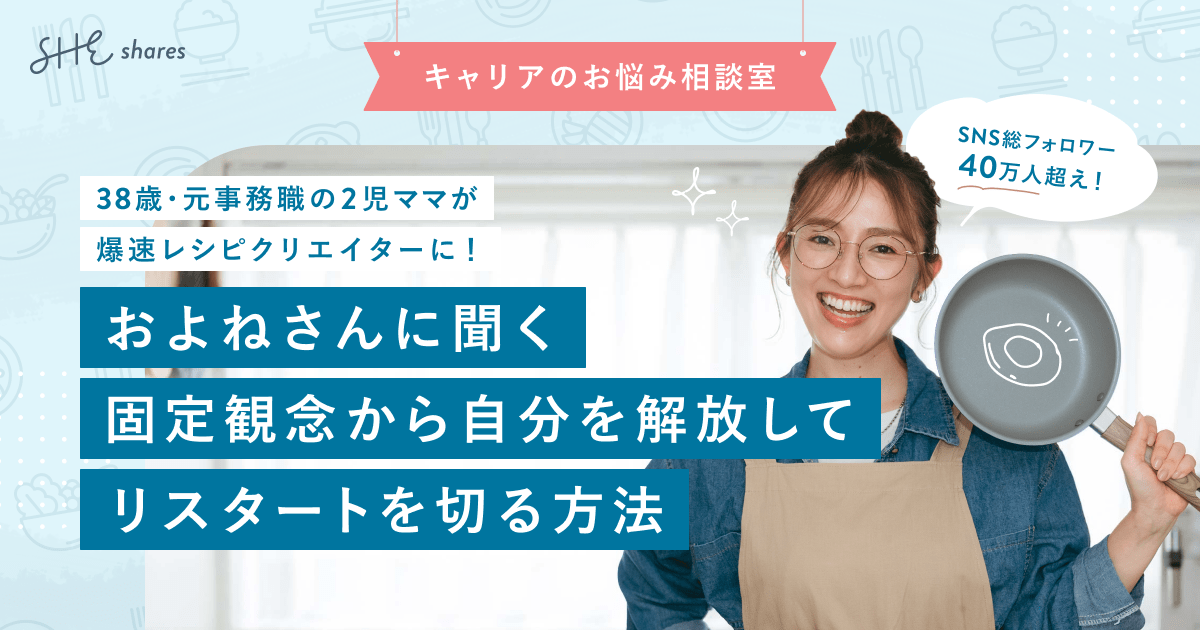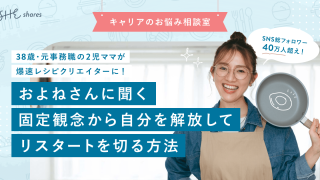ビジネス環境がめまぐるしく変化する今、幅広い知識や経験を生かして活躍できるゼネラリストの注目度が高まっています。プロジェクトで重宝されやすいほか、適職の選択肢が増えるなど多くのメリットがある職種です。
一方、スペシャリストの需要の高まりから、「ゼネラリストの将来性は本当にあるのか?」と不安になる人もいるでしょう。
そこで本記事では、ゼネラリストとは何かを紐解いたうえで、スペシャリストとの違いや適正の見極め方、どんなメリットがあるのかなどを詳しく解説します。ゼネラリストの今後についても触れるので、ぜひ最後までお読みください。
ゼネラリスト(ジェネラリスト)とは?

ゼネラリストとは、豊富な経験や幅広い知識を生かしてオールラウンドに活躍できる人材のことです。「ゼネラリスト」という言葉が普及していますが、本来の英語の発音に近い「ジェネラリスト」と呼ばれることもあります。ちなみに、英語の「generalist」の意味は「多方面の知識を持つ人」「博学な人」「万能家」です。
ビジネスシーンでは、特定の知識やスキルを極めているスペシャリストとよく比較されます。それぞれの特徴を理解しておくと、今後のキャリアを考える際に役立つかもしれません。まずは、ゼネラリストの特徴を解説します。
ゼネラリストの特徴
ゼネラリストの特徴は主に以下の3つです。知識やスキルの幅、視野の広さなどに注目しつつより深く理解していきましょう。
万能型である
幅広い知識の持ち主であるゼネラリストは、万能型のプレイヤーといえます。分野を横断した複合的な知識や経験を持っている人が多いため、さまざまな知識やスキルを生かして問題を解決し、プロジェクトを成功に導けるでしょう。
時には、不測の事態に陥った際の予備要員としての役割を担うことも。幅広い業務をカバーできるオールラウンド型の特性を持つゼネラリストは、チーム全体のバランスを取れる頼もしい存在になり得るのです。
各所との調整を得意とする
幅広い分野に精通しているゼネラリストは、他部署や担当者との連携や交渉をスムーズに進める調整役としても力を発揮します。多様な価値観を持つメンバーの意見をまとめ、必要に応じて専門性の高いスペシャリストの力を借りながらプロジェクトを推進できるでしょう。
たとえば、製品開発の段階でマーケターとエンジニアの要望が食い違った際も、双方の立場を理解した折衷案を見つけやすい点が大きな強みです。複数の選択肢を検討し、柔軟に対応できるゼネラリストがいることで、チーム全体のパフォーマンス向上が期待できます。
広い視野を持つ
ゼネラリストには、物事を俯瞰して考えられるという強みもあります。豊富な経験を通じて得た幅広い分野の知見により、多角的な判断ができる点も魅力です。
特にビジネスシーンでは、これまでに経験したことのないトラブルに見舞われたり、臨機応変な対応を求められたりする場面が多くあるでしょう。そうした不足の事態に陥った場合も、広い視野を持ったゼネラリストであれば、状況に応じたスムーズな対応ができるのです。
ゼネラリストとスペシャリストの違い
ゼネラリストとスペシャリストは、多分野を広く扱うか、1点集中で専門性を極めるかという点で大きく異なります。幅広い分野に関する情報を常に刷新しつつ人脈を構築することに関しては、ゼネラリストが長けているといえるでしょう。一方スペシャリストは、特定の分野に関する知識を深め、専門とする業務に特化しているのが大きな強みです。
そのためゼネラリストとスペシャリストは、業務面での性質において対照的であるといえます。チーム内ではお互いに支え合い、協力体制を築くことが大切です。ゼネラリストがスペシャリストに業務を割り振り、専門知識のあるスペシャリストが実務に関するフィードバックを行うなど、お互いに自分の能力を最大限発揮できるような仕組み作りを行いましょう。
ゼネラリストの適正
ゼネラリストは、以下のような強みを持つ人に向いています。
- コミュニケーション能力が高い人
- 柔軟性のある人
- 学習意欲が旺盛な人
- チームをまとめる経験をしたことがある人
幅広い業務をスムーズにこなすためには、多彩な分野への興味や新しい情報を吸収する姿勢が欠かせません。また、さまざまな職種・ポジションの人と関わる場面が多いため、相手の意見を汲み取ってまとめる力や状況に合わせて臨機応変に対応できる力を持つ人も向いているでしょう。
ゼネラリストに向いているかどうか診断したい人は、まず上記の特徴に当てはまるかを基準にするのがおすすめです。逆に、誰にも負けない得意分野がある人や、はまったらとことんやり込む凝り性な人は、スペシャリスト向きかもしれません。
ゼネラリストのメリット
スペシャリストと比較して専門分野を持たないゼネラリストは「役に立たないのでは?」と思う人がいるかもしれませんが、チームにとって欠かせない存在です。ゼネラリストとして活躍することで得られるメリットは、主に以下の3つあります。
メリットを知っておくと今後のキャリアを考える際に役立つでしょう。それぞれ詳しく解説します。
さまざまなプロジェクトに貢献できる
一般的にゼネラリストとなる人は、多分野に関する幅広い知識を持っていたり、チーム全体を俯瞰してみてきた経験を持っていたりする人が多いです。そのため、特定の部署に限らず、営業やマーケティング、人事、財務、顧客サービスなど、あらゆるチームの業務に柔軟に従事できるでしょう。
特に設立したばかりのスタートアップや、経営全体を俯瞰できる人材を求めている企業にとって、柔軟性を持って業務にあたれる人材は貴重な存在です。多角的な視点を持つゼネラリストは、企業の経営戦略に関する意思決定にも貢献できると考えられます。
管理職に向いている
多様な視点から組織全体を俯瞰できるゼネラリストは、管理職向きです。たとえばプロジェクト内容に合わせて組織内の人員を調整したり、予算を管理したりなど、メンバーがスムーズに業務を進めるために欠かせない環境作りが管理職の主な仕事ですが、まさにゼネラリストにうってつけのポジションといえるでしょう。
特定の専門領域にとらわれないことで、新たな取り組みやイレギュラーな事態に柔軟に対応できる点も、管理職としての適正がある理由です。特定の分野でスキルを高めるのが苦手な人でも、ゼネラリストとしてのスキルを高めていくと、管理職としてのキャリアを構築できるかもしれません。
キャリアの選択肢が広がる
ゼネラリストは、これまでの知識や経験をさまざまな場面で応用できるケースが多いため、新しい環境や役割にスムーズに馴染みやすいです。たとえば、営業から企画へジョブチェンジした場合でも、コミュニケーション能力や調整力など、共通して求められるスキルを生かせます。
広い視野で全体を見渡せる視点があるからこそ、部署間の連携や潜在的な課題の抽出、リスク管理などにも長けているケースが多いです。どこへ行っても使える強みが評価されれば、リーダー候補として抜擢される可能性も。ゼネラリストは業界や会社の枠を越えて活躍しやすいだけでなく、キャリアパスの選択肢が広がるポジションでもあるといえるでしょう。
ゼネラリストのデメリット
ゼネラリストは幅広く活躍できるメリットがある一方、その特性がデメリットに働く場合もあります。主なデメリットは大きく分けて以下の2点です。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
器用貧乏になりがち
ゼネラリストは幅広い知識や経験を得られる半面、専門分野のスキルが育ちにくいデメリットがあります。業務で高度な専門性が求められる場面では、スペシャリストに任せることになるでしょう。
また、組織の運営を考えると、ゼネラリストだけであらゆるトラブルを完全に解決するのは難しいケースも少なくありません。経営陣としては、比較的安定した業務にゼネラリストを配置しつつ、スペシャリストを徐々に育てるなど、人材配置や育成の工夫が求められます。さらに、チームメンバーやスペシャリストを信頼し、思いきって任せる器量も、ゼネラリストとして大切な要素になりそうです。
得意分野をアピールしにくい
ゼネラリストは幅広い経験を持つ一方、専門分野の深さではスペシャリストに及ばず、転職時に能力を可視化しにくい弱点があります。そこでおすすめなのが、実績や資格取得により知識やスキルを客観的に証明することです。
たとえば、中小企業診断士やマーケティング・ビジネス実務検定などの資格を取得し、経営やマーケティングの知識をアピールすると、組織内で高く評価される可能性が広がります。多様な経験に資格を組み合わせれば、特色あるオールラウンダーとして活躍しやすくなり、キャリアアップのチャンスも増えるでしょう。
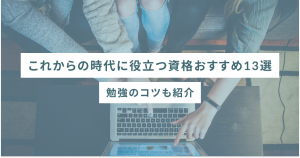
ゼネラリストに適したポジション・職種
ここからは、ゼネラリストに適したポジション・職種を紹介します。
最近ではリスキリングを推進する動きもあり、働きながらスキルを身につけやすい環境になってきました。職種に合わせて必要なスキルを磨けば、さらに役立つ人材として成長できるでしょう。それぞれのポジション・職種について詳しく解説します。
人事・総務
ゼネラリストに向いている仕事の一つに、人事や総務などのバックオフィス業務があります。採用スケジュールの調整や人材配置など幅広いタスクをこなす人事には、各部署とのコミュニケーションが欠かせません。
加えて、備品・消耗品・固定資産などの管理や保安・防災、福利厚生業務、施設管理、文書管理、社内行事の企画・運営といったさまざまな業務があります。多岐にわたる業務を担うため、柔軟に対応できる力が必要です。担当範囲が広い業務こそ、ゼネラリストの視野の広さが生きるポジションといえるでしょう。
マネージャー・管理職
マネージャーや管理職は、企業のビジョンを踏まえて組織を指揮し、メンバーを支援する重要なポジションです。特にプロジェクトを成功へ導くうえで、豊富な経験と幅広い知識を兼ね備えたゼネラリストは大きな力を発揮できます。
たとえば、チームの状況や経営状況を広く見渡して人員や予算に関する総合的な判断を担う管理職の業務では、ゼネラリストの豊富な知識や広い視点が大いに役立つでしょう。こうした総合力が必要とされるポジションには、ゼネラリストが適しているのです。
コンサルタント
ゼネラリストに向いている職業の一つとして、コンサルタントが挙げられます。コンサルタントとは、クライアントの課題を分析・特定し、解決まで導く専門家のことです。最近では提案だけにとどまらず、実行支援まで行うことも少なくありません。コンサルタントが活躍する分野は多岐にわたりますが、一般的に以下3つの仕事内容が共通しています。
- クライアントの現状分析と課題の把握
- 課題に関する情報の収集
- 課題解決に向けたビジョンの策定と実行支援
クライアントに対して的確な提案を行うためには、幅広い知識や社会情勢への洞察力が求められます。時には柔軟な発想や問題解決スキルも必要です。総合力を発揮する点で、コンサルタントはゼネラリストの資質を存分に生かせる職業といえるでしょう。
Webディレクター
Webディレクターは、Web制作においてプロジェクト監督・指揮・管理を担います。プログラマーやデザイナーをまとめてクライアントの要望に沿ったサイトを構築することが、Webディレクターに求められる大きな役割です。
企画立案から予算管理、運用まで業務領域が広く、チームを導く総合力が必要となります。幅広い知識とマルチタスク能力が求められるため、視野の広いゼネラリストにぴったりのポジションといえるでしょう。
スタートアップ・ベンチャー企業の社員
スタートアップやベンチャー企業は、ゼネラリストが活躍できる舞台の一つです。基本的に少人数体制の企業がほとんどのため、創業者や社員が複数の業務を兼任することも多く、まさにマルチタスク力が求められます。
創業間もない企業や成長段階の組織では、ゼネラリストが活躍しやすいでしょう。もちろん、会社が成長して組織規模が大きくなり、スペシャリストが増えた段階でも、全体を俯瞰してまとめるゼネラリストは必要不可欠な存在であることに変わりはありません。
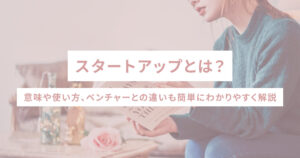
「ゼネラリストは時代遅れ」って本当?
専門性が重視される風潮から「ゼネラリストは時代遅れだ」とされ、スペシャリストの需要が高まっているといわれることがあります。ここでは、スペシャリストが求められるようになった背景と、ゼネラリストの今後について見ていきましょう。
スペシャリストが求められてきた背景
近年のIT技術の発展にともない、処理すべき情報量が増加して業務の専門化が進みました。そのため、多くの業務で専門的な技術や知識が求められています。単純な作業の自動化が進んで複雑な知的労働の割合が高くなったことで、これまで以上に専門的な領域に強みを持つ人材が求められるようになりました。
今後もIT技術の進歩にともない、スペシャリストを求める声はますます高まっていくでしょう。特に最近は終身雇用が衰退しつつあり、職務内容と成果目標に合わせて人材を採用する「ジョブ型雇用」への切り替えが広がっています。雇用形態の変化も相まって、特定のスキルを持つスペシャリストが即戦力として重宝されるようになってきたのです。
ゼネラリストの今後
専門分野を深く追求するスペシャリストと、幅広い業務に対応するゼネラリストは、一見すると真逆の特性を持つ人材ですが、「プレイングマネージャー」というポジションで両立を目指す道もあります。
たとえば、営業職で成果を出した後、マネージャーとしてチームをまとめながら自らも営業を続ける働き方が考えられます。実務とマネジメントを両方担う分負担は増えますが、現場を把握しながら組織を動かせる人材は、企業や転職市場で重宝されるでしょう。ゼネラリストとして末長く活躍するには、時代に合わせた役割を担えるようになることが大切です。
時代のニーズにあったゼネラリストを目指そう
人材の流動化が進む今、あらゆる角度から物事を捉えてプロジェクト全体をまとめ上げる力がより一層求められています。特にこれからの時代のゼネラリストは、幅広い知識だけでなく、組織や経営全体を俯瞰して捉えられる力やマネジメントスキルを習得することが大切です。
もし「自分の可能性をもっと広げたい」「時代の変化があっても通用する能力を身につけたい」と考えているなら、オンラインキャリアスクールSHElikes(シーライクス)をチェックしてみてください。
プロジェクトマネジメントや基礎的なビジネススキルを身につけながら、デザインやプログラミングなどの専門技術まで学べるのが魅力です。興味がある方は、ぜひ一度無料体験レッスンに参加してみてはいかがでしょうか。