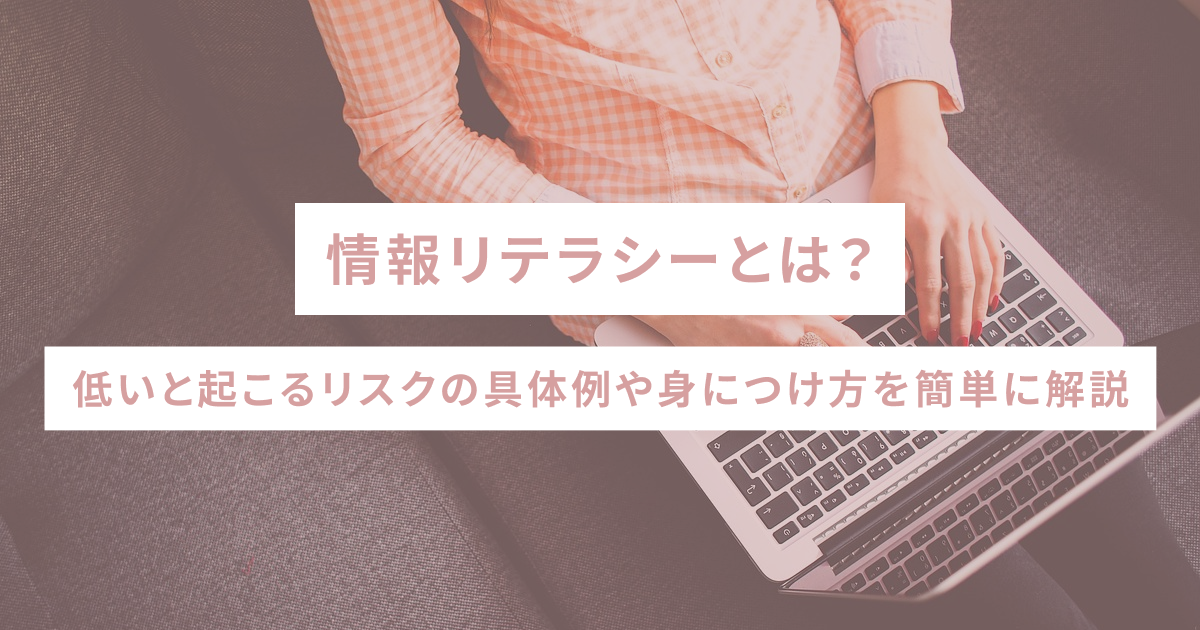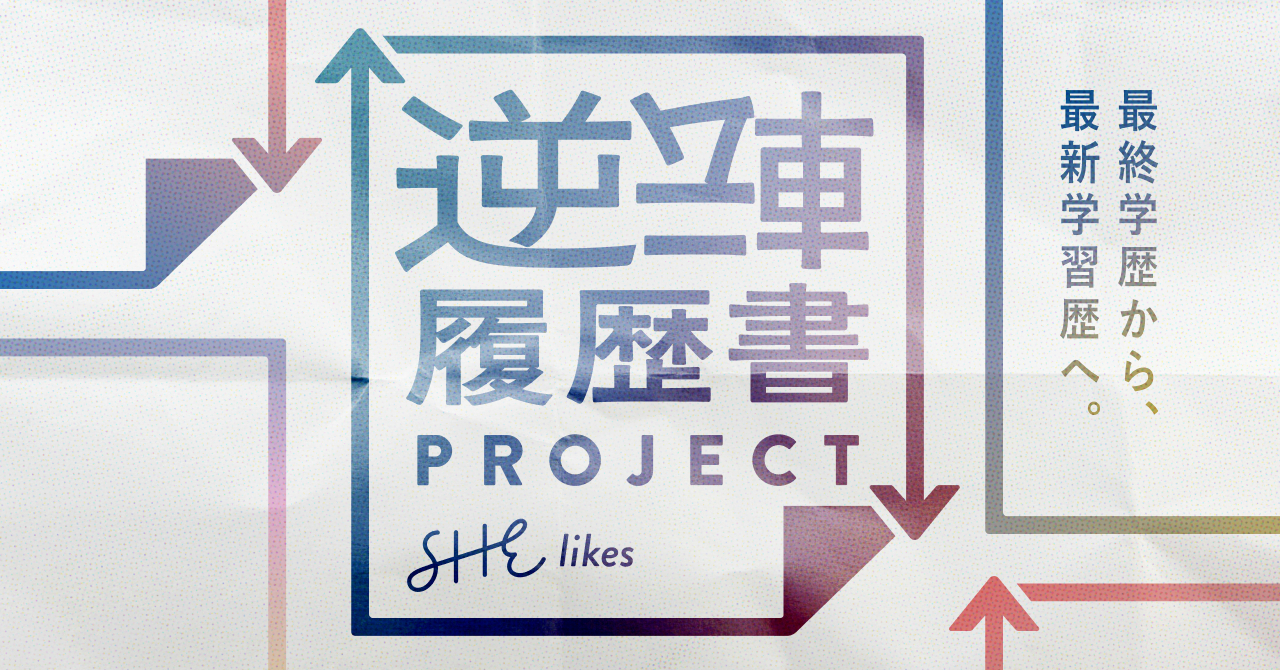インターネットの普及・発達が急速に進む現代において、情報リテラシーは身につけておくべきスキルの一つです。一方で「情報リテラシーとは具体的にどんなもの?」と疑問をもつ人もいるのではないでしょうか。
そこで本記事では、「情報リテラシーとは何か?」といった概要を簡単に紐解いたうえで、高める方法やリスクを抑えるための対策などをわかりやすく解説します。情報リテラシーへの理解を深めたい人や情報社会で避けては通れないリスクについて詳しく知りたい人は、ぜひ最後までお読みください。
情報リテラシーとは?簡単に解説

情報リテラシーとは、簡単にいうと「正しい情報を入手して活用できる能力」のことです。インターネットを通じてさまざまな情報にアクセスできるようになった今、個々の情報リテラシースキルが重要視されています。
Oxford Referenceでは、情報リテラシーは「問題解決のために情報を入手、識別、評価、整理する能力」と定義されています*1。具体的な能力は、以下の3つです。
- 質の高い情報を識別するスキル
- フェイクニュースに気づくスキル
- 必要な情報を見つけるリサーチスキル
インターネットの普及により個人が自由に情報発信できるようになった現代では、利便性が向上した反面、誤った情報を受け取ってしまうリスクもあります。正しい情報を見抜き、活用する力が求められているのです。
ネットリテラシーやメディアリテラシーなど、似た言葉との違い
情報リテラシーと似たような意味合いで使われる言葉に「ネットリテラシー」や「メディアリテラシー 」などがあります。それぞれの違いは、簡単にいうと「対象とする範囲」に集約されます。以下の表にそれぞれの定義をまとめました。
| 用語 | 意味 | 対象とする範囲 |
|---|---|---|
| ネットリテラシー | インターネットの情報を正しく 理解して使いこなす能力 |
インターネット上に存在する情報全般 |
| メディアリテラシー | メディア(広告、ニュース、映画、書籍など) の情報を読み解き使いこなす力 |
あらゆるメディア・媒体における情報 |
| ITリテラシー | コンピュータやネットワークといったIT(情報技術)を 正しく理解し、業務や日常生活で活用できる能力 |
IT(情報技術) |
情報リテラシーは、上記3つのリテラシーを内包する言葉ともいえるでしょう。情報リテラシーについて考えるとき、自分にはどの分野のどのスキルが必要なのか、細分化して捉えることが重要です。
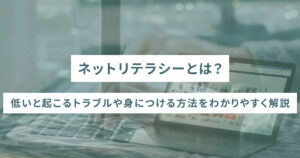
情報リテラシーが重要視される背景
情報リテラシーが重要視される背景には、現代の急速なテクノロジーの進化による「情報の増加」があります。現代は、デジタルデバイスとインターネット環境があれば、誰でも情報の入手・発信ができる時代です。
しかし、私たちが日常で取り込む情報のなかには、フェイクニュースや不確かな内容が紛れていることも珍しくありません。情報リテラシーを高めることは、本当に必要な情報を見つけ活用するために役立つでしょう。ここでは、情報リテラシーが重要視される2つの背景について詳しく解説します。
インターネットの普及による誤発信の増加
インターネットが普及し、誰もがSNSやブログを通じて容易に情報を拡散できるようになった半面、真偽が不確かな内容が瞬く間に広まりやすくなりました。その結果、社会的混乱を招いてしまうケースもあります。
いち早く情報をキャッチできる環境が整った一方で、スピードを優先するあまり曖昧な情報が流通しやすくなっているのです。誤情報を一度拡散してしまうと訂正が難しいので、発信する前に情報の正誤を判断できるスキルが欠かせなくなってきたといえます。
SNS等での個人発信の広がり
ひと昔前と比べると、FacebookやInstagram、X(旧Twitter)などを通じ、誰もが手軽に情報を公開できるようになりました。その結果、誤情報や誹謗中傷が瞬く間に広まり、大きな社会問題へと発展する事例が増えています。炎上もその一つです。
特に私的な感情や根拠の乏しい主張が拡散されると、当事者だけでなく多くのユーザーを巻き込み、深刻な混乱を招く恐れも。そのため、投稿前に情報の正確性や表現を再確認する姿勢が欠かせません。個人発信をする際も、情報リテラシーを身につけておく必要があるのです。
情報リテラシーを高めるための政府の取り組み
令和5年6月、総務省は「ICT活用のためのリテラシー向上に関するロードマップ」を公表しました。そのなかで、国が目指すべきゴールと現在の課題への解決策を示しています。
引用:総務省|「幅広い世代を対象としたICT活用のためのリテラシー向上推進事業」より
令和5年には、これからのデジタル社会において身につけるべきリテラシーの全体像を定めました。主に以下の5つの能力を身につける必要があると主張し、各能力の到達レベルを詳細に区分しています。
引用:総務省|「幅広い世代を対象としたICT活用のためのリテラシー向上推進事業」より
令和6年以降は年齢層別に必要な知識やスキルが習得できるよう、教材開発などを行う方針を固めているようです。
一方海外諸国では、先行して情報リテラシー教育への取り組みが進んでいます*3。特に欧米各国では「Digital Education Action Plan」や「Online Media Literacy Strategy」をいち早く策定し、情報リテラシーを身につける教育体系を整えてきました。
総務省は、今後海外諸国の先行事例を参考に教材の開発を行い、保護者や教職員、生徒など、それぞれに適した取り組みを展開することが望ましいと示しています*3。継続的な施策の強化により、誤情報が拡散しやすいデジタル社会のなかでも、正しい情報を見極められるようになることが期待されているといえるでしょう。
情報リテラシーが低い状態におけるリスクの具体例
情報リテラシーが低い状態で起こり得るリスクには、以下のような例があります。
よくあるリスクを把握しながら、適切な防止策や対処法を考えてみましょう。
正確な意思決定ができない
正しい情報を見極めるスキルがない場合、間違った情報をもとに意思決定をしてしまう可能性があります。すべて鵜呑みにするのではなく、正しい情報である根拠を見つけながらリサーチを行わなければなりません。
たとえば、個人が提供している情報は、発信者のバイアスや思い込みが内容に反映されていることもあるでしょう。情報の正誤が判断しかねる場合は、専門機関や関連企業のWebサイトを確認して情報を照らし合わせるなどの作業も必要です。信頼できる一次情報をもとに、誤情報かどうかを判断する癖をつけてみてください。
サイバー攻撃によって被害に遭う
ITツールへの知識不足により起こり得る被害として、サイバー攻撃によるコンピュータの乗っ取りや情報漏洩が挙げられます。なかには、以下のような場面で被害に遭うケースも。
- スパムメールに気づかずファイルを開く
- 悪質なWebサイトに気づかずアクセス
- 公共Wi-Fiの利用によるウイルス感染
たとえば「マルウェア」と呼ばれる悪質なソフトウェアに感染してしまうと、個人情報が抜き取られたり、デバイスの操作ができなくなったりします。普段から上記のようなリスクがはらんでいることを念頭に置き、パソコンやインターネットを使用しましょう。
機密情報の漏洩や紛失が懸念される
情報リテラシーが必要になる場面は、インターネットを利用するシーンだけではありません。対面で人と話すときに「相手に伝えて良い情報」と「企業内に留めておくべき情報」を認識しておかないと、内部機密が社外に漏洩・拡散する可能性があります。
漏洩した内容によっては、「独自の技術を他社に奪われる」「世間から反感を買う」など、企業が大きな損害を受ける可能性もあるでしょう。社外機密を従業員全員が把握し、適切な行動を取れるように、組織内で一律のルールを規定することが重要です。
不適切な情報発信で炎上する可能性がある
特に企業の公式SNSアカウントやWebサイトなどでは、情報リテラシー不足が原因で炎上するリスクがあります。以下に炎上の可能性がある発信内容の例を挙げました。
- 差別的、モラルが欠如した発信
- 著作権・意匠権・肖像権を侵害する発信
- 真偽が定かではない情報の発信
ビジネスを拡大すべく、SNSを活用する企業は増えてきています。一方、不適切な投稿をしてしまった場合の拡散力はかなり早く、一度公開した情報の修正・完全な削除は非常に難しいです。
企業の信用度や好感度が低下すると、売上だけでなくビジネスの継続に影響が出るかもしれません。これまで築き上げてきた信頼やブランディングを一気に損なう恐れもあります。一つの投稿が大きな損失を生むこともあるので注意しましょう。
意図せず知的財産権を侵害してしまう
現代では、簡単に情報にアクセスできるからこそ、インターネットの情報が他人の財産であるという認識が薄れてしまうこともあるようです。知的財産権の侵害が発覚した場合、たとえ知らなかったとしても法的な措置や罰則が科せられる可能性があります。
悪意なく他人の著作権を侵害してしまうケースも少なくありません。たとえば、「インターネットで見つけたデザインをコピーして転用し、相手の著作権を侵害してしまう」といった事象が起こり得ます。著作権のルールを改めて調べるなどして、知的財産権への知識を高めましょう。
【個人向け】情報リテラシーを高める方法
情報リテラシーは、個人の努力で十分高められます。たとえば、以下の5つの方法を試してみると良いでしょう。
普段から気軽に取り入れられるものが多いです。現代に欠かせない情報リテラシーを身につけるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
複数ソースからの情報収集を心がける
情報収集の際は、複数の媒体をチェックすることを意識してみましょう。同じニュースでも、報道機関やSNS、媒体によって切り口が異なる場合があります。多方面から情報を得ることで、過激な意見や偏った主張に左右されにくくなるのでおすすめです。
たとえば、SNSで気になった話題を見つけたら、別のメディアや専門サイトも確認すると、発信者の意図や真偽が掴みやすいでしょう。普段読む機会が少ないであろう雑誌や新聞をあえて手に取るのも、新しい視点を得るうえで有効です。視野を広げる行動を意識するだけで、より正確な判断ができるようになります。

発信元を確認する
情報を受け取る際は、信頼できる発信元かチェックする習慣を身につけましょう。フェイクニュースに惑わされないためには、情報の出所を注意深く見極めることが重要です。特に匿名のブログやSNSでは、真偽が不明な情報と正当な情報が入り混じっています。
公的機関や専門家など、発信元の信頼度を確認したうえでファストチェックを行うと安心です。できれば一次情報までさかのぼって内容の正誤を確認すると、誤報を鵜呑みにするリスクを減らせます。
事実と意見を区別する意識を持つ
ニュースやSNSに触れるときは、事実と意見を混同しないよう注意してください。事実と意見の違いは以下の通りです。
- 事実…本当にあった不変的な出来事。誰にとっても同じ。
- 意見…個人の判断や考え。人によって変わるもの。
たとえば、コメンテーターの憶測が含まれたコメントを聞いて、そのまま真実として捉えてしまうケースも珍しくありません。「この人の意見は正しいだろう」という先入観を疑う、「考えられる」「〜のようです」といった表現はあくまで個人の主観と捉える意識を持つなどして、事実と意見を区別するようにしましょう。
情報発信の習慣をつける
情報リテラシーを身につけるには、自ら情報発信する習慣を取り入れることが効果的です。自分で調べた内容をSNSやブログにまとめる過程で、信頼できるソースの再確認や情報の正確性を意識する機会が増えます。
特にSNSやブログの場合は、発信に対してリアクションやコメントを得られることも。受信者からのフィードバックを通じて、わかりやすい表現にすることや正しい情報を届けることに意識が向くようになるでしょう。小さな実践を積み重ね、客観的かつ正確に情報を扱えるスキルを身につけていきましょう。
関連資格の取得を目指す
情報リテラシーを強化するには、資格取得を通じて段階的に学ぶ方法も有効です。試験対策の過程でセキュリティやIT関連の基礎知識を学び、実務や日常生活で実践すれば、情報リテラシーが自然と高まりやすくなるでしょう。
資格を持っていると客観的にスキルを証明できるため、信頼にもつながります。以下に、情報リテラシーを高めるのに役立つ代表的な資格試験をまとめました。身につけたい知識やスキルに合わせて、取得する資格を選んでみてください。
| 用語 | 資格の概要 |
|---|---|
| ITパスポート試験 | 情報処理推進機構が実施する国家試験。 ITやセキュリティ対策の基礎知識に加え、 経営戦略やマーケティングなど 幅広いビジネス分野が学べる。 |
| 情報セキュリティマネジメント試験 | 情報処理推進機構が実施する国家試験。 企業や組織で情報を管理する際に必要な リスク対策やセキュリティの知識を評価し、 適切な運用と保護の手法を学べる。 |
| 情報検定(J検) | 文部科学省後援で行われる試験。 情報活用、情報システム、情報デザインなど 複数の分野に分かれており、 目的に合わせて選択・受験が可能。 |
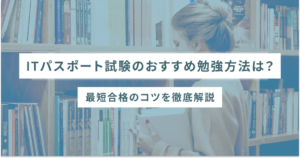
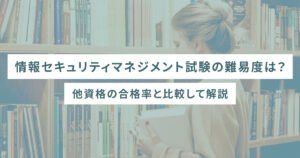
情報リテラシーを高めて正しく扱おう
情報リテラシーは、ビジネスシーンや日常生活のあらゆる場面で必要とされるスキルです。膨大な情報のなかから正しい内容を選び取り、活用できるかどうかは、私たちが安心してデジタル社会を生き抜くための大きなカギといえます。
もし「どこから始めればいいかわからない」と感じているなら、まずは基本のリテラシーやIT関連スキルを学ぶところからスタートすると効果的です。自分に合った学習方法で、段階的に知識と経験を積み重ねていくと、自然と判断力や発信力が身につくでしょう。
こうしたスキルを体系的に身につけたい人には、女性向けキャリアスクールSHElikes(シーライクス)がおすすめです。WebデザインやプログラミングなどのITスキルとあわせて、著作権とNDAについても学べます。情報リテラシーやIT関連のスキルを高めたい人は、ぜひ一度無料体験レッスンに参加してみてはいかがでしょうか。
※参考
*1:Oxford Reference「Information literacy」より
*2:文部科学省「第4章 情報教育」より
*3:総務省|「メディア情報リテラシー向上施策の現状と課題等に関する調査結果報告」p94より