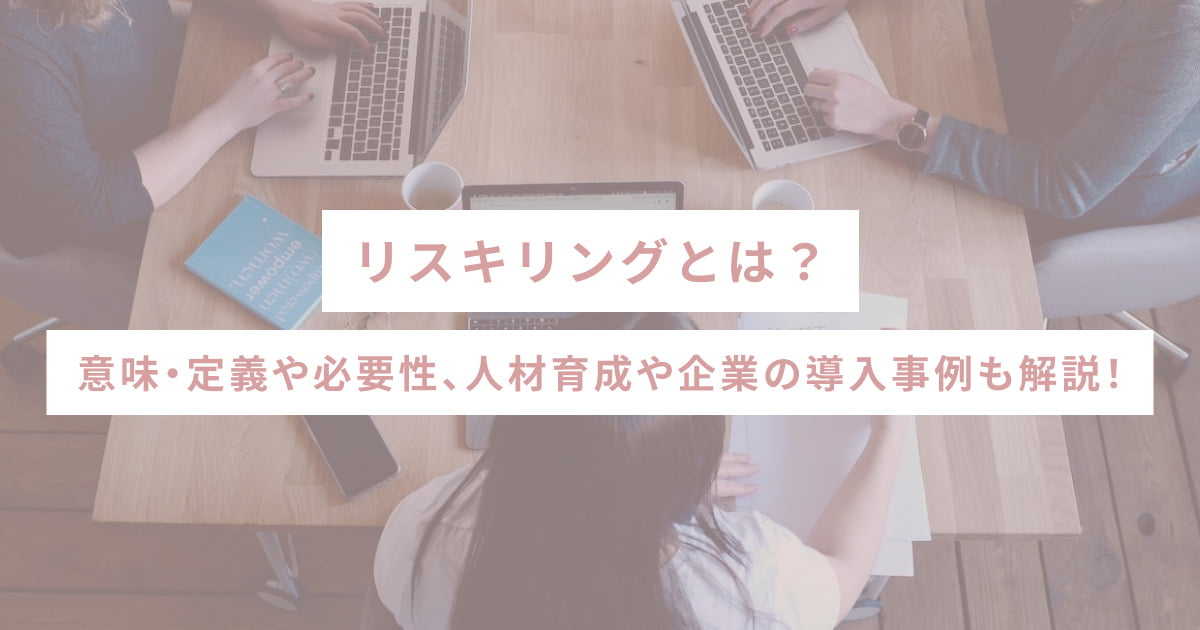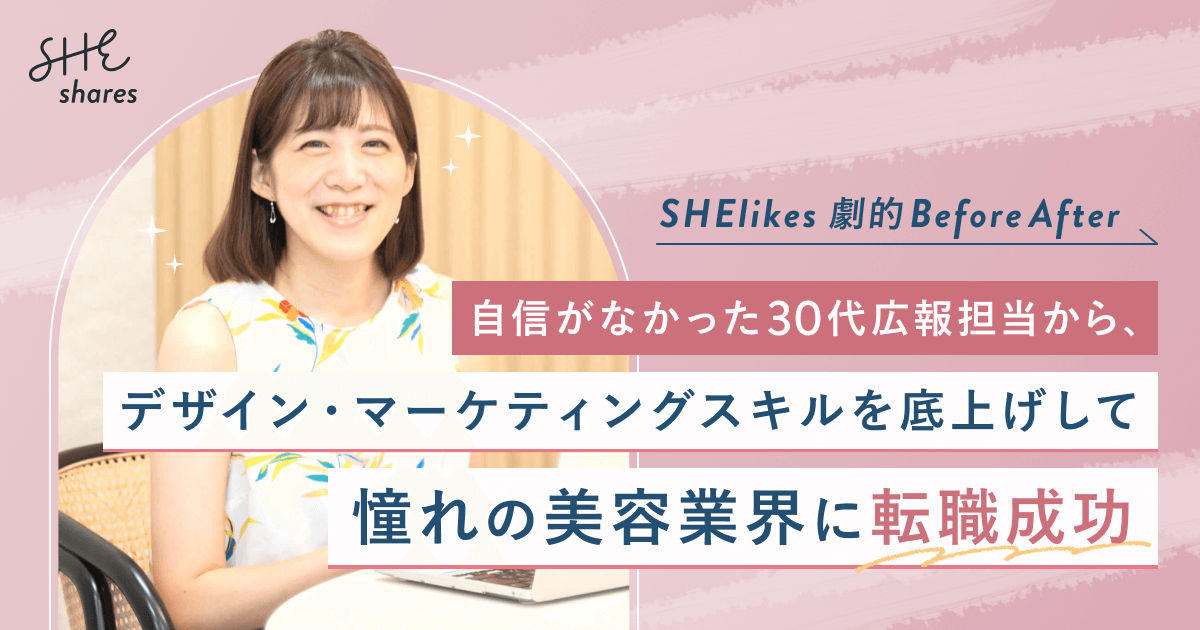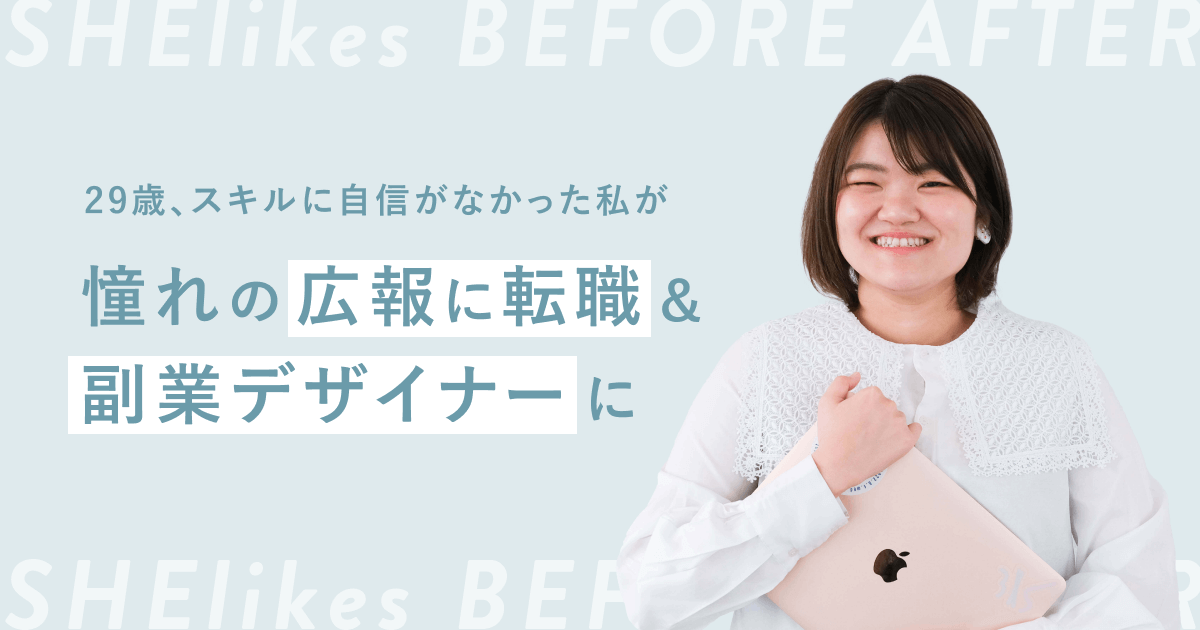リスキリングとは、企業の中長期的な成長戦略において、業務上必要とされるスキル・知識を学ぶことです。2020年のダボス会議でリスキリングが議題にあがったことや、2022年に政府が5年で1兆円規模のリスキリング支援を行うと表明したことを皮切りに、多くの人がリスキリングに注目をしています。
「リスキリングの言葉をよく耳にするものの、どういう意味か深く理解していない」
「リスキリング支援に対して、個人または企業は何をすべきか」
など、さまざまな疑問をもつ人に対して、リスキリングの定義やメリット、リスキリングへの取り組み方や事例について解説します。
リスキリングとは?
経済産業省によると、リスキリングとは「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること※1」と定義されています。
リスキリングは個人で主体的に行うものと、企業や団体がリスキリング施策を主導するものに大別されます。ただ、リスキリングや人事分野の専門家によると、「リスキリングの起点は企業や組織であるべき」という意見も見られ、企業の人事施策の一つとして進めるケースが多いでしょう。
リスキリングの必要性
リスキリングの目的は、「新しい仕事に就くこと」「今の仕事で技術革新やビジネスモデルの急速な変化に適応すること」です。この目的に照らして具体的なリスキリングを考えると、「事業でDX推進をするためにIT知識を学ぶ」「アナログな業界にAI技術を取り入れるために、ChatGPTのようなAI活用法を学ぶ」などが挙げられます。
なお、「リスキリング=IT技術の習得」という限定的な解釈には少々誤解があります。将来の経営戦略や事業計画を考慮するとIT技術への適応は避けられませんが、新しい仕事に就くことやビジネスモデルの変化への適応のためのリスキリングと捉えれば、より幅広い学習テーマが想定されるでしょう。
より具体的な学習テーマについて知りたい方は、以下の記事もあわせてご一読ください。
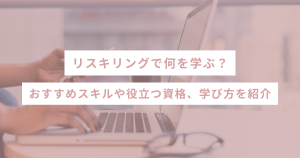
リスキリングとリカレント教育の違い
リスキリングと類似した言葉に、リカレント教育や学び直しがあります。リカレント教育とは、学校教育を離れた後に、仕事の能力を磨くための社会人教育を指します。リカレント教育と学び直しは同義語であり、厚生労働省や経済産業省、文部科学省などが連携して、社会人教育のきっかけになる支援を実施しています。
国が提供する労働者向けのリカレント教育支援には、雇用保険の教育訓練給付金やキャリアコンサルティング、公共職業訓練などが挙げられます。くわえて、事業主向けのリカレント教育支援では、人材育成支援施策である人材開発支援助成金やセルフキャリアドッグが代表的です。
リカレント教育は、社会人になっても学びと仕事を行き来しながら繰り返すことを意味しており、リスキリングと異なる概念です。また、スキルアップという言葉は、現在の仕事の役割に対して不足するスキルを習得する意味をもつため、将来の仕事を想定してスキルを学ぶリスキリングとは異なります。
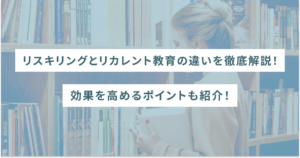
リスキリングが注目されている理由
リスキリングが世の中から注目されはじめた理由は、世界的な技術革新や、働き方の多様化などが背景にあります。ここでは、リスキリングが注目された理由を3つ解説します。
- 産業構造の変化
- 多様な人材の労働参加と企業成長
- デジタル技術への対応
それぞれ詳しく見ていきましょう。
産業構造の変化
近年、第四次産業革命としてAIをはじめとする技術革新が世界的に進み、グローバル化もあいまって、産業構造そのものが不連続的に変化を続けています。重工業が台頭した第二次産業革命の「同質な製品を大量生産する」時代とは大きく異なり、AIやDXなどの技術革新は、消費者の個別ニーズに最適化したサービスの登場やテレワークのような新たな働き方を推進しました。
今後も技術革新が進み、AIやDXが社会に浸透していくと、ハード面の設備投資ではなく人間の「知」に対する投資により差別化を図る必要が出てきます。社会・経済が変化したことで人への投資、すなわちリスキリングが重要視されてきたのです。
多様な人材の労働参加と企業成長
産業構造の変化にくわえて、少子高齢化で労働人口が減少の一途をたどる今、これまで以上に一人ひとりの労働者が貴重な存在となります。1人あたりの労働生産性を高めるには、ダイバーシティ社会を目指して、女性・シニア・外国籍人材・障がい者・フリーランスといった多様な人材の能力を引き出す必要があるでしょう。
また、組織でイノベーションを生むためには、多様な人材が多面的な発想を持ちより、企業の持続的な成長につなげる意識が重要です。働き方改革で「一億総活躍」と言われているように、多様な人材全員を戦力化するために、リスキリングをはじめとする人材教育や人材投資が必要となります。
デジタル技術への対応
IT技術の発達によって、日々新しいサービスや価値が生み出される現代では、変化に対応する力が重要視されています。変化が激しい社会・経済の中で企業価値を創造し続けるために、従業員のリスキリングが必要と考えられています。
変化に対応する必要性や、「企業はどう変わりたいのか」「そのために、どういった能力・スキルが必要か」などと具体案を考えてリスキリングに取り組まなければ、企業の中長期的な存続が危ぶまれるでしょう。
IT技術やAI、DX推進を理解し、さまざまな技術を使いこなせる人材が不可欠となったからこそ、リスキリングに注目が集まっているのです。
企業がリスキリング施策を推進するメリット
企業がリスキリング施策に取り組むメリットを3つご紹介します。
- イノベーションによる企業価値の創出
- DXの実現を後押しする
- 業務効率化や生産性の向上
それぞれ詳しく解説します。
イノベーションによる企業価値の創出
リスキリングは、新たな知識・スキル習得をして技術を使いこなすだけではありません。専門性の高い知識を得たうえで、課題解決の提案・推進を行い、イノベーションを生み出します。イノベーションが生まれれば新たな企業価値の創出につながり、市場で生き残るための企業成長が期待できるでしょう。
DXの実現を後押しする
企業がDXに取り組む際は、バリューチェーン上のありとあらゆる職務が変化するため、全従業員のリスキリングが不可欠となります。逆にとらえれば、全ての従業員がリスキリングを行って新しい仕事のやり方を習熟し、新たな職務(ジョブ)遂行に必要なスキルを身につけることができれば、DXの実現がより現実的になると考えられます。
業務効率化や生産性の向上
従業員のリスキリングを支援し、デジタルツールの活用や高度専門技術による課題解決が進めば、業務効率化や一人ひとりの生産性向上につながります。ただ、リスキリングで学ぶ分野の専門性・難易度が高いほど、習得するのに時間を要するため、リスキリング施策を行えばすぐに生産性が向上するわけではありません。
長期的な計画を立てながら、リスキリングによる構造改革や生産性向上に努める視点が大切です。
企業がリスキリングにより人材育成に取り組むための4ステップ
企業がリスキリングを進めるステップをご紹介します。
- 人事戦略立案と人材要件を整理する
- 従業員のマインドセットを作る
- リスキリングの機会提供を行う
- リスキリングを組織に浸透させる
それぞれ詳細を説明します。
1.人事戦略立案と人材要件を整理する
最初のステップでは、経営戦略および事業計画と連動させた人事戦略を立案します。さらに、人事戦略の1つとして人員計画を立て、事業に必要とされる人物像を設定し、その人物像に紐づくスキルや知識を洗い出します。もちろん、IT技術を使いこなせる高度専門人材はどの企業でも必要な存在ですが、リスキリングの対象はITやAIといったテーマだけではありません。
自社の事業に新たな価値を見出すために必要な要件は何か、今後の企業に求められるものは何か、企業が掲げるビジョン達成のためにどのようなスキルの人材が必要かなど、複数の視点で考えながら要件整理をしましょう。
2.従業員のマインドセットを作る
従業員にいきなり学習機会を提供するのではなく、より効果的に学習に取り組める下地作りを行います。例えば、リスキリングを推進する専門部署やチームを立ち上げたり、デジタルツールの活用で課題解決事例を学ぶ機会を作ったりする方法があります。
大前提として、日本の労働者は自己啓発時間が海外諸国よりも短く、能動的に学習する習慣がありません。学ぶための準備運動として、マインドセットを作るステップを取り入れると良いでしょう。
3.リスキリングの機会提供を行う
リスキリングはeラーニングのような教材を一律に与えるだけでなく、社内で実践的な学習の場を提供するアプローチも有用です。リスキリングの企業事例を見ると、「デジタル化プロジェクトに非デジタル部門の人材を登用する」といった実践の場を与えて学ばせる取り組みもあります。
ほかにも、「手を挙げた人材に責任をもたせ、学ばざるを得ない仕組みを作る」といった、制度・ルール創設による機会提供も可能です。
4.リスキリングを組織に浸透させる
リスキリングはたった1日、1週間などの短期間の学習をすれば終わりではありません。なぜ学ぶのか、学んだうえでどのような仕事ができるようになるか考えながら、継続的に学習を行う必要があります。
経営者自らが学んで従業員に伝え続けたり、リスキリングで得たスキルにより課題解決した従業員を評価したりするなど、組織に浸透・定着させることが重要です。
企業のリスキリング導入事例
リスキリング施策を導入した企業事例を4社ご紹介します。
- トヨタ自動車株式会社
- 西川コミュニケーションズ株式会社
- 鶴巻温泉 元湯陣屋
- 久野金属工業株式会社
それぞれの事例を詳しくご紹介します。
トヨタ自動車株式会社(大手自動車メーカー)
大手自動車メーカーのトヨタ自動車株式会社※2は、多様な人材こそがイノベーションを生み出す原動力となると考え、「採用」「人材シフト(異動)」「再教育」の3つに取り組んでいます。2025年までに、リスキリング教育の受講者を9,000人に拡大することを目標としつつ、社内に散らばっていたデジタル関係の育成講座の整備・体系化に取り組んでいます。
ただ単に車を「作る人」を育成するのではなく、「企画する人」「推進する人」「データを活用する人」など多様なデジタル人財を育成、採用して、新たな価値創出を進めていくそうです。
西川コミュニケーションズ株式会社(印刷業)
印刷業を営む西川コミュニケーションズ株式会社※3は、デジタル化に伴い厳しい状況に置かれた既存事業を残しつつ、長期的なリスキリングにより3DCGデザイン事業の実施を決断しました。企業所在地を鑑みると、IT人材の外部採用よりも人材育成すべきと判断したそうです。
1年ほどかけて夜間の専門学校通学の支援や、外部講師による教育機会を提供。本人のやる気、自主性を尊重するために「手挙げ制」をとりながら伴走を続けた結果、多くのDX関連の新規事業を創出しました。また、紙を扱うデザイナーから新規事業の営業職への転換など、リスキリングにより新たな職務を担う人材も多く輩出しました。
鶴巻温泉 元湯陣屋(老舗旅館)
1918年創業の老舗旅館である神奈川県の鶴巻温泉 元湯陣屋※4は、リスキリングにより経営を黒字化しました。倒産寸前だった頃は、パソコンを使える従業員が1人しかおらず、顧客情報は従業員の記憶や紙のメモに頼る状態だったそうです。意を決して予約管理システムの導入を行い、紙の台帳は一切使わないように徹底。予約管理システムにタイムカードを備えることで、従業員が嫌でも使える状態を作り出しました。
座学ではなく実践を通して粘り強く取り組み、従業員が使いやすいUIにこだわり続けた結果、従業員自身がデータを主体的に使いこなせるようになり、企業風土も大きく変化したそうです。
久野金属工業株式会社(自動車部品のプレス加工メーカー)
自動車部品のプレス加工メーカーの久野金属工業※5は、徹底的な自動化でDX推進を行い、変化創出のリスキリングを成功させています。同社は基盤システムの開発の際に、あえてシステム会社に丸投げをせず、共同で開発を進めました。しかし、当時は社内に開発プロジェクトを担える人材がおらず、育成の必要があったため、複数名をプロジェクトメンバーにアサインして巻き込み型かつ実践の場でリスキリングに取り組みました。
多くの実践と学びを繰り返した結果、仕事の自動化・効率化が進み、最終的には時間外労働の削減につながったそうです。残業削減により従業員の意欲が向上し、さらなるリスキリングに取り組もうと、好循環サイクルが回っています。
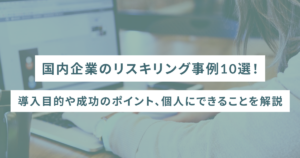
企業がリスキリングを実施するときのポイントや注意点
企業が、従業員のリスキリングを推進する施策をおこなうときのポイントや注意点を解説します。
- 従業員の意識改革が必要
- 経営戦略・人事戦略と連動したリスキリング施策の検討
- 社内周知と段階的導入を推奨
それぞれ詳しく解説します。
従業員の意識改革が必要
リスキリングに取り組んだ企業の中には、「せっかくスキル習得の機会提供をしたのに、従業員が積極的に学んでくれなかった」という失敗談も多く聞かれます。
そもそも、日本の大企業では終身雇用制を長く採用しており、社内でジョブローテーションをしながら、企業の事業・人員状況にあわせてキャリアを描くことが一般的でした。そのため、個人が自ら「主体的に自分のキャリアを考え、選びとる」ことに慣れていないのです。
「新卒で大手企業に入れば、定年までキャリアは安定」という考えが根付いた従業員に対して、ある日突然「自ら新しいスキルを習得し、自律的なキャリアを描いてください」と伝えても、なかなか適応は難しいものです。
まずは、社会・経済情勢の変化や、企業が今後目指す方向性の共有、そして従業員に今後求められる要素について丁寧な説明を行いながら、意識改革に取り組む必要があるでしょう。
経営戦略・人事戦略と連動したリスキリング施策の検討
リスキリングは、個人が主体的に行う必要がある一方で、個人が興味をもったことを好き勝手に学べばいいわけでもありません。また、どんなに質の良い学習教材を用意しても、その内容が先々の経営戦略や事業に結びつかなければ無意味な投資となるでしょう。
まずは企業が中長期経営計画と経営戦略を立てて、経営戦略に紐づく人事戦略を描き、その中に採用や育成、組織開発といったテーマを連動させます。今後企業に求められる人物要件を見出しながらリスキリング施策を進めるよう注意が必要です。
社内周知と段階的導入を推奨
リスキリング施策をはじめ、企業が新たな人事施策に取り組む際、どうしても現場に負荷がかかります。企業の新しい施策に対して柔軟に受け入れる従業員もいれば、「忙しくて業務以外は対応できない」と反発する人もいるでしょう。そのため、リスキリングはいきなり全社で取り組むのではなく、特定の部署や職種から限定的にスタートして、段階的導入を行うのも手です。
また、リスキリングの意味、目的、取り組むメリットなどを丁寧に説明し、繰り返し社内周知に取り組みながら従業員の理解を得ることも重要です。経済情勢の変化や人手不足課題を乗り越えるため、企業がリスキリング施策を推進するのは急務ではあるものの、急ぎ過ぎると失敗するリスクも潜んでいます。
リスキリングの進め方について不安がある企業は、専門家の意見をあおぎながら慎重に取り組むことをおすすめします。
「リスキリング人材」と「企業」のマッチングを促すサービスの紹介
女性向けキャリアスクールSHElikesを運営するSHE株式会社では、SHElikesでスキルを身につけた個人を「リスキリング人材」と名付け、即戦力として企業にマッチングをする「SHE WORKS」を提供しています。SHE WORKSは、リスキリング人材をマッチングして紹介するだけでなく、人材の定着・活躍までを伴走支援するサービスです※6。
リスキリングに注目が集まっている一方で、中小企業は従業員に対して十分なリスキリング支援を実施する余力がない点が課題です。自社でリスキリング施策を行うことが難しい場合は、すでにデジタルスキルやクリエイティブスキルを身につけた人材を外部パートナーとして迎え入れる方法を検討してみるのもおすすめです。
今後必要になるスキルを主体的に学び、リスキリングに取り組もう
リスキリングとは、個人が新しい仕事に就くため、または現職で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために新たなスキル・知識を習得したり、企業が学びの支援をしたりするものです。
AIやDXが社会に浸透し、産業構造そのものが変化し続ける現代で、企業が存続していくために「人への投資」は必要不可欠といえます。
リスキリングの重要性を理解していても、自社で従業員のリスキリングを促し、支援するのは非常に負荷がかかるものです。社内で育成を行うだけでなく、先々の業務で必要とされる最新技術を習得している個人を、外部採用する方法も視野に入れると良いでしょう。
なお、個人で積極的にリスキリングに取り組みたい方は、女性向けキャリアスクールSHElikesをご活用ください。SHElikesでは、幅広い業種で必要とされるIT・Webの専門スキルやクリエイティブスキルを学べます。
女性向けキャリアスクールSHElikes無料体験レッスンはこちら
*出典
*1:リクルートワークス研究所 「リスキリングとは」
*2:TOYOTA 統合報告書2022
*3:株式会社三菱総合研究所「実践事例 変化する時代の キャリア開発の取組み」
*4 *5:リクルートワークス研究所 中小企業の リスキリング入門
*6:SHE、企業とリスキリング人材のマッチングから定着・活躍まで伴走支援するサービス「SHE WORKS」を提供開始