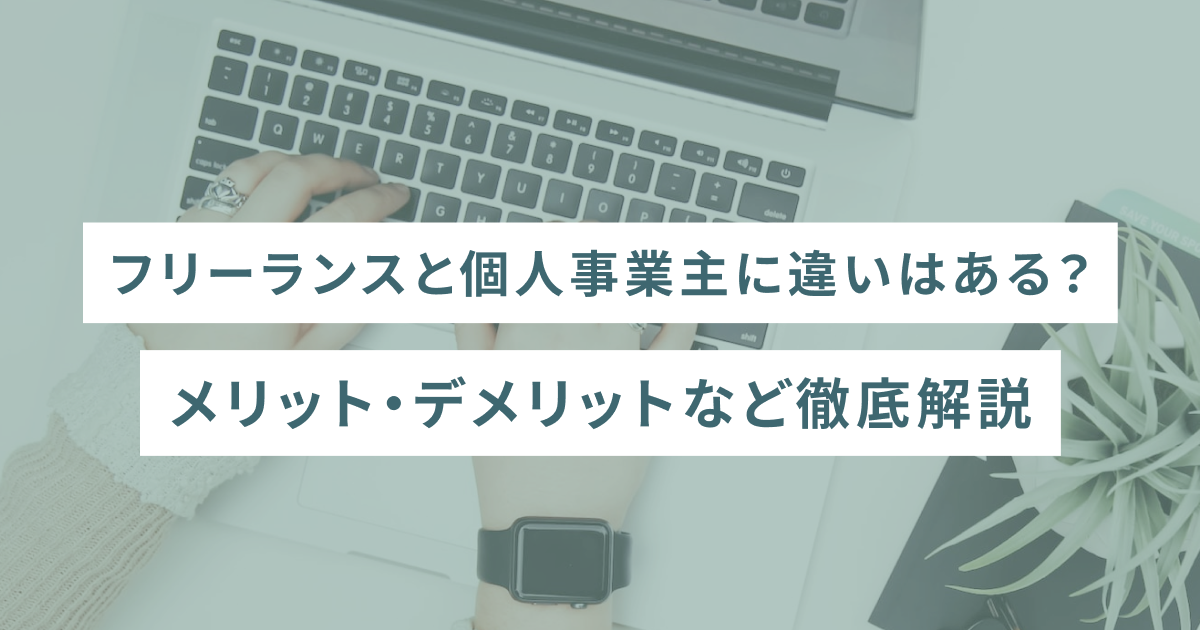「フリーランスと個人事業主に違いはあるの?」「独立するにあたって、メリットが多いのはどっち?」など、疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
本記事では、フリーランスと個人事業主の違いはあるのか解説します。それぞれのメリット・デメリットや、個人事業主になるための具体的な手続きも紹介するので、個人で仕事を始めようと考えている方はぜひ参考にしてください。
フリーランスと個人事業主に違いはある?
フリーランスと個人事業主は混同されやすい言葉ですが、フリーランスは「働き方」を指すのに対し、個人事業主は「税務上の区分」を意味します。ゆえに、双方は対等に比較できるものではありません。
一般的に、フリーランスは特定の企業や団体に属さず、複数の企業から仕事を請ける働き方を指します。一方、個人事業主とは、税務署へ開業届を提出したうえで、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる個人のことです。
対等に比較できる言葉ではないものの、フリーランスの働き方を選択した場合は開業届を提出している人がほとんどと考えられるので、双方はほぼ同じものと捉えて良いでしょう。
フリーランスの定義と特徴
フリーランスとは、企業や組織に属すことなく、個人で仕事を請け負う「働き方」のことを指します。
明確な定義はありませんが、一般的に複数の企業と契約を交わし、案件ごとに報酬を受け取る働き方を指すことが多いです。企業とは雇用契約ではなく業務委託契約を交わして仕事を受注するため、「労働基準法」などの法律が適用されません。
一般的にフリーランスと呼ばれる職種には、ライター、デザイナー、エンジニア、コンサルタントなどが挙げられます。飲食店を起業して営む場合や、開業医や弁護士として独立して事業を行う場合、フリーランスよりも「自営業」と呼ばれることが多いです。
個人事業主の定義と特徴
個人事業主は、法人を設立せずに、個人で継続的に事業を営んでいる事業者のこと。
税務署に開業届を提出すると個人事業主に分類され、毎年所得税を計算して確定申告を行う必要があります。また、自分で店舗を経営し、家族や店員など複数の従業員で事業を行っている場合も、法人を設立していなければ「個人事業主」です。
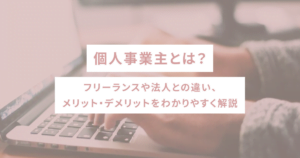
フリーランスのメリット・デメリット
ここでは、フリーランスの働き方について、どのようなメリット・デメリットがあるのかをみていきましょう。
メリット
- いつでもどこでも仕事ができる
- スケジュールを柔軟に決められる
- 収入がアップする可能性がある
- 定年退職がない
フリーランスの大きなメリットは、働く場所や時間を自分で決められることです。多くの場合通勤の必要がないので、在宅ワークやノマドワークがしたい方に向いてます。旅行しながら仕事をするワーケーションもできるでしょう。
基本的に、案件の納期さえ守れば自分で稼働時間や進行方法を決められるため、家庭の事情やプライベートの予定に合わせて柔軟にスケジュールが組めるのも魅力です。
さらにフリーランスは、実績やスキルによって収入アップも期待できます。定年退職もないので、得意なスキルを伸ばして収入を増やしていきたい方や、長期的に好きなことを仕事にしたい方に向いているでしょう。
デメリット
- モチベーションの維持が難しい
- 社会的信用が不安定になってしまう
- 生活リズムが乱れてしまう
多くのフリーランスは通勤の必要がなく、仕事しているとき周りに人がいません。コミュニケーション量が減ることからも、モチベーションの維持が難しいというデメリットがあります。チームで業務をこなす達成感や連帯感を感じられなかったり、一人の時間が多いことから孤独を感じやすくなったりするでしょう。
基本的に上司や同僚という存在もないので、自己管理がきちんとできていないと生活リズムも乱れやすくなります。一人になるとついだらけてしまい、締め切り直前に慌てて徹夜で仕事をする事態になることも。
また、収入が不安定になることで、社会的な信用を得られにくくなるというデメリットもあります。特に収入が少ないうちは賃貸やローン、クレジットカードなどの審査に通りにくい傾向にあるので、独立前に手続きしておくのがおすすめです。
個人事業主のメリット・デメリット
フリーランスの働き方をしている人のほとんどは、個人事業主として開業しています。ここでは、個人事業主のメリット・デメリットを見ていきましょう。
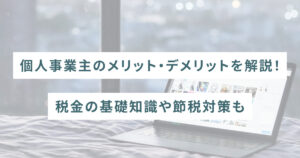
メリット
- 一定の要件を満たすことにより青色申告ができる
- 会社員よりも節税できる可能性がある
- 屋号つきの口座を開設できる
個人事業主になる大きなメリットは青色申告による節税効果が期待できる点です。
個人事業主が行う確定申告には、青色申告と白色申告があります。白色申告は記帳が簡単な「単式簿記」を選択できるため、経理の負担がかかりにくいです。一方、青色申告で55万円や65万円の青色申告特別控除を使いたい場合は経費や取引を細かく仕訳けする「複式簿記」で記帳します。青色申告にすると帳簿や確定申告の手間は増えますが、最大65万円の青色申告特別控除を受けることで、大きな節税効果につながるでしょう。
また、開業届を出して屋号を得ることで、屋号付きの銀行口座を開設できるようになります。屋号付きの銀行口座があると、クライアントが安心して金銭のやり取りをしやすくなるでしょう。
デメリット
- 確定申告の手続きが複雑になる
- 失業保険の受給期間中に個人事業主になると、給付が停止される可能性も
個人事業主になるデメリットは、経理が複雑になる点です。青色申告では財産情報の把握のために、経費や取引を細かく仕分けする複式簿記が必要になります。地域の青色申告会で学ぶ、税理士に相談する、有料の会計ソフトを使うなどして、確定申告時に困らないように対策をしましょう。
なお、失業保険を受給している期間に個人事業主として開業した場合、仕事を再開したとみなされて給付が停止されてしまう可能性があります。失業保険の手続きをした後の独立を検討している方は、地域の自治体がどのような取り決めをしているのかをあらかじめ確認し、開業のタイミングを決めるようにしましょう。
フリーランス・個人事業主として働きやすい職業
ここからは、フリーランス・個人事業主に多い職種を紹介します。
- ライター
- デザイナー
- エンジニア
- 動画編集者
- イラストレーター
- コンサルタント
- マーケター
- カメラマン
特にフリーランスや従業員を持たずに1人で事業を展開している個人事業主は、クリエイティブスキルやビジネススキルといった「専門スキル」が必要となる職種が多い傾向にあります。オンラインでクライアントと連絡を取ることが多いので、パソコンで業務ができる案件が多いです。
どの職種もスキルや実績が重視されるため、独立するには企業で実績を積んだり、本業をしながら副業で実績を積んだりしなければなりません。未経験の場合は、スクールなどを利用してスキルを習得すれば、上記のような職種で活躍することも可能です。
個人事業主とフリーランス、結局どっちがいい?
「個人事業主とフリーランス、結局どっちがいいの?」と思う方もいるでしょう。両者は並列関係にある言葉ではないものの、一般的に多くの個人事業主はフリーランスとして働くことになると考えられます。そのため、双方に違いはほとんどないと捉えておいて問題ありません。
個人事業主として正式に開業すれば確定申告の手間こそ増えますが、節税できたり屋号つきの口座を開設できたりといったメリットも多いです。次のセクションでは、個人事業主になるために必要な手続きを解説します。
個人事業主になるために必要な手続き
個人事業主になるために必要な手続きは以下のとおりです。
順番に詳しく見ていきましょう。
【必須】税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出する
開業届の提出は簡単です。個人事業の開業等届出書を作成して、e-taxで提出するか、印刷して所轄の税務署に持参または郵送で提出します。個人事業開業等届出書は「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」からダウンロードできます。
確定申告を青色申告で行う際は、青色申告承認申請書の提出も必要です。青色申告承認申請書は国税庁の「所得税の青色申告承認申請手続」からダウンロードできます。開業届同様、提出方法はe-Taxか税務署への持参または郵送での提出です。
ちなみに新規開業の場合は、青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業する場合は、業務開始から2ヶ月以内)に青色申告承認申請書を提出する必要があります*1。
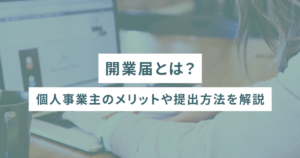
【任意】事業用の銀行口座・クレジットカードをつくる
こちらは任意の手続きになりますが、開業する際は事業用の銀行口座を開設するのがおすすめです。事業用の口座があると、事業の収支が明確になるので日々の経理業務や確定申告のための帳簿付けがスムーズになります。同様の理由で、事業用のクレジットカードを作っておくとよいでしょう。
フリーランス・個人事業主の税金・年金事情
会社員を辞めて独立した場合、保険・年金の手続きも必要になります。ここでは、それぞれの手続きや細かい事情について見ていきましょう。
フリーランス・個人事業主の税金
フリーランス・個人事業主が支払う主な税金は以下のとおりです。
- 所得税・復興特別所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
- 固定資産税(償却資産税)
所得税とは、「1年の所得金額に応じて課税される税金」のこと。個人で仕事をおこなうフリーランス・個人事業主は、1月1日から12月31日までの間に得た所得から所得税を計算し、確定申告を行わなくてはなりません。所得税の納税者は自動的に復興所得税も対象になります。復興所得税は東日本大震災の復興に向けた財源確保を目的としていて、所得税に2.1%乗じて課される税金です。
個人事業税は年間の所得が290万円を超える場合発生するもの、消費税は課税事業者のみ払うものとなっています。インボイス登録をすると自動的に消費税の課税事業者になります。固定資産税(償却資産税)は、土地・家屋以外の事業用の資産を所有している場合に課税される税金です。
フリーランス・個人事業主の社会保険
フリーランス・個人事業主が加入する健康保険は基本的に「国民健康保険」です。企業と折半で負担する社会保険と違い、国民健康保険は全額自己負担になります。保険料の算出方法は自治体ごとに異なるため、金額が気になる方は地域のWebサイトなどを確認してみましょう。
なお、会社員から個人事業主になる場合、勤めていた会社の社会保険を退職後も継続できる「任意継続保険」を利用することも可能です。退職日までに2か月以上継続して社会保険に加入していることが条件で、独立してから2年間利用できます。これまで会社が負担していた分も支払うことになりますが、国民健康保険にはない、傷病手当制度などがあります。
また、独立してすぐの時期は、年収が130万円未満の方もいるでしょう。この場合は、家族の健康保険に被扶養家族として入れる可能性があります。詳しくは各自治体の窓口に問い合わせてみてください。
フリーランス・個人事業主の年金
会社員・公務員は国民年金と厚生年金に加入できますが、フリーランス・個人事業主が加入できるのは国民年金のみです。会社員からフリーランスになる場合は、退職を証明する書類を持参のうえ、役所や年金事務所で年金の切り替え手続きが必要になります。
厚生年金に加入している会社員・公務員は、満期を迎えたときに国民年金と厚生年金の両方を受け取れます。しかし、個人事業主は国民年金しか受給できないため、老後の生活費をどのように賄うのか考えておくことが大切です。国民年金に上乗せされて受給できる、国民年金基金制度などもあるので、合わせてチェックしてみてください。
よくある質問
最後に、フリーランス・個人事業主についてよくある質問に回答します。
- フリーランスとして働くために必要なスキルはありますか?
- フリーランスとして働く際に気をつけるべき法的なポイントはありますか?
- 個人事業主が受けられる補助金・助成金はありますか?
- 個人事業主になれない人はいますか?
気になる疑問があればここで、解消しておきましょう。
フリーランスとして働くために必要なスキルはありますか?
フリーランスとして働くには、それぞれの職種に特化した専門スキルだけでなく、基本のビジネススキルが不可欠です。
たとえば、案件の納期を守るためには、スケジュール管理力が欠かせません。クライアントが増えるほど、それぞれに納期や請求日などが発生するため、スケジュールが複雑になります。タスク管理ツールやアプリを使って、スケジュールを管理する必要があるでしょう。
ほかにも、企業に営業して報酬や納期の交渉を円滑に進めるコミュニケーション能力や、収入や経費を管理する経理の知識も必要になります。
フリーランスとして働く際に気をつけるべき法的なポイントはありますか?
フリーランスとして働く場合、税金・保険・年金などの手続きをすべて自分で行う必要があります。正しい知識がないと税金で損をしてしまう可能性もあるので、基本的な経理を学んだうえで行いましょう。
また、クライアントと契約する際は、契約書の項目を丁寧に確認することが大切です。企業によって契約書の内容が異なるため、契約内容に不審な点がないか注意しましょう。
個人事業主が受けられる補助金・助成金はありますか?
個人事業主が受けられる可能性がある助成金・補助金は以下の通りです。
<助成金>
<補助金>
以下の記事では個人事業主を支援する給付金も紹介しているので、合わせてチェックしてみてください。
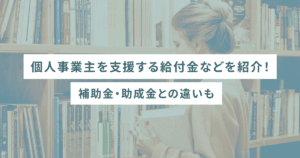
個人事業主になれない人はいますか?
個人事業主になれない人は、「公務員や副業が禁止されている企業に勤めている人」です。資格や実績などは問われません。
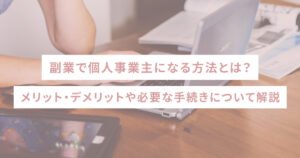

フリーランス・個人事業主として働くためには専門スキルを身につけるのがおすすめ!
フリーランスは「働き方」を、個人事業主は「税務上の区分」を指す言葉なので、そもそも対等に比較できるものではありません。ただし、フリーランスの働き方を選択した人の多くは税制面でのメリットを得るために開業届を出して個人事業主になるので、双方はほぼ同じものと捉えて良いでしょう。
いずれにしても独立するために必要になるのが、何かしらの専門スキルです。最近ではデザイナー・ライター・マーケターといったWebスキルを活用した職種に人気があります。
未経験から上記のようなスキルを身につけたいなら、女性向けキャリアスクールSHElikes(シーライクス)がおすすめです。Webデザイン、ライティング、マーケティング、動画編集など、フリーランスに向いている50以上の職種スキルを学べます。無料体験では人気コースを試せるので、気になる方はぜひ一度参加してみてください。

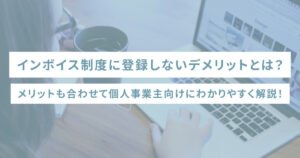
出典:
*1:国税庁「青色申告制度」より