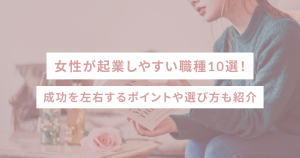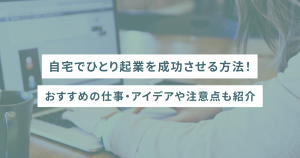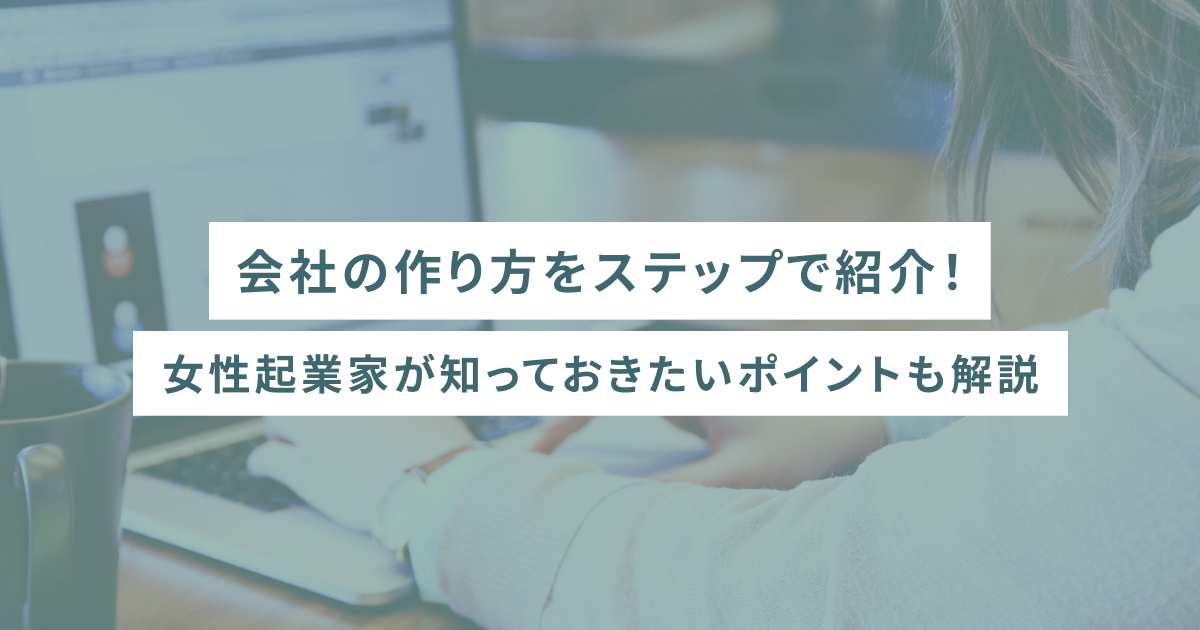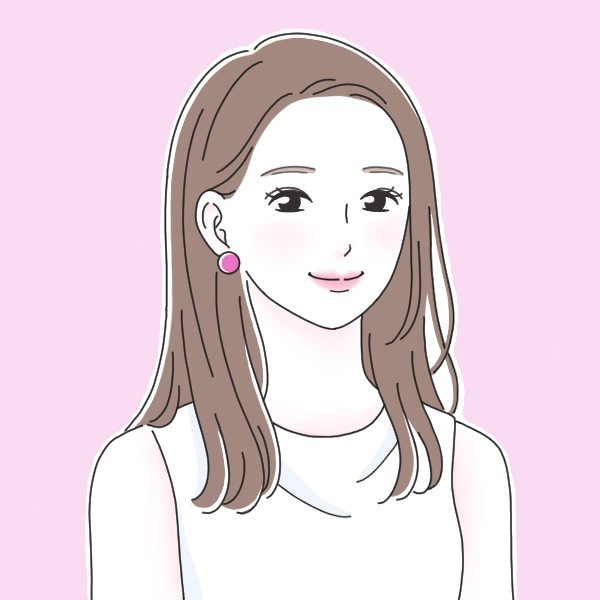起業に興味や憧れがあっても、「会社の作り方がわからない」「自分にもできるのだろうか」など、疑問や不安を抱えている方もいるでしょう。この記事では、会社設立の基礎知識や流れ、必要な手続きなどについてわかりやすく解説します。
理想の起業を実現するために、ぜひ参考にしてみてください。
会社設立の前に知っておきたい基礎知識
会社設立の前に、会社の作り方の基礎知識として以下の3つについて知っておくことが大切です。
それぞれについて解説します。
会社の種類
現在日本で新設できる会社形態は『株式会社』『合同会社』『合資会社』『合名会社』の4つです。ただし実務的には、株式会社と合同会社が圧倒的に多く選ばれています。株式会社は出資者と経営者の役割が切り離されており、株式を発行して集めた資金をもとに経営する会社形態です。
株式会社以外の合同会社・合資会社・合名会社は「持分会社」と呼ばれ、出資者自らが経営も行います。出資者の責任範囲は、「有限責任」と「無限責任」に分けられます。会社が倒産した場合に、有限責任の出資者は出資額以上の負債を負う必要がないのに対し、無限責任の出資者は出資額以上の負債も負わなければなりません。
株式会社と合同会社の場合、出資者は有限責任ですが、実務では代表者が会社借入の連帯保証人になることも多いため、リスクが完全になくなるわけではありません。合資会社は無限責任社員と有限責任社員がそれぞれ1名以上、合名会社は無限責任社員のみで構成されるため、会社が倒産した際には出資額以上の負債を負うリスクがあります。
責任範囲だけでなく、設立費用や手続きなども会社形態によって異なります。それぞれの特徴を理解したうえで、事業の目的や規模感などに応じた会社形態を選択することが大切です。
会社設立のメリット・デメリット
会社設立のメリットは、社会的な信用を得やすく、資金調達や取引がスムーズになりやすい点です。会社を設立すると、商号(社名)や所在地、資本金、事業目的などが登記簿に公開されるため、法人としての透明性が高まり、取引先や金融機関からの信頼につながります。
また、個人事業主に比べて経費として認められる範囲が広く、役員報酬を経費にできるなど節税効果を得やすいのも特徴です。さらに、青色申告を行えば欠損金(赤字)を最大10年間繰り越せる制度も活用できます。
一方で、会社設立には登録免許税などの初期費用が必要で、設立後も登記や決算などの事務手続きが増えるため負担が大きくなります。また、法人は社会保険への加入義務があるため、従業員を雇えば会社が負担する保険料も発生します。
資本金の考え方
資本金とは、会社が事業を行うための元手となる資金のことです。新しい取引先との契約や銀行融資の審査の際に与信調査の対象となるほか、会社の規模を示す指標としても使われます。資本金の額は、取引の信用力や資金調達の上限に影響するため、単なる数字以上の意味を持ちます。
株式会社は資本金1円からでも設立可能ですが、あまりに少額では金融機関や取引先からの信用に不利になることがあります。特に株式会社は社会的信用を前提に設立されるケースが多いため、100万円以上の資本金を用意しておくと安心です。目安としては、3か月から半年分の運転資金をカバーできる金額を設定するとよいでしょう。
一方、合同会社は比較的コストを抑えて小さくスタートする目的で選ばれることが多いため、資本金はそれほど大きくなくても問題ありません。まずは少額で始め、事業が軌道に乗った段階で増資や株式会社への組織変更を検討する方法もあります。
以下の記事では、リスクを抑えて起業を行うステップについて解説しています。起業を目指す方におすすめの女性向けキャリアスクールSHElikes(シーライクス)についても詳しく紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
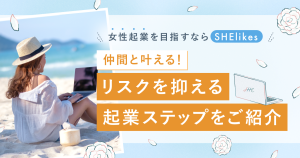
会社の作り方をステップで解説
会社の作り方は、次の7つの手順で進めるのが一般的です。
それぞれのステップについて詳しく解説します。
1.事業計画を立てる
まずは事業計画を立てて、事業の内容や今後の進め方などを明確化して整理します。具体的には、事業の目的やビジョン、具体的な事業内容、戦略、必要な設備、人員計画、資金計画などをまとめていきます。
事業計画は、「事業計画書」として取りまとめておくことが大切です。事業計画書は法的に提出を求められるものではないものの、会社設立時の資金調達などで役立つ場合があります。金融機関や投資家が事業の将来性や収益性などを判断する際に必要となる場合も多いため、いつでも提示できるように用意しておきましょう。
2.会社形態を決める
現在新設できる会社形態は『株式会社』『合同会社』『合資会社』『合名会社』の4種類がありますが、実務的に選ばれているのはほとんどが株式会社か合同会社です。事業の目的や規模、重視するポイントに応じて、この2つから検討するのが一般的です。株式会社は大規模な事業展開に向いている一方で、設立費用やランニングコストの負担が大きいという特徴があります。合同会社は小規模な組織に向いている反面、株式会社に比べると社会的信用度や認知度が低く、資金調達の手段も限られているという特徴があります。
それぞれの会社形態の特徴を理解し、事業内容や事業規模、資金調達、出資者の責任範囲、経営の自由度などを考慮したうえで選択することが大切です。
3.会社概要を決定する
会社を設立する際には、会社概要を決定する必要があります。決定が必要な主な項目は、次のとおりです。
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金額
- 会社設立日
- 会計年度(事業年度)
- 株主の構成(持株比率)
- 役員の構成
これらの項目は定款に記載する必要があるため、あらかじめ決定しておきましょう。
4.定款を作成・認証する
定款とは、会社の基本規約や基本規則などを記載した、会社の設立や運営において重要な書類です。会社の設立時には必ず作成しなければならないもので、登記をする際に法務局に提出する必要があります。
定款に記載する内容は、必ず記載が必要な「絶対的記載事項」、記載しなくても問題ないものの、記載がないとその事項について効力が認められない「相対的記載事項」、会社法に違反しない範囲内で任意に記載できる「任意的記載事項」の3種類です。
必ず記載が必要な「絶対的記載事項」は、「事業目的」「商号(法人名)」「本店所在地」「資本金額」「発起人の氏名と住所」の5つです。株式会社を設立する場合は、作成した定款を公証役場に提出し、公証人による認証を受ける必要があります。
5.資本金の払い込み
定款の認証が完了したら、資本金の払い込みを行います。この時点では会社設立登記が完了しておらず法人口座を開設できないため、振込先は発起人の個人口座になります。法人登記申請の際には資本金の証明書類として振込明細や通帳のコピー、インターネットバンキングの取引履歴などが必要になるため、大切に保管しておきましょう。
6.法務局へ登記申請
ここまでの手順が完了したら、法務局へ登記申請を行います。登記申請は、管轄の法務局の窓口、郵送、オンラインのいずれかの方法で行います。申請を行った日が会社の設立日となるため、縁起のよい日を考慮して決めたい場合などは逆算して準備を進めておきましょう。
申請に必要な書類は次のとおりです。
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款
- 発起人の同意書(発起人決定書、発起人会議事録)
- 代表取締役の就任承諾書
- 取締役の就任承諾書
- 監査役の就任承諾書
- 取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込証明書
- 印鑑届出書
- 「登記すべき事項」を記載した書面、または記録媒体
申請書類に不備があると補正して再提出しなければならないため、十分に確認したうえで提出するようにしましょう。
7.各種届出・手続き
会社設立の手続きが完了したら、税務署に「法人設立届出書」と「源泉所得税関係の届出書」を提出し、必要に応じて青色申告や消費税に関する届出も行います。また、社会保険・労働保険の手続きや、資金管理のための法人口座開設の手続きなども行いましょう。
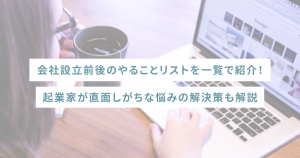
女性起業家が知っておきたい起業のポイント
女性が一人で会社を作る際には、次の5つのポイントについて確認しておくとよいでしょう。
それぞれのポイントについて解説します。
自分の「強み」と「好き」を活かす
自分の「強み」と「好き」を活かせる分野を選ぶと、より情熱を持って取り組めるため、お客さまが満足する商品やサービスの提供や、自分自身の人生の充実にもつながるでしょう。自分が欲しいと思った商品やサービスがビジネスのアイデアにつながったり、他社との差別化につながったりするケースもあります。
保有資格やこれまでの職歴、特技、趣味などを洗い出し、自分の「強み」と「好き」を活かせる業種を検討してみましょう。
スモールスタートを意識する
女性が一人で会社を作る際は、最初から大規模な事業を始めるのではなく、「スモールスタート」を意識した会社の作り方がおすすめです。スモールスタートとは、必要最小限のリソースでスタートし、市場の反応を見ながら事業を改善・拡大していくことです。
スモールスタートを意識すると、初期費用や運転資金を抑え、低リスクで事業をスタートできます。生活との両立や家計への影響を抑え、自分のペースで柔軟に事業を進めていけるでしょう。
人脈・ネットワークを活用する
会社設立の際には、人脈やネットワークを活用することで「仕事を依頼される」「的確なアドバイスをもらえる」「有益な情報を入手できる」などビジネスチャンスをつかむ可能性が広がります。
ビジネスに活かせる人脈やネットワークがない場合は、女性起業家が集まる交流会や、興味のある分野のセミナーなどに参加してみるのもおすすめです。また、SNSで情報を発信し、業界関係者や同じ志を持つ人と関係性を構築してもよいでしょう。
学び続ける姿勢を持つ
長期的な成功を実現するためには、常に学び続ける姿勢が必要です。新しい技術や市場トレンドを把握したり、新たなスキルを身につけたりすることは、事業の成長やビジネスの成功につながります。
セミナーやワークショップへの参加、書籍やオンライン講座での学習など、積極的に学ぶ機会を設けましょう。また、習得した知識やスキルを積極的にビジネスに活かしたり、ビジネス上の困難や失敗を客観的に分析して次へ活かしたりすることも大切です。
ライフスタイルとの両立を計画しておく
長く続けられるビジネスを実現するためには、ライフスタイルとの両立を計画しておくことが大切です。たとえば、在宅ワークが可能な業種や時間に融通が利きやすい業種を選ぶのも方法のひとつです。
また、こどもの預け先を検討したり、必要に応じて家事代行サービスの利用を検討したりしてもよいでしょう。家族やパートナーとの協力体制を整えておくことも大切です。
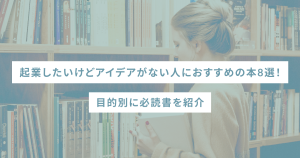
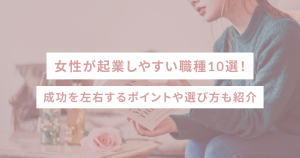
会社設立に関するよくある質問
一人で会社を作る際には、さまざまな疑問が生じるでしょう。会社設立に関するよくある質問は、以下のとおりです。
それぞれの質問について解説します。
会社設立に費用はどのくらい?どうやって調達する?
株式会社を設立する場合は、登録免許税(資本金300万円未満なら通常15万円)、定款認証手数料(1.5万~5万円)、定款謄本交付手数料などが必要です。紙の定款を作成する場合のみ印紙税(4万円)がかかります。合計ではおおよそ17万~20万円台が目安です。
また、合同会社の場合、登録免許税(資本金857万円未満なら6万円)が主な費用で、株式会社に比べて安く設立できます。紙の定款を作成する場合は印紙税(4万円)が必要ですが、電子定款なら不要です。合名会社・合資会社も制度上は設立可能ですが、現在はほとんど選ばれていません。
費用の調達方法は、自己資金、金融機関からの融資、出資、クラウドファンディング、国や自治体の補助金・助成金、家族や友人からの借り入れなどがあります。
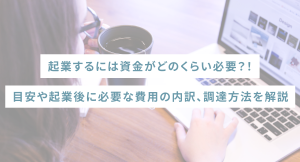
ひとりでも会社は設立できる?
株式会社、合同会社、合名会社は、ひとりで設立することが可能です。ひとりで会社設立をする場合は、発起人や株主、取締役などの役割を自分自身で行うことになります。また、定款の作成や登記申請などの手続きもすべて自分自身で行うため、計画的に準備することが大切です。
なお、合資会社については無限責任社員と有限責任社員の2人以上が必要なため、ひとりでは設立することができません。
会社設立はどのくらい時間がかかる?
会社設立にかかる期間は、書類準備を含めて2~3週間程度が目安です。ただし、必要書類を早めに整えれば1週間前後で登記が完了することもあります。具体的には、公証役場での定款の認証に1週間程度、登記申請から登記完了まで1〜2週間程度かかるのが一般的です。
ただし、登記申請までに必要な準備をスムーズに進められるか、申請書類に不備がないかなどによっても完了までにかかる期間が異なります。
会社設立に関して質問はどこにすればいい?
近くの商工会や商工会議所、よろず支援拠点、税務署、中小企業基盤整備機構、日本政策金融公庫などの公的機関では、起業に関する疑問や悩みを無料で相談することが可能です。会社設立に関する相談は、分野ごとに適した専門家がいます。登記の専門は司法書士、税務は税理士、労務は社会保険労務士が担当します。また、建設業や飲食業など許認可が必要な場合は行政書士に相談すると安心です。
女性が起業を目指すならSHElikes
女性が起業を目指すなら、女性向けキャリアスクールSHElikesがおすすめ。SHElikesは50以上の職種スキルが定額で学び放題で、起業に必要なスキルを幅広く学べます。
ここでは起業を目指す際にSHElikesがおすすめな理由と、SHElikesを活用して起業を実現した2人の女性起業家の事例を紹介します。
SHElikesなら起業に必要なスキルが学べてサポートも充実
SHElikesは50以上の職種スキルが学び放題なので、単一のスキルではなく、複数のスキルを組み合わせて学べます。デザインや動画編集、マーケティング、ビジネススキルなど、起業に必要なスキルを幅広く身につけることが可能です。
講師は実際にフリーランスや起業家として活動している専門家が務めているため、プロによる実践的なサポートも受けられます。「一人で会社を作るには何から始めたらいいかわからない」という場合は、会社設立の流れや基礎知識、自分に合った会社の作り方などを学べる「起業コース」がおすすめです。実際に起業している講師から、起業について実践を交えながら丁寧に学べます。
以下の記事では、リスクを抑えた起業のステップについて解説しています。SHElikesについても詳しく紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
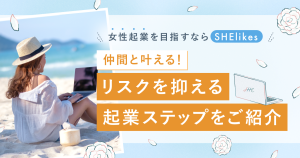
SHElikesで学び起業した方の事例を紹介
ここでは、SHElikesを活用して起業を実現した2人の女性起業家の事例を紹介します。
理想の起業を実現したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
ずっと起業に憧れていた薬剤師。大学院進学やMBAでも叶えられなかった夢をSHElikesで叶えた方法とは Sakiさん
薬剤師として働いていたSakiさんは、起業への憧れを抱いていたものの、ずっと一歩を踏み出せずにいました。しかし、SHElikesの無料体験レッスンに参加したことで「起業のきっかけを掴めるかも?」と思い入会を決意。
グループコーチングを通して自分が本当にやりたいことが明確になったそう。受講生同士で交流できるコミュニティでは、起業を本気で成し遂げたい人を中心にした「起業クラブ」を立ち上げ、夢に向かって進む仲間のサポートもしています。
現在はアパレルブランドを含む3つの事業を展開しています。SHElikesで出会った仲間とともに、夢だったファッションショーの準備も進めているそうです。

営業からフォロワー2万人のインフルエンサー&起業家に さきまるさん
生命保険営業として働いていたさきまるさんは、営業と子育ての両立が簡単ではないことを知り、もやもやした気持ちを抱えていました。もともと起業を夢見ていたこともあり、興味のあったWebスキルが学び放題のSHElikesなら無駄がないと思い、入会を決意したそうです。
Webデザインやコンテンツマーケティング、プロジェクトマネジメントなどさまざまなコースを受講していくなかで、とくに惹きつけられたのがブランディングコース。ブランディングコースがきっかけで大好きな「味噌汁」を軸に起業し、現在ではインフルエンサー・ブランド創業者として活躍しています。

会社の作り方の流れを理解し、理想の起業を実現しよう
会社の作り方の流れを正しく理解して行動することは、理想の起業を叶えるための第一歩です。事業の目的や将来像を明確化し、適切な手順で準備を進めていきましょう。
SHElikesは50以上の職種スキルが学び放題で、起業に必要なスキルを学べるコースも充実。あなたもSHElikesで学び、理想の起業を実現してみませんか?SHElikesが気になる方は、ぜひ無料体験レッスンに参加してみてください。