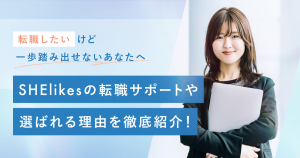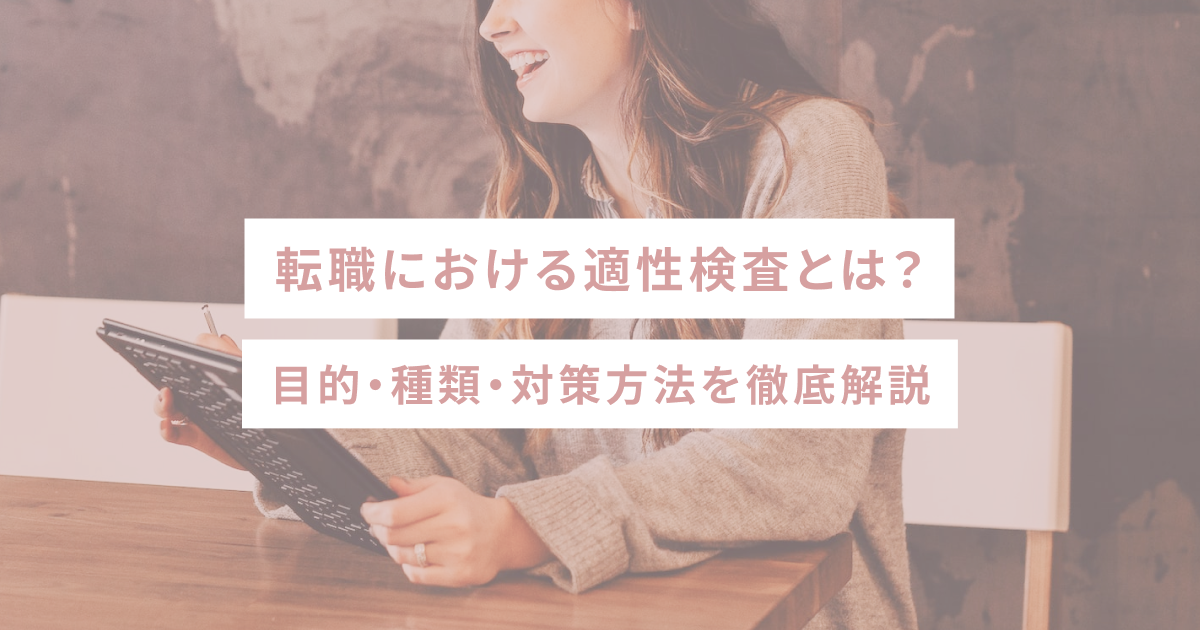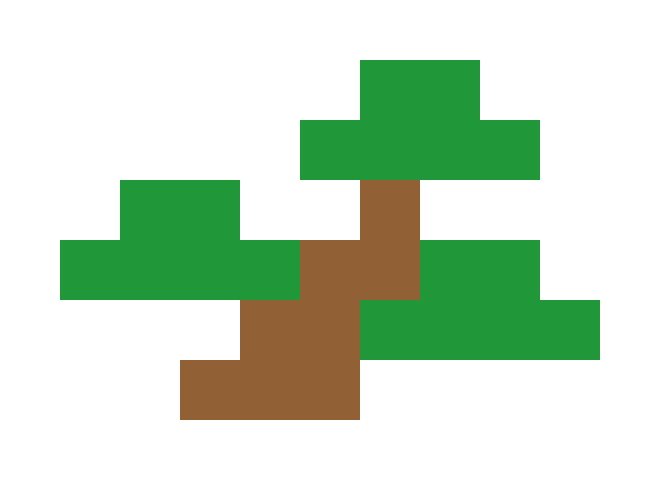転職活動において、適性検査は多くの企業で導入されている重要な選考プロセスのひとつです。どういった内容なのか、どのように評価されるのか、不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、適性検査の目的や種類、企業がどのように活用しているかを詳しく解説します。また、事前にできる対策やよくある質問への回答も紹介します。不安を減らし、自分の力を存分に発揮するためにも、ぜひ参考にしてください。

そもそも適性検査とは?
適性検査とは、応募者の性格や価値観、思考の傾向、対人関係のスタイル、職務適応力などを数値化し、仕事内容や企業との相性を測るためのツールです。
転職や中途採用の選考では、スキルや経験だけでなく、職場環境や業務内容とのマッチ度を見極めるために適性検査が活用されています。書類選考や面接では採用担当者の主観が入ってしまいがちですが、適性検査は客観的な視点で評価しやすいことから、採用のミスマッチを防ぐ判断材料のひとつとして重視されています。
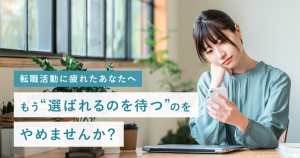
新卒・中途採用の適性検査の違い
新卒採用と中途採用では、適性検査の目的や重視されるポイントに違いがあります。新卒の場合は、職務経験がないことを前提に、将来の成長性や人柄、協調性といった「伸びしろ」を見極める傾向があります。検査の内容も、性格や基礎的な思考力を幅広く把握するものが中心です。
転職を前提とする中途採用では、これまでの働き方や経験を踏まえたうえで、新しい環境への適応力や実務への対応力が評価されやすくなります。責任感やストレス耐性など、実際の業務に直結する要素に注目が集まる点が特徴です。評価の基準も、実務に直結するスキルや行動特性が重視され、即戦力として活躍できるかどうかが判断基準となります。
適性検査の実施タイミングと形式
適性検査は、応募書類の提出後から内定までの選考プロセスの中で実施されることが一般的です。タイミングは企業によって異なりますが、一次面接の前に行われるケースが多く、最終面接の直前や内定通知の前に実施されることもあります。特に中途採用では、即戦力としての適応力や、職場との相性を確認する目的で使われることが多く、選考の中で一定の比重を占めることがあります。
実施形式はペーパーテストの場合もありますが、近年はWeb上での受検が主流です。自宅などからアクセスできるため、対面式に比べて運用の手間が少なく、多くの企業が採用しています。受検者にとっても、落ち着いた環境で臨めるのが利点といえるでしょう。
適性検査の主な分類
適性検査は、一般的に「性格診断」と「能力診断」の二つに大別されます。ここでは、それぞれの検査がどのような特徴を持ち、選考の中でどのような意図で用いられているのかを解説します。
性格診断
性格診断は、受検者の価値観や行動の傾向、人との関わり方などを把握するための検査です。職場でどのように立ち振る舞うか、チームとの関係性にどんな特徴があるかを見極める際に活用されます。たとえば、「周囲を引っ張るリーダーシップ型か」「慎重に物事を進めるか」など、働くうえでの姿勢や判断のクセを客観的に知る手がかりとなります。
転職においては、これまでの働き方や経験を踏まえたうえで、新しい職場環境への適応度を判断する材料として使われることも多くなっています。
能力診断
能力診断は、仕事を進めるうえで求められる基本的なスキルや思考力を測る検査です。具体的には、文章を正確に読み取る力、計算や数値の分析、論理的な思考力、図やパターンの理解力などが問われます。その分野を重視するかは職種によって異なり、たとえばデスクワークや事務職では正確性や処理スピードが、営業や企画職では柔軟な発想力や情報の整理力が重視される傾向があります。
転職の選考では、過去の実績だけでなく、こうした能力のバランスも見られることが多いです。業務への適応力や将来的な成長の可能性を判断する材料として活用されています。
企業が適性検査を行う理由
適性検査は、新卒・中途を問わず、多くの企業が採用選考に取り入れています。特に転職時には、スキルだけでなく、応募者の性格や職場との相性を見極める手段として重視される傾向があります。ここでは、企業が適性検査を実施する主な理由を3つの視点から紹介します。
企業が適性検査を行う理由と目的を把握し、受検に役立てましょう。
応募者を客観的な指標で判断するため
限られた面接時間や提出書類だけで、応募者の人物像を正確に把握するのは簡単ではありません。特に面接では、第一印象や話し方に評価が左右されることも少なくないため、選考が主観的になりがちです。こうした偏りを補う手段として、多くの企業が適性検査を活用しています。
適性検査では、応募者の性格傾向や思考のクセ、行動パターンなどが数値化されます。可視化されたデータをもとに判断することで、先入観にとらわれない選考が可能となり、企業と応募者の双方にとって納得感のあるマッチングへとつながっていくのです。
自社の社風にあった人材か判断するため
企業が人材を採用する際は、スキルや経験だけでなく、組織との相性も重視されます。どれほど能力が高くても、企業文化や働き方の価値観が合わなければ、力を十分に発揮できないケースもあるからです。適性検査で応募者の性格傾向や価値観、行動の特徴を数値化することで、職場の雰囲気やチームの構成との相性を客観的に見極める手がかりとなります。
たとえば、決められた手順の中で着実に取り組むタイプなのか、変化に柔軟に対応できるタイプかといった特性が、企業が求める人物像と合致しているかどうかを判断する際に活用されています。
入社後のキャリア構築に活用するため
適性検査は、採用時の合否判断だけでなく、入社後の人材育成やキャリア設計にも活用されます。検査を通じて得られる性格傾向や思考のスタイル、ストレス耐性、リーダーシップの特性などは、その人の強みや課題を客観的に把握する材料となります。企業はこうしたデータをもとに、適性にあった職務への配置や、個々に合わせた研修計画を検討し、早期の戦力化や長期的な成長支援につなげていきます。
また、転職者にとっても、自分に合った環境で力を発揮しやすくなるというメリットがあります。
転職の適性検査の主な種類と問題の傾向
適性検査と一口にいっても、実施される形式や出題される問題の内容にはさまざまな種類があります。ここでは、代表的な適性検査の種類と、それぞれで問われる内容の傾向について紹介します。
特に転職では、スキルや経験に加えて性格や思考のクセ、職場との相性などを多角的に見られます。それぞれの検査の傾向を理解して、対策を進めましょう。
SPI3
SPI3は、リクルート社が提供する適性検査で、新卒・中途問わず、国内の多くの企業の採用選考で導入されています。
検査は「能力検査」と「性格検査」の二部構成です。能力検査では、言語(語句の意味・空欄補充など)と非言語(確率・損益算・表の読み取りなど)の問題が出題され、基礎的な理解力や論理的思考力が見られます。性格検査では、仕事への姿勢や価値観、対人関係の傾向を測定し、組織との相性や職務適性を評価します。
実施形式にはテストセンター・Web・ペーパーテストなどがあり、形式ごとに出題傾向や制限時間が異なる点に注意が必要です。転職選考でも幅広く活用されており、性格と能力の両面から、応募者と企業のマッチ度を客観的に判断するための手段として用いられています。
CAB
CAB(Computer Aptitude Battery)は、日本エス・エイチ・エル社が提供するIT系職種向けの適性検査です。主にSEやプログラマーなど、論理的思考や処理能力が求められる職種で導入されています。
検査は「暗算」「法則性」「命令表」「暗号」の4分野に加え、「パーソナリティ」で構成されます。たとえば「命令表」では、指定されたルールに従って図形を操作する問題が出題され、プログラミング的な思考が問われます。
実施形式はマークシートとWebの2種類。Web形式では、出題数は少ないものの制限時間が短く、スピードと正確性の両立が求められます。転職時の選考でも活用されており、性格とのバランスを総合的に見て、企業との相性を判断する材料として活用されています。
GAB
GAB(Graduate Aptitude Battery)は、日本エス・エイチ・エル社が開発した適性検査で、主に新卒総合職向けに設計されたものです。現在では、転職選考でも広く利用されています。
検査は「言語」「計数」「パーソナリティ」の3分野で構成されます。言語では長文を読み、論理性や要点を正しくつかむ力を評価。計数では、表やグラフから数的推論を行い、ビジネスの場での処理能力が問われます。いずれも設問数が多く、制限時間が短いためスピードと集中力が求められます。
パーソナリティ検査では、対人関係の傾向や仕事への向き合い方を測定し、職場との相性を見極める材料として活用されています。性格と知的能力の両面から総合的に判断するための検査として、転職者にも対応しています。
クレペリン検査
クレペリン検査(内田クレペリン検査)は、単純な計算作業を通じて作業能力と性格の傾向を同時に測る心理検査です。心理学者・内田勇三郎によって開発され、多くの企業で採用選考や人材配置に活用されています。
内容は、1桁の数字を隣同士で足して、その結果の下一桁を連続して書いていくというシンプルなもの。1分ごとに行を変えながら、前後半それぞれ15分ずつ、合計30分間続けます。
検査では、作業量や誤答数、時間経過にともなうペースの変化をもとに、集中力・粘り強さ・緊張への耐性といった行動特性が評価されます。回答操作が難しいため信頼性が高く、転職選考でも、業務への取り組み姿勢やメンタル面の安定性を測る目的で用いられています。
玉手箱III
玉手箱Ⅲは、日本エス・エイチ・エル社が提供するWeb形式の適性検査です。もともとは新卒採用向けに設計されており、特に大手企業の選考で多く導入されています。
最大の特徴は、設問形式の多さです。「言語」「計数」「英語」の問題が出題されます。言語では「趣旨判定」や「論理的読解」など、係数では「四則逆算」「表の空欄補充」などが出題されます。形式によって解き方が大きく異なるため、事前に出題パターンに慣れておくことが重要です。英語や性格検査も含まれており、スピード・正確性・適応力を多角的に評価されます。
転職選考での導入は一部に限られるようですが、対応力を見られる高度な検査として位置づけられています。
CUBIC
CUBIC(キュービック)は、性格と基礎能力の両面から人物像を把握する適性検査です。採用選考だけでなく、人材配置や研修などにも幅広く使われています。
性格検査では、意欲・価値観・対人傾向に加え、回答の一貫性もチェックされます。基礎能力検査は、「言語」「数理」「図形」「論理」「英語」の5科目で構成され、各科目に基礎・応用・総合レベルの出題があります。
制限時間内に多くの問題を解く必要があり、処理スピードと正確さが問われます。Web・紙のどちらでも対応可能で、結果は数値やグラフで視覚的に提示されます。転職選考でも活用されており、性格と能力を総合的に判断する材料として企業に評価されています。
3Eテスト
3Eテストは、エン・ジャパンが提供するWeb適性検査です。「3E-i(能力)」「3E-p(性格)」の2部構成で、所要時間はおよそ35分。3E-iでは、論理的思考や数的処理、情報の読解力などが問われます。3E-pでは、性格傾向やストレス耐性、価値観、職務適性を多角的に測定します。スマートフォンからも受検可能で、手軽に実施できるのが特徴です。
検査結果は、合否判断だけでなく、配属や育成の方針を決める参考にも使われています。特に中小企業や成長企業での導入が多く、転職時にも活用されています。
SCOA
SCOA(スコア)は、日本経営協会総合研究所が開発した総合適性検査です。企業や自治体の採用選考で広く導入されており、転職選考でも利用されることがあります。
検査内容は多岐にわたり、基礎学力・事務処理能力・性格傾向などを総合的に評価します。「SCOA-A」では、言語・数理・論理・英語・常識の5分野を60分で解答します。「SCOA-C」では、照合・分類・言語・計算・読図・記憶の6分野から構成され、事務職のスキルを測る検査です。
性格や価値観をみる「SCOA-B」も多くのケースで併用されます。実施形式は、テストセンター、Web、マークシートなど多様。事前に出題形式や所要時間を確認し、スピードと正確性を意識した対策が大切です。
V-CAT
V-CAT(ブイ・キャット)は、SKK式適性検査とも呼ばれる紙筆式の適性検査です。新卒・中途の採用選考はもちろん、人材配置や昇格判定などにも幅広く使われています。
検査内容は、1桁の数字を連続で加算するというシンプルな作業です。作業の量やスピード、誤答の傾向から、集中力・ストレス耐性・作業の正確性といった特性が測定されます。試験時間は50分。作業中のクセや修正跡も評価対象となるため、意図的な操作がしにくい検査として知られています。
企業は、V-CATの結果をもとに、面接では見えにくい内面的な傾向や精神的な安定性まで把握します。転職選考でも導入されており、地道な作業に真摯に取り組む姿勢が問われる検査です。
転職の適性検査の対策方法
転職活動で適性検査を受けるとなると、少し身構えてしまう方も多いかもしれません。とはいえ、事前に押さえておきたいポイントを知っておくだけで、落ち着いて取り組むことができます。ここでは、転職の適性検査に備えるための基本的な対策を紹介します。
焦らず、一つずつ取り組んでいきましょう。
模擬問題や過去問で練習する
転職の選考で使われる適性検査は、出題形式や制限時間に特徴があります。初見では戸惑いやすいため、事前に模擬問題や過去問に取り組んでおくことが大切です。
特にSPIや玉手箱のような検査は、問題パターンに慣れることで解きやすくなります。時間を計りながら練習することで、スピード感も養えます。本番で焦らず力を発揮するためにも、余裕をもって対策を進めておきましょう。
苦手分野の問題を繰り返し解く
転職の適性検査では、全体的なバランスも評価されるため、苦手分野を放置しないことが大切です。計算や図表の読み取りに不安がある場合は、そこを重点的に繰り返し練習して慣れておきましょう。
苦手をそのままにすると、本番で時間配分が乱れやすく、他の問題にも影響が出る可能性があります。焦らず基礎から取り組むことで、少しずつ解ける感覚が身につきます。
性格検査は対策せず素直に答える
性格検査には明確な正解がありません。企業は、回答の内容から価値観や行動の傾向を読み取ろうとします。無理に良く見せようとすると、回答に一貫性がなくなり、かえって評価を下げることもあります。よって、転職活動では、素直に答えることが大切です。
普段の考え方や感じ方をそのまま表現することで、自分に合う職場かどうかも見えてきます。飾らず、自然体で臨むのが性格検査の基本です。
転職の適性検査についてよくある質問
転職活動で適性検査を受けるとき、「適性検査がボロボロだと落ちる?」「事前に内容はわかるの?」など、気になる点は誰にでもありますよね。ここでは、よくある質問をもとに、適性検査への不安解消に役立つ情報をまとめました。
安心して選考に臨むための参考にしてください。
適性検査がボロボロだと選考に落ちる?
適性検査の結果だけで選考が決まることは少なく、多くの企業は書類や面接とあわせて総合的に判断します。たとえ検査がうまくいかなくても、職務経験や人柄が評価されていれば通過する可能性は十分あります。
ただし、極端に低い結果や一貫性のない回答は懸念材料になることも。苦手な分野がある場合は、事前に練習しておくと安心です。
転職の選考で適性検査はどのくらい重要?
転職の選考において、適性検査はあくまで評価項目のひとつです。書類や面接とあわせて総合的に判断されるのが一般的であるため、検査の結果だけで合否が決まることは、そう多くありません。
ただし、極端にスコアが低い場合や、性格検査に一貫性がない場合は注意が必要です。特に未経験職種やポテンシャル採用では、能力や適性の判断材料として重視されることもあります。安心して本番に臨むためにも、事前の準備をおすすめします。
事前に適性検査の内容を教えてもらえる?
企業によっては、適性検査の種類や実施形式(SPIや玉手箱など)を事前に案内してくれることがあります。ただし、具体的な問題の内容まで教えてもらえるケースはほとんどありません。案内に記載がない場合は、問い合わせても差し支えないでしょう。
どの検査も出題傾向に一定のパターンがあるため、模擬問題などで事前に形式に慣れておくことが大切です。
転職の適性検査は、対策と自然体がカギ
適性検査は、転職選考結果のすべてを左右するものではありません。不安視する声も多いですが、自分の特性を客観的に知るチャンスでもあります。必要なのは完璧な結果ではなく、自分らしく向き合う姿勢です。焦らず準備を進めて、次のキャリアへ自信を持って一歩を踏み出しましょう。
転職やキャリアチェンジに向けて一歩踏み出したい方には、女性向けキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」がおすすめです。Webデザインやライティング、マーケティングなど、50以上の職種スキルを学べるほか、コーチングやコミュニティサポートも充実しています。
自分の可能性を広げたいと感じたら、まずは無料体験レッスンに参加してみてください。