生産年齢人口が減少傾向にあり、売り手市場が続くなかで、若手人材の確保や定着に悩む企業は多いかもしれません。そこで注目されているのが、従業員のスキル向上や離職防止に役立つ「フォローアップ」です。
そこで本記事では、ビジネスにおけるフォローアップとは何を意味するのか解説します。よく聞く言い換え表現や重要な理由、具体的な方法もまとめたので、ぜひチェックしてみてください。
フォローアップとは
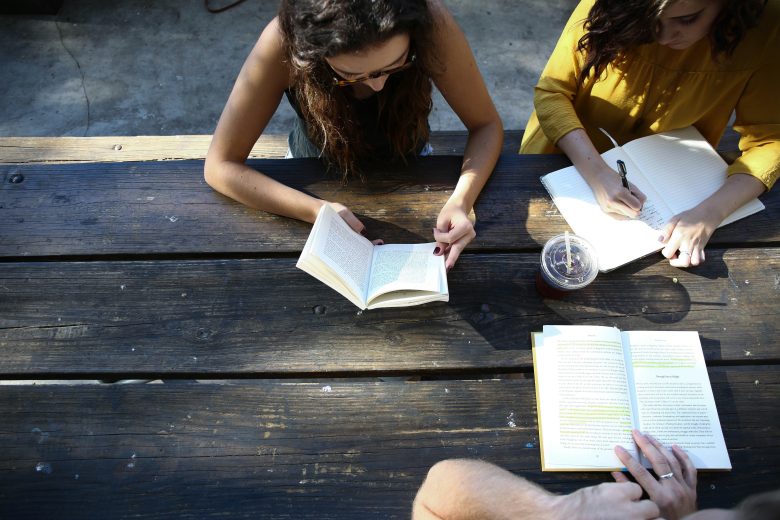
ビジネスでいう「フォローアップ」とは、すでに実施した行動を振り返り、さらに成果を伸ばす・あるいは改善するために支援する取り組みを指します。人材育成でも注目されていますが、実は教育・スポーツ・医療など、幅広い現場で使われている言葉です。
辞書には以下のように定義されています。
「ある事柄を徹底させるために、あとあとまでよく面倒をみたり、追跡調査をしたりすること」
goo辞書|「フォローアップ(follow-up) とは? 意味・読み方・使い方」より引用
もともとの英語「follow up」は「再確認する」「追跡する」という意味がありますが、分野によって少しずつニュアンスが変わってきました。たとえば医療分野では「経過観察」を指しますが、スポーツなら「チームメイトの攻撃をサポートすること」を意味するなど、場面により解釈が異なります。
フォローとの違い
「フォローアップ」と似た言葉に「フォロー」があります。フォローは、相手の不足分を代わりに補うイメージ。たとえば部下がミスしたとき、上司がサポートするのが「フォロー」にあたります。
一方、フォローアップは、相手が自力でできるようになるまで付き添い、成長を後押しするものです。短期的なサポートが「フォロー」、長期的なサポートが「フォローアップ」と考えるとわかりやすいでしょう。
フィードバックとの違い
フォローアップは、継続的に状況を見守りながら目標達成を支える取り組みです。一方、フィードバックは、成果や行動を評価して改善点を伝えることに重きを置きます。
たとえば、新人の業務習熟度を定期的に観察し、こまめに補足説明を加えていくのがフォローアップです。一方、提出物されたアウトプットに対してコメントし、改善策を提示するのがフィードバックにあたります。両方の違いを理解してうまく使い分けると、個々の成長をより効率的にサポートできるでしょう。
フォローアップの言い換え
ビジネスにおけるフォローアップを別の表現に言い換える場合、以下のような日本語を使うとイメージが伝わりやすいです。
- 追跡
- 再教育
- 経過観察
- 進捗確認
いずれも、「継続的に様子を見る・対応する」という意味合いを持っています。英語の類義語としては「sequel(続編)」「continuation(継続)」「supplement(補足)」などが挙げられます。シーンに合わせて使い分けてみてください。
ビジネスにおけるフォローアップ
ビジネスにおけるフォローアップは、主に以下の2つの分野でよく使われています。
ここでは、それぞれの分野で具体的にどんなことを行うのか解説します。
マーケティングにおけるフォローアップ
マーケティング分野での「フォローアップ」とは、取引先や顧客に改めて連絡を取り、新規契約や信頼関係の強化を目指す行動のことです。過去の商談相手に近況を尋ねたり、購入済みのお客様へアフターフォローを案内したりといった例が挙げられます。
継続的にコミュニケーションをとる(フォローアップをする)ことで、顧客満足度やリピート率のアップが期待できます。長期的なお付き合いを考えている取引先や顧客がいれば、定期的な連絡や情報提供を意識してみましょう。
人事におけるフォローアップ
人事での「フォローアップ」は、研修や教育訓練を受けた従業員へ、学習内容が定着しているかを確認するものです。「フォローアップ研修」と呼ばれることも多く、一般的に新入社員の研修後に取り入れられます。
そのほか、中堅社員の成長をサポートするためのフォローアップとして、昇進やキャリアアップのタイミングに合わせて研修をする企業も。次の章では人事におけるフォローアップを深掘りしていくので、気になる方はあわせてチェックしてみてください。
人事においてフォローアップが重要な理由
企業の人事分野においてフォローアップが重要な理由は、以下の3つです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
離職率の低下を図るため
フォローアップは、新入社員の離職率を下げるうえで役立つ取り組みです。厚生労働省の調査によると、令和3年3月卒業の新規学卒就職者のうち、高卒で38.4%、大卒で34.9%の割合で3年以内に離職したことがわかっています*1。
早い段階で職場に適応できず退職してしまうのは、企業にとって痛手です。研修後も継続的にフォローアップを行えば、「仕事についていけない」「人間関係に悩んでいる」といった声を早めに把握しやすくなるでしょう。結果として、離職率の低下も期待できます。
従業員のスキルを向上させるため
フォローアップは、従業員が研修や講習で学んだスキルを実務で生かせるようサポートする取り組みでもあります。1回の研修ですべてをマスターできる人は少ないもの。実務を重ねながらフォローを入れることで、現場力も伸びやすくなります。
さらに、キャリアアップの節目でフォローアップを実施すると、従業員の応用力や判断力を養いやすいです。必要なときに適宜サポートできる環境があれば、従業員一人ひとりがより高いパフォーマンスを引き出せるでしょう。
企業理念の浸透のため
入社時に共有された理念も、日常業務のなかで振り返る機会がないと定着しづらいかもしれません。フォローアップは、そうした企業理念の浸透にも役立ちます。
たとえば、新人研修後に先輩社員が営業に同行し、先方とのコミュニケーションや報告の仕方が理念に合っているかアドバイスをするなど、定期的に取り組むと意識づけしやすいです。全社員が共通の目標や価値観をもつことで、組織全体が同じ方向に進みやすくなります。
フォローアップの具体的な方法
実際にフォローアップを行う方法として、以下の4つが挙げられます。
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
人事担当との面談
人事担当者が従業員に直接ヒアリングをする方法です。業務上の悩みや不安、キャリアプランなどについて本音を聞き出し、現状を把握してから改善点や目標を立てます。
上司や先輩だといいづらいことも、フラットな立場の人事担当者なら話しやすいと感じる従業員もいるでしょう。現場のリアルな声を吸い上げることで、人事制度や教育プログラムの改善にもつなげやすくなります。
上司との1on1
所属部署の上司と1対1で面談を行うのも方法の一つです。普段から部下の行動を見守っているぶん、各従業員の得意・不得意を把握しているため、的確なアドバイスがしやすいでしょう。
また、グループではなく1対1であれば気兼ねなく話せるというメリットもあります。月一などで定期的に部下との面談を設定し、キャリアプランや業務上の悩みをサポートしていくことで、フォローアップの効果はさらに高まるでしょう。
研修形式
研修形式は、新人研修などの一定期間後に、同期や同僚を集めて学びを振り返るやり方です。研修で習った知識やスキルを業務でどう活用しているか話し合ったり、実際に起きたトラブルの解決策や成功体験をシェアしたりして、理解を深めていきます。
フォローアップ研修は社内で行うケースもあれば、グループ会社の社員を集めて外部で行う場合も。会社の規模や対象社員の人数、研修を実施するメンバーのリソースを含めて選択すると良いでしょう。
メンター制度の利用
メンター制度は、先輩社員が後輩社員のサポート役になる仕組みです。多くの場合、業務上利害関係のない部署が異なる先輩が担当するため、直属の上司や同僚にはいいにくい悩みも相談しやすいというメリットがあります。
メンターの主な役割は、新入・若手社員の相談に乗り、精神的なサポートをすること、課題解決に向けて効果的なアクションを起こせるよう支援することです。サポートを受ける側は気軽に相談できる相手がいることで安心して業務に専念できますし、メンター側も先輩としての自覚が芽生えます。双方にとって魅力的な制度でしょう。
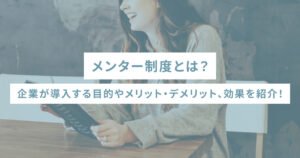
効果的なフォローアップを行うための3つのポイント
フォローアップの効果を高めるためには、前述した方法をただ取り入れるだけでなく、注意すべきポイントを押さえたうえで実施することが大切です。ここでは、効果的なフォローアップを行うためのポイントとして、以下の3つを紹介します。
それぞれ見ていきましょう。
PDCAサイクルを回す
PDCAサイクルは、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)をぐるぐると回し続ける方法です。フォローアップにPDCAサイクルを取り入れると従業員が成長を実感しやすく、モチベーションアップにも効果的でしょう。
「フォローアップの計画を立てて(P)実行(D)し、社員の変化を見る・フィードバックをもらう(C)などして、改善(A)を加えていく」の流れを習慣化してみてください。徐々にフォローアップの精度が高まるだけでなく、形骸化を防ぐことにもつながります。
話しやすい雰囲気を作る
フォローアップの場では、対象者が気軽に本音を話せる雰囲気づくりが大切です。余計なプレッシャーを感じさせるような場だと、建前や当たり障りのない意見しか出てこないかもしれません。
事前にアイスブレイクを入れたり、日頃から上司やメンターがこまめに声をかけたりすると安心感が高まります。リラックスした環境では、問題や不安をスムーズに共有でき、解決への道筋も立てやすくなるでしょう。
視野を広げられる環境を作る
対象者同士でアウトプットし合う場や勉強会を開催するなどして、視野が広がる環境を整えるのも大切です。同じ立場にいるメンバーが定期的に意見交換することで、新しい気づきやモチベーションアップが期待できます。
また、自分が学んだことをアウトプットできる場を作ると、知識やスキルの定着度もグッと高まるでしょう。「ビジネス現場でのフォローアップはこうあるべき」という固定観念に囚われすぎず、柔軟に環境を整えることを心がけてみてください。
フォローアップに関するよくある質問
最後に、フォローアップについてよくある3つの質問をまとめました。
気になる疑問の解決にお役立てください。
フォローアップを行う適切なタイミングは?
フォローアップには、「日常的に行う方法」と「一定期間後にまとめて実施する方法」の2パターンがあります。日常的に行う場合は、対象者の状態や希望に合わせてこまめに面談などを設定するケースが多いです。一方、研修や教育訓練の3ヶ月後・1年後など、定期的な節目で実施するパターンも。
「どちらが正解」というわけではないので、社員や会社の風土にあったタイミングで実施すると良いでしょう。余裕があれば両方を組み合わせるのもおすすめです。日々の不安を即座に解決しつつ、定期的な振り返りもできるため、習得した知識やスキルを業務で生かしやすくなります。
フォローアップを行うデメリットはある?
フォローアップは人材育成に役立つ一方で、以下のようなデメリットがあります。
- 手間時間がかかる
- 効果がわかりにくい
- 対象従業員がストレスを感じるおそれがある
個別の対応が必要なぶんスケジュール調整が大変ですし、成果が数字にあらわれにくく評価しづらい面もあります。タイミングが合わないと、対象者が負担に思うかもしれません。あらかじめ対象者のニーズや状況を把握し、無理なくフォローできる体制を整えることが大切です。
フォローアップ研修ではどんなことを実施すれば良い?
フォローアップ研修では、以下のような内容を取り入れると効果的です。
- 新入社員研修の復習:現場でぶつかった課題を振り返り、学んだ知識をもう一度チェックする
- キャリアプランの形成:将来の目標を整理し、自分の強みと課題を明らかにする
- コミュニケーション研修:ロールプレイなど実践的な方法で対話スキルを磨く
定期的に研修を取り入れると、自分の成長度を客観的に把握する機会が増えます。働き方を振り返るきっかけにもなるので、企業と従業員の双方にメリットがあるフォローアップ方法といえるでしょう。
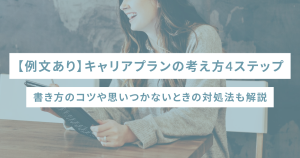

フォローアップは人材育成や離職防止に効果的!
継続的なフォローアップがあると、従業員のモチベーションやスキルが高まり、組織全体にも良い影響を与えます。生産年齢人口が減少傾向にあり、売り手市場が続く今こそ、こまめなフォローアップが離職率を下げる大きな鍵になるでしょう。自社の課題や従業員の声を確認しながら、上手に取り入れてみてください。
「もっとビジネスに役立つノウハウを増やしたい」「自分らしいキャリアを築きたい」と感じた方には、オンラインキャリアスクールSHElikes(シーライクス)がおすすめです。ビジネス系コースを含む全50以上の職種スキルが学べるほか、実践的な課題や案件にも挑戦できるので、実際の現場で役立つスキルが身につくでしょう。興味がある方はぜひ無料体験レッスンに参加してみてください。

※参考
*1:厚生労働省|「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」より

















