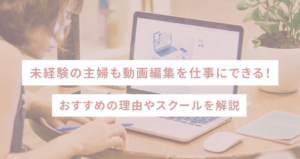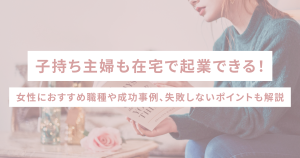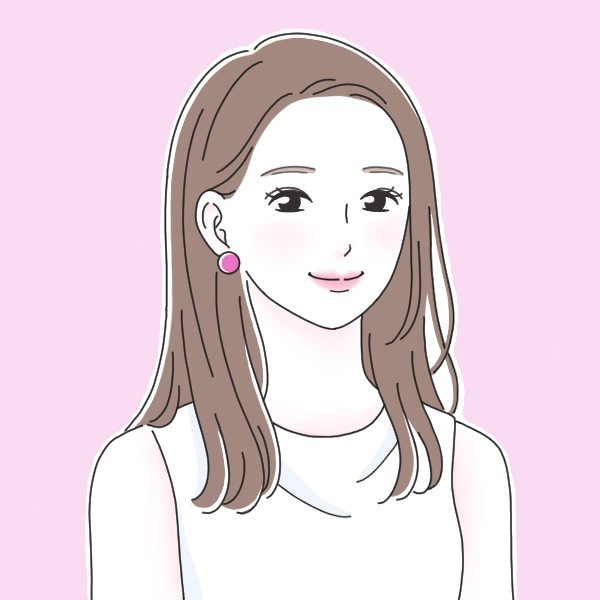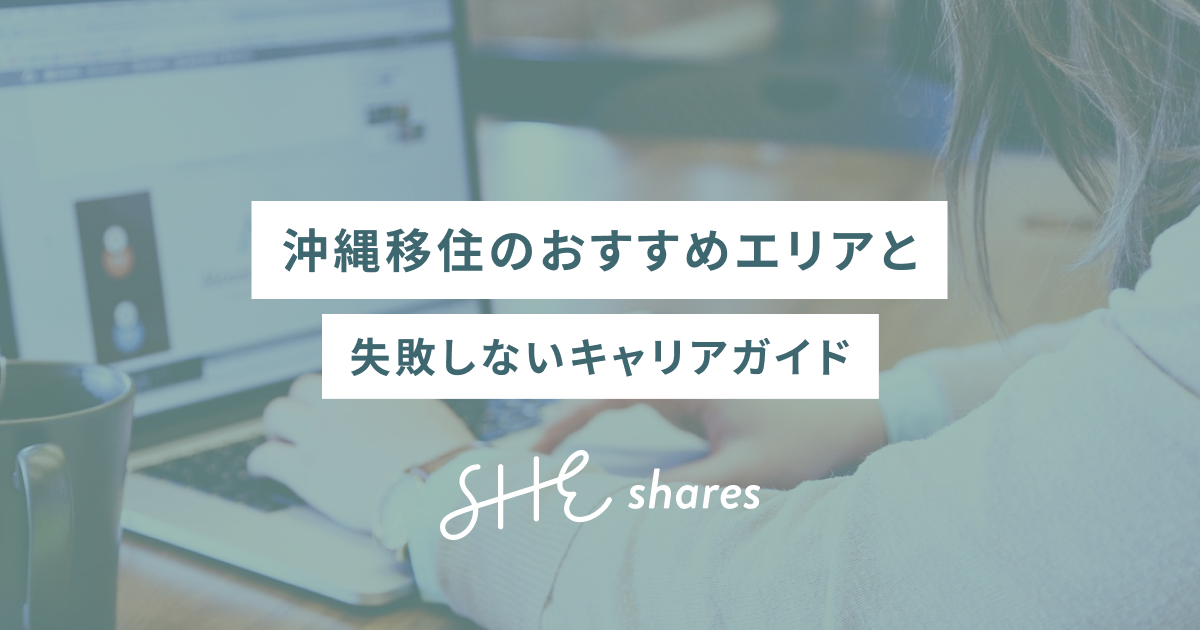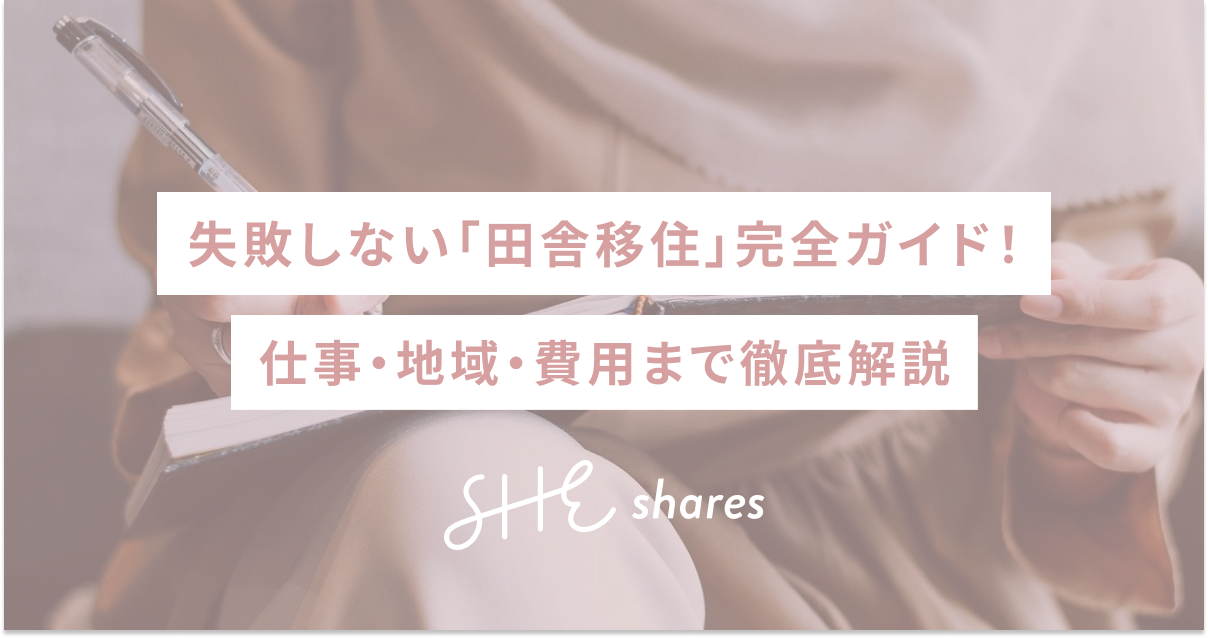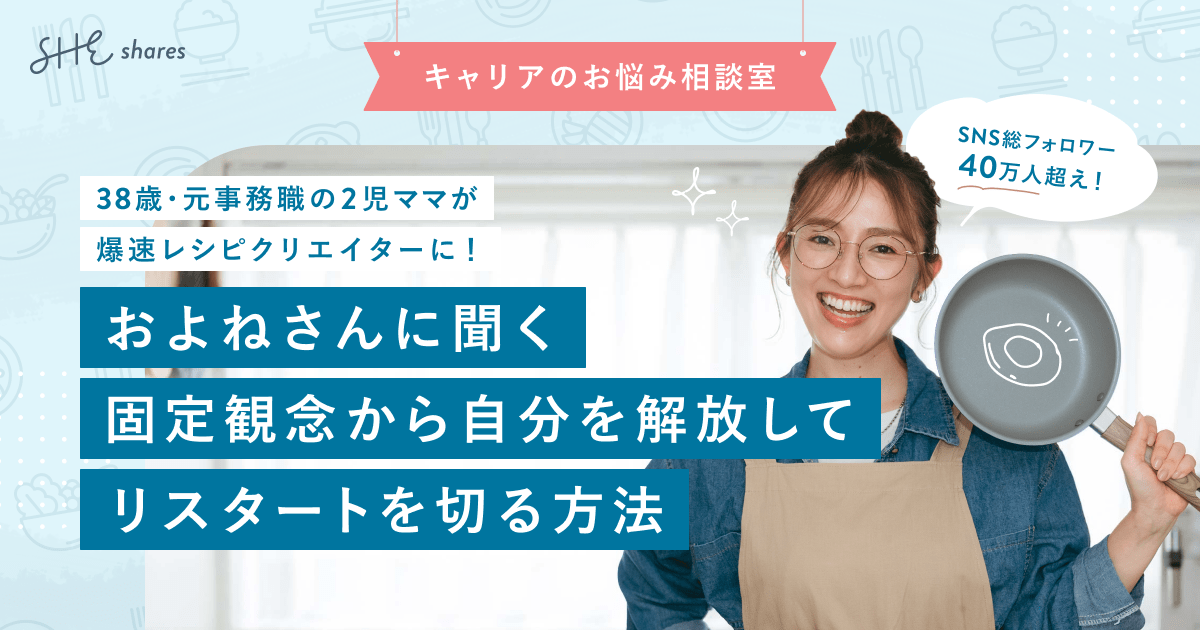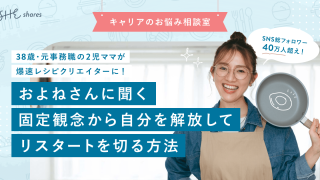子育てや介護、パートナーの転勤など、さまざまな理由から「個人事業主」として働くことに興味をもつ主婦の方も多いのではないでしょうか。一方で、「主婦が個人事業主になるにはどうしたらいいかわからない」「具体的なイメージが湧かずに挑戦できない」という方もいるでしょう。
そこで本記事では、個人事業主になりたい主婦の方に向けて、主婦が個人事業主になるメリット・デメリットや必要な手続き、おすすめの職種などを解説します。実際に主婦が個人事業主になった事例も紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
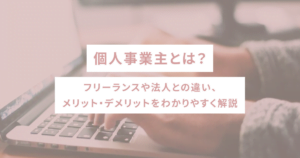
主婦も個人事業主になれる?
結論からいうと、主婦が個人事業主になることは可能です。開業届を提出し、個人で何らかの事業を営んでいれば、主婦に限らず誰でも個人事業主になれます。
そもそも個人事業主とは、「個人で事業を営んでいる人」のことです。法人を設立せず、企業や団体などの組織にも属さずに、個人で事業を運営します。いわゆる自営業者として起業することで、主婦はもちろん、誰でも個人事業主として事業を行えるのです。
主婦が個人事業主になるメリット
主婦が個人事業主になることに対して、多少なりとも不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。しかし、実は主婦が個人事業主になることのメリットはたくさんあります。ここでは、主婦が個人事業主になる主なメリットを3つ紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
自身のスキルや経験を生かせる
個人事業主におすすめの職種はたくさんあります。そのなかでも自分が得意な分野で開業すれば、これまで身につけたスキルや経験を仕事に生かすことが可能です。英語のスキルを活用して英会話レッスンや通訳の仕事をしたり、趣味でやっていたブログの経験を元にWebライティング案件を獲得したりなど、自身の強みを生かした事業を始めてみてください。
過去の勤務経験や取得した資格、趣味や特技で得たスキルなど、人によって強みとなるスキルや経験はさまざまです。個人事業主は、こうした自分の得意なことを事業に生かしやすい点がメリットといえます。
自由な時間管理ができる
会社員やパート勤務などの場合と比べて、個人事業主は時間のやりくりがしやすいです。打ち合わせ日や納期さえ守っていれば、仕事量や働く時間を比較的柔軟に調整できることも多いため、家事や育児、介護などとも両立しやすい点がメリットといえます。
「子どもの下校時間が早い日はスキマ時間でできる仕事を入れよう」「家族の急な体調不良に備えて予備日を設けておこう」など、自分や家族の都合に合わせて働けるのが、主婦にとって大きな魅力です。自宅で働く場合は通勤時間がないため、より時間を有効活用できるでしょう。
自分で収入をコントロールできる
会社員やパート勤務などの給与と違い、個人事業主は自分で働いて成果を出した分だけが収入になります。事業を始めてすぐの頃はなかなか思うように収入が確保できないかもしれませんが、事業が軌道に乗れば収入をコントロールできるようになるでしょう。
報酬の高い案件に挑戦できたり、効率的に仕事ができるようになったりすると、同じ時間働いたとしても得られる収入は増えます。事業が成長していけば、より収入や働く時間のバランスを調整しやすくなるのです。
主婦が個人事業主になるデメリット
主婦が個人事業主になりたいと思った際には、メリットだけではなくデメリットも理解したうえで行動することが大切です。ここでは主婦が個人事業主になるデメリットを3つ紹介します。あとから「知らなかった」と後悔しないように、事前にチェックしておきましょう。
収入が不安定、または減少する可能性がある
個人事業主は、会社員のように毎月決められた給与をもらえるわけではありません。成果を出した分、あるいは稼働した分が収入となるため、不安定になりがちです。安定した収入を得られるようになるまでに時間を要する場合もあります。
また、順調に収入が増えてきたとしても、クライアント事情で案件が終了するなど、思わぬタイミングで収入が減少してしまうことも。収入源を複数確保しておけば、急な収入の減少へのリスクを抑えられます。個人事業主として働く場合は、万が一の事態を考慮しながら調整することが重要です。
社会保険の扶養を外れる可能性がある
個人事業主としての収入が一定額を超えると、社会保険の扶養から外れることになります。配偶者の社会保険の扶養に入りたい場合は、扶養認定の条件をよく確認しておかなければなりません。
社会保険の被扶養者になるためには、年間収入が130万円未満であり、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが条件になります。ただし、対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、年間収入が180万円未満となります*1。
社会保険の扶養を外れる場合は、国民健康保険料や国民年金保険料を支払わなければなりません。保険料の支払いや手取りで残る金額のバランスなどを総合的に考え、社会保険の扶養の範囲で働くか、扶養を外れても支障がないくらいの収入を目指すかを判断しましょう。
確定申告が必要になる
個人事業主として開業した場合、基本的には毎年確定申告を行う必要があります。確定申告が必要なケースは次の通りです。
- 専業で個人事業をしていて、年間の事業所得が48万円以上の場合*2
- パートなどと兼業していて、年間の給与所得以外の所得が20万円以上の場合*3
初めて確定申告をする場合、日々の帳簿付けや必要な手続きが手間に感じるかもしれません。しかし、確定申告が必要な人が手続きを怠ると、無申告加算税などの罰則を受けることも*4。確定申告の直前で慌てることがないよう、必要な情報を集めて準備をしておきましょう。
やりたいことをお金で諦めない。
年収UP&好きなことで生きるためのお金のスキルを身につけませんか?
SHEmoney無料マンツーマン講座↓
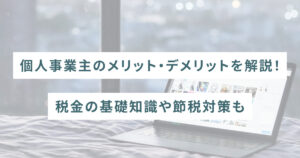
主婦が個人事業主になるために必要な手続き
主婦が個人事業主になるためには、はじめに「開業届」と「青色申告」の2つの手続きをしておく必要があります。ここでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
主婦が個人事業主になるには「開業届」の提出が必要
個人事業主として事業を開始する際は、納税地の所管税務署へ「個人事業の開業届出書」を提出しましょう。開業届は、国税庁のホームページからダウンロードできます。原則事業を開始してから1ヶ月以内に提出してください。窓口で提出するほか、郵送やe-Taxでも提出が可能です。
開業届を提出する際は、任意で屋号を定めることが可能です。屋号は銀行口座の開設や、ビジネス用クレジットカードの作成時に名義として使用できます。
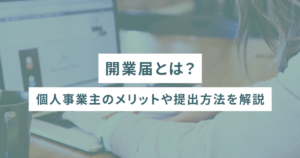
節税のためには「青色申告承認申請書」を提出しよう
個人事業主として開業する際には、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」も税務署に提出しましょう。青色申告とは、確定申告で事業所得に対する所得税を申告するための方法のひとつです。
ちなみに、申告方法は「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。それぞれの特徴は次の通りです。
| 申告方法 | 記帳方式 | 控除額 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 青色申告 | 複式簿記 | 10万円または55万円または65万円 | 最初に青色申告をしようとする年の3月15日まで (その年の1月16日以後、 新たに事業を開始した場合には、 その事業開始等の日から2か月以内) |
| 白色申告 | 簡易簿記 | なし | 書類提出の必要なし |
白色申告は簡易簿記という比較的シンプルな記帳方法での申告が可能ですが、青色申告特別控除のような控除額はありません。一方、青色申告は複式簿記という複雑な記帳方法ですが、控除額は10万円または55万円または65万円と節税効果が高まります。経済面で考えると、青色申告を選択するほうが良いでしょう。
「複式簿記は難しそう」と思う人もいるかもしれませんが、会計ソフトを使用すれば複雑な計算はほとんど必要ありません。「青色申告承認申請書」は、国税庁のホームページからダウンロードできます。開業届と同じように窓口、郵送、e-Taxのいずれかの方法で提出が可能です。
ただし副業の場合は基本的に事業所得ではなく雑所得という扱いになり、青色申告を使うことはできないので注意しましょう(例外的に青色申告を使える場合もあります)。
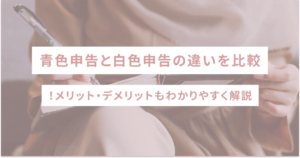
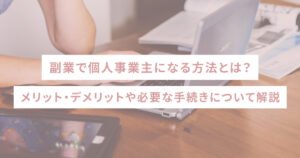
個人事業主を目指す主婦におすすめの職種7選
「個人事業主」とひと言でいっても、職種はさまざまです。これから個人事業主になりたい主婦の方には、未経験からスキルを身につけやすい職種に挑戦することをおすすめします。ここでは、主婦におすすめの未経験から始めやすい職種を7つ紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
| おすすめの職種 | 主な仕事内容 |
|---|---|
| 1. Webデザイナー | WebサイトやWeb上に掲載する バナーのデザインを担当する |
| 2. ライター | Webサイトや雑誌などに掲載する 記事や文章を執筆する |
| 3. SNSマーケター | SNSを通してマーケティング活動を行う |
| 4. カスタマーサクセス | 商品を購入した顧客に能動的に 働きかけ、企業の利益を生み出す |
| 5. 動画編集者 | 依頼に応じて動画コンテンツを作成する |
| 6. 広報・PR | 業務委託契約を結んだ企業の 広報業務を請け負う |
| 7. コーチング講師 | 個人や企業向けのコーチングや コーチングセミナーの講師など、 コーチングスキルを生かして仕事をする |
1. Webデザイナー
Webデザイナーとは、WebサイトやWeb上に掲載するバナーのデザインを担当する職種のことです。バナー制作やサイト全体の設計など仕事内容はさまざまですが、自宅で自分のペースで作業できるのが魅力のひとつといえます。
Webデザイナーとして働くために特別な資格は必要ありませんが、Webデザインに関する専門的な知識やスキルは必須です。未経験から効率的にスキルを身につけたい方は、オンラインスクールや講座などで学んでから始めるとよいでしょう。

2. ライター
ライターとは、Webサイトや雑誌などに掲載する記事や文章を執筆する仕事です。とくに、Webサイトのコンテンツを執筆するWebライターは求人数も多く、ネット環境さえ整っていれば特別な資格がなくても挑戦できます。未経験から始めやすく在宅で仕事ができる点で、主婦の方におすすめの職種です。
ただし、経験が少ないうちに挑戦できる案件は、低単価な傾向にあります。そのため、得意分野を見つけたり、これまでの経験が生かせる専門知識に関するジャンルで執筆したりと工夫が必要です。安定した収入を得るためにも、コツコツと実績を積み上げていくことを意識してみてください。

3. SNSマーケター
SNSマーケターとは、InstagramやX(旧Twitter)などのSNSを通して、マーケティング活動をする職種のことです。個人事業主としてSNSマーケターの仕事をする場合、企業や個人のSNSの運用代行や、自身のSNSアカウントで発信をする方法などがあります。
パソコンやスマートフォンがあれば作業できるため、時間や場所に縛られずに働けることがメリットのひとつです。ただし、企業のSNS運用を代行する場合は、企業が定めた目標を達成することが求められ、実践的なマーケティングスキルが欠かせません。スクールや講座で知識やスキルを学んでから始めるのが良いでしょう。

4. カスタマーサクセス
カスタマーサクセスとは、商品を購入した顧客に能動的に働きかけ、継続的に企業の利益を生み出す仕事です。たとえば、サブスクリプション型サービスの場合「顧客満足度の向上」や「解約率低下」のために、ユーザーがサービスを継続的に活用したいと思える企画を考案します。
有効な施策を提案するためには、顧客へのヒアリングや問い合わせへの対応なども欠かせません。個人事業主であれば企業と業務委託契約を結んで働くケースが多いです。オンラインで完結する業務なら自宅など好きな場所で働くこともできるでしょう。

5. 動画編集者
動画編集者とは、クライアントからの依頼に応じて動画コンテンツを制作する仕事です。近年、動画市場が拡大傾向にあることから、動画編集者の需要は高まっています。娯楽としての動画だけではなく、PR活動やビジネスシーンでも動画を使用するケースが増えているためです。
動画編集の仕事は、編集ソフトやアプリを使用するスキルがあれば始められます。撮影以外の作業はパソコンで完結することが多く、時間や場所を選ばずに働けるのがメリットのひとつです。
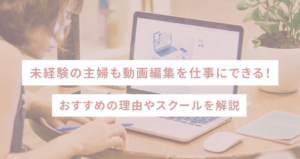
6. 広報・PR
個人事業主として広報・PRの仕事を行う場合、業務委託契約を結んだ企業の広報業務を請け負うケースが多いです。プレスリリースの作成やイベントの企画、調査リリースの作成など、広報・PRに関するさまざまな業務を担当します。
広報・PR業務を通して成果を上げるには、SNS運用の知識やライティングスキル、マーケティングスキルなど、複数の知識や経験が必要です。業務内容が多岐に渡るため、まずは自分のスキルで担当できる業務から始め、少しずつ業務の幅を広げると良いでしょう。
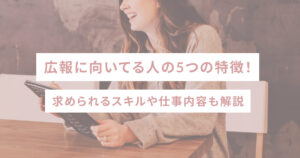
7. コーチング講師
コーチングとは、対象者の自発的な行動を促進するためのコミュニケーション技術のことです。個人事業主としてコーチングを行う場合、個人や企業向けセッションのほか、セミナーの講師やコミュニティ運営など、さまざまな事業の形があります。
通常コーチとして働くために特別な資格は必要ありませんが、仕事を得るにはクライアントからの信用が欠かせないでしょう。SNSやプラットフォームを活用してコーチングの実績を積むほか、開業前に資格を取得しておくのも方法のひとつです。コーチングについて詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
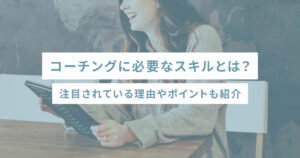
主婦が個人事業主になるにはSHElikesで学ぶのもおすすめ!
主婦が個人事業主になるには、興味のある職種で生かせる知識やスキルを身につけるのが近道です。「どんなスキルが必要かわからない」「数ある選択肢から自分に合った職種を見つけたい」という主婦の方は、女性向けキャリアスクールSHElikesを活用してみてはいかがでしょうか。ここでは、SHElikesの特徴と主婦におすすめの理由を紹介します。
女性向けキャリアスクールSHElikesの特徴
SHElikesは、全50以上の職種スキルが学べる女性向けキャリアスクールです。Web・IT系分野を中心にスキルの習得が可能なため、時間や場所に縛られない働き方の実現に向けて準備ができます。具体的に受講できるコースは、次の通りです。
多種多様なコースから自由に組み合わせて学べるため、複合的にスキルアップできます。また、コース受講以外に学習サポートが充実している点も魅力でしょう。
たとえば月に1回利用できるコーチング*では、目標に対してどのくらい達成できているのかをシェアすることで、学習計画の見直しやモチベーションの回復ができます。そのほか、学んでいてわからないことを講師に質問できる機会があるのもおすすめポイントです。
*コーチング:夢や理想に近づくために、コーチと一緒に目標設定・振り返りを行う場。
SHElikesが主婦におすすめな理由
SHElikesはオンラインで好きな時間に受講できるため、家事や育児に忙しい主婦でもスキマ時間を有効活用して学ぶことが可能です。たとえば、子どもが学校に行っている時間や、家族が寝静まった夜の時間など、自分の好きなタイミングで学習できます。
また、コーチングやコミュニティ*を活用すれば、一緒に学ぶ仲間を見つけやすいです。1人では挫折しやすい学習も、仲間が入ればモチベーションを保ちやすく継続しやすくなるでしょう。努力する仲間の姿が刺激になったり、互いに励まし合ったりと、主婦にとって一緒に学ぶ仲間の存在は心強いものといえます。
*コミュニティ:「デザイン」「朝活」など、関心のあるトピックやコース別にさまざまなコミュニティがあります。受講生が運営し、定期的にイベントを開催しています。
主婦から個人事業主として独立を果たした先輩たちの事例
個人事業主になることを目指している主婦の方は、実際にキャリアスクールでキャリアアップに成功した先輩たちの事例も参考になるかもしれません。ここでは実践的なスキルを身につけ、理想の働き方を実現した先輩たちの事例をご紹介します。
事務職からフリーの動画クリエイターへ|子育てと個人事業主としての活動を両立
2児のママであるあっこさん。事務職として働きながら、プライベートで動画編集をしていたそうです。友人から褒められることも多く、「私、動画編集に向いているかも」と思い始めました。その後「もっと動画編集が上手くなりたい」という気持ちから、SHElikesに入会を決意します。
動画編集系のコースをすべて受講し、ツールの使い方を身体で覚えられるまで、何度も繰り返しました。また、ほかの受講生が作った作品やSNS広告を見て、講座だけでは学べないテクニックも積極的にインプット!スキル習得後は、SHEのお仕事紹介を活用して実績を積んだそう。現在はフリーの動画クリエイターとして、子育てと仕事の両立を実現しています。
あっこさんが手にした成果
- 2人の子どもを育てながらもフリーの動画クリエイターとして独立
- 趣味だった動画編集をプロレベルのスキルに向上させて仕事に
- 子育てと個人事業主としての活動を両立
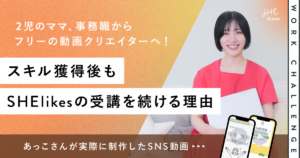
専業主婦からフリーのスライドデザイナーへ|会社員月収の3倍を達成
会社の体勢が変わりフル出社になったことで、子育てと仕事の両立に悩むようになったhisaさん。持続可能な働き方を模索するため、退職して専業主婦になったそうです。そんなときにSHElikesに出会い、デザインのスキルを習得するために入会します。
「スライドデザインコース」を受講し、スライドデザイナーという職種があることを知ったhisaさん。「営業企画時代から好きだった資料作成が仕事になるかも!」と可能性を感じ、スキルを高めていきました。そして受講から4ヶ月でフリーランスのスライドデザイナーに転身!実績を積み重ね、会社員時代の月収3倍も達成しています。
hisaさんが手にした成果
- 専業主婦からフリーランススライドデザイナーに転身
- 会社員時代のスキルや得意なことを生かして仕事に!
- 会社員時代の月収3倍も達成

主婦でも個人事業主になれる!自分に合った働き方を目指そう
自身のスキルや経験を生かすことで、主婦も個人事業主になることが可能です。個人事業主として自分に合った働き方を見つけられれば、家庭も仕事も両立しながら過ごせるようになるなど、メリットも多くあります。
「どんな職種で事業を始めればいいかわからない」「スキルに自信がないのでこれから身につけたい」と考える主婦の方には、女性向けキャリアスクールSHElikesがおすすめです。
SHElikesでは、主婦が個人事業主として働くために必要なさまざまな知識やスキルを学べます。SHElikesで興味のあることや好きなことを学び、個人事業主として活躍してみませんか?気になる方はぜひ一度無料体験レッスンに参加してみてください。

※出典
*1:全国健康保険協会「被扶養者とは?」より
*2:国税庁「No.1199 基礎控除」より
*3:国税庁「確定申告が必要な方」より
*4:国税庁「延滞税について」より