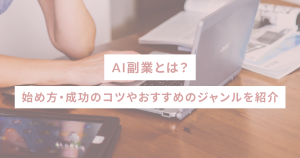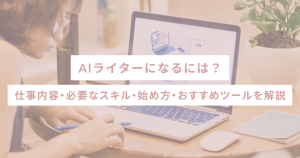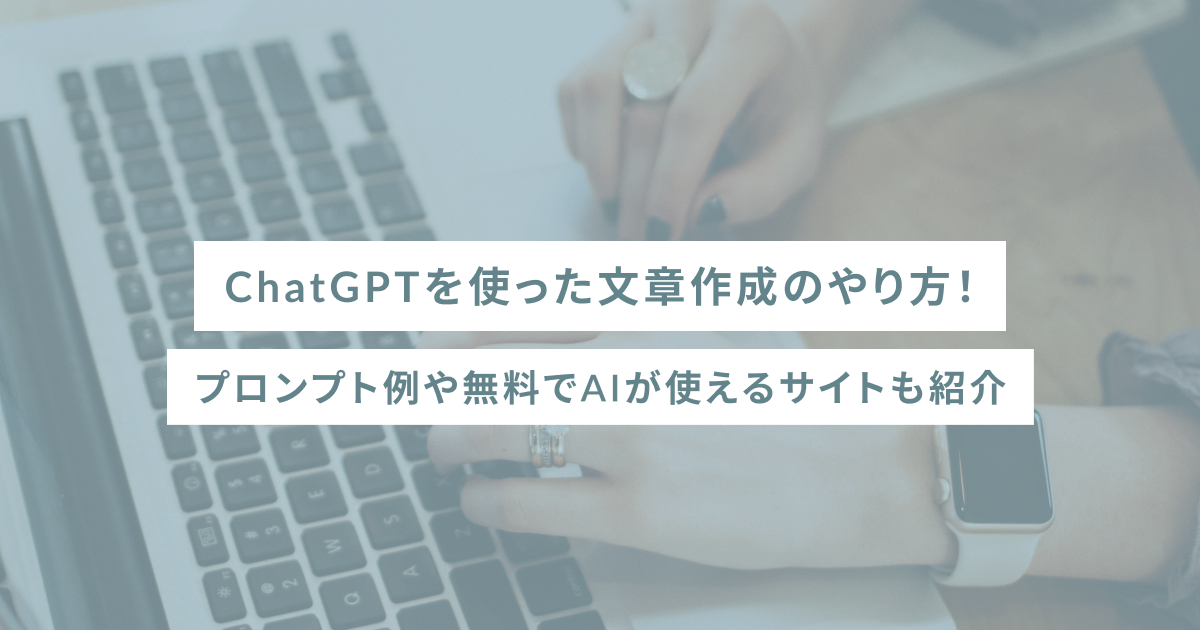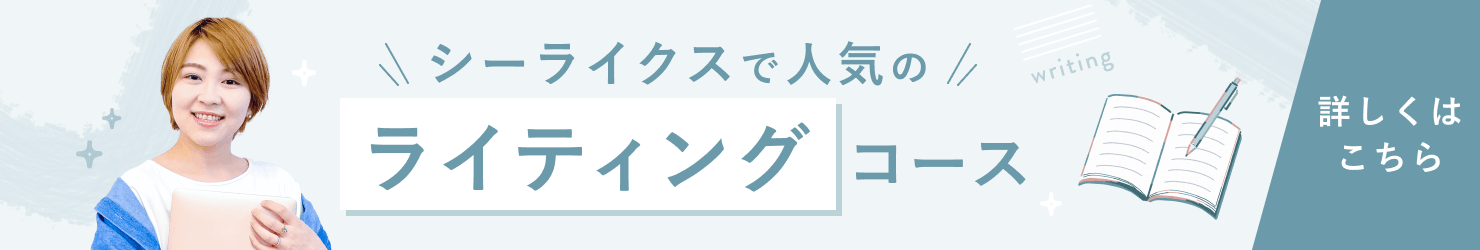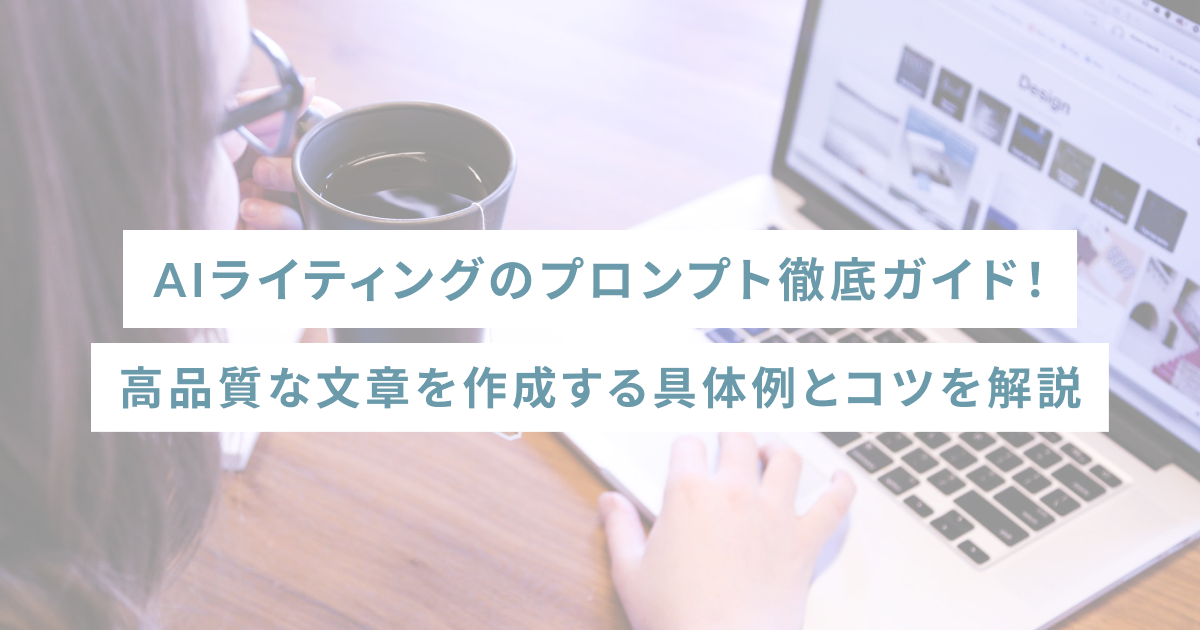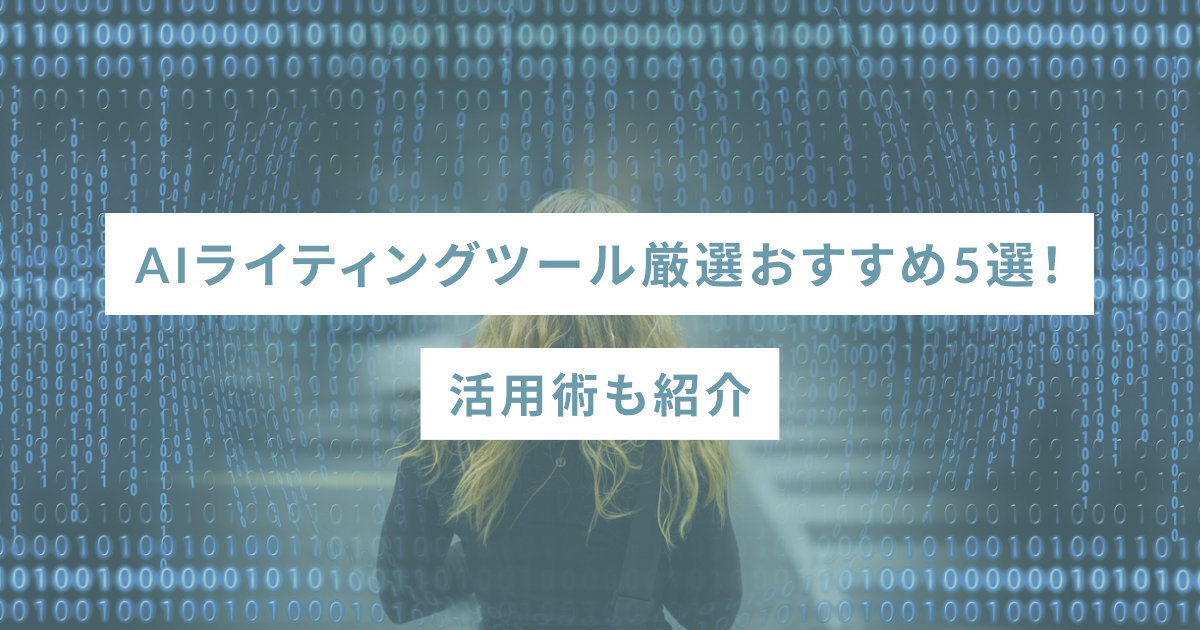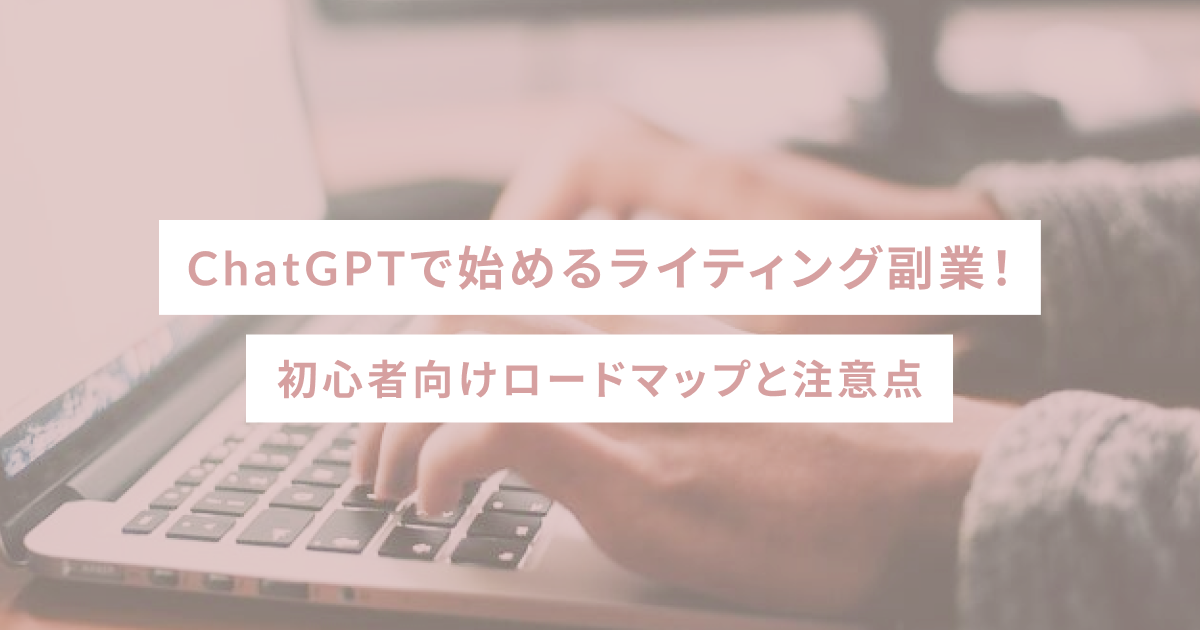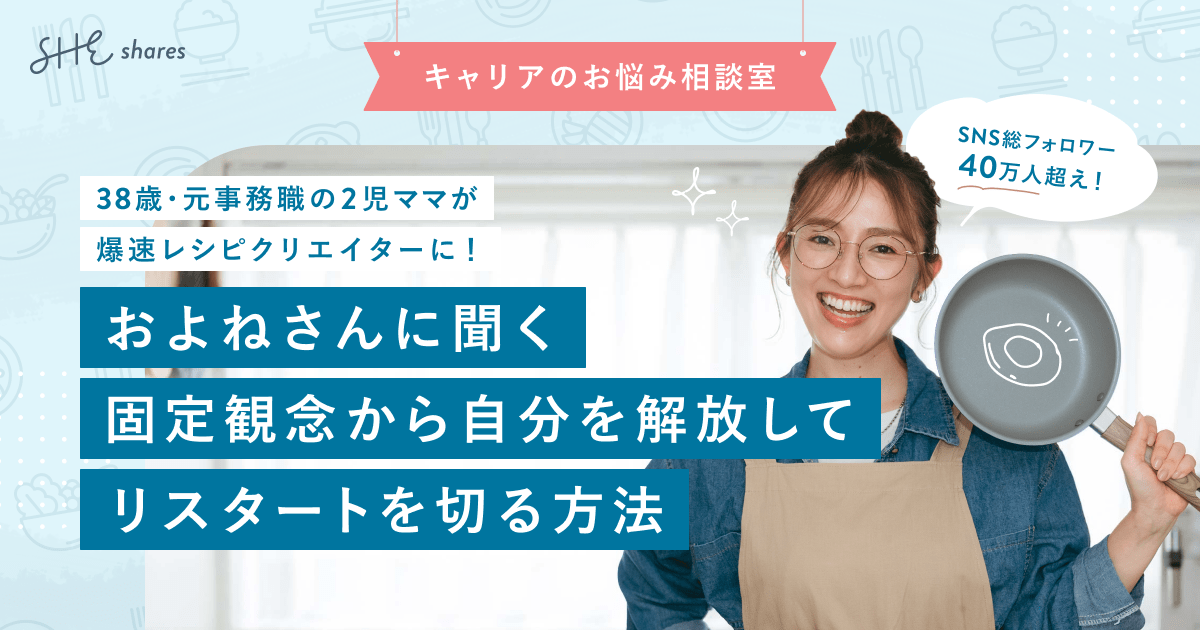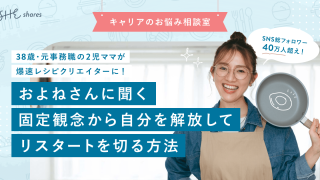無料でも使えるAIツールとして注目を集めている「ChatGPT」。ブログ記事の作成やレポートの下書きなど、文章を書く作業を劇的に効率化できるツールとして多くの人が使い始めています。
この記事では、初心者の方でも理解しやすいよう、ChatGPTを使った文章作成のやり方、プロンプトの具体例とコツ、無料でChatGPTの機能が使えるサイトまで解説します。
ChatGPTを使った文章作成のやり方
ChatGPTを使えば、文章作成の時間をぐっと短縮できます。
ここでは、初心者でも迷わず試せるやり方をステップごとに紹介します。
1.無料版か有料版のChatGPTに登録する
ChatGPTで文章作成を始めるには、無料版、または有料版に登録する必要があります。公式サイトでアカウントを作成し、メール確認・ログインまで完了させましょう。登録後は、会話画面へアクセスすればプロンプト(指示文)を入力する画面が出てきます。
無料版でも基本的な文章作成機能は十分に使えますが、有料版はより高性能。ファイルアップロードが無制限、コード実行や画像入力ができるなどのメリットがあります。
2.プロンプトを入力する
次に、プロンプトを入力して、ChatGPTに文章作成を依頼します。「〇〇というテーマで、◯◯をターゲットとした1000文字程度のブログ記事を書いてください。」といったように具体的に指示すると、狙いどおりの文章が得られやすくなります。
さらに、「SEOを意識した構成」「文体はですます調」など条件を付けることで、より実用的な文章が得られます。
3.出力内容を確認し必要なら修正指示を出す
ChatGPTが生成した文章をそのまま使うのではなく、「内容が正確か」「誤字脱字はないか」「文体にズレはないか」などを確認します。このとき、「もっとカジュアルな口調で」「箇条書きを入れてください」など、再度プロンプトで修正指示を出すことがコツです。
初めに入力した指示だけで期待どおりにならないケースも多く、必要に応じて修正の指示を出した方が完成度の高い文章が生成されます。
4.文章をリライト・編集する
最後に、生成された文章をリライト・編集します。AIを使った文章作成は確かに効率的ですが、そのままだと機械的な印象になりがち。導入に「ちなみに」という語り口を加えたり、親しみのある口調を足したりすることで、より自然な文章になります。
また、一次情報として参照したエビデンス(研究論文や専門家の発言)を本文内に取り込み、信頼性を高めることも重要です。以下の記事では、AI副業で稼ぐための具体的な方法や注意点を解説しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。

ChatGPTで作成できる文章の種類とプロンプト例
ChatGPTを使えば、ブログ記事の構成からメール文、SNS投稿、要約まで、幅広い文章を作成できます。
ここでは、実際のプロンプト例を交えながら、実践的な文章生成のやり方を紹介します。
Web記事・ブログ記事の構成案と本文作成
ブログやオウンドメディアの記事制作では、ChatGPTを記事作成のサポートに使うのがおすすめです。テーマを入力するだけで、見出し構成から本文案まで自動で提案してくれます。
SEO記事の構成を考えるときは「どのような読者を想定して、何を伝えるか」を明確にしておくと、出力の精度がアップ。さらに「タイトル」「導入文」「H2・H3構成」を具体的に指定すると、検索に強い記事のベースをスムーズに生成できます。
プロンプト例
構成案を作成する場合
「20代女性に向けて『在宅ワークの始め方』をテーマに、SEOを意識したWeb記事の構成案と導入文を作成してください。全体で2,000文字程度、前向きで親しみやすいトーンでお願いします。」
本文を作成する場合
「以下の構成に沿って、記事の本文を作成してください。読者が共感しやすいエピソードや具体例を交えて、自然で読みやすい文章にしてください。見出しごとに300〜400文字程度、です・ます調でまとめてください。」
プロンプトのポイント
構成案を依頼するときは、テーマ・読者像・目的(SEO、集客、共感など)を具体的に伝えると精度が高まります。本文を生成する際は、構成案の各見出しを指定して出力すると、情報の重複や流れの乱れを防ぐことができます。
また、「語尾はです・ます調」「前向きでやわらかいトーン」といった文体のルールを事前に設定しておくのもポイント。さらに、「もっと簡潔に」「事例を加えて」など再度指示を重ねることで、より完成度の高い記事に仕上がります。
メール・ビジネス文書の作成
メールや報告書などのビジネス文書も、ChatGPTが得意とする分野です。出力された内容を自分らしいトーンに調整することで、時間を大幅に節約できます。
取引先へのお礼メールや上司への報告文を書く際は、「件名→挨拶→本文→締めの一文」といった基本の構成をChatGPTに指示するとスムーズです。定型の流れをふまえたうえで、自分の言葉を加えることで自然で誠実な印象の文章に仕上がります。
プロンプト例
「クライアントへの納品完了報告メールを作成してください。「件名→挨拶→本文→締めの一文」で構成してください。丁寧で誠実なトーンで、感謝の気持ちを伝える一文も入れてください。」
プロンプトのポイント
状況や相手の立場を具体的に入力すると、文脈に合った文章が生成されます。一方で、ChatGPTが出した文面をそのまま使うのではなく、「敬語のバランス」や「相手の名前・日付」などは手動で確認しましょう。特にビジネス文書では、AIの提案を下書きとして使い、自分の意図に合わせて編集するのがコツです。
SNS投稿・キャッチコピーの作成
SNSでは、短く印象的な言葉が求められます。ChatGPTにテーマや目的を伝えると、複数のコピー案を出してくれるので、アイデア出しに便利です。「自分のサービスをより多くの人に知ってもらいたい」「季節の投稿をおしゃれにまとめたい」というとき、ChatGPTは効果的な表現を提案してくれます。
プロンプト例
「20代女性向けのライフスタイルブランドのInstagram投稿文を3パターン作成してください。秋の新作発売を告知する内容で、ハッシュタグ案も5つ提案してください。文体は上品なものにしてください。」
プロンプトのポイント
SNS向けの場合は、感情や共感を引き出す言葉を指定することがポイント。また、文体を「カジュアル」「ナチュラル」「上品」などに指定することで、ブランドの世界観を統一できます。出力された文章は「少し短くして」「より親しみのある表現に」などと再指示することで、投稿用に最適化できます。
文章の要約
長文の要約もChatGPTの得意分野です。記事、レポート、議事録などを短時間でまとめられるため、ビジネスや学習の効率化に役立ちます。特に「自分の言葉で理解する前段階の整理」として使うと便利。AIに一度まとめてもらったうえで、自分の意見を加えるのがおすすめです。
プロンプト例
「以下の文章を中学生にもわかるように300文字以内で要約してください。重要な数値や結論は残してください。」
プロンプトのポイント
要約の目的(例:資料作成、報告、学習)を明確に伝えることで、必要な情報が抽出されやすくなります。「語尾はです・ます調で」「中学生にもわかるように」など、トーンを指定することで、用途に合わせた仕上がりになります。
ChatGPTで質の高い文章を作成するコツ
ChatGPTでの文章作成は、やり方とプロンプト次第で仕上がりが大きく変わります。
ここでは、すぐ実践できるコツを厳選して紹介します。具体的な指示やペルソナ設定などを意識するだけで、精度も表現もぐっと向上します。
具体的な指示を出す
まずは「どう書いてほしいか」を明確にするのが大切です。目的、読者層、文字数、トーン、構成などを細かく指定すると、ChatGPTが意図を正確に理解しやすくなります。「結論を先に」「600字で」「親しみやすく」といった細かい指示を添えるのがポイントです。
段階的に指示する
一度に完璧な文章を求めず、「構成を作る→本文を書く→推敲する」と段階的にプロンプトを出すのが効果的です。各ステップで「もっと簡潔に」「語尾を統一して」など具体的に伝えることで、最終的な完成度がぐっと高まります。
ペルソナを設定する
指示を出す際には、読者像(=ペルソナ)を明確にすると、伝えたい内容や語彙選択が自然と洗練されます。年齢や職業、悩み、読むシーンまで具体的に設定し、「この人に届く言葉」をプロンプトに落とし込むのがコツ。「20代後半の女性」「仕事に悩む人に寄り添うトーン」などを伝えると精度が上がります。
追加指示をする
初回の出力は下書きとして受け取り、「具体例を2つ追加」「表現をやわらかく」「段落を短く」など、追加指示を重ねてブラッシュアップしましょう。短い指示でも繰り返すほど完成度が上がります。ちなみに、修正点を箇条書きにすると反映率が高くなるのでおすすめです。
文章の型(フレームワーク)を指定する
PREP法(結論→理由→例→まとめ)やPASONAの法則など、文章の型を指定すると読みやすい文章を生成できます。特にSEO記事やレポートでは、先に構成の枠を決めてから本文を依頼するのがおすすめ。「問題→原因→解決策→まとめ」で整理すると、読みやすく説得力のある文章に仕上がります。
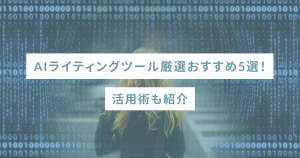
ChatGPTを使った文章作成の注意点
ChatGPTは便利なツールですが、使い方を誤ると誤情報が含まれたり著作権の問題につながったりすることもあります。
ここでは、文章作成をより安全かつ信頼性高く行うために知っておきたい3つのポイントを紹介します。AIを正しく活用するための基礎として押さえておきましょう。
ファクトチェックを行う
ChatGPTで生成された文章は、一見正確に見えますが、情報源が明示されていない場合も多く、誤ったデータや古い情報が混ざる可能性があります。統計や企業名、専門的な用語の説明などは、公式サイトや公的データベースなど一次情報での裏取りが欠かせません。
これは読み物コンテンツだけでなく、SNS発信やビジネスメールでも同様に意識したいポイントです。
著作権やオリジナリティに配慮する
ChatGPTが生成する文章は、膨大な学習データをもとに作られています。そのため、似た表現や既存の文章と類似のものが出力されるケースも。そのため、出力内容をそのまま転載するのではなく、自分の経験や意見、感情を加えてリライトし、オリジナリティを担保することが大切です。
AIの力を借りつつも、読者があなたにしか書けない視点を感じ取れる文章にすることが、これからの時代に求められるライティング力です。
AIと人間の役割分担を理解する
ChatGPTは「文章を整える」「構成を整理する」といった作業を得意とする一方で、感情や体験を伴うリアリティのある表現は人間の得意な領域です。文章作成をする際には、AIに構成と本文のたたきを依頼し、その後に自分で経験談や具体例を加えるような使い方をしていくことが重要です。
AIと人間が得意分野を分担しながら共創することで、効率とオリジナリティの両立が可能になるでしょう。
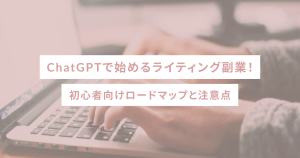
【無料あり】ChatGPTと連携し文章作成ができるサイト
ChatGPTを使った文章作成は、専用ツールを活用することでさらに効率化できます。
ここでは、無料プランでも使いやすく、ライティング初心者にも人気のChatGPTと連携した3つのサイトを紹介します。記事作成やSNS投稿、コピーづくりなど、目的に合わせて使い分けてみましょう。
Catchy
「Catchy」は日本語対応しており、ChatGPTと連携して多彩なテンプレートから文章を自動生成できるサイト。キャッチコピー、記事タイトル、LP文面、SNS投稿など、用途ごとに最適なフォーマットが選べます。
無料プランでも一定回数の生成が可能なので、まずは試して感覚をつかむのがおすすめです。
Copy.ai
「Copy.ai」は、ブログ記事やInstagramのキャプションなど、さまざまなコンテンツを作成できるAIライティングプラットフォームです。ユーザーが入力したプロンプトに基づいて、広告コピー、ブログ概要、メール文などを瞬時に生成します。
現在は90種類以上のテンプレートが利用可能で、30以上の言語に対応(日本語の入力・出力も可能)。管理画面は英語表記ですが、シンプルな設計で直感的に操作できる点も特徴です。
SAKUBUN
「SAKUBUN」は、日本国内で開発されたAIライティングツール。記事作成を中心に、SNS投稿文や商品紹介文など、100種類以上のテンプレートを活用して幅広いコンテンツを生成できます。SEO記事の叩き台を短時間で作成できるため、記事制作コストを最大70%削減できる点が強みです。
また、ペルソナ(読者像)の設定機能やSEOスコア分析機能を搭載しており、ターゲットに合わせた最適な文章を作成可能。無料プランも提供されており、学習用途からビジネス利用まで幅広く活用できるツールです。
AI時代に強い「掛け合わせスキル」を学ぶならSHElikes
ChatGPTを使った文章作成スキルは、今やライターやマーケターだけでなく、どのような職種にも役立つ汎用スキルになりつつあります。とはいえ、AIの力を最大限に活かすには、デザインやマーケティング、ブランディングなど他分野との掛け合わせが重要です。
女性向けキャリアスクールSHElikes(シーライクス)では、Webライティング、デザイン、マーケ、SNS運用など50以上の職種スキルが定額で学び放題。自分の感性とAIスキルを組み合わせることで、これからの時代に求められるクリエイティブなキャリアを築くことができます。

ChatGPTを味方につけて、自分らしい文章を届けよう
ChatGPTを使った文章作成は、発想を広げ、作業を効率化する手助けとなります。ただし、AI任せにするのではなく、情報の正確性を確かめ、自分らしい表現を加えることが大切。目的や読者に合わせてプロンプトを工夫すれば、AIと人の良さを掛け合わせた魅力的な文章が生まれます。
一方で、文章力や発信スキルをさらに高めたいなら、SHElikesがおすすめ。Webライティングやマーケティング、デザインなどを横断的に学びながら、AI時代に求められる「考えて伝える力」を育てることができます。初心者でも安心のカリキュラムと、モチベーションを高め合えるコミュニティが揃っているのも魅力です。
まずは、無料体験レッスンでSHElikesを体感してみませんか?AIを味方にしながら、自分らしいキャリアを描く第一歩を踏み出しましょう!