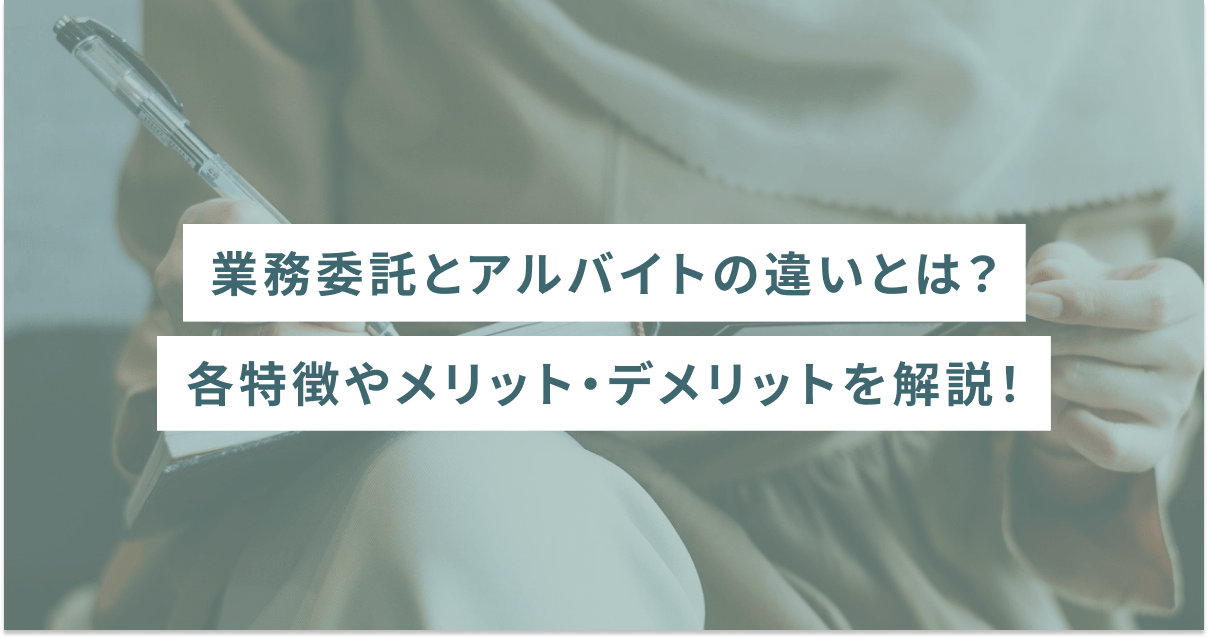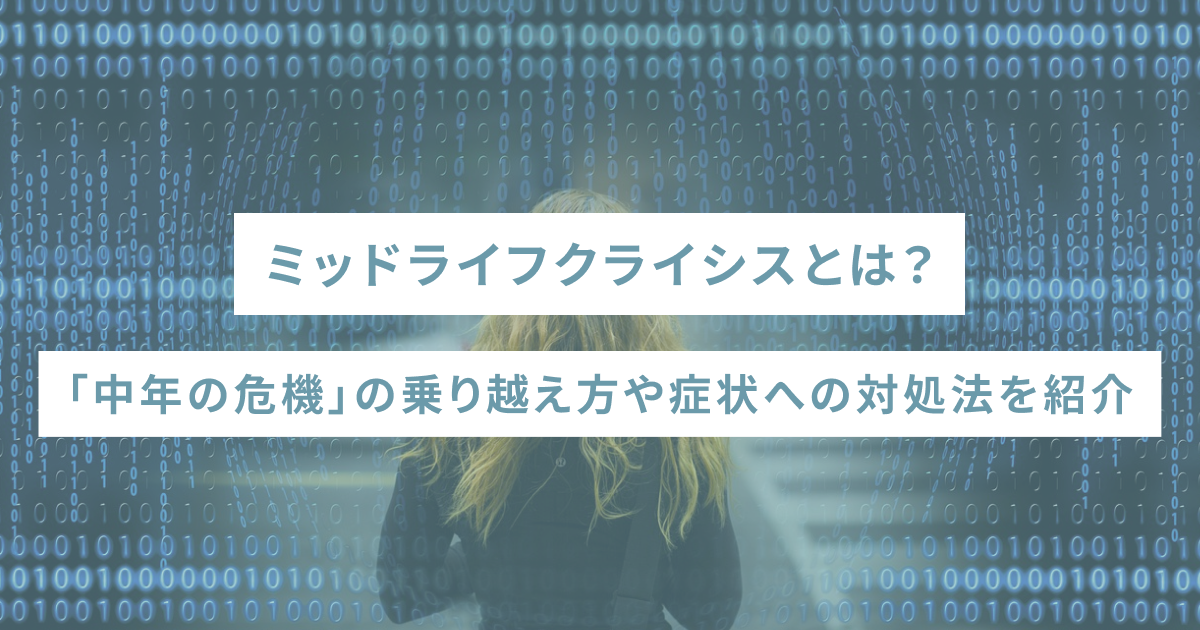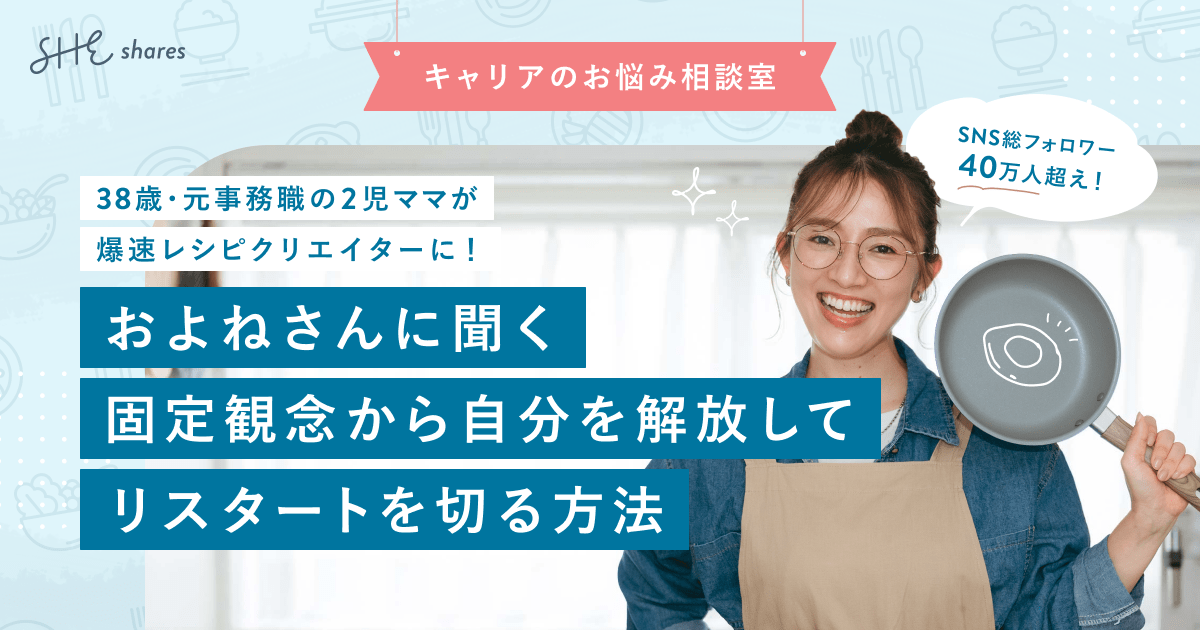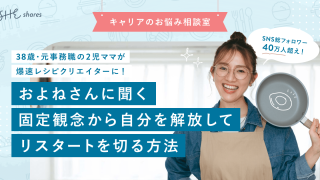働き方が多様化している近年、正社員以外の雇用形態も広まりつつあります。具体的に挙げられるのが「アルバイト」や「業務委託」などです。これらは雇用形態や加入できる保険が異なるため、契約前に違いを知っておきましょう。
本記事では、業務委託とアルバイトの違いについて解説します。それぞれのメリット・デメリットも解説するので、希望に合わせて柔軟な働き方がしたい方はぜひ参考にしてください。
業務委託とアルバイトの違い
「業務委託とアルバイトってどう違うの?」「業務委託だったら保険は入れないの?」など、業務委託とアルバイトの違いがいまいちわからない方も多いのではないでしょうか。
業務委託とは、「企業が一部の業務を外部の個人や事業者に委託すること」です。企業から依頼された案件に対して、成果物を納品したり業務を遂行したりすることで報酬を得ます。仕事を受ける側は「個人事業主」に該当するため、基本的に労働基準法が適用されません。
一方アルバイトは、パートタイム労働法で定義された「短時間労働者」のこと。企業に直接雇用されている「労働者」にあたるため、労働基準法が適用されます。
つまり業務委託とアルバイトは、雇用形態や加入可能な社会保険の種類が異なるのです。契約前に2つの違いを知っておきましょう。
| 業務委託の場合 | アルバイトの場合 | |
|---|---|---|
| 雇用形態 | 業務委託契約 | 雇用契約 |
| 加入可能な社会保険の種類 | 国民健康保険 国民年金保険 介護保険 |
健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 介護保険 |
| 勤務時間の決め方 | 制約がない。 納期に合わせて自分で調整する |
規定の労働時間に沿って働く |
| 報酬の支払い方 | 成果物に対して報酬が支払われる成果報酬制、 毎月一定額が決められている固定報酬制など |
日給・時給をもとに稼働時間に対して 給与が発生する時間単価性 |
雇用契約
業務委託とアルバイトの大きな違いは、雇用契約の有無です。業務委託の場合、働き手は企業と「業務委託契約」を結びます。基本的には受注した仕事が完了するまでの契約となり、そこに雇用関係はありません。業務の進め方や時間、場所は定められず、働き手の裁量で進められるのが特徴です。
アルバイトの場合、働き手は企業と「雇用契約」を結ぶため、雇用主と従業員という関係になります。業務委託の場合と異なり、企業は労働者に対し業務内容や進め方、勤務時間を指示することが可能です。
社会保険の種類
会社員が加入する社会保険は「健康保険」「年金保険」「雇用保険」「労災保険」の4つがあり、生活に困難が生じた際、国から一定の給付が受けられます。
業務委託の場合、企業に属していないため社会保険に加入できません。代わりに、個人で手続きすることで国民健康保険と国民年金に加入できます。万が一業務中にケガや病気で働けなくなった場合は保障が受けられないため、生活費の備えや民間保険の加入など、自分で対策しておくことが大切です。
一方アルバイトの場合は、条件を満たせば社会保険へ加入できます。保険料の一部を企業に負担してもらえたり、傷病手当金や障害年金の対象になったりと、メリットも多いです。
勤務時間の決め方
業務委託の場合、労働基準法の制約を受けないため労働時間や残業という概念がなく、勤務時間が決められていません。クライアントに指定された納期さえ守れば、自分で調整して好きなタイミングで働くことができます。
アルバイトの場合は、あらかじめ決まっている労働時間に沿って働くのが基本です。企業によって、自分で勤務時間を決めたりシフト制だったりと、勤務時間の決め方は異なります。
報酬の支払い方
業務委託の報酬形態は、業種や職種により異なります。たとえば、遂行した業務や成果物に対して報酬が発生する「成果報酬制」や、毎月一定額が決められている「固定報酬型」、成果報酬制と固定報酬制を組み合わせた「複合報酬型」などがあります。
アルバイトの報酬は、基本的に時間単価制です。はじめに定めた日給や時給をもとに、働いた時間に対して給与が発生します。所定労働時間を超えて働いた場合残業代も発生し、勤務時間が長いほど給与が増える仕組みです。
給与明細書の発行義務にも違いがある
業務委託とアルバイトは、給与明細書の発行義務にも違いがあります。原則として、発注者は業務委託の契約者に給与明細書を発行する必要はありません(そもそも業務委託契約で支払われるものは給与ではないので、給与明細書自体がない)。業務委託の契約者は、自分で収益や経費を管理する「独立した事業者」と見なされるためです。
一方、雇用者はアルバイト労働者に対しては、給与支払ごとに給与明細書を発行する法的義務があります。収入の内訳が記載された給与明細書があることで、賃金の透明性を確保できるのです。
業務委託として働くメリット・デメリット
前述したように、業務委託は業務を委託するクライアントと働き手が対等の立場となり、業務を受発注する契約形態のことです。ここでは、業務委託として働くメリット・デメリットを見ていきましょう。
メリット
- 働き方の自由度が高い
- 自分で仕事を選択できる
- スキル次第で収入アップが見込める
業務委託のメリットは、働き方の自由度が比較的高いことです。職種によっては時間や場所に縛られず自由に働けるため、ライフスタイルや業務内容に合わせて自分でスケジュールを組めます。リモートで働ける案件も多いので、海外や地方に住んでいる方や、育児や介護で通勤が難しい方も働きやすいでしょう。
また、受注する案件を自分で選べる点、実績や成果次第で収入アップが見込める点も魅力です。特にライティング、デザイン、マーケティングといったクリエイティブスキルは専門性が求められるので、市場価値を高められれば正社員やアルバイトよりも高い報酬を得られる可能性もあります。
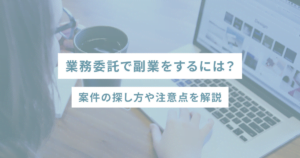
デメリット
- 収入が安定しない可能性がある
- 労働基準法の保障が受けられない
- 確定申告しなければならない
業務委託は労働基準法が適用されない立場なので有給休暇や労災保険などが適用されず、毎月の収入に保証がありません。急遽契約が打ち切られるなどして、収入が変動することもあるでしょう。そのようなリスクを理解し、継続案件を受注したり営業したりして、常に自分で仕事を確保する働きかけが大切です。
また、保険料の支払いや確定申告も自分で行う必要があります。確定申告を毎年行わないと、申告漏れによるペナルティが発生することもあるので注意しましょう*1。
アルバイトとして働くメリット・デメリット
アルバイトは企業と個人で雇用契約を交わし、企業に所属する働き方です。企業に雇われることで収入が安定しやすいメリットがある一方、勤務時間や勤務場所が決まっているデメリットがあります。それぞれ詳しくみていきましょう。
メリット
- 収入が安定しやすい
- オンとオフの区別がつけやすい
- 社会保険や労働基準法が適用される
アルバイトは時給(または日給)と労働時間があらかじめ決まっているため、収入が把握・安定しやすいというメリットがあります。オンとオフが区別しやすく、プライベートの予定が立てやすいのも魅力でしょう。
また、前述したようにアルバイトは社会保険や労働基準法の適用対象者です。バイト中のけがや病気で傷病手当金がもらえたり、万が一失業しても保障を受けられたりします。企業が年末調整するため、自分で確定申告する必要もありません。
デメリット
- 勤務時間や勤務場所が決まっている
- 大幅な収入アップはしにくい
多くの場合、アルバイトは勤務時間・場所が決まっています。業務委託と比べて在宅ワークが少なかったり、体調が悪いときも休みづらかったりする点は、人によってはデメリットに感じるかもしれません。
業務委託とアルバイト、それぞれどんな人に向いている?
業務委託とアルバイトの違いをふまえ、それぞれに向いている人の特徴を解説します。働き方で悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。
業務委託に向いている人
時間や場所にとらわれず自由な働き方がしたいなら、業務委託が向いています。自由に働けるぶん自己管理は欠かせませんが、自分のスキルや専門性を活かして収入を得ることができます。
実績やスキルアップが収入に影響しやすいため、スピード感を持って高収入を目指したい人にもよいでしょう。まずは副業として業務委託で働き、収入が増えたら独立する選択をとる人も多くいます。
アルバイトに向いている人
アルバイトは決まった時間に働くことができるため、規則正しい生活を送りたい人や、安定した収入を得たい人に向いています。自己管理が苦手な人にとって、あらかじめ勤務時間が定まっている点はメリットになるでしょう。
また、アルバイトは複数のスタッフとチームになり働く職場が多い傾向にあります。周囲とコミュニケーションを取りながら働きたい人にもおすすめです。
よくある質問
最後に「アルバイトに確定申告は必要?」「業務委託のリスクや注意点は?」など、業務委託とアルバイトに関するよくある質問に回答します。
疑問や不安な点はここで解消しておきましょう。
アルバイトに確定申告は必要?
アルバイトは雇用先が行う年末調整の対象になりますが、場合によっては自身で確定申告する必要があります。アルバイト労働者が確定申告が必要な要件は、以下のとおりです*2。
- 年末調整を受けた給与所得以外に、20万円を超える所得がある
- どのアルバイト先でも年末調整を受けていない
- 2カ所以上から給与所得を受け取っていて、1ヵ所のみで年末調整を受けており、年末調整をされなかった給与収入とその他の所得の合計が20万円を超える
- アルバイトを掛け持ちしていて、誤って2カ所以上で年末調整を受けている
- 年末までにアルバイトをやめて年末調整を受けていない
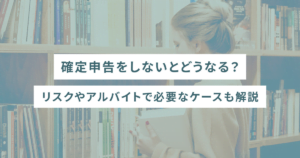
アルバイトとパートの違いは?
アルバイトとパートは、法律上の区別がありません。どちらもパートタイム・有期雇用労働法である「パートタイム労働者」に該当します*3。ちなみにパートタイム労働者とは、同じ事業主で働く正社員に比べて、1週間の所定労働時間が短い労働者のことです。
業務委託として働くうえでのリスクや注意点は?
業務委託で案件を受注する際は、業務内容や契約書の内容を慎重に確認しましょう。
業務委託の契約のなかには、成果物の納品を委託する際に適用される「請負契約」があります。請負契約を締結すると、完成物に欠如や不具合があった際に、発注者が請負人に当該箇所の修正や、損害の賠償を求められる「契約不適合責任」が生じます。納品後のトラブルを避けるためにも、契約締結前に求める成果物のイメージや、担当する業務範囲のすり合わせを慎重に行いましょう。
業務委託の働き方ができる職種にはどんなものがある?
業務委託はオンラインでクライアントと連絡を取ることが多いので、パソコンでできる案件が多いです。たとえば、以下のような職種が挙げられます。
- Webライター
- Webデザイナー
- Webマーケター
- 動画編集
- ITエンジニア
どの職種も専門スキルや知識が必要です。ただし、勉強次第では未経験からでも目指せるので、興味のある方は学んでみてはいかがでしょうか。
スキルを身につけて働き方の選択肢を広げるならSHElikes(シーライクス)がおすすめ!
業務委託・アルバイトいずれの雇用形態を選ぶにせよ、働き方の選択肢を広げるなら手に職をつけるのがおすすめです。たとえば女性向けキャリアスクールSHElikes(シーライクス)なら、Webデザイン、ライティング、マーケティング、動画編集など、在宅ワークやノマドワークに向いている全45種類の職種スキルを学べます。生徒同士で交流する機会もあるので、仕事を始めたあとも支え合える仲間をつくるきっかけにもなるでしょう。
実際に、SHElikesを通して働き方を変えた方はたくさんいます。以下の記事では、SHElikesを通してスキルを身につけ、自由な働き方を手に入れた方の事例を掲載しています。具体的なロードマップやキャリアチェンジ後の生活も紹介しているので、気になる方はチェックしてみてください。


業務委託とアルバイトの違いを理解しよう
業務委託とアルバイトはそれぞれにメリットとデメリットがあり、どちらがいいかは人によって異なります。自己管理をしながら自由に働きたい方は業務委託、労働時間を決めてメリハリをつけたいならアルバイトというように、理想に合った働き方をしましょう。
いずれの雇用形態を選ぶにせよ、選択肢を広げたいならスクールを活用してスキルを身につけるのがおすすめです。女性向けキャリアスクールのSHElikesでは、Webデザイン、ライティング、マーケティング、動画編集など全50以上の職種スキルが学べるため、自分に合った仕事を見つけるきっかけにもなります。気になる方は、まずは無料体験レッスンに参加してみてください。
出典:
*1:国税庁「延滞税について」より
*2:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」より
*3:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法の概要」より