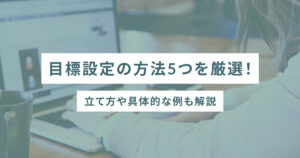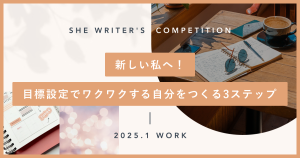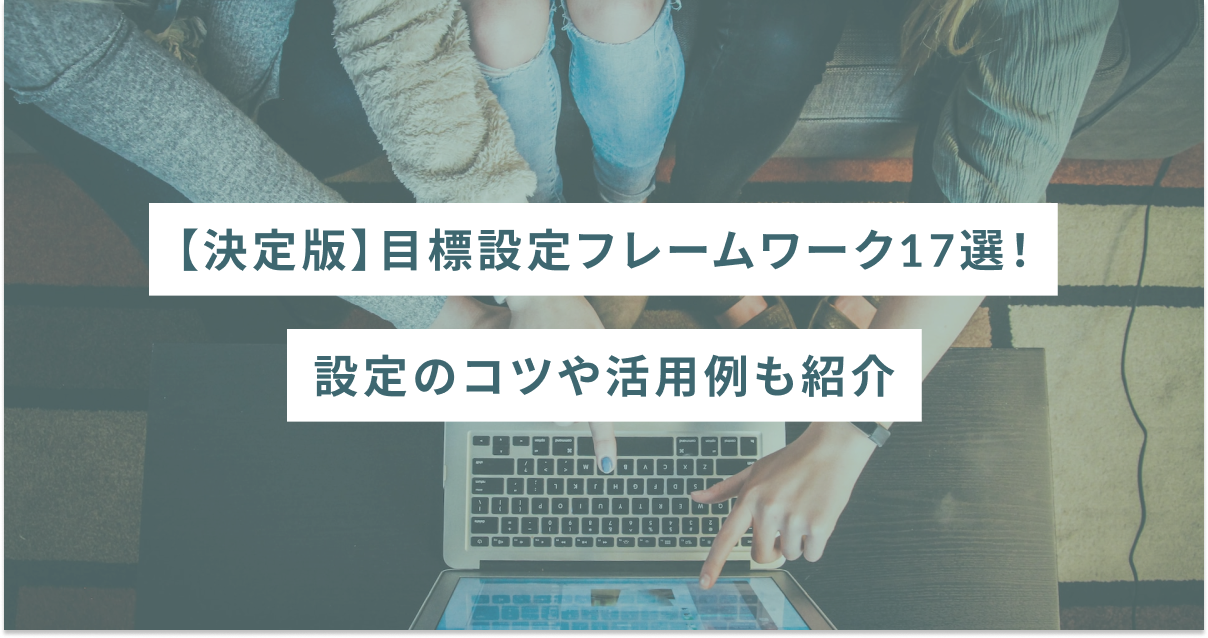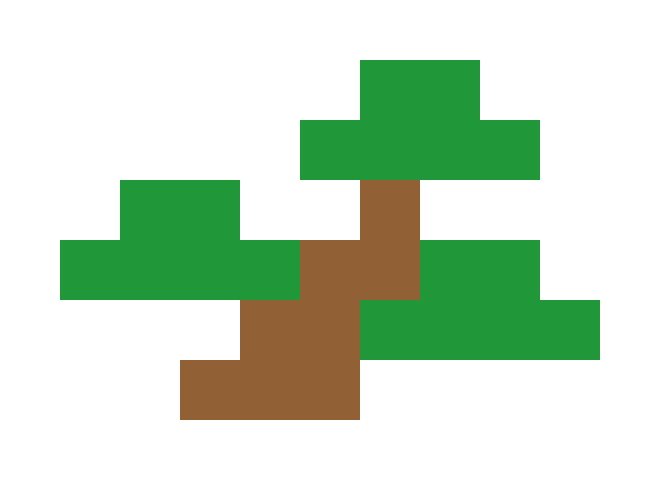目標を立てるとき、「どう計画を立てればいいのかわからない」「途中で挫折してしまう」と悩むことはありませんか?そんなときに活用したいのが、目標設定のフレームワークです。目標の明確化や進捗管理、モチベーション維持、パフォーマンス改善などに役立ちます。
この記事では、キャリアアップやスキル向上を目指すうえで役立つ17の目標設定フレームワークについて詳しく解説します。自分に合った手法を見つけて計画的に取り組み、目標達成を目指しましょう。
目標設定のフレームワークとは?
目標設定のフレームワークとは、目標を明確にし、達成までのプロセスを整理するための枠組みのことです。目標を立てる際には、「何を」「いつまでに」「どのように」達成するのかを具体的に考える必要があります。
計画が漠然としていれば、途中で方向性を見失い、行動に移しにくくなってしまう可能性も。そこで役立つのがフレームワークです。決まった手順やルールに倣うことで効率よく計画が立てられ、着実に行動へと繋げることができます。
目標設定フレームワークを使うメリット・注意点
目標設定にフレームワークを活用すると、目的が明確になり、効率よくゴールに向かうことができます。具体的な手順を踏むことで、漠然としがちな目標が達成しやすい形に整理されるのが大きなメリットです。また、進捗を確認しやすくなり、モチベーションの維持にもつながります。
ただし、フレームワークにこだわり過ぎると、柔軟な発想ができなくなることも。目的と手段が入れ替わらないように、「何のために目標設定をするのか」を常に意識しましょう。
目標設定フレームワーク選びのポイント
目標設定のフレームワークを選ぶときは、自分やチームの状況に合ったものを選ぶことが大切です。たとえば、個人の目標を設定する場合は、自分の成長や達成感を重視できるフレームワークが適しています。一方で組織やチームとしての目標を立てる場合は、進捗やゴールを適宜共有しやすいフレームワークを選ぶと効果的です。
また、細かく計画を立てて進めたいのか、大まかな指針を決めて柔軟に動きたいのかによっても、適したフレームワークは変わります。一概に「このフレームワークが優れている」というわけではありません。目的に合わせて適したものを選びましょう。
代表的な目標設定フレームワーク17選
ここでは、キャリアアップやスキル向上に役立つ17のフレームワークを紹介します。
- SMARTの法則
- ベーシック法
- 三点セット法
- ランクアップ法
- ベンチマーク法
- 期中設定法
- NLP式目標設定法
- OKR
- MBO
- KPIツリー
- GROWモデル
- HARDゴール
- マンダラチャート
- 目的・目標の4観点
- バックキャスティング
- KDI法
- WOOPの法則
自分に合った目標設定のフレームワークを見つけ、理想の未来に向かって一歩を踏み出しましょう。
1.SMARTの法則
SMARTの法則は、目標設定の可視性を高めるためのフレームワークです。Specific(具体的に)・Measurable(測定可能に)・Achievable(達成可能な範囲で)・Relevant(目的に合っているか)・Time-bound(期限を決める)の5つの要素から成り立っています。
たとえばSMARTの法則を活用すると、「英語を勉強する」ではなく、「半年後のTOEICで700点を取るために毎日1時間勉強する」といったような目標が設定され、行動の指針が明確になります。特に個人のキャリアアップやスキル習得の場面で役立つフレームワークです。
2.ベーシック法
ベーシック法は、「目標項目」「達成基準」「期限設定」「達成計画」の4つのステップで構成されたシンプルなフレームワークです。「いつまでに」「何を」「どのように」達成するかを明確にし、具体的な行動計画を立てていきます。難しいルールがないため、個人の目標からチームや組織の目標まで幅広く活用できるのが魅力です。
たとえば、「スキルアップしたい」という漠然とした目標ではなく、「半年以内にWebデザインの基礎を習得するために、オンライン講座を週に3回受講する」といった形に落とし込むといった使い方ができます。多くのフレームワークの基礎となるため、押さえておくとよいでしょう。
3.三点セット法
三点セット法は、ベーシック法をさらに掘り下げた目標設定のフレームワークです。「テーマ」「達成レベル」「達成手段」の3つの要素をセットで考えます。
今回は、「リーダーシップを強化する」というテーマを掲げた場合を例に挙げて考えてみました。たとえば達成レベルを「半年以内に会議でのスムーズな進行・意見の調整ができるようになる」とし、達成手段として「週一回チームミーティングを実施」と決めることで、目標に向けた具体的な道筋を描くことができるでしょう。
4.ランクアップ法
ランクアップ法は、段階的に目標を設定し、ステップを踏みながら成長を目指すフレームワークです。「改善」「代行」「研究」「多能化」「ノウハウの普及」「プロ化」の6段階で目標を設定することで、自信をつけながら成長できます。
たとえば「Webデザインスキルを習得する」という目的がある場合、最初の目標は「1か月以内にCanvaを使ってバナーを3つ作成する」、次に「3か月以内にFigmaを使ったLPデザインに挑戦する」といったように、少しずつステップアップしていくのが効果的です。大きな目標に向かう際も、小さく区切ることで挫折しにくくなるでしょう。
5.ベンチマーク法
ベンチマーク法は、目標とする基準や優良事例(ベンチマーク)を設定し、それに向かってスキルや実績を高めていくフレームワークです。ビジネスや投資の場面でよく使われています。自分の課題やウィークポイントを客観的に把握することで、改善のための具体的な目標が設定できるのが魅力です。
たとえば「Webデザインのスキルを向上させたい」という目的がある場合、ベンチマークとして「人気デザイナーが作ったバナーを参考にし、同じクオリティのクリエイティブを作れるようになる」などの基準を設定すると、目指すべきものより具体的になります。なぜうまくいっているのか、どこが自分より優れているのかをできるだけ明確にするのがポイントです。
6.期中設定法
期中設定法は、あえて曖昧な目標を設定し、状況に応じて振り返りや調整を行うフレームワークです。最初に具体的な目標を立てる必要がないので、気軽に始めやすいでしょう。定期的に進捗を確認しながら軌道修正することで、無理なく継続できるのもメリットです。
たとえばライティングの仕事を増やすために、最初に「半年以内に5件の案件を受注する」という目標を設定したとします。3か月後くらいに「現在の案件数は目標の半分に届いているか」「改善すべき点はあるか」などを確認し、必要なら学習時間を増やすなどの対策を講じるイメージです。定期的に振り返りながら、目標を具体化することを意識しましょう。
7.NLP式目標設定法
NLP式目標設定法は心理学や言語学、神経科学を組み合わせたフレームワークで、自分の感情や倫理観に沿った目標を設定するのが特徴です。ただ数値的なゴールを決めるのではなく、「その目標が達成されたとき、どんな気持ちになれるのか」をイメージしながら進めます。
たとえばSNS運用のスキルを習得したい場合、目標設定の際に「フォロワーが増えたらどんな仕事ができるようになるか」「どんな人とつながれるか」を具体的に想像し、モチベーションアップを狙うイメージです。NLP式目標設定法では肯定的な表現を使い、具体的なイメージを持つことが大事なポイントになります。
8.OKR
OKR(Objectives and Key Results)は、「目標(Objectives)」とその達成度を測る「主要な成果(Key Results)」を組み合わせたフレームワークです。一般的に、企業が掲げるビジョンに合わせて各部署が連携し、成果を追求するための羅針盤として活用されます。
短期間(通常四半期ごと)で目標を設定し、定期的に進捗を確認することで、柔軟に軌道修正が可能です。ちなみに、このフレームワークは企業だけでなく個人のキャリア形成にも活用できます。目標を明確にし、達成までのプロセスを具体化することで、モチベーションを保ちながら成長につなげられるでしょう。

9.MBO
MBO(Management by Objectives)とは、日本語で「目標管理制度」のこと。目標を上司やチームと共有し、合意のもとで設定するフレームワークです。他のフレームワークとの違いは、当人が主体的に目標を設定し、達成に向けて進捗を管理できる点にあります。個人だけで決めるのではなく、組織全体の方向性とすり合わせながら目標を設定するため、キャリアアップを考える際にも有効です。
たとえばマーケティングスキルを伸ばすために、上司と相談しながら「半年でフォロワーを1,000人増やす」という目標を設定したとします。その場合は「週1回分析レポート作成」「競合アカウントの調査」「月2回の改善ミーティング」といった具体的な行動計画を考え、定期的に進捗を確認するのが効果的でしょう。このように、組織の成果と自身の成長を両立しやすくなるのがMBOの特徴です。
10.KPIツリー
KPIツリーは、最終的な目標(KGI)を達成するために、具体的な指標(KPI)をツリー状に細かく分けて管理するフレームワークです。大きな目標を細分化することで、何をどのように改善すればよいのかが明確になります。
たとえばSNSを活用して集客力を高めたい場合に、KGIは「半年以内にInstagram経由の問い合わせ数を月50件に増やす」と設定したとしましょう。そこから、KPIとして「フォロワーを1万人に増やす」「投稿の保存率を20%以上にする」「月4回のキャンペーン実施」などの細かい目標を決めます。ただし、KPIツリー内に同じような要素が含まれていると無駄な業務が発生し、生産性が低下しかねないので注意してください。
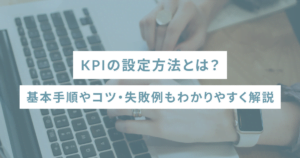
11.GROWモデル
GROWモデルは、目標達成までの道筋をGoal(目標)・Reality(現状)・Options(選択肢)・Will(意志)の4つのステップで整理するフレームワークです。コーチングの基本手法を取り入れています。
たとえば「3か月以内に5本の動画を編集する」という目標を設定した場合で考えてみましょう。まずは「基本的な編集ソフトの操作ができるか」という現状を確認し、「講座を受講する」「実際に動画を作って練習する」などの選択肢を洗い出します。そして先ほどの選択肢の中から目標達成のために効果的な手段を選び、行動に移すという流れです。漠然とした目標を具体的な行動計画に落とし込める点がメリットでしょう。
12.HARDゴール
HARDゴールは、情熱や達成感を重視しながら目標設定を行うフレームワークです。ちなみに「HARD」は、Heartfelt(心から望む)・Animated(具体的にイメージできる)・Required(必要不可欠な)・Difficult(挑戦的な) の頭文字を取っています。「自分にとって意味のある目標」を設定することで、モチベーションを維持しやすくなるのがメリットです。
たとえば、「ライティングで収入を得たい」場合、Heartfelt では「書くことが好きで、言葉で人を動かしたい」、Animated では「自分の書いた記事が多くの人に読まれる姿を想像する」とします。HARDゴールは他のフレームワークよりも感情に根付いているので、自分のキャリアを考えるときに適したメソッドといえるでしょう。
13.マンダラチャート
マンダラチャートは、目標を中心に置き、関連する要素を広げながら整理するフレームワークです。メジャーリーガーの大谷翔平選手が使っていたことでも話題になりました。目標を達成するために必要な行動やスキルを可視化し、具体的なステップを明確にするのに役立ちます。
たとえば「Web系のフリーランスとして働けるスキルを身につけたい」という目標を設定した場合、中心にその目標を書き、周囲に「ライティング」「デザイン」「マーケティング」などの必要なスキルを配置します。それぞれのスキルを習得するための行動を細かく書き出すと、やるべきことが明確になるのでおすすめです。
14.目的・目標の4観点
目的・目標の4観点は、「私的有形」「私的無形」「他者的有形」「他者的無形」の4つの視点から考えるフレームワークです。より具体的で達成しやすい計画を立てられるのがメリットといえます。
たとえばWebマーケティングのスキルを習得したい場合、私的有形の目標は「半年でSNS運用案件を3件受注する」、私的無形は「分析スキルを磨き自信をつける」といった個人の成長に関わるものがメインです。一方他者的有形では、「クライアントのフォロワー数を1.5倍に増やす」、他者的無形では「企業のブランド価値を高め、ユーザーに親しみを持たせる」といったように、周囲への影響を意識した目標を設定します。
15.バックキャスティング
バックキャスティングは、理想の未来を描き、そこから逆算して目標を設定するフレームワークです。「今できること」から考えるのではなく、「将来こうなりたい」というビジョンを起点に計画を立てます。特に劇的な変化が必要な課題や、現状では実現が難しい目標に高い効果を発揮するのが特徴です。
たとえば、「3年後にWebデザイナーとして独立したい」と考えた場合は、まず理想の働き方をイメージしましょう。次に、「1年後までにポートフォリオサイトを作成する」「半年以内にデザインソフトの基礎を習得する」といった形で、具体的なステップを決めていきます。未来から逆算することで、目標達成に向けたルートを見つけやすくなるという仕組みです。
16.KDI法
KDI(Key Do Indicator)法は、目標達成に必要なスキルや知識を具体的に洗い出し、それを習得するための行動進捗を管理するフレームワークです。最終ゴール(KGI)から具体的な指標(KPI)と行動量(KDI)を逆算することで、目標の適切さと達成のための行動量を把握できます。
たとえば「動画編集の仕事を受注できるようになりたい」と考えた場合、まず重要な要素(K)として編集スキルや企画力などを挙げます。次に、それらを身につけるための手段(D)としてオンライン講座を受講する、実際に動画を3本作るといった方法を決めましょう。最後に、指標(I)として編集スピードの向上や案件獲得数などを設定し、進捗を確認します。進捗を可視化できるのがメリットです。
17.WOOPの法則
WOOPの法則は、目標を達成するために、理想だけでなく現実的な障害も考慮しながら計画を立てるフレームワークです。「願望(Wish)」「結果(Outcome)」「障害(Obstacle)」「計画(Plan)」という4つのステップの頭文字をとっています。
たとえば、「ライティングの仕事で安定した収入を得たい」と考えた場合、願望は「ライターとして独立したい」、結果は「毎月◯万円の収入を得る」、障害は「案件がなかなか取れない」、計画は「毎日1件応募する」「執筆スピードを上げる」などになるでしょう。目標達成を妨げる要因を事前に想定することで、途中でつまずいても冷静に対応できるのがこのフレームワークの強みです。
フレームワークを活用し目標設定するコツ
せっかく目標を立てても途中で挫折してしまったり、うまく行動につなげられなかったりしては本末転倒です。ここでは、誰でも取り入れられる目標設定のコツを紹介します。
参考にして、ぜひ実践してみてください。
無理な目標を設定しない
まず、自分の現状に合った無理のない目標を立てることが大切です。意欲的に高い目標を掲げることは良いことですが、あまりにも現実とかけ離れたものだと、途中で挫折する原因になります。たとえば、「未経験から1か月でフリーランスとして月100万円稼ぐ」といった目標を立てると、達成できなかったときに自信を失ってしまうかもしれません。
SMARTの法則を活用し、「3か月でライティング案件を5件受注する」「毎週1本noteを書く」といった具体的かつ頑張れば達成可能な目標を設定すると、着実に前に進めます。目標の現実性をチェックするために、WOOPの法則を使って障害を想定し、対策を考えておくのも効果的です。
短期・中期・長期の目標を設定する
目標設定をするときは、短期・中期・長期の3つに分けて考えることで無理なくステップアップできます。いきなり大きな目標を掲げても、何から始めればいいのかわからず挫折しやすくなるため、段階的に計画を立てることが大切です。
たとえば「1年後にWebデザイナーとして副業を始めたい」と考えた場合、バックキャスティングを使って逆算すると、以下のような具体的な行動が見えてきます。
- 1か月以内にデザインの基礎を習得
- 3ヶ月以内にバナーデザインを50個トレースしてソフトの操作方法を習得
- 6か月以内にポートフォリオを作成
- 1年以内に仕事を受注
あわせてKPIツリーを活用すれば、目標達成のために必要なスキルや行動を細分化でき、効率よく学習を進められるのでおすすめです。
目標は頻繁に変更しない
一度決めた目標をすぐに変えずに、一定期間は継続することも大切です。目標を立てた直後はモチベーションが高くても、少し進めると「このやり方で合っているのかな?」と不安になり、違う目標に変えたくなることがあるでしょう。しかし、頻繁に変更してしまうと成果が見えにくくなり、成長の実感を得られなくなる可能性も。
フレームワークを活用することで、目標に対するブレを防ぐことができます。たとえばOKRを使えば、短期間の成果を測りながらも大きな方向性は変えずに進められます。期中設定法を活用し、定期的に振り返ることで変更は必要かどうかを冷静に判断するのも効果的です。
達成度を可視化し振り返りを行う
目標を設定したら、達成度を可視化し、定期的に振り返ることが大切です。進捗が見えないままだと、「本当に前に進めているのか」と不安になり、モチベーションが下がってしまうことがあります。目標達成のためには、都度成果を確認しながら軌道修正していくことが欠かせません。
途中経過が可視化できるフレームワークを活用すると、進捗管理がスムーズになります。たとえば、KPIツリーを使って目標達成に向けた細かい指標を設定すれば、進捗を数値で確認できます。GROWモデルを活用して定期的に振り返り、必要に応じて行動を見直すのも良いでしょう。目標設定後は可視化と振り返りを習慣化し、確実に前進できるように工夫することが大切です。
目標設定フレームワークの活用例
目標設定フレームワークは、企業の戦略的な計画はもちろん、個人のキャリアアップ・スキルアップなどさまざまな場面で活用できます。ここではフレームワークの活用例を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
企業の目標設定における活用例
企業では、チームや組織全体の成長を促すために、目標設定フレームワークを活用して戦略的に計画を立てることが一般的です。たとえばOKRを用いれば、企業のビジョンと個人の目標を連携させながら進捗を管理できます。
ある企業が「1年以内に新規顧客を増やす」という目標を立てた場合を例に考えてみましょう。まず具体的な指標(KPI)として「半年以内に問い合わせ数を20%増加」「月に2回のSNSキャンペーン実施」などを設定します。その後、各部署が役割を分担して決め、達成度を定期的に確認する流れです。組織全体の目標と個人の業務が結びつき、成果の創出が期待できます。
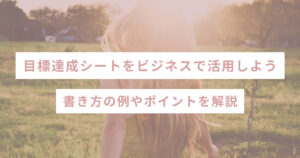
個人のキャリアや自己成長における活用例
目標設定フレームワークは、スキルアップやキャリアチェンジ、副業の準備など、個人の自己成長の場面でも活用できます。特に、何から始めればいいのかわからないときや、途中でモチベーションが続かなくなりそうなときに役立つのでぜひ活用してみてください。
たとえば転職を目指す場合にバックキャスティングを活用すれば、「半年後に希望の職種へ転職する」という理想から逆算して必要なスキルや資格を整理できます。副業を始める場合はKPIツリーを使い、「月5万円の収入を得る」という目標に対して、具体的なアクションを細分化するのが効果的です。目標設定のフレームワークを使って自分の進むべき道を可視化すれば、迷わず行動できるようになるでしょう。
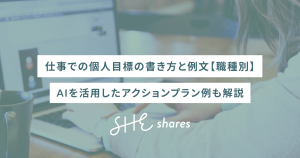

目標設定フレームワークを活用して理想の未来を手に入れよう
目標設定のフレームワークといっても、個人のスキルアップに役立つ「SMARTの法則」や「GROWモデル」、チームや企業の成長を促す「OKR」や「KPIツリー」など、種類はさまざまです。それぞれ特徴があるので、目的に応じたフレームワークを活用すれば目標達成への道筋が明確になります。「何から始めればいいかわからない」と感じたときは、まずは自分の状況に合ったフレームワークを試してみてください。
目標設定を進めていくなかで「Webスキルを身につけたい」「未経験からWeb系の職種に転職したい!」とやりたいことが出てきた方には、女性向けキャリアスクールSHElikes(シーライクス)がおすすめです。Webデザインやマーケティング、ライティングなど、50以上の職種スキルが学べます。
まずは無料体験レッスンに参加して、キャリアを変える一歩を踏み出してみませんか?