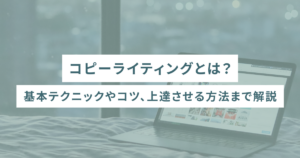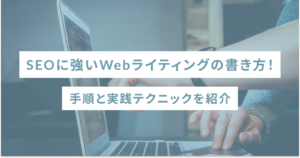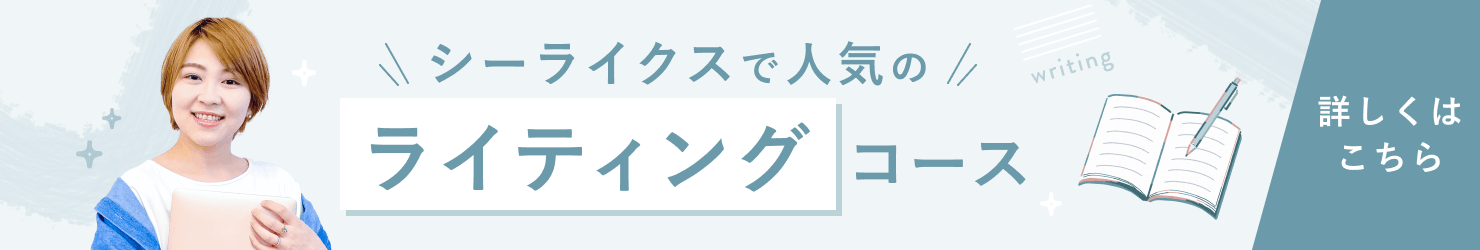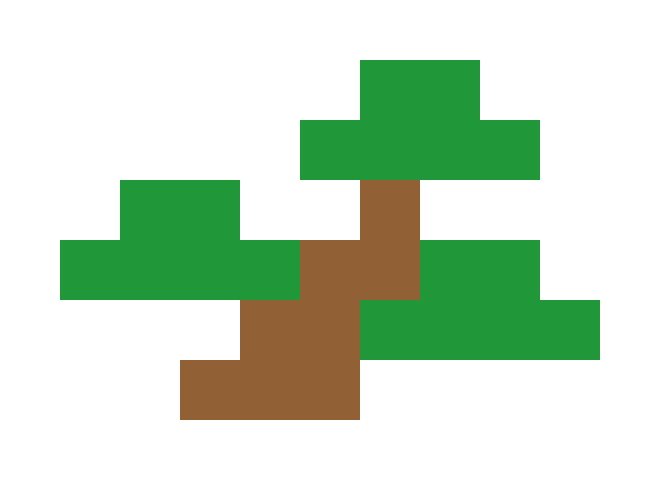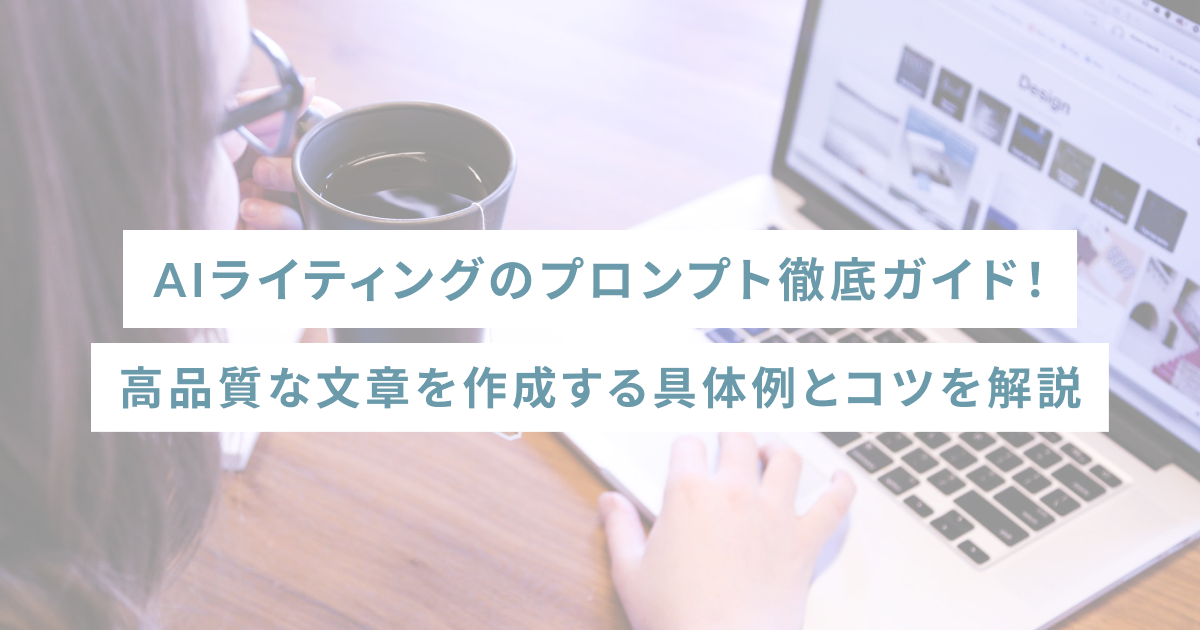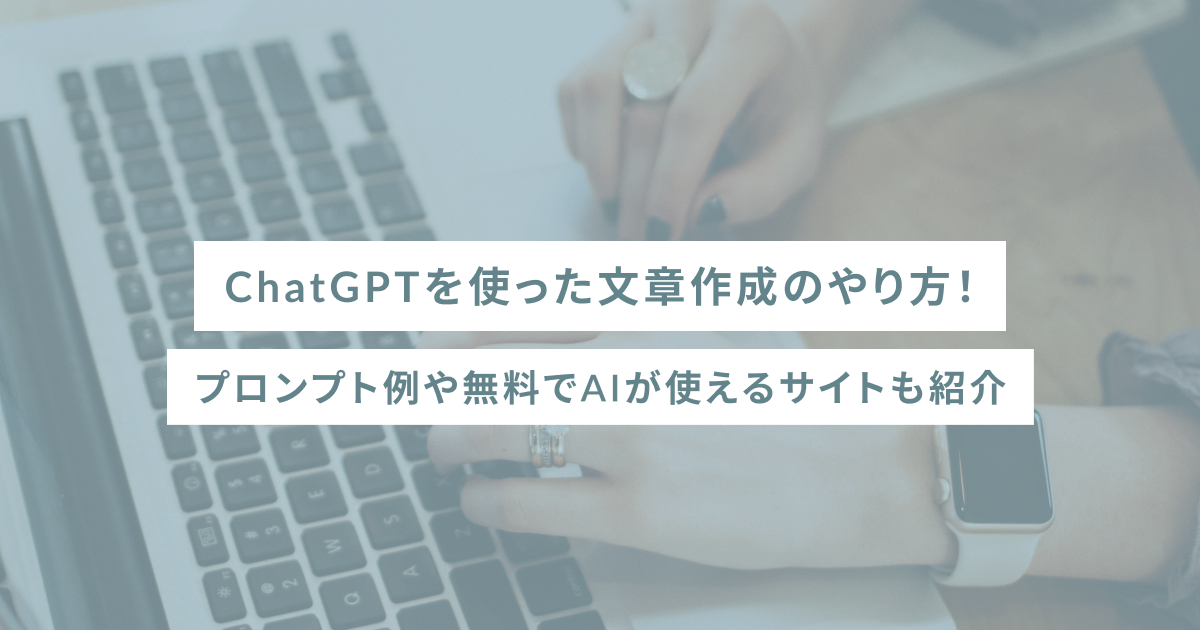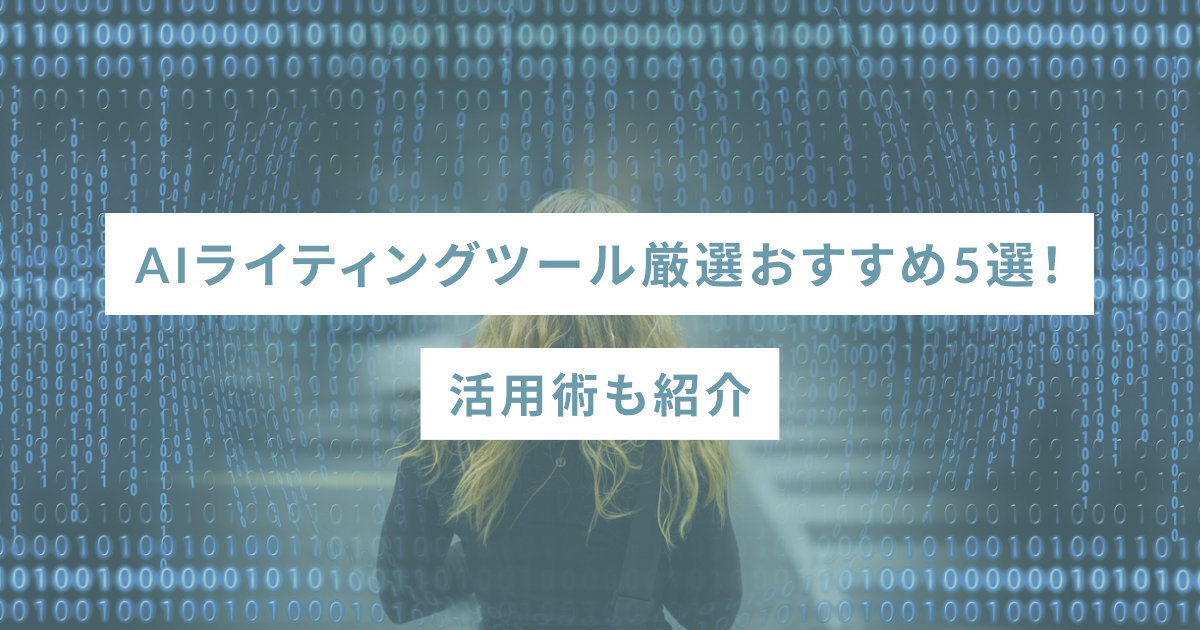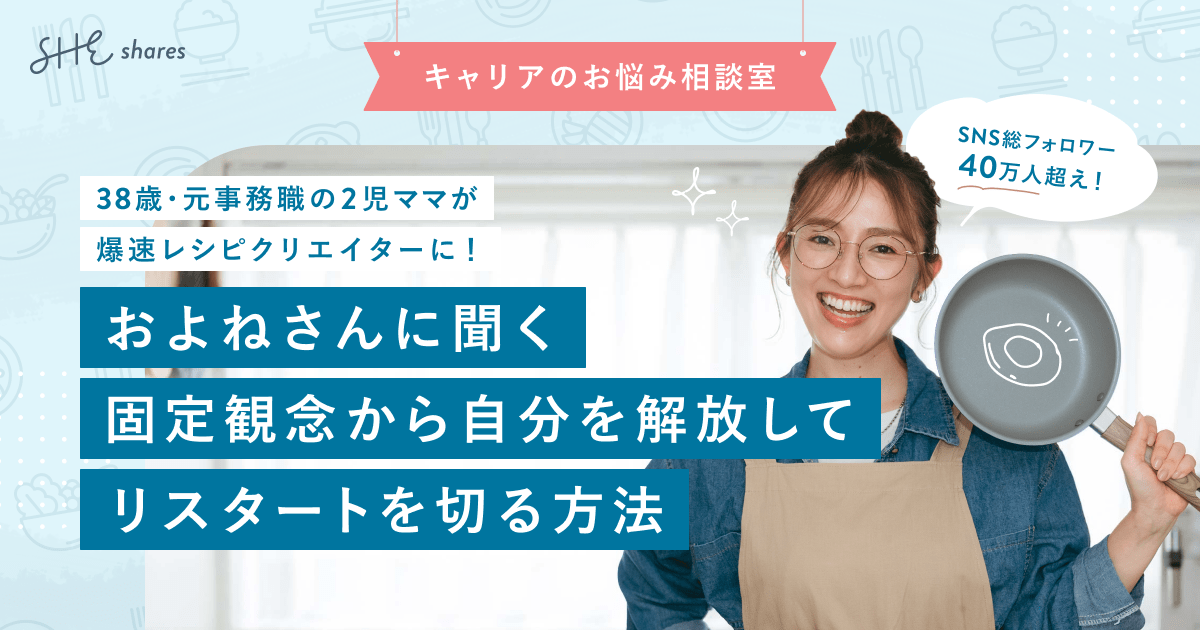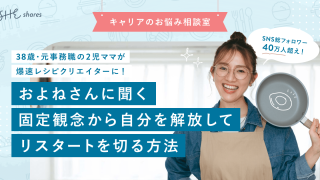ライティングの仕事に興味はあるけれど、インタビューライティングは難しそう……と感じている方は多いのではないでしょうか。実はちょっとしたコツを押さえるだけで、誰でも魅力的な記事を書けるようになります。
この記事では、インタビュー記事の企画から取材、執筆、公開までをステップごとに解説します。ライター初心者でも実践しやすい書き方のポイントや、プロの取材術を学びたい方は、ぜひ参考にしてください。
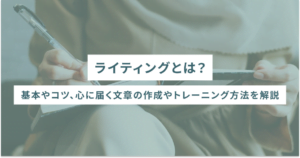
インタビューライティングとは
インタビューライティングとは、インタビュー(取材)を通じて読者に価値ある情報を届けるライティング技術です。ここでは、インタビューライティングの目的や、具体的なスタイル(形式)を紹介します。
インタビューライティングの目的
インタビューライティングの最大の目的は、取材相手(インタビュイー)の考えや経験を引き出し、読者にとって価値のある情報を伝えることです。聞いた話をそのまま記事にするのではなく、テーマに沿って整理してわかりやすくまとめる必要があります。
また、質問の仕方ひとつで記事のクオリティが大きく変わるため、ライターには相手の魅力や情報を引き出す工夫が求められます。
インタビューライティングのスタイル(形式)の種類
インタビューライティングは、取材相手の魅力や情報を読者に伝えるために、どのようなスタイルでまとめるかが重要となります。ここでは、以下の3つのスタイルの特徴を解説します。
それぞれの特徴を理解し、記事の目的や読者に合わせたベストなスタイルを選びましょう。
Q&A形式
Q&A形式は、インタビューでのやりとりを再現するように記事にする形式です。質問と回答を並べるシンプルな構成なので、取材相手の言葉をダイレクトに伝えられるのが特徴です。話し手の個性や考え方がストレートに伝わるため、読者にとって親しみやすいメリットがあります。一方で、単調になりがちなので質問の組み立て方や構成には工夫が必要です。
ストーリー形式
ストーリー形式は、取材内容をライターが再構成して一つの流れのある記事にまとめる形式です。単なる会話の記録ではなく、取材相手の背景や経験を踏まえながら、読者に伝わりやすい形に整えます。特に人物の人生や仕事に焦点を当てた記事に適しており、時間軸に沿って話を展開することで、より自然で引き込まれる記事となるのが特徴です。
記事内引用形式
記事内引用形式は、インタビュー内容を記事の一部として組み込みながらライターが解説や考察を加えていく形式です。ニュース記事や専門的な解説記事でよく使われ、取材相手の意見を要所で引用しながら全体の流れをライターが調整します。客観的な視点を保ちつつ、専門家や関係者の意見を取り入れることで、記事に説得力を持たせられる点がメリットです。
インタビュー企画から取材・記事公開までの流れ 8STEP
インタビュー記事の作成には、企画立案から取材、文字起こし、構成決め、最終的な公開に至るまで、多くのステップがあります。ここでは、インタビュー企画から記事公開までの流れを8つのステップで解説します。
各ステップのポイントを押さえることで、スムーズにインタビューを実施できるようになります。
1.企画立案
インタビュー記事を作成する際に、最初にすべきことは企画立案です。ここでは企画立案のポイントを3つお伝えします。
企画立案のポイントその1:企画の目的を考える
何のために取材を行い、読者にどのような情報を届けるのかを決めることで、記事の方向性が定まります。たとえば新商品の開発秘話を伝えたいのか、業界の専門家から知見を引き出したいのかによって、記事の切り口は変わります。目的が曖昧だと取材や記事執筆の際に焦点がぶれてしまうため、企画段階でしっかり考えることが大切です。
企画立案のポイントその2:テーマを決める
企画の目的が決まったら、次に設定するのが「テーマ」です。テーマは記事全体の核となるもので、読者の関心を引くために、わかりやすくかつ具体的に設定する必要があります。テーマが広すぎると話が散漫になりがちなため、取材対象者の専門性や記事のゴールを意識しながら、適切な範囲に絞るようにしましょう。
企画立案のポイントその3:記事のスタイルを決める
テーマが固まったら、どのような記事のスタイルで伝えるかを決めます。インタビューライティングには「Q&A形式」「ストーリー形式」「記事内引用形式」などのスタイルがあり、それぞれメリットが異なります。記事の目的やターゲット読者に適したスタイルを選択しましょう。
2.取材依頼・アポ取り
インタビューライティングを行う際に、取材依頼・アポ取りは必須です。まず取材対象者に対して、記事の目的やテーマを簡潔に伝え、取材を受けるメリットを理解してもらいます。依頼の際は、取材の形式(対面・オンライン・メールなど)、所要時間、掲載予定の媒体を明記し、相手の都合に配慮した日程を提案しましょう。
また、質問内容の概要を伝えることで取材相手が準備しやすくなり、より充実した回答を得やすくなります。
3.インタビューの事前準備
クオリティの高いインタビュー記事を執筆するには、入念な事前準備が欠かせません。まず、取材対象者や関連分野について情報収集を行い、基礎知識を身につけましょう。その上で、取材相手に事前に送る質問状を作成し、大まかな話の流れを共有しておくとスムーズな取材が可能になります。また、当日の取材で深掘りできるように質問リストも準備しておくと安心です。
4.インタビュー実施
インタビューをスムーズに進行するために、段取りは事前に整えておきましょう。ICレコーダーやスマートフォンを用いて確実に音声を記録し、万が一に備えてバックアップも準備します。話の流れを妨げないように、カメラマンによる撮影のタイミングなどを事前に打ち合わせしておくことも大切です。
そして、より充実したインタビューを実施できるように、4つのポイントを解説します。
インタビュー実施のポイントその1:当日の身だしなみ
インタビュー当日は取材相手に不快感を与えないように、清潔感のある身だしなみを心がけましょう。服装は場の雰囲気に合わせて、シンプルで落ち着いたスタイルを選ぶのが無難です。また、爪や髪型の乱れ、靴の汚れなども意外と見られているものなので注意してください。
インタビュー実施のポイントその2:アイスブレイクを設ける
インタビューとは言え、いきなり本題に入ると相手が緊張してしまい、良い回答を引き出せないことがあります。まずは雑談や共通の話題を探し、リラックスできる雰囲気作りをしましょう。たとえば天気や最近のニュース、相手の仕事に関する軽い話から始めると効果的です。
インタビュー実施のポイントその3:リアクション
インタビューで相手の話を引き出すために、リアクションはとても重要なポイントです。うなずきや相づちを入れることで、相手は「きちんと話を聞いてもらえている」と感じ、安心して話しやすくなります。また、「なるほど」「すごいですね」「わかります」など、驚きや共感を表情や声で伝えると会話が弾みます。
インタビュー実施のポイントその4:メインの話題を深堀りする
より充実した記事を作成するためには、表面的な回答にとどめず、メインの話題を深掘りすることが大切です。相手が話した内容に対して「具体的には?」「その時どう感じましたか?」と追加の質問を投げかけると、エピソードや本音を引き出しやすくなります。事前に用意した質問にこだわりすぎず、相手の言葉に興味を持って掘り下げていくとよいでしょう。
5.文字起こし
インタビュー後の文字起こしは、記事の質を左右する工程と言っても過言ではありません。録音データをもとに発言内容を正確にテキスト化し、ニュアンスを損なわないよう注意しましょう。話し言葉はそのままだと読みにくいため、適宜調整を加えつつも取材相手の個性や意図を反映させるように工夫する必要があります。
また、ICレコーダーやスマートフォンの録音データを活用し、音声認識ツールを使用すると効率的に作業できます。
6.構成決め
構成決めは、インタビュー記事の伝わりやすさを左右する重要な工程です。まず記事の目的や読者層を再確認し、次に導入・本題・結論の流れを意識しながら、適切な順序で配置します。その際にポイントとなる3つの要素について解説します。
構成のポイントその1:メディアの方針に沿ったタイトル決め
タイトルは、記事の第一印象を決定づける大切な要素です。たとえばビジネスメディアなら専門性や権威性を意識したタイトル、エンタメ系メディアなら親しみやすさや話題性を重視するとよいでしょう。また、SEOを考慮し、読者が検索しそうなキーワードを盛り込むのも効果的です。
構成のポイントその2:リード文は本文を書いた後に仕上げる
リード文には、記事の最初で読者の関心を惹きつける役割があります。そのため、読者の興味を引く要素を盛り込み、記事の全体像を簡潔に伝えることが大切です。具体的には、インタビューのキーポイントや取材相手の魅力を凝縮し、記事の核心に触れる部分を示唆する内容にします。
また、基本的にリード文は本文を執筆した後に仕上げます。本文を書くことで記事全体のポイントや結論が明確になるためです。
構成のポイントその3:インタビュー現場の温度感を届ける本文
読者に取材時の雰囲気や会話の流れを感じてもらうためには、インタビュー現場の温度感を届ける工夫が必要です。たとえば少し砕けた記事の場合、取材相手の語調やちょっとした笑いなども文章に反映することでより臨場感を伝えられます。これにより読者がインタビューを追体験でき、深く共感したり興味を持ったりすることができます。
7.初稿提出
初稿提出は、取材内容をもとに構成した記事を編集者やクライアントに提出し、内容や方向性についてフィードバックをもらうステップのことです。初稿の段階で完璧を目指す必要はなく、編集者とのやり取りを通じて、記事をブラッシュアップしていきます。提出後は必要な修正や加筆を加え、最終的な形に仕上げていきます。
8.修正・公開
修正・公開は、インタビュー記事作成の最終段階です。初稿に対するフィードバックをもとに修正を行い、内容や構成を整えます。この時点で、誤字脱字の確認や表現が適切で伝わりやすいか、メディアポリシーに適しているかなどの再評価も行い、問題がなければ公開します。
インタビュー記事の書き方のコツ
インタビュー記事を書く際は、ただ話を聞いてそのまま書くだけでは読者に響く内容にはなりません。ここでは取材相手の魅力を引き出し、伝えたい情報をわかりやすくまとめるためのコツを解説します。
- 適した記事スタイル(形式)の選定
- インタビュイー(取材相手)を説明するための項目が必要かを判断する
- 記事のサビを明確にする
- 省略されている言葉を補う
- インタビュイー(取材相手)の人柄を表現する
- 事実や真意を捻じ曲げないように注意する
これらのポイントを押さえることで、読者にとって魅力的なインタビュー記事を作成することができます。
適した記事スタイル(形式)の選定
読者層や記事の目的に応じてスタイルを選ぶことで、情報をより効果的に伝えることができます。たとえば、取材内容が専門的であれば記事内引用形式を用いて、専門家の意見を引き立てながら解説を加えます。インタビュー相手の個性やエピソードに焦点を当てたい場合は、ストーリー形式が読者に響きやすいです。気軽に読める記事にしたい場合は、シンプルなQ&A形式を選択するのもよいでしょう。
インタビュイー(取材相手)を説明するための項目が必要かを判断する
インタビュイーが有名であれば、背景や経歴を簡潔に紹介する程度でも読者に理解してもらえます。あまり知られていない人物の場合は、記事の主題に関連する情報をピックアップし、過剰になりすぎない程度に紹介を加えるのがポイントです。
記事のサビを明確にする
サビとは、記事の中で最も印象的で伝えたいメッセージの部分です。このサビを明確にすることで、読者が記事を通して何を得られるのかが一目でわかり、記事の軸がブレなくなります。また、サビの要素を記事の導入部分や結論に織り交ぜることで、読者の興味をより強く惹きつけることができます。
省略されている言葉を補う
インタビュー中、インタビュイーが自然な会話の中で言葉を省略することがあります。そのまま記事に載せると、読者にとってわかりづらくなる場合があるため注意が必要です。省略された部分や意味が曖昧な言葉を適切に補うことで、文脈が明確になり、読みやすくなります。
インタビュイー(取材相手)の人柄を表現する
インタビュイーの話し方や言葉の選び方、態度、表情からも、その人の性格や考え方は浮かび上がるものです。記事でもインタビュー時に見えた人柄を表現することで、読者はインタビュイーと親近感を持てるようになります。たとえば、ユーモアを交えて話してくれたならその面を強調したり、真剣な話題ではその真摯さを感じさせる表現を使います。
事実や真意を捻じ曲げないように注意する
インタビュー記事で事実や真意を捻じ曲げないように注意することは、信頼性と誠実さを保つためにも重要です。取材中に得た情報はそのまま正確に伝えることが基本であり、インタビュイーの言葉を編集する際は意図を歪めないよう注意を払う必要があります。言葉のニュアンスや強調を正確に表現し、誤解を招くような書き方は避けましょう。
良いインタビュー取材を行うコツ
インタビュー取材で相手の本音を引き出すためには、取材の進め方や工夫が欠かせません。ここでは、準備段階からインタビュー中の工夫、そして相手とのコミュニケーションを大切にする方法まで、良いインタビューのコツを紹介します。
これらのポイントを意識することで、より深みのあるインタビュー記事を作成できます。
徹底した事前リサーチ
インタビュー取材は、事前の準備・リサーチで9割成否が決まると言っても過言ではありません。取材相手のバックグラウンドや最近の活動、関連するテーマについてしっかり調べておくことで、具体的で的を射る質問ができます。
また、事前に知識を得ておくことでインタビュー中に話が逸れてもスムーズに元の話題に戻すことができ、取材の質が格段に向上します。リサーチが完璧であれば、相手の信頼も得られます。
取材相手に興味を持つ
良いインタビュー取材を行う秘訣は、取材相手に心から興味を持つことです。相手の経歴や活動内容を事前に調べてからインタビューに臨むことで、鋭い質問の投げかけや新しい視点を引き出すことが可能になります。また、冒頭から相手の話に共感を示すことで、リラックスした雰囲気が作られて自然な会話が生まれるメリットもあります。
質問リストを作る
事前に質問を用意することで取材の進行がスムーズになり、聞き漏れを防ぐことができます。取材相手の背景を調査した上で、核心に迫る質問と導入しやすい質問をバランスよく組み込みましょう。また、具体的なエピソードや感想を引き出せるように、「はい・いいえ」で終わらない質問を意識してください。
仮説を立てる
インタビュー取材では、事前に仮説を立てることで質問の焦点が明確になり、より深みのある回答を得やすくなります。仮説とは、事前リサーチをもとに相手の考えや行動を予測して出す仮の答えのことです。
たとえば、「この成功の背景には独自の工夫があるはず」と仮説を立てることで、「具体的にどんな工夫をしましたか?」といった深掘りする質問が可能となります。取材の流れがスムーズになる他、相手の新たな視点や意外なエピソードを引き出しやすくなるメリットがあります。
時系列を意識する
インタビュー取材を行う際にも、時系列を意識することが大切です。たとえば、「そのアイデアが生まれたのはいつですか?」「そこからどう発展しましたか?」と段階を踏んで質問すると、話がスムーズに進みます。取材相手も回答しやすくなり、その結果充実した回答が得られれば、読者に伝わりやすい記事を作成することができます。
【あわせて知っておきたい】インタビューライティングの分野で活躍するために大切なこと
当然ながら、インタビューで得た情報を正確で読みやすい文章に書き起こすには、土台となる書く力が不可欠です。
基礎的なライティングスキルには、論理的な文章展開、適切な語彙選択、読み手を意識した構成力、そして文章全体のリズム感などが含まれます。これらの基礎がなければ、どれほど優れた内容のインタビューでも、その魅力を記事として読者に伝えることは難しいでしょう。
実践のチェックポイント
- 基本的な文法や表現ルールを正確に使い、読みやすい文章を心がける
- 論理的な文章展開を意識し、インタビュー内容を整理して伝える
- 読み手にとって理解しやすい構成と表現に整える
ライティングスキルの鍛え方や執筆のコツについては、以下の記事で詳しく解説しています。文章力向上のための具体的な方法や効果的なフレームワークを紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
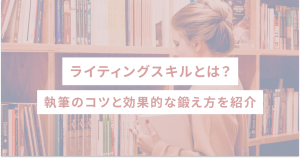
インタビューライティングが学べるおすすめスクール・講座3選
インタビューライティングのスキルを体系的に学ぶなら、プロから直接指導を受けられるスクールの活用がおすすめです。ここでは、実践的なライティング力や取材のスキルを身につけられるスクールを5つご紹介します。
1. SHElikes(シーライクス)
SHElikesは、ライティング含む50以上の職種スキルが学べる女性向けキャリアスクールです。インタビューライティングコースでは、企画立案から執筆までの流れや事前準備のポイント、現場の温度感を伝える技術を習得できます。プロの添削付きの実技試験(100点満点中80点以上で合格)でスキルを確実に身につけられるのが特徴です。
こんな人におすすめ
- インタビューライティングを基礎から学びたい女性
- 複数のライティングスキルを組み合わせたい方
- コミュニティで仲間と学びたい方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用(税込) | レギュラープラン:352,000円/12ヶ月分一括の場合 スタンダードプラン:16,280円/月 入会金:162,800円 |
| 受講形式 | オンライン |
| サポート体制 | ・月1回のコーチング ・講師への質問 ・受講生同士が繋がれるコミュニティ |
2. Writing Hacks
Writing Hacksは買い切り型のライティング講座で、一度購入すれば永続的に学習できるのが最大の特徴です。Webライティングの基礎に加え、取材記事の書き方やインタビューのコツを動画で学べます。LINE@での質問が無制限にできるため、疑問点をすぐに解決できるのも魅力でしょう。
こんな人におすすめ
- 自分のペースでじっくり学びたい方
- 月額費用を気にせず学習したい方
- 疑問点をすぐに質問したい方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用(税込) | 89,800円(買い切り) |
| 受講形式 | オンライン動画 |
| サポート体制 | ・LINE@での質問無制限 ・講座内で3回の添削あり |
インタビューライター養成講座
インタビュー特化のメディア・制作会社が運営するインタビューライター養成講座。取材の企画から、取材、執筆、案件獲得方法まで、インタビュー記事制作の一連の流れを実践的に学べます。個別のフィードバック(添削)が充実しており、未経験からプロのライターを目指せるカリキュラムが特徴です。
こんな人におすすめ
- 未経験からインタビューライターとしての一歩を踏み出したい方
- 実践的なスキルを身につけ、仕事に繋げたい方
- インタビュー特化のスクールを探している方
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用(税込) | 動画学習コース:9,815円/月 スタンダードコース:19,669円/月 プロフェッショナルコース:39,377円/月 |
| 受講形式 | オンライン |
| サポート体制 | ・個別の5回以上添削 ・キャリア支援 |
SHElikesでスキルアップした先輩たちの活躍事例
インタビューライティングスキルの習得を目指している方には、実際にキャリアスクールを活用し、活躍の幅を広げた先輩たちの事例も参考になるかもしれません。ここではSHElikesでインタビューライティングを学び、それぞれの理想の働き方やライフスタイルを実現した先輩たちの事例をご紹介します。
完全未経験からインタビューライター へ|著名人への取材も多数担当
完全未経験から大手メディアで執筆するフリーライターとして活躍する彩さん。体調を崩して会社を辞めたことをきっかけにキャリアを見直し、SHElikesに入会します。
ライティングコースでの学びを活かし課題やコンペに挑戦し、入賞記事をポートフォリオに掲載していきました。さらに、SNS発信とメディアへの営業活動をアグレッシブに行い、現在は文春オンラインやWoman typeなどで執筆。現在は著名人への取材や記事の企画・ディレクションも行っています。
SHElikesの添削課題や実技試験を通じて実力を養い、仲間と切磋琢磨する環境が背中を押してくれたと語る彩さん。「私にはこれくらいの幸せで十分」と限界を決めず、新たな挑戦をしたことで、理想の働き方を実現できた事例です。
彩さんが手にした成果
- 完全未経験から著名人を取材するライターに転身
- SNS発信やメディアへの直接営業で案件を獲得
- 取材だけではく記事の企画・ディレクションも担当

憧れのインタビューライターに挑戦!月1〜4万円の副収入も
YouTube運営やオウンドメディアのライティングを担当していたなこてんさんは、職場環境が厳しく長期間続けていく自信を失っていたそう。自分のスキルやキャリアへの迷いを抱えながらも、未経験分野への挑戦意欲と副業への関心を持っていました。SHElikesのイベントがきっかけで転職に成功したあと、「インタビューライティングにも挑戦したい!」という想いが芽生え、改めて学んでみることに
ライティングコースやインタビューライティングコースを通じて、企画立案から取材準備まで総合的に学習し、取材に臨む基礎的な姿勢を身につけました。学習成果をポートフォリオにまとめたところ、それをきっかけに初の取材案件を獲得!現在はカスタマーサクセスの本業をしながら取材・コラムライターとして月1〜4万円の副収入を得てます。
なこてんさんが手にした成果
- 改めて自分のやりたいことに気づき、勉強を開始
- 憧れのインタビューライターとして副業で月1〜4万円の安定収入獲得
- ライティングの自主制作を集めたポートフォリオから継続案件受注
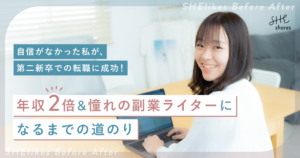
取材をもとに魅力を引き出すインタビューライティング
今回は、取材を通じて価値ある情報を読者に届けるインタビューライティングについて解説しました。インタビューライティングは、記事の目的を明確にしてテーマやスタイルを工夫することで、より伝わりやすい内容に仕上げることができます。また、事前準備やインタビュー時の工夫次第で、相手の魅力を最大限に引き出すことが可能です。
この記事を通じて、インタビューライティングの奥深さを感じてもらえたのではないでしょうか。学んだ知識を活かし、ぜひインタビュー記事作成に挑戦してみてください。