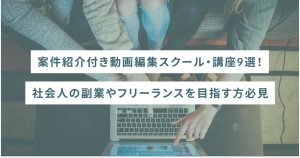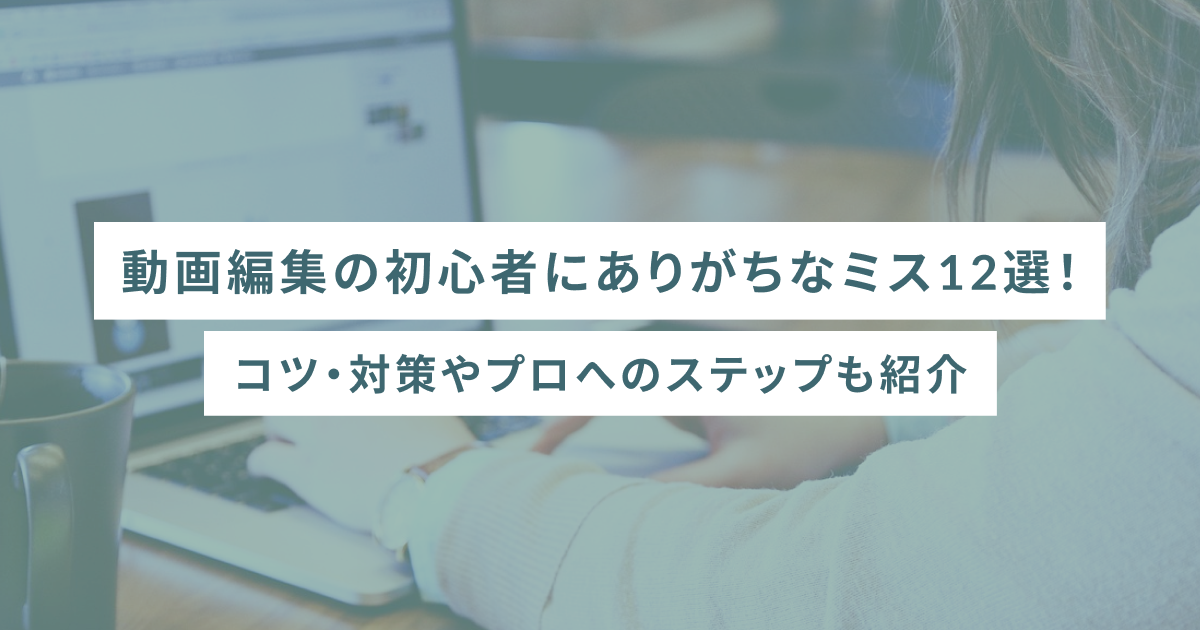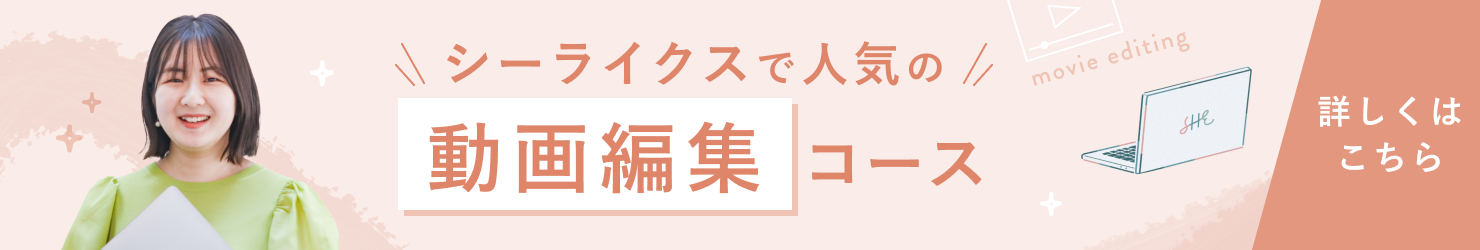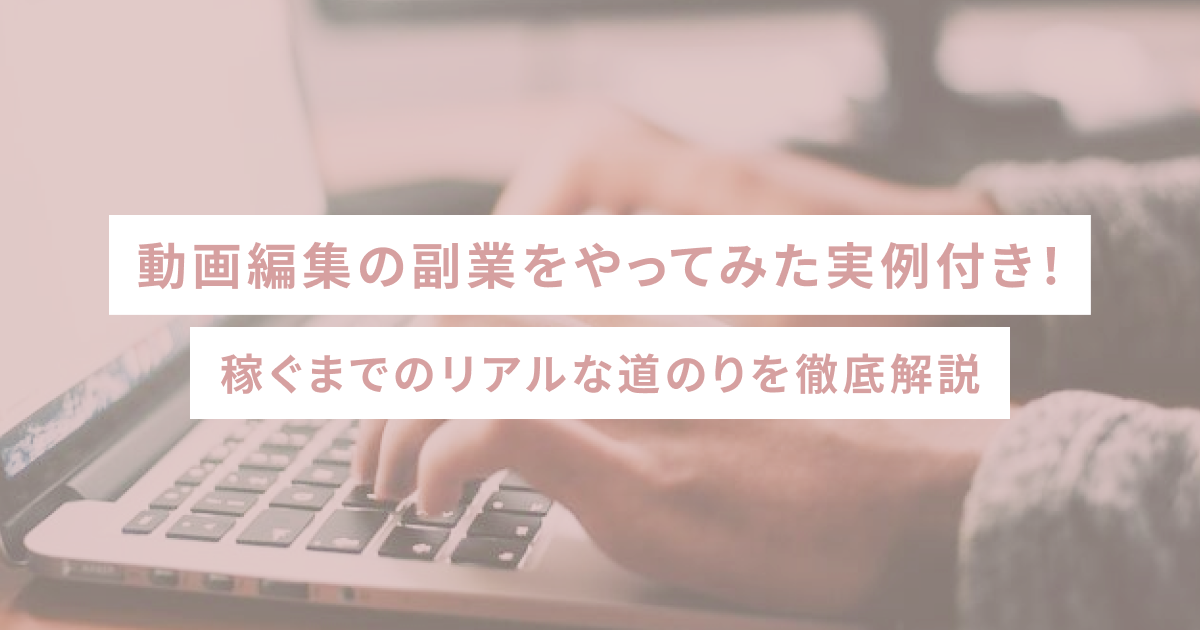動画編集を始めたての頃は、「何から手をつければいいの?」「このやり方で合ってるのかな?」と迷うことが多いもの。特に初心者は、気づかずにちょっとしたミスをしてしまいがちです。
今回の記事では、動画編集を始めたばかりの方にありがちなミスの例を挙げながら、失敗を防ぐためのコツや上達のステップをわかりやすく紹介します。これから動画編集を始める方は、ぜひ参考にしてください。
動画編集初心者が挫折やミスをしやすい理由
動画編集初心者が挫折やミスをしやすいのは、基礎知識が不足したまま感覚的に作業を進めてしまいやすいためです。動画編集は、素材の整理、カット割り、BGMのタイミングなど、細かな工程が多く、手順を理解していないと編集が思うように進みません。
その結果、映像の流れが不自然になったり、音ズレなどのミスが重なったりし、途中でやる気を失ってしまう方も少なくありません。
また、他人の完成度の高い動画と比べて「自分にはセンスがない」と感じ、モチベーションを保てなくなるケースもあります。挫折を防ぐには基本から順序立てて学び、効率的な編集の流れを身につけることが大切です。
女性向けキャリアスクールSHElikes(シーライクス)では、動画編集を含む50以上の職種スキルが学び放題です。以下の記事では、これからの時代に動画編集を仕事にするためのノウハウを解説しています。興味のある方はぜひチェックしてみてください。

動画編集の初心者にありがちなミス12選!対策やコツも紹介
動画編集を始めたばかりの初心者は、経験やスキル不足により思わぬ失敗をしてしまう場合があります。ここでは、動画編集で初心者がつまずきやすいポイントを3つのカテゴリ別に解説し、対策やコツもセットで紹介します。
ありがちなミスは、初心者なら陥りやすいもの。コツをしっかり押さえてスキルアップを目指しましょう。
環境・ツール・準備編
動画編集を始める前に、まず整えておきたいのが「環境」と「ツール」です。ここでは、編集作業の効率や品質に直結する初期段階のミスと対策を解説します。
パソコンのスペック不足
動画編集では高画質な映像を扱うため、パソコンの性能が足りないと作業中に画面が固まったり、動作がカクカクしたりします。特に、4K動画やエフェクトを使う編集では、書き出しだけで時間がかかることも。
まずは、使いたい編集ソフトの公式サイトで推奨スペックをチェックしましょう。メモリは最低16GB以上、保存はSSDがおすすめです。予算が厳しい場合は、プロキシ編集という軽いデータで作業する機能を使えば負担を減らせます。スペック不足はストレスの原因になるため、快適な編集環境を整えることが上達への第一歩です。
使用ソフトの選定ミス
いきなりプロ向けの高機能ソフトを使おうとして、操作が複雑すぎて挫折するパターンはよくあります。逆に無料ソフトだと機能が足りず、やりたい表現ができないことも。
大切なのは、自分のレベルや目的に合ったソフトを選ぶことです。たとえば、SNS投稿用の動画編集がメインなら、初心者向けの直感的な操作が可能なソフトからスタートし、慣れてきたら徐々にステップアップすればOKです。多くのソフトには無料体験版があるので、実際に触ってから決めましょう。
編集前の準備不足(動画素材の整理・台本など)
撮影した動画をとりあえずソフトに入れて、思いつきで編集を始めてしまうのも、初心者あるあるです。具体的には、撮影した動画素材が整理されていなかったり、カットやテロップの指示が曖昧な台本しかなかったりする状態が挙げられます。この状態で編集を始めると、素材探しに時間がかかるうえ途中で構成に迷ってしまうなど、作業が大幅に遅延します。
そのため、編集前に素材をフォルダやカテゴリごとに整理して、どのシーンをどの順番で使うか簡単な台本やメモを作っておきましょう。特に、長い動画や複数のカメラで撮った素材は、ファイル名に日付や内容を入れておくと後から探すのが楽になります。
目的が明確でない
誰に何を伝えたいのか、ターゲットがぼんやりしたまま編集を進めると、テロップの言葉選びや演出の方向性がブレてしまいます。
たとえば、10代向けならテンポよくポップに、ビジネスパーソン向けなら落ち着いたトーンで情報整理するなどの工夫が必要です。編集を始める前に「この動画は誰のどんな悩みを解決するのか」「見終わった後にどう行動してほしいのか」を書き出してみましょう。目的が明確になれば、編集の軸がブレず、視聴者の心に届く動画が作りやすくなります。
技術・クオリティ編
続いては、動画の仕上がりの質に関わる技術面とクオリティ面に起こりやすいミスと対策を解説します。
テンポが悪い
動画のテンポが悪いと、視聴者は途中で離脱しやすくなります。初心者にありがちなのが、無音の間や「えー」「あのー」といった言い淀みを、そのまま残してしまうことです。こうした細かい部分が積み重なると、全体の印象が冗長になり、せっかくの内容も伝わりにくくなってしまいます。
不要な間(ま)は思い切ってカットし、会話や映像の切り替わりにメリハリをつけましょう。とはいえ、削りすぎると逆に機械的で不自然に感じられ、視聴者が聞きづらくなるリスクも。自然な間を残しつつ、リズムよく編集すれば、視聴者が飽きない動画に仕上げられます。
動画の尺が長すぎる・情報過多
伝えたいことを全部詰め込もうとして、結果的に長すぎる動画になってしまうというケースも、ありがちな失敗です。情報量が多すぎると視聴者は疲れてしまい、最後まで見てもらえない可能性が高くなります。
特に、SNSのように短時間で判断されるプラットフォームでは、「最初の数秒で何を伝えるか」「どのシーンを残すか」が勝負どころ。企画の段階で「届けたい核心は何か」を見極め、重要度の低い要素は思い切って削る勇気を持ちましょう。もし、複数のテーマを扱いたい場合は、シリーズとして分けるのも効果的。短くても印象に残る構成こそ、良い動画の第一歩です。
エフェクトやテロップの多用
派手なエフェクトやテロップをたくさん入れれば豪華に見えると想像しがちですが、実は逆効果です。確かに一瞬は目を引きますが、情報量が多すぎると視聴者の目が疲れ、どこに注目すればよいのか分からなくなってしまいます。その結果、いちばん伝えたかった内容が埋もれてしまうことも。
特に初心者のうちは「せっかく機能があるなら全部使ってみたい」という気持ちになりがちですが、そこは冷静になりましょう。エフェクトやテロップは、視覚的なアクセントや理解を助けるスパイスのような存在。必要な部分だけに絞れば、映像全体にまとまりが生まれ、伝わる動画に仕上がります。
音量バランスが一定でない
BGMが大きすぎてナレーションが聞こえない、シーンごとに音量がバラバラといった音のトラブルは、視聴者にストレスを与えます。初心者は映像ばかりに気を取られて音声調整を後回しにしがちですが、音のクオリティは動画の印象を左右する重要なポイントです。
編集ソフトのオーディオメーターを見ながら、ナレーションや声は聞き取りやすく、BGMは邪魔にならない程度に抑えましょう。スマホやイヤホンなど複数のデバイスで再生チェックすると安心です。
色味に統一感がない
シーンごとに明るさや色調がバラバラだと、どうしても素人っぽく見えてしまいます。特に、違う時間帯や場所で撮った素材をつなげると、色味の違いが目立ちやすくなります。
そのため、編集ソフトのカラーコレクションを活用して、全体のトーンを統一する作業を忘れないようにしましょう。まず基準となるシーンを一つ決め、ほかのシーンも明るさや彩度を合わせて調整します。LUT(ルックアップテーブル)を使うと、あらかじめ設定された色味を適用できるため、初心者でもプロのような仕上がりに近づけることができます。
マインド・仕事術編
動画編集を仕事として捉えるうえで、初心者の成長を妨げるのが、仕事への向き合い方やマインドセットに関わるミスです。途中で迷ったり挫折したりしないためにも、基本のポイントをしっかり押さえておきましょう。
完璧主義
「完璧な作品を作らなければ」と思い詰めるあまり、細部にこだわりすぎて編集が進まなくなることがあります。初心者ほどこの思考に陥りやすく、一つの工程に何時間もかけた結果、納期に間に合わなかったり途中で心が折れたりすることも少なくありません。
動画編集のスキルは、経験を重ねることで磨かれていきます。最初から100点を目指すのではなく、まずは70点でも完成させて公開することを意識して、量をこなしていきましょう。
データの保管ミス
編集途中のデータや素材のバックアップを取らずずに作業すると、パソコンのトラブルやソフトのクラッシュで全てが失われるリスクがあります。何時間もかけた編集データが一瞬で消えるショックは計り知れません。
このようなミスを防ぐためには、作業の区切りごとにこまめに保存し、さらに外付けハードディスクやクラウドにも定期的にバックアップを取ることが大切です。プロジェクトファイルだけでなく、使用した素材もまとめて一つのフォルダで管理すると、万が一のときも復旧がスムーズに行えます。
納期管理の意識が低い
趣味として始めた動画編集でも、仕事として受ける場合は納期を守ることが絶対条件です。しかし、初心者は作業時間の見積もりが甘く、直前になって慌てたり、クオリティを妥協せざるを得なくなったりするケースは少なくありません。
対策として、編集作業を細かい工程に分け、それぞれにかかる時間を記録しましょう。そうすることで、次回以降の見積もりの精度が上がります。余裕を持ったスケジュールを組み、予期せぬトラブルに備えてバッファ(予備時間)を確保することが大切です。

動画編集初心者からプロとして活躍するためのステップ
ここからは、初心者がプロとして活躍するまでの具体的な始め方を、4つのステップに分けて解説します。
それぞれのコツも含めて、順に見ていきましょう。
1.基礎スキルの習得と編集環境の最適化
動画編集の始め方として、まず基礎スキルをしっかり身につけましょう。独学でも問題ありませんが、スクールを活用すると体系的に学べて時短になります。
まずは、自分が目指す分野(YouTube、SNS、広告など)を決めて、その目的に合った手順で学習を進めましょう。この段階では、チュートリアル動画を見ながら手を動かすインプットとアウトプットの繰り返しが重要です。カットやテロップ挿入などの基本操作を覚えることからスタートし、ほかのクリエイターの作品を研究するのも効果的です。
2.強みをアピールするポートフォリオの作成
基礎が身についたら、次は自分の実力を見せるポートフォリオ作りです。ポートフォリオは、営業ツールであり、あなたの名刺代わりになるもの。得意なジャンルやターゲットとする案件に合わせたジャンル(エンタメ系、教育系、YouTube特化、企業PR風など)など、最低でも3〜5本の作品を用意しましょう。
クライアントは「この人に頼んだらどんな動画ができるか」を知りたがっています。単に多くの作品を羅列するより、厳選した質の高い作品を載せるほうが印象に残ります。実案件が未経験の場合は、架空の案件を想定した作品を掲載すると説得力が増します。
3.実案件の獲得・信頼関係の構築
ポートフォリオができたら、いよいよ実案件にチャレンジです。最初はクラウドソーシングサイトや知人の紹介など、小さな案件から始めましょう。報酬が安くても、実績を積むことが何より大切です。納期を守り、丁寧なコミュニケーションを心がければ、クライアントとの信頼関係が生まれます。
信頼関係が築ければ、継続依頼やリピート案件につながり、安定した収入の基盤になります。レスポンスの速さや修正対応の柔軟さも評価ポイントです。
4.単価向上への挑戦・スキルの拡張
実績が増えてきたら、次は単価アップを目指しましょう。そのためには、付加価値をつけることが重要です。動画編集だけでなく、企画提案や撮影、マーケティングなど、関連スキルの幅を広げていきましょう。
スキルアップは、自分の市場価値を高める近道になります。また、特定のジャンルのスペシャリストになるのもおすすめです。「この分野ならこの人」と認識されれば、高単価案件のオファーが来やすくなるでしょう。動画編集の収入相場や案件の受注方法は、以下の記事でも詳しく解説しているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
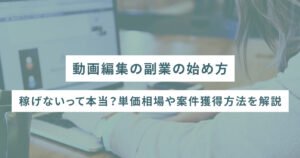
動画編集をはじめ幅広くスキルを磨くならSHElikes
動画編集のようなクリエイティブ分野で活躍の幅を広げたい方には、女性向けキャリアスクールSHElikes(シーライクス)がおすすめです。ここでは、SHElikesの特徴と受講生の活躍事例を紹介します。
動画編集を含む50以上の職種スキルが定額・学び放題
SHElikesでは動画編集だけでなく、Webデザインやライティング、マーケティングなど50以上の職種スキルが定額で学び放題です。一つのスキルに特化するのもいいですが、複数のスキルを掛け合わせることで市場価値はグッと高まります。
たとえば、動画編集スキル×マーケティングの知識があれば、ただ編集するだけでなく戦略的な提案ができる編集者に。オンラインで自分のペースで学べるため、仕事や家事の合間の時間を有効活用してスキルアップできます。

SHElikesで動画編集を学び活躍している実例
続いては、SHElikesで初心者から動画編集スキルを身につけ、自分らしい働き方を実現した受講生の実例を紹介します。
YouTube登録者数60万人突破!未経験から副業動画編集者になった方法 しらたまさん
しらたまさんは、動画編集未経験からSHElikesで学び、副業をスタートさせた卒業生です。Webデザインや動画編集のコースを受講し、仲間との交流を通して多角的なクリエイティブスキルを磨いていきました。
学んだスキルを掛け合わせて、料理研究家である母親のYouTubeチャンネルの編集を担当し、チャンネルは1年半で登録者数60万人を突破。その経験を活かして、クラウドソーシングで女性向けのVlog案件を受注するなど、着実に活動の幅を広げています。

初心者にありがちなミスを回避して動画編集の世界で活躍しよう
動画編集を始めた初心者のうちは誰もがつまずくものです。しかし、今回紹介したポイントを意識すれば、多くのミスは未然に防げます。
独学に不安を感じる方には、SHElikes(シーライクス)がおすすめです。映像制作に必要な知識や基本的なツールの使い方が学べる動画編集コースだけでなく、受講生同士で交流できるコミュニティや、実際の案件を受注できる機会も用意されており、学びを実践に結びつけやすい環境が整っています。
失敗を恐れず、まずは一本動画を完成させてみましょう。その小さな一歩が、プロへの道の始まりです。SHElikesが少しでも気になる方は、ぜひ無料体験レッスンで学びの第一歩を踏み出してみてください。